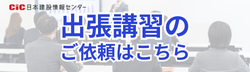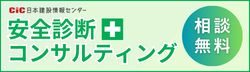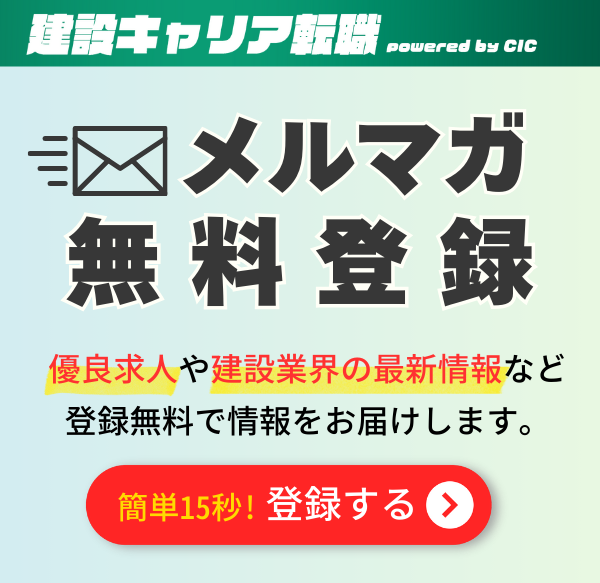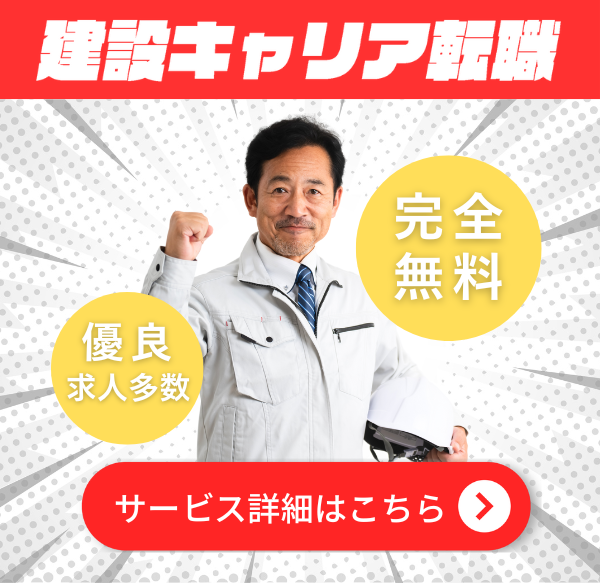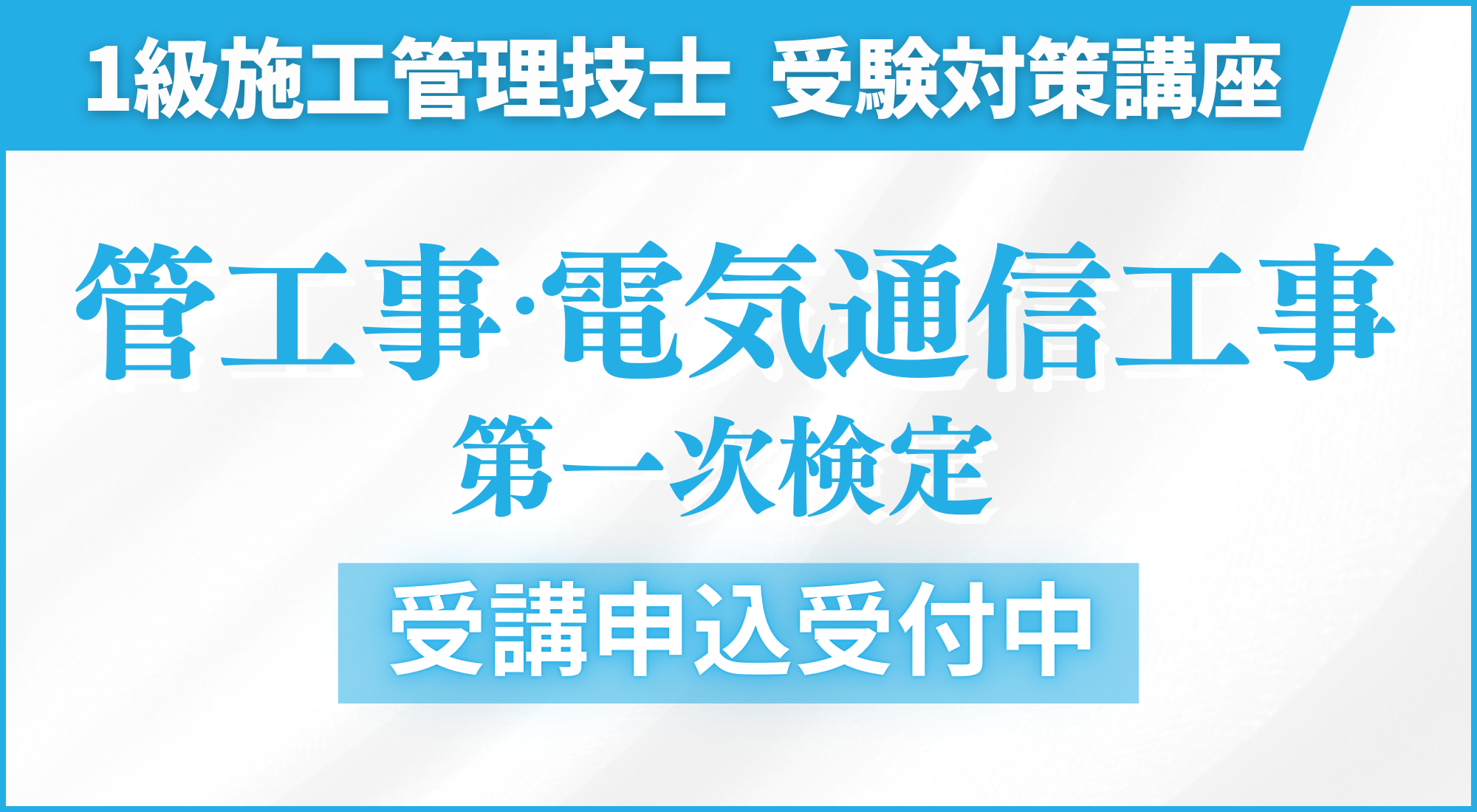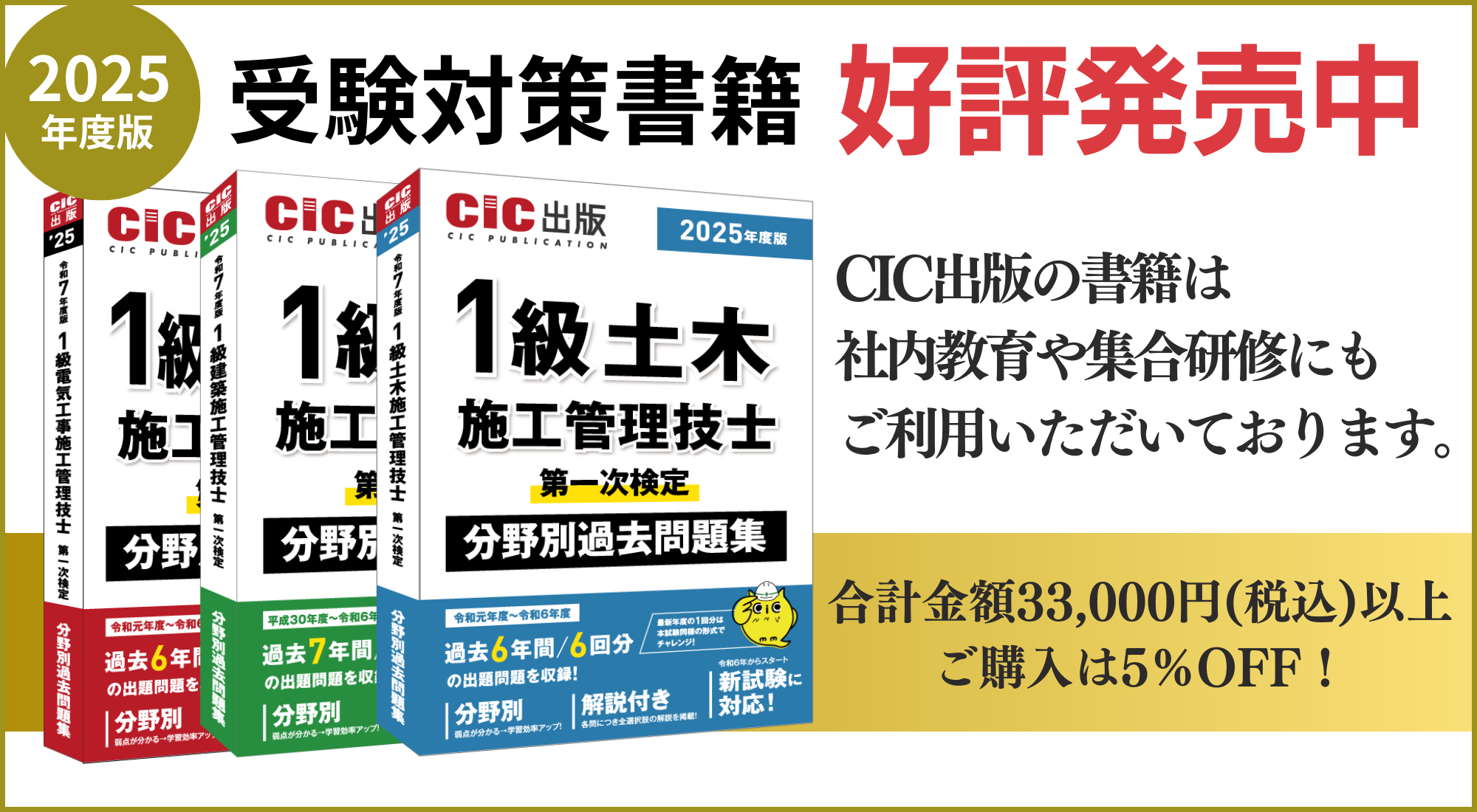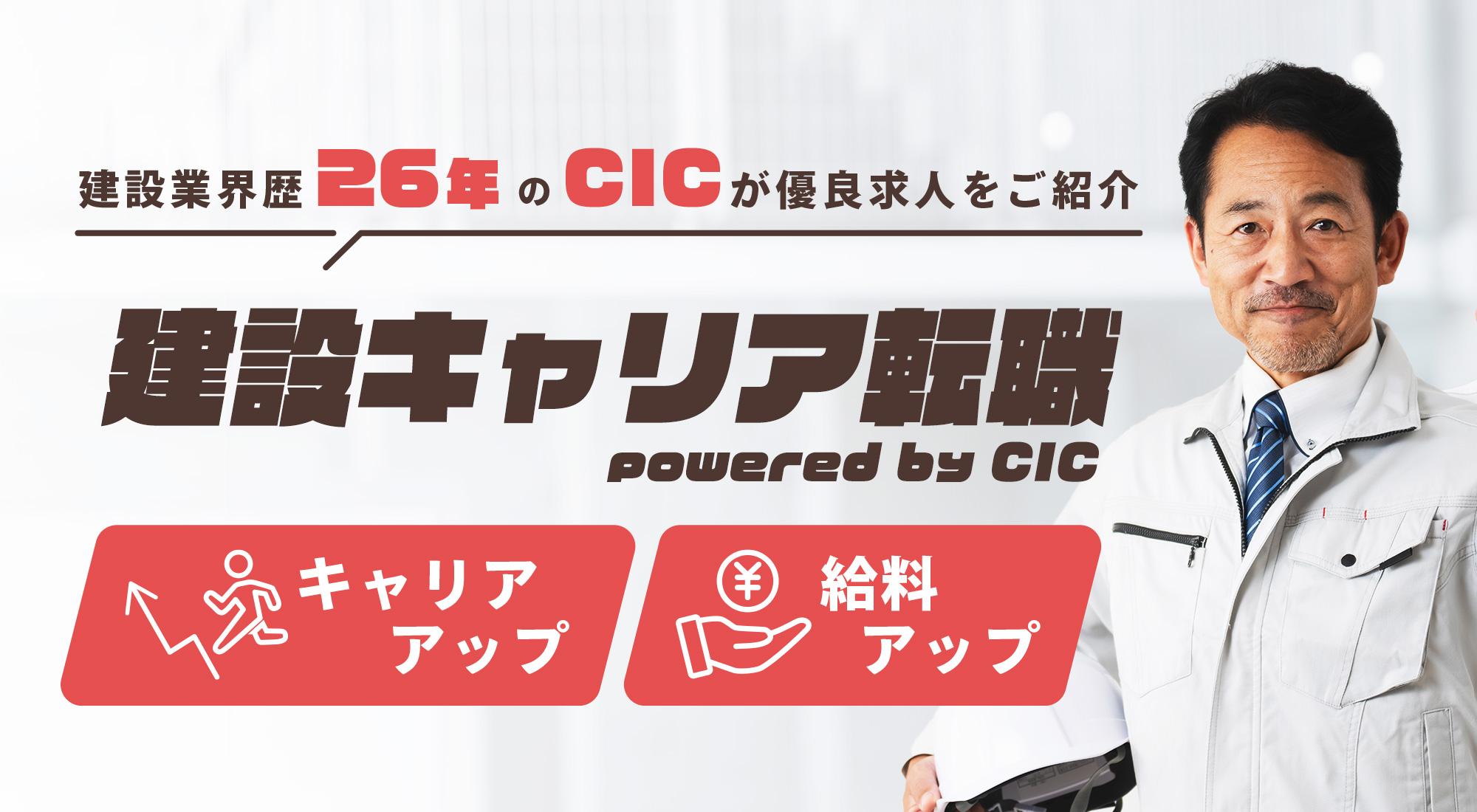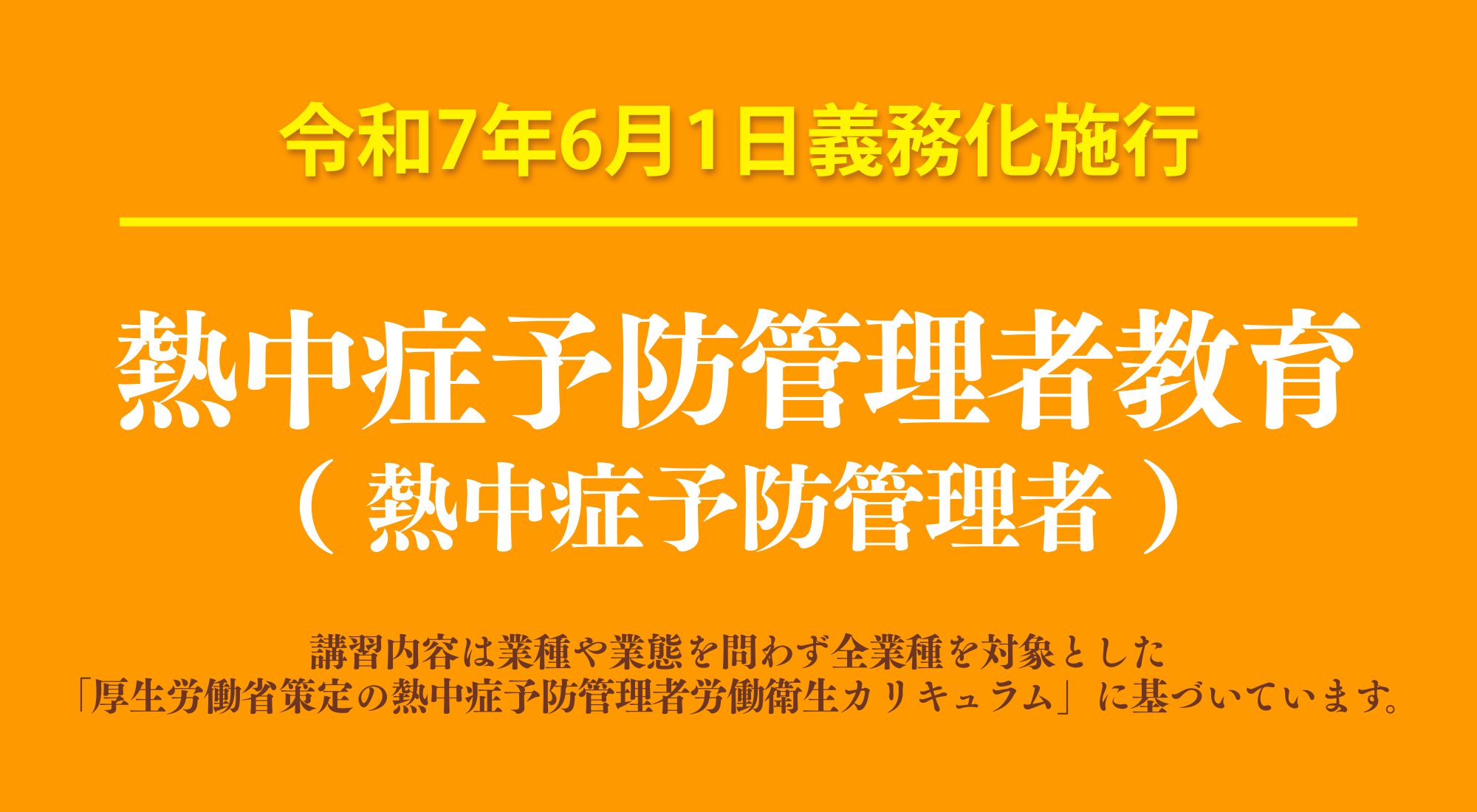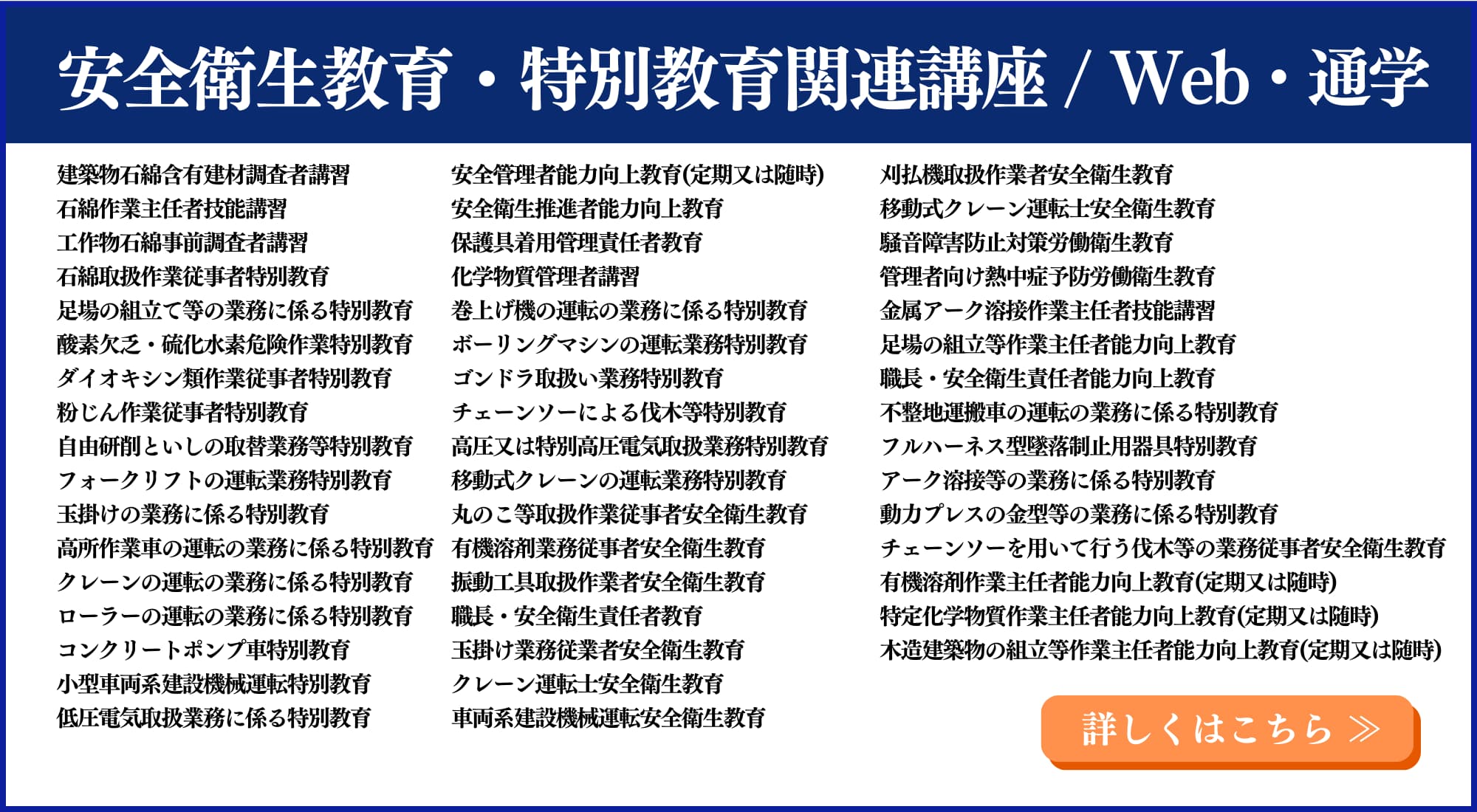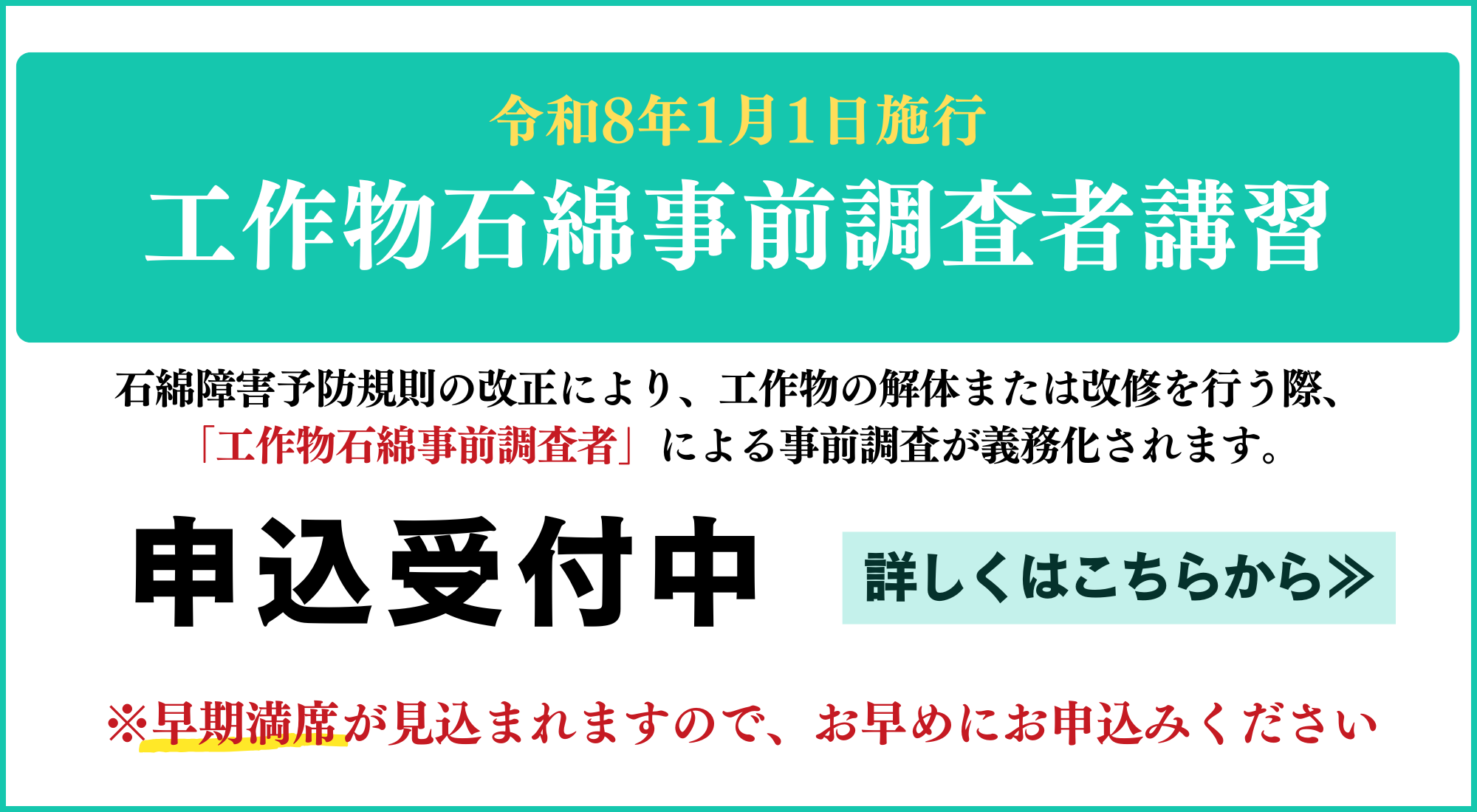施工管理技士合格をアシスト
建設業特化の受験対策
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- 小型ボイラー取扱業務特別教育
- ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
- ロープ高所作業者特別教育
- テールゲートリフター特別教育
- タイヤ空気充てん作業特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
- チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
- 雇入れ時安全衛生教育
- 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育
- フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 衛生管理者能力向上教育(初任時)
- プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
インストラクター養成講座
その他教育
設備関連資格
建設・職場衛生関連資格
お知らせ・講座情報
-
2025.05.23
5月25日(日)は第二種電気工事士〔上期:学科(筆記方式)〕の試験日です
- NEW
- お知らせ
- 電気工事士
-
2025.05.22
第一種電気工事士〔上期:学科試験〕 合格発表(令和7年度試験)
- NEW
- 講座情報
- お知らせ
- 電気工事士
-
2025.05.19
【タイヤ空気充てん作業特別教育】新規開講のお知らせ【Web講座】
- NEW
- お知らせ
- 講座情報
- タイヤ空気充てん作業特別教育
-
2025.05.14
【プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)】新規開講のお知らせ【Web講座】
- NEW
- 講座情報
- お知らせ
- プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
-
2025.05.12
【施工管理者等足場点検実務者研修】新規開講のお知らせ【Web講座】
- NEW
- 講座情報
- お知らせ
- 施工管理者等足場点検実務者研修
1分でわかるCIC資格講座の特徴
CIC開設26年。個人のかたはもちろん、業界リーディングカンパニーをはじめ
企業からの一括受講も多数。信頼の実績。

短期集中型の講習会だから
仕事に支障をきたさず
参加できた

自分の都合に合わせた
映像講義で
無理なく学習

本番でも施工経験記述に
不安を感じることなく
挑めた