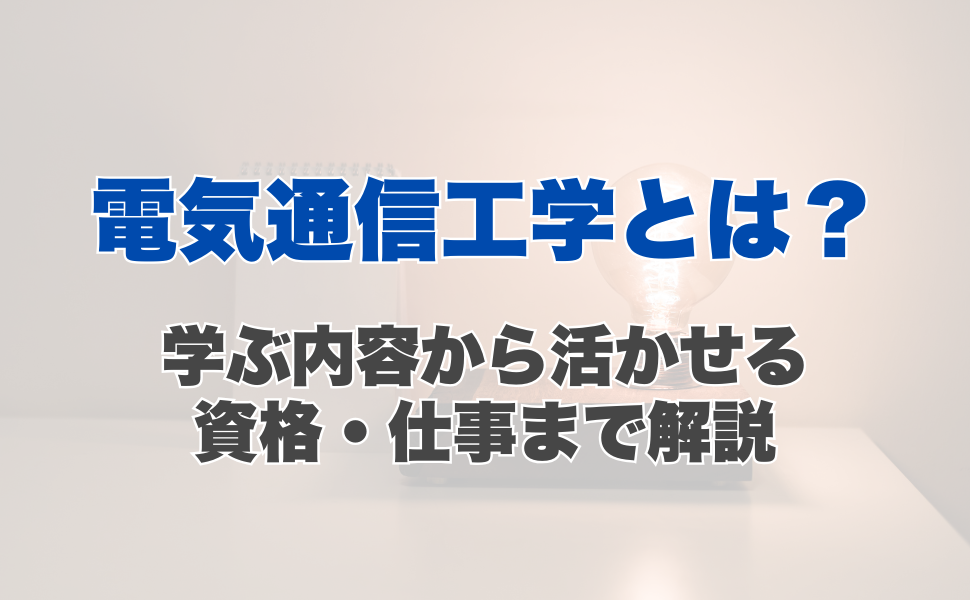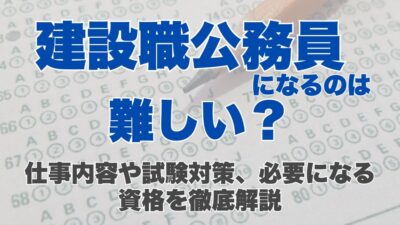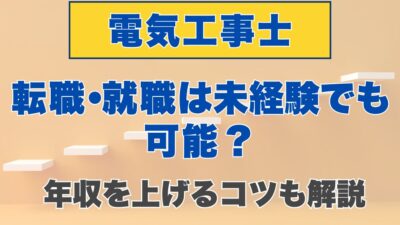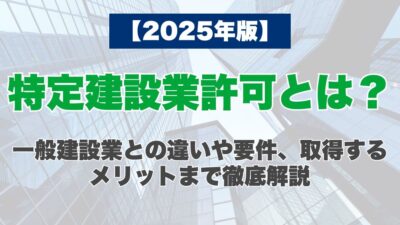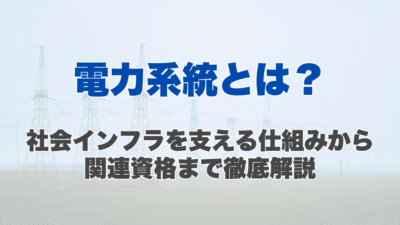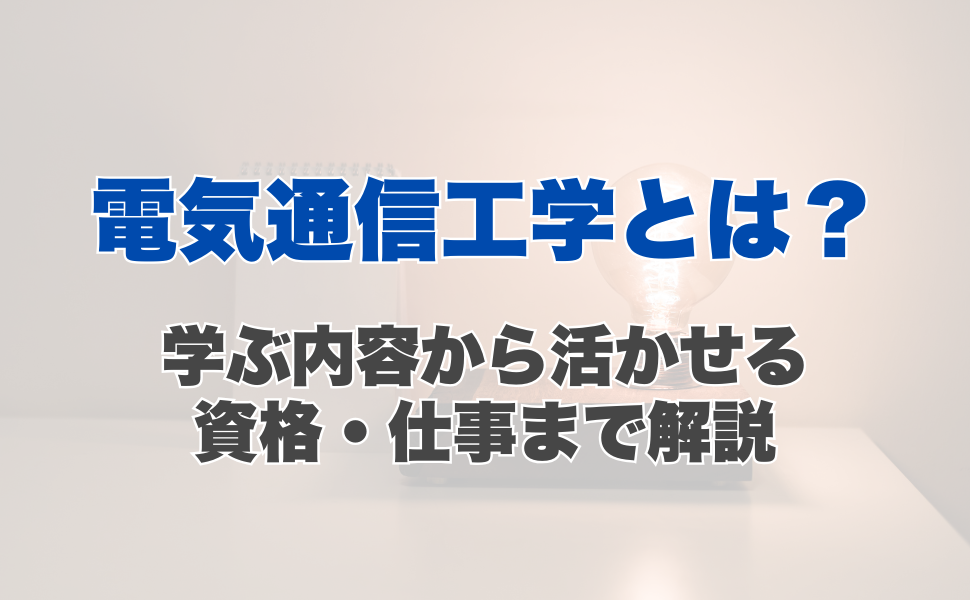
電気通信工学は、スマートフォンやインターネットなど、私たちの生活に欠かせない通信技術を支える重要な分野のことです。現在、情報社会の発展に伴って、電気通信工学の知識を持つ技術者の需要は年々高まっています。
中でも建設業界では、5G基地局の整備やデータセンターの建設など、通信インフラ構築において電気通信工学の専門知識がより重要となっている傾向です。
この記事では、電気通信工学の基礎知識から建設業界での活用方法、さらに電気通信工事施工管理技士をはじめとする関連資格まで詳しく解説します。電気通信工事の業界従事をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。



電気通信工学とは?現代社会に不可欠な情報伝達の科学

電気通信工学は、現代の情報化社会を支えるための基盤ともいえる技術です。私たちが日常的に使用するあらゆる通信サービスの背後には、電気通信工学の理論と技術が存在しています。
まずは、電気通信工学の基本的な概要と、混同されやすいほかの工学分野との違いについて解説します。
電気通信工学の概要
電気通信工学とは、電気信号を用いて情報を遠隔地に正確かつ効率的に伝達するための技術や理論を追及する分野のことです。私たちの身の回りにあるスマートフォン・インターネット・テレビ放送・GPS・Wi-Fiなど、あらゆる通信サービスが電気通信工学の内容をもとに実現しています。
電気通信工学の技術体系は、大きく以下の3つの要素に分類されます。
| 送信技術 |
情報を電気信号に変換して送り出す技術 |
| 伝送技術 |
光ファイバーや電波などの伝送路を介して情報を運ぶ技術 |
| 受信技術 |
送られてきた電気信号を元の情報に復元する技術 |
上記の技術がスムーズに連携することで、高速かつ大容量の情報伝達が可能となっています。現代・今後の社会では、IoT機器の普及やAI技術の発展、メタバースの実現などの観点からも電気通信工学の重要性が計り知れません。
今後も成長が見込まれるだけでなく、技術者の重要性が高まる業界といえるでしょう。
電気通信工学と電気工学・情報工学との違い
電気通信工学と関連する分野には、電気工学や情報工学が挙げられます。それぞれの分野の関連性は高いものの、扱う対象や目的において違いがあります。これらの違いを理解することで、各分野の特徴がより詳細に把握できるでしょう。
以下の表は、各工学の違いをまとめたものです。
| 工学 |
概要 |
扱うもの |
| 電気工学 |
エネルギーとしての電気を扱う分野。 |
発電所での電力生成や送電線による電力供給、モーターや変圧器などの電気機器に関して扱う。 |
| 情報工学 |
技術開発を主な目的とする分野。 |
プログラミング言語、データベース、人工知能、機械学習などを扱う。 |
| 電気通信工学 |
情報を電気信号として「伝える」ことに特化した分野。情報を確実に目的地まで届けることが主な目的となっている。 |
無線通信、光通信、ネットワーク技術などを扱う。 |
とはいえ、近年のIoT機器やスマートデバイスの開発では、これら3分野の技術が融合しつつあります。そのため、分野の境界は徐々に曖昧になりつつある傾向です。
建設業界における電気通信工学の役割

先ほど、電気通信工学の基本的な概要をご紹介しました。建設業界において、電気通信工学の知識は通信インフラの構築に不可欠です。5Gネットワークの整備やスマートシティの実現に向けて、電気通信工学の専門知識を持つ技術者の需要は高まっています。
続いて、建設業界で電気通信工学がどのような役割を担っているのか具体的にみていきましょう。
社会を支える通信インフラ工事とは?
電気通信工学の知識が最も活かされる建設分野は、通信インフラ工事です。
通信インフラは現代社会のライフラインとして、電気・ガス・水道と同等以上の重要性を持っており、具体的な工事として携帯電話の基地局設置工事などがあります。
現在であれば、5Gサービスの展開に伴って多くの基地局が必要となっており、建物の屋上や鉄塔への設置工事が全国で進められています。また、光ファイバーケーブルの敷設工事も重要な工事の1つです。地下管路や電柱を利用して、各家庭や企業まで高速通信を可能にする光回線を張り巡らせています。
このように、電気通信工事は単に機器を設置するだけでなく、電波の伝搬特性や干渉対策など高度な専門知識が求められます。そのため、電気通信に関する知識・技術力を有した技術者の付加価値が高まっているというわけです。
オフィスビルやデータセンターにおける通信設備工事
電気通信工学は、大規模な通信インフラだけでなく、オフィスビルやデータセンターなどの建物内の通信設備工事においても大切です。
オフィスビルでは、LAN配線・ビジネスフォン・構内放送・防犯カメラ・入退室管理システムの工事が含まれます。特にデータセンターの構築では、配線作業に加えて、冗長性のある通信経路設計やセキュリティ対策としての通信暗号化、不正アクセス防止システムの導入などで、電気通信に関する高度な知識が求められます。
このような工事の役割を担うのも電気通信工事の技術者の特徴です。
電気通信工学の知識を活かせる仕事とキャリアパス

電気通信工学の知識は、さまざまな職種で活用できます。特に建設業界では、通信設備工事の需要増加に伴って専門資格を持つ技術者が求められている傾向です。
電気通信工学の知識を活かせる資格・仕事に関しては、主に以下の3つが挙げられます。
- 電気通信工事施工管理技士
- 工事担任者
- 電気通信主任技術者
ここでは、それぞれの資格・仕事について解説していきます。
電気通信工事施工管理技士
電気通信工事施工管理技士は、電気通信工学の知識を建設現場で活かせる国家資格です。
資格保有者は、電気通信工事における施工計画・工程管理・品質管理・安全管理などの重要業務に従事できます。
資格は1級と2級に分類されており、1級は監理技術者、2級は主任技術者として活躍できるのも特徴です。電気通信工事施工管理技士は、5G基地局整備やデータセンター建設等に伴って需要が高まっており、転職市場で有利な武器となるでしょう。

工事担任者
工事担任者は、端末設備やデジタル伝送路設備の接続工事を行うための国家資格です。
この資格は以下5つに分類されており、それぞれで扱える設備の規模や種類が異なります。
- 第一級アナログ通信
- 第二級アナログ通信
- 第一級デジタル通信
- 第二級デジタル通信
- 総合通信
上記の中でも総合通信は、アナログ・デジタル両方の設備を制限なく扱えるのが特徴です。実際の業務でみても、電話システムやインターネット回線、データ通信設備の設置・保守などを担当し、光ファイバー回線の普及によって活躍の場も広がっています。
電気通信工事施工管理技士の受験資格要件の一部でもあるため、キャリアアップにもつながりやすい資格・仕事といえるでしょう。

電気通信主任技術者
電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事・維持・運用の監督を担う国家資格です。伝送交換主任技術者と線路主任技術者の2種類があり、通信インフラの安定運用に不可欠な存在といえます。
業務内容は設備の保守点検やトラブル対応、新規設備導入時の技術検証や作業員への技術指導、行政対応など幅広いのが特徴です。通信事業者には有資格者の選任が義務付けられている関係から、資格・仕事の需要は安定しています。
まとめ

電気通信工学は、現代の情報化社会を支える基盤の技術として、重要性が今もなお高まっています。実際、スマートフォンやインターネットなど、私たちの生活に欠かせない通信サービスの実現には、電気通信工学の理論と技術が必要不可欠です。
建設業界においては、5G基地局の整備や光ファイバー網の拡充、データセンターの建設などで通信インフラの需要が高まっています。これらの工事には、電気通信工学の専門知識を持つ技術者が必要不可欠であり、有資格者の付加価値も高まっているというわけです。
具体的には、電気通信工事施工管理技士・工事担任者・電気通信主任技術者といった国家資格を取得することで、電気通信工学の知識・技術力を証明できます。そのため、建設業界での活躍を目指す方でも、これらの資格を取得することでより付加価値を高めてキャリアアップを目指せるでしょう。
CIC日本建設情報センターでは、工事担任者や電気通信工事施工管理技士の受験者に向けたWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら効率的に学べる内容になっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。