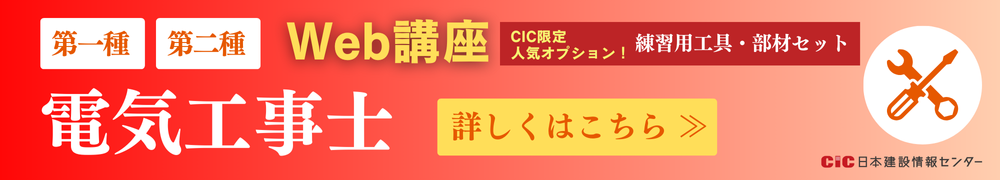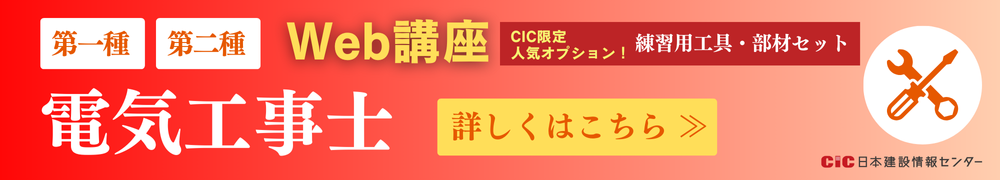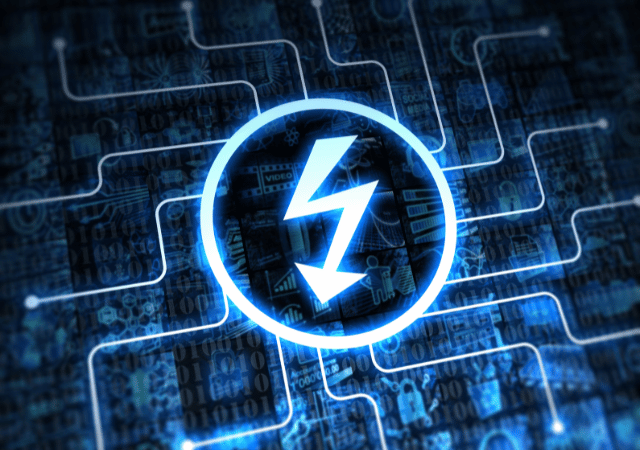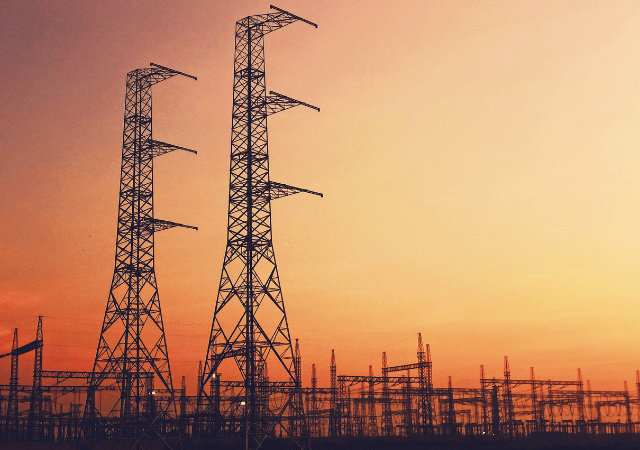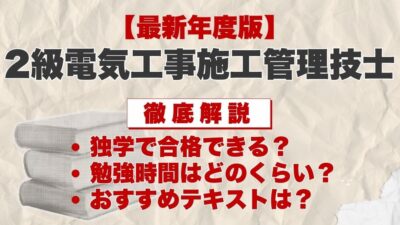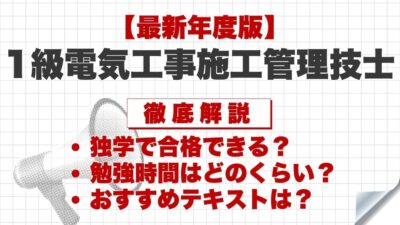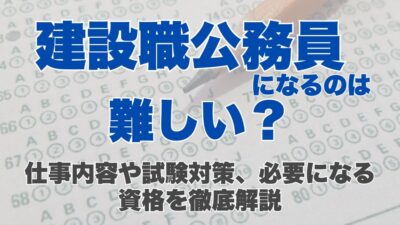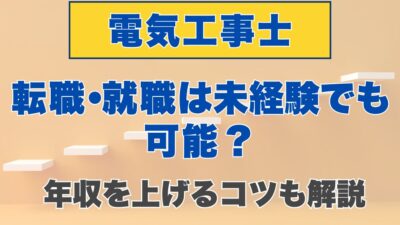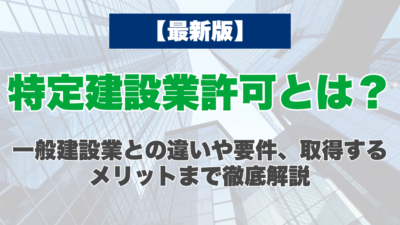電気系の資格試験では、電気工学と呼ばれる分野の問題が多く出題されます。電気工学とは、電気や磁気、光(電磁波)が持つエネルギーや情報を、社会の役に立つ「かたち」に変換し、応用するための技術を研究する学問分野のことです。
スマートフォン・インターネット・AI・エネルギーなど、現代社会を形作ったり重要性の高いテーマとして取り上げられたりするテクノロジーと電気工学は、密接した関係を有します。極めて影響する範囲の広い学問ですが、電気系資格ではエネルギーなどを中心に学習するため、どんな分野があるのか勉強方法とセットで把握しておくと良いでしょう。
この記事では、電気工学の概要や各分野の詳細について解説していきます。関連する資格や勉強方法などもご紹介しますので、「電気工学って具体的に何を学ぶの?」と気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
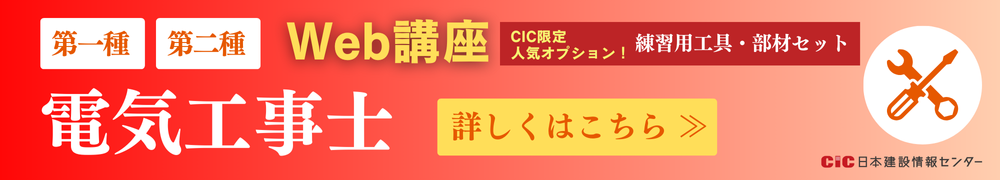

電気工学は?社会に不可欠なエネルギーと情報を学ぶ学問
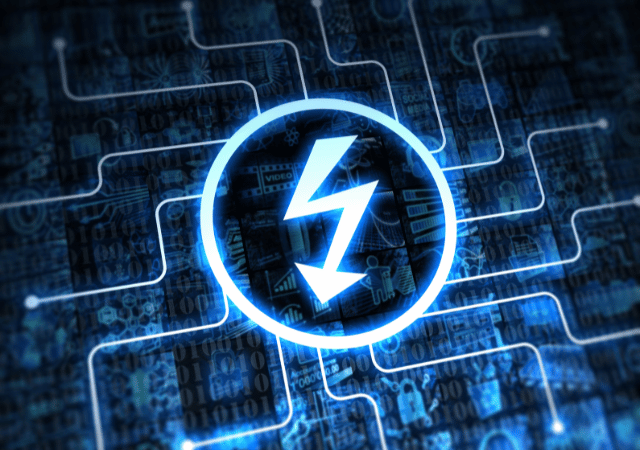
電気工学とは、電気や磁気、光(電磁波)が持つエネルギーや情報を、社会の役に立つ「かたち」に変換し、応用するための技術を研究する学問分野のことです。単なる「電気回路」のような分野に留まらず、非常に広い範囲で影響を及ぼします。
電気工学は、主に2つの内容に分けられます。
| エネルギーとしての電気工学 |
発電所で作られた電気を、工場や家庭に安定して届け、モーターや照明といった「動力」や「光」として利用するための技術。
(例:電力システム、パワーエレクトロニクス)
|
| 情報としての電気工学 |
電気信号を使って情報を「記録」「伝達」「処理」するための技術。半導体やコンピュータ、通信システムなどが当てはまる。
(例:電子回路、情報通信システム、制御システム)
|
現代社会におけるインフラの中でも「エネルギー」と「情報」に影響を及ぼす学問です。このことからも、非常に重要性の高い学問であることが分かります。
次項からは、どんな分野があるのかどのような資格で登場するのかなどを詳しくみていきましょう。
電気工学を構成する4つの主要分野
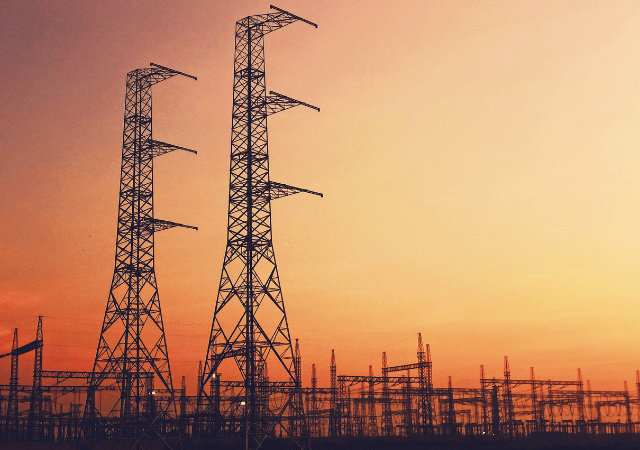
電気工学は、扱う内容によって大きく以下4つの専門分野に分かれています。
- エネルギー・電力分野
- 電子・デバイス分野
- 情報・通信分野
- 制御・システム分野
ここからは、それぞれがどんな分野なのかを詳しく解説します。
分野1. エネルギー・電力分野
エネルギー・電力分野は、電気を作る・送る・動かすための技術を扱う分野です。発電所(火力・水力・原子力・再生可能エネルギー)で電気を創り出し、それを送電網を通じて効率よく届け、建物の照明をつけたり工場の大規模なモーターを動かしたりなど、社会の電力インフラそのものを支えています。
近年では、太陽光発電や風力発電などの電源を安定して電力網に繋いで最適化していくための「スマートグリッド」や、電気自動車(EV)や産業用ロボットなどにも影響する「パワーエレクトロニクス」技術などが注目されています。
分野2. 電子・デバイス分野
電子・デバイス分野は、電気を操るための超小型の道具(デバイス)を作る分野です。電気工学で得てきた成果などを手のひらに収まるほどの製品に凝縮させる技術で、代表的なものに「半導体」が挙げられます。
また、CPUやメモリといった集積回路(LSI)の設計・製造技術は、スマートフォンやパソコンの性能を決定づけるものです。ほかにも、LEDやレーザー、センサーなど、電気と光を相互に変換するデバイス(光デバイス)もこの分野に含まれます。
分野3. 情報・通信分野
情報・通信分野は、電気や光を使って情報を遠くまで速く・正確に届ける技術を扱う分野です。私たちが日常的に利用するインターネットやスマートフォン、テレビ放送、GPSなどは、情報・通信分野の技術によって成り立っています。
現在であれば、光ファイバーによる超高速の大容量通信や、5Gおよび研究開発段階にある次世代の6Gといった移動体通信システムの開発、データを効率的に圧縮・伝送するための信号処理、情報を守るための暗号技術など、現代の情報化社会における重要な部分を担っています。
分野4. 制御・システム分野
制御・システム分野は、機械やシステムを人間の思い通りに賢く・自動で動かすための分野です。工場のロボットアームが製品を正確に掴んだり、エアコンが室温を一定に保ったりするのは、「フィードバック制御」と呼ばれる制御技術に基づくためです。
フィードバック制御は、現状をセンサーで把握して目標との差を計算し、モーターなどを動かして目標に近づける制御技術のことを指します。近年では、AI(人工知能)と制御理論を組み合わせ、より複雑で予測困難な状況に対応する研究が活発化しています。
電気工学の有する課題や将来性

電気工学は、単に既存の技術を支えるだけでなく、現代社会が直面する大きな課題を解決して社会をより良くしていくためのポイントを担っています。例えば、以下のような点で将来性があるといえるでしょう。
| 脱炭素社会の実現 |
太陽光や風力といった不安定な再生可能エネルギーを、社会の主要な電力源として活用するためには、高度な電力制御技術(スマートグリッド、パワーエレクトロニクス)が不可欠です。電気工学は、地球環境問題解決の重要要素となる技術。 |
| スマート社会(Society 5.0)の実現 |
あらゆるモノがインターネットに繋がるIoTの世界では、膨大なデータを処理する半導体技術、データを瞬時に送る通信技術、そしてモノを賢く動かす制御技術が求められる。電気工学は、AIやIoTといった先端技術を社会に実装するための基盤となる。 |
今後、カーボンニュートラルの実現やAI・Iot技術の活用が注目されている中で、それらの技術の中心部分に位置する電気工学は非常に重要な学問といえます。
直接仕事で関わることは少ないかもしれませんが、学習しておくことで日々のニュースや発表の中で、どのように社会が変わるのか、仕事でどう活かせるのかなどをイメージしやすくなるでしょう。
電気工学に関連する電気系資格

電気工学に関連する電気系の資格としては、主に以下の3つあります。
- 電気工事士
- 電験三種(第三種電気主任技術者)
- 電気工事施工管理技士
それぞれの電気系資格について詳しくみていきましょう。
資格1. 電気工事士
電気工事士は、一般家庭から商業施設、製造工場に至るまで、様々な建物の電気設備工事に携わるための国家資格です。
資格は第二種・第一種の2つに区分されており、第二種は、住宅や小規模な店舗といった600V以下の低圧受電設備の工事を担当できます。第一種になると、第二種の業務範囲に加え、ビルや工場などで使用される高圧受電設備の工事も手がけることも可能です。
電気工事士の試験形式は学科と技能の2段階で構成されています。学科試験においては、電気工学の幅広い分野から出題され、電気回路学や電磁気学といった基礎理論はもちろん、電気機器の特性や配電に関しての問題など実践的な知識まで問われます。現場で求められる基礎的な知識と応用力が試される問題内容です。
また、受験資格や実務経験などの条件は設けておらず、誰でも受験が可能です。特に第二種は合格率が40〜60%程度で推移しており、電気工学の知識を実践に結びつける第一歩としておすすめの資格です。
CIC日本建設情報センターでは、第二種電気工事士試験対策の講座をご用意しています。効率的な内容で、モチベーションを維持しながら着実に合格を目指せる環境を整えていますので、ぜひご活用ください。
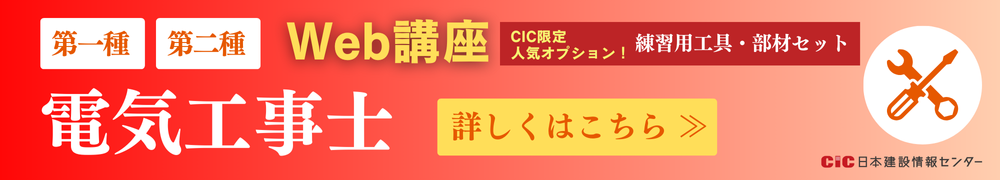
資格2. 電験三種(第三種電気主任技術者)
電験三種(第三種電気主任技術者)は、工場やビル、発電施設や変電施設などにおける電気設備の保守・管理を担うための国家資格です。5万ボルト未満の事業用電気工作物に関する保安業務を独占的に行える資格であることから、電気業界での需要は極めて高く、技術者としての市場価値を大きく高める資格となります。
電験三種は「理論」「電力」「機械」「法規」の4つの科目から構成されており、問題を解くためには電気工学の専門知識を体系的に習得していなければなりません。なかでも「理論」科目は、電気回路や電磁回路、制御系の知識など、電気工学の核心となる分野から多く出題されます。
合格率は10〜20%前後という狭き門ですが、科目別合格制度が採用されており、3年間で4科目すべてに合格すれば資格を取得できます。
資格3. 電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、電気工事における計画の立案から進捗管理、品質確保、安全対策に至るまで、工事全般のマネジメントを担うための国家資格です。
資格は1級・2級に分かれており、1級取得者は特定建設業における専任技術者または監理技術者として大型プロジェクトの指揮を担うことが可能です。2級取得者であっても、一般建設業の専任技術者または主任技術者として中小規模の工事現場を管理できます。
電気・建設業界において施工管理技士のニーズは継続的に高く、安定した高収入と将来的なキャリア発展が見込めます。電気業界でのキャリアを考えていく中で、ぜひとも取得しておきたい資格の1つといえるでしょう。
CIC日本建設情報センターでは、電気工事施工管理技士試験対策の講座をご用意しています。

電気工学・資格試験の学習方法

最後に、資格試験で合格するために電気工学をどのように学習するのがよいかご紹介します。主な学習方法としては、以下の3つです。
- 参考書などで基礎から学習する
- 動画やWebサイトを活用して学習する
- 資格のWeb講座を通して学習する
それぞれの内容について詳しく解説します。
方法1. 参考書などで基礎から学習する
参考書を用いた学習は、電気工学を体系的に身に付けられる方法です。初心者向けの入門書から始めて問題集で応用力を養うことで、段階的に学習できるでしょう。
また、図解やイラストが豊富な参考書・問題集であれば、難しい内容であっても視覚的に理解しやすく、自分のペースで何度も読み返してじっくり学習できます。
ただし、疑問点は自力で解決する必要があり、モチベーションの維持も自分の管理に依存するため、計画的な学習スケジュールを設定できるかどうかが大切です。
方法2. 動画やWebサイトを活用して学習する
現代ならではともいえる学習方法として、動画・Webサイトの活用があります。YouTubeやWebサイトを活用した学習であれば、視覚と聴覚の両方から情報を吸収できるだけでなく、実際の映像やアニメーションで直感的に理解可能です。
また、通勤時間やスキマ時間にスマートフォンで手軽に学習できるため、忙しい方でも継続しやすいのもメリットといえます。
ただし、コンテンツの信頼性にばらつきがあるため、信頼できる動画配信者を見極める必要があります。その点をクリアできれば、参考書と併用することで、効率よく理解を深められるでしょう。
方法3. 資格のWeb講座を通して学習する
資格取得を目標としたWeb講座を受講するのも、おすすめの方法です。Web講座は、プロ講師による体系的なカリキュラムで効率的に学習できる方法で、電気工事士や電験三種など、目標とする資格試験の合格に向けて集中して学習できる環境が整います。
また、必要な教材がすべて揃うだけでなく、出題傾向を踏まえた分析をもとに最短距離で合格を目指せるのがメリットです。質問サポートが受けられる講座も多く、疑問点をすぐに解決できるため、モチベーションを保ちながら合格を目指せます。
CIC日本建設情報センターでも、この記事でご紹介した電気工事士・電験三種・電気工事施工管理技士などのWeb講座を提供していますので、最短距離で合格を目指したい方はぜひご検討ください。
まとめ

電気工学とは、電気や磁気、光(電磁波)が持つエネルギーや情報を、社会の役に立つ「かたち」に変換し、応用するための技術を研究する学問分野のことです。エネルギー・電力、電子・デバイス、情報・通信、制御・システムの4つの主要分野から構成されています。
現在、電気工学は脱炭素社会やスマート社会の実現に不可欠な技術として、重要性を高めています。関連資格として電気工事士、電験三種、電気工事施工管理技士があり、これらの取得により専門性の高いキャリアを築けることでしょう。