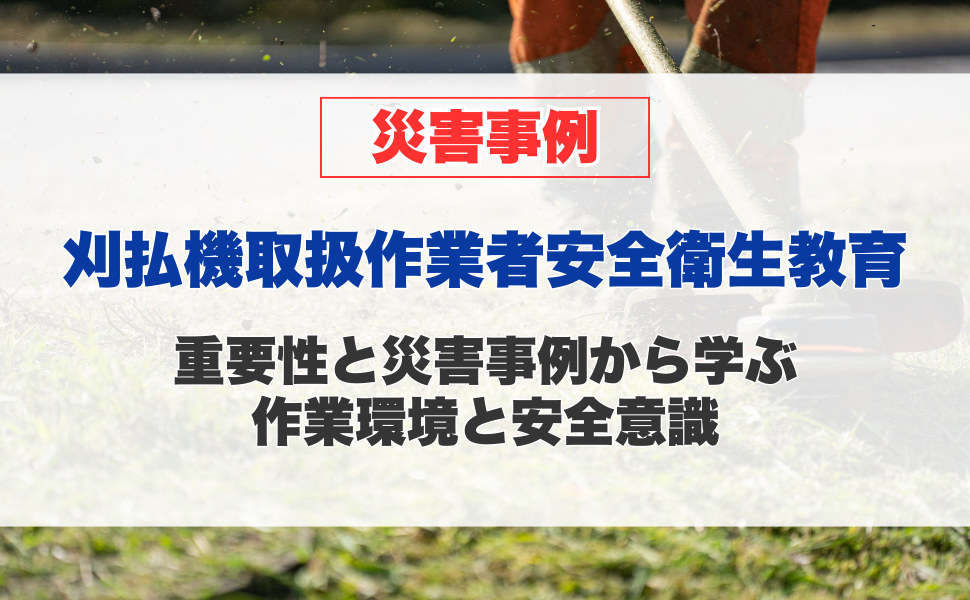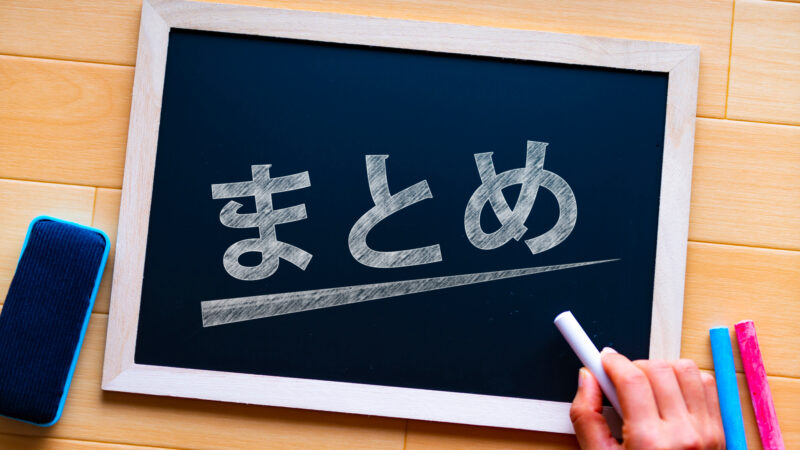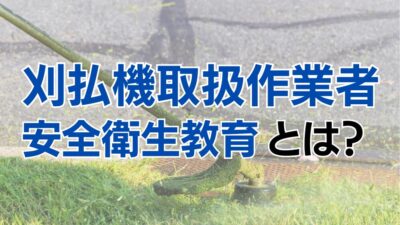刈払機とは、肩掛け式や背負い式の草刈機のことで、草や小径木を刈り取るために両手でハンドルを操作する小型の機械のことをいいます。狭い場所や障害物の多い場所での草刈りに適しており、家庭で使用する人も多いのではないでしょうか。
しかし、エンジンやモーターを動力源として高速回転する刃を使用するため、使い方を誤れば労働災害につながる危険があります。
今回は刈払機を使用した労働災害事例を安全意識の観点からご紹介します。刈払機を使用する事業者の方は必見です。
刈払機についての詳しい内容はこちらをご覧ください。