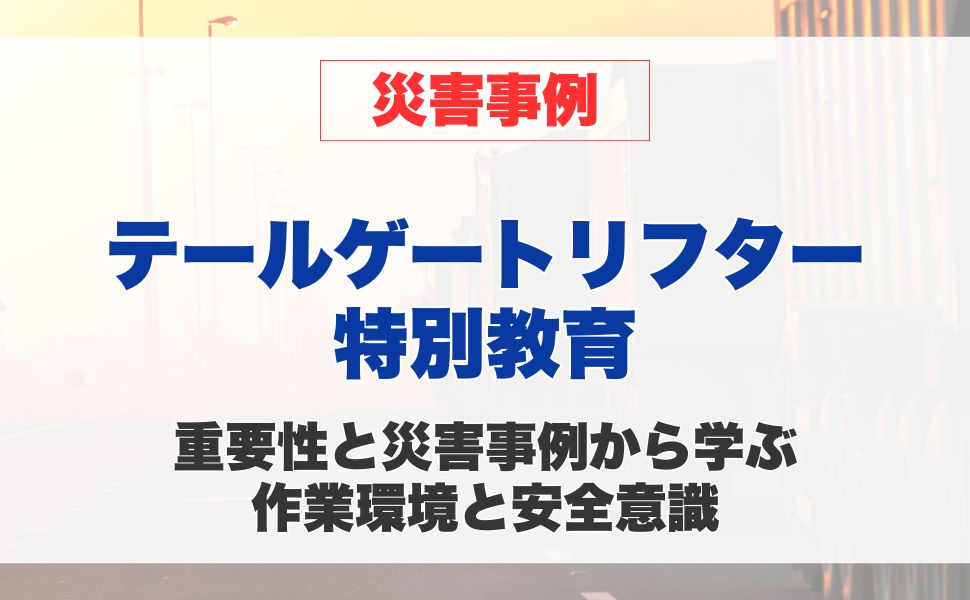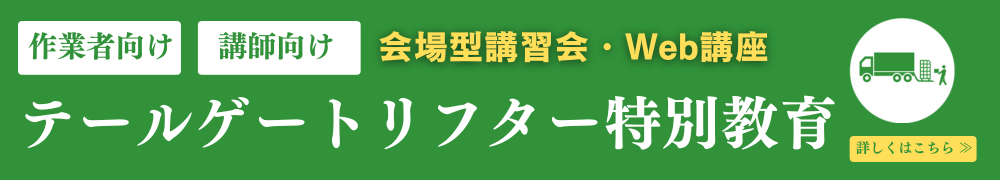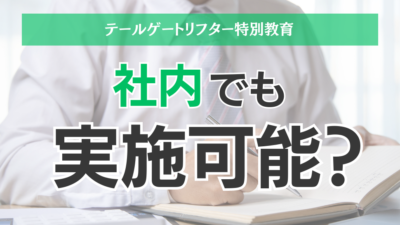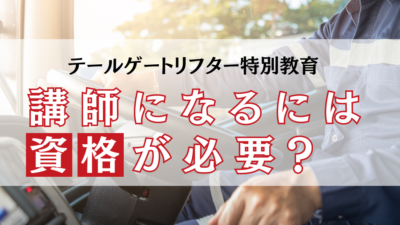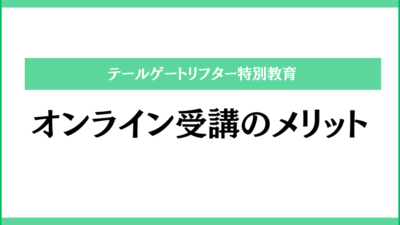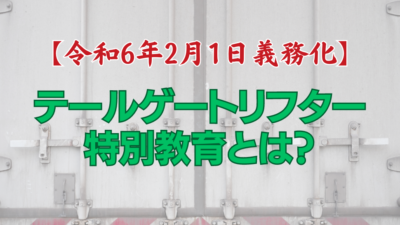テールゲートリフター特別教育の重要性

テールゲートリフター(Tailgate Lifter、以下TGL)は、貨物自動車の荷台と地面との間で荷物を昇降させるための装置で、物流業界や建築現場などで作業の省力化・効率化に貢献しています。しかしその一方で、操作を誤れば重大な災害を引き起こすリスクも伴い、過去にも多くの労働災害が発生しています。
労働安全衛生規則第36条では、TGLを使用する作業に従事する者に対して事業者が特別教育を実施する義務を明記しています。この教育では、装置の構造や機能、操作方法、関係法令、災害事例、緊急時の対応などについて、学科10時間以上のカリキュラムを通じて学びます。教育修了者には修了証が交付され、これは企業としての安全管理体制の一環でもあります。
教育を受けた作業者は、TGLのリスクを適切に理解し、災害を未然に防ぐための安全行動がとれるようになります。これは本人だけでなく、現場全体の安全を確保するうえでも非常に重要です。
テールゲートリフターに関する代表的な災害事例

ここでは、実際に発生したTGLによる災害の中から代表的な3つの事例を取り上げ、それぞれの状況・原因・結果・防止可能性について整理します。
事例1:「テールゲートリフターから地面に転落災害」
発生状況
被災者は、テールゲートリフター(以下TGL)上で200Lの工業用油入りドラム缶を荷台から降ろす作業中であった。ドラム缶を後ずさりしながら運んでいた際に、足元の確認が不十分なまま後方へ踏み外し、テールゲートリフターの昇降板からトラック後方に、頭部から転落し、落下したドラム缶で死亡する事故が発生した。
事故の原因
事故の原因は、被災者が後ろ向きの姿勢で作業していたことで視界が悪く、足元や後方の安全確認が不十分だったこと。TGLの昇降板が揺れやすく安定性に欠けていたことも一因と考えられます。
結果(けが・死亡・周囲への影響)
被災者は転落による頭部外傷を負い、意識不明に陥った。わずか78cm下の地上に頭部から転落し、倒れていた被災者の頭にドラム缶も落下し、死亡につながる重大災害となる事例である。
防げたポイント
後方や足元の安全を事前に確認していれば防ぐことができた。作業スペースが狭い状態での無理な運搬を避け、昇降板の揺れや不安定さを認識したうえで慎重に行動すべきであった。また、作業の高さに関わらず保護帽を正しく着用していれば、致命傷のリスクを軽減できたと考えられる。
出典:日野自動車 PR誌 2023年1月号
事例2:「昇降中の荷が傾き下敷きに」
発生状況
パレットに積載された資材をTGLでトラックの荷台に搬入する作業中、TGLのストッパーをしていなかった。ロールボックスパレットのキャスターが脱輪転落したため、支えようとした被災者が下敷きになり死亡する事故が発生した。
事故の原因
TGLのストッパーをしていなかったため、キャスターが脱輪転落した。また、TGLの傾きや地面との段差も確認されていなかった。
結果(けが・死亡・周囲への影響)
荷が直撃した被災者は、胸部を強く圧迫されて死亡した。現場では長時間の調査と作業中断が発生し、安全体制の見直しが求められた。
防げたポイント
TGLのストッパーを確実に行い、荷物の固定状況やバランスを事前に確認する。また、昇降前の荷の状態確認と作業手順の見直しが求められる。
出典:改正労働安全衛生規則等の概要について(貨物自動車関係) 厚生労働省
事例3:「テールゲートリフター昇降板端部からの転落・下敷き死亡災害」
発生状況
被災者は、TGLを使用してトラックの荷台から重量機器を降ろす作業を行っていた。昇降板の端部付近に立っていた被災者は、バランスを崩し機器と一緒に地面へ転落し、落下した機器の下敷きとなり重大な事故となった。
事故の原因
事故の原因は、被災者がTGLの昇降板端部に立っていたことでバランスを崩しやすい状況にあったこと、転落先に大型機器があり、下敷きという致命的な状況となったと推測される。
結果(けが・死亡・周囲への影響)
被災者は、転落時に重量機器の下敷きとなり、即死または即時に致命的な損傷を受けて死亡した。現場では緊急対応・調査が行われ、作業は長時間にわたり停止、以降の業務計画にも支障をきたした。
防げたポイント
作業区分の明確化、安全距離の確保、複数人による作業管理があれば、転落事故は未然に防ぐことができた。
出典:改正労働安全衛生規則等の概要について(貨物自動車関係) 厚生労働省
事故の背景・原因分析
これらの災害事例を分析すると、いずれも複数の要因が重なって発生している。教育・訓練の不足も事故の背景にあり、特別教育を受けていない作業者がTGLを操作していたケースでは、装置の危険性に対する認識が不十分であったことが災害の原因となっています。加えて、作業手順が形骸化しており、マニュアルや指示を守らず独自の方法で作業を行っていたことも原因のひとつです。
テールゲートリフターによる災害を防ぐための現場対策と教育

テールゲートリフターによる災害を未然に防ぐためには、教育と現場対策を同時に強化する必要があります。まず、特別教育は一度受けたら終わりではなく、現場や使用機器が変わった場合、あるいは新人が現場に入った場合には再度の教育やOJTが求められます。教育修了者のリストを作成し、管理者が常に確認できる状態を維持することが重要です。
現場には、誰でも理解できる操作マニュアルや安全手順を掲示し、見える化を図ることが推奨されます。文字だけでなく、写真や図を用いることで、新人や外国人労働者でも直感的に理解しやすくなります。
作業前には必ず危険予知活動を実施し、その日の作業内容に応じたリスクを洗い出して共有します。チェックリストの活用により、毎回の作業で安全確認を確実に行う文化を育てることができます。
また、TGL本体やリモコン、安全装置などの定期点検は欠かせません。異常が確認された場合には、即時に使用を停止し、上司や管理者に報告する体制を整えることが求められます。機器の状態を記録することで、トラブルの予兆を見逃さないようにすることも効果的です。
まとめ

テールゲートリフターは、物流や現場作業を効率化する一方で、誤った使い方をすれば重大な災害につながるリスクを持つ装置です。実際に発生した事故の多くは、確認不足や教育の未実施、作業手順の軽視といった「ヒューマンエラー」と呼ばれる要因によって引き起こされています。
しかし、これらは裏を返せば、正しい教育と日常的な確認作業、安全意識の共有によって防げるものであるともいえます。事業者は、法定教育の実施と管理だけでなく、職場全体に安全文化を根付かせる努力が求められます。
特別教育の受講、作業マニュアルの整備、安全確認の徹底、危険予知活動の継続、そして機器の保守点検。この一つひとつの取り組みが、現場の安全を支える土台となります。
TGLを扱うすべての職場において、これらの取り組みがあたりまえになるよう、安全対策の強化が今こそ求められています。
なお、CIC日本建設情報センターでは法定要件を満たした「テールゲートリフター特別教育」を実施しており、実践的なカリキュラムを通じて作業者の安全意識向上をサポートしています。義務化に対応した質の高い教育をお求めの企業様は、ぜひCICの特別教育の受講をご検討ください。