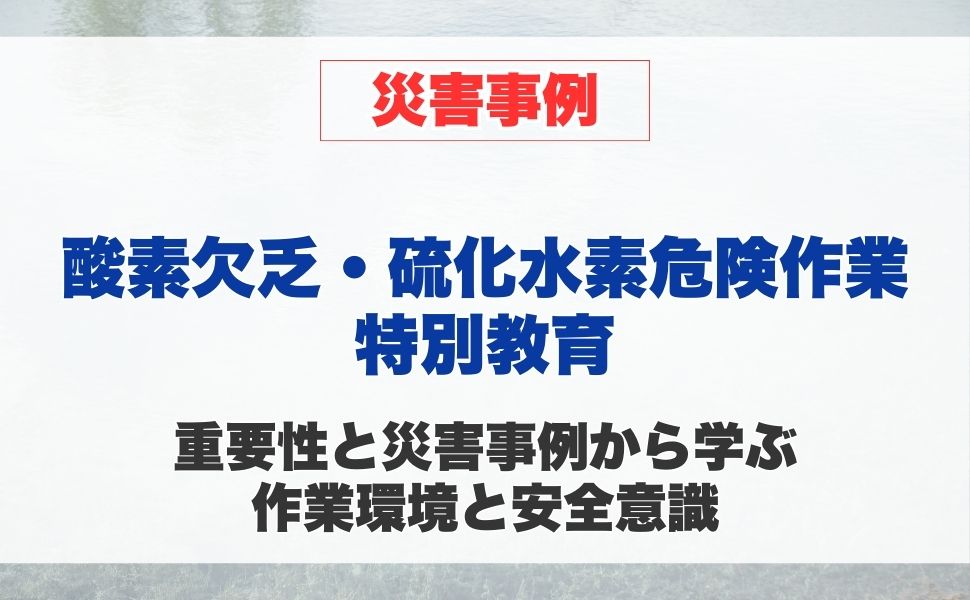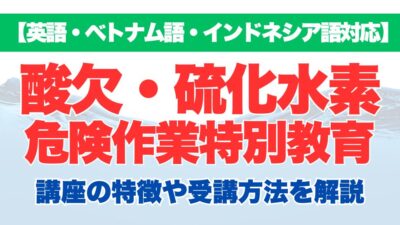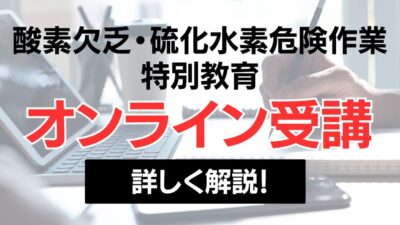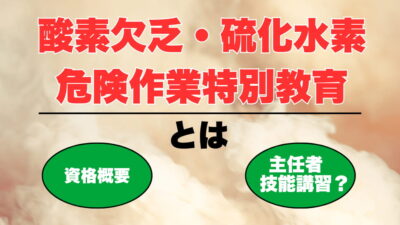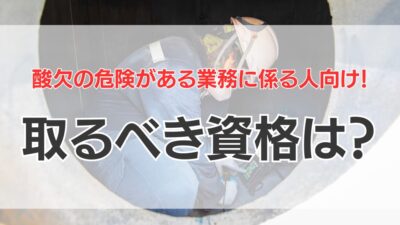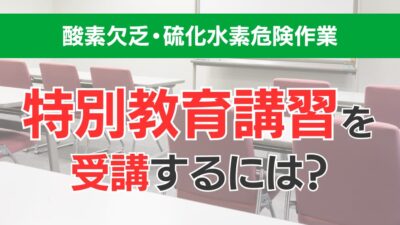酸素欠乏症や硫化水素中毒は、密閉空間や地下作業において発生する労働災害です。作業者の油断や判断ミスが命取りとなるだけでなく、救助の方法も誤ると二次災害に発展する恐れもあります。
そのため労働安全衛生法では、酸素欠乏危険場所や硫化水素が発生する恐れのある場所での作業に従事する労働者に対して酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が義務付けられています。ただし、特別教育がなぜ必要なのか、その重要性を十分に理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の重要性について詳しく解説します。実際に発生した災害事例から原因を分析し、労働災害を防止するために必要な対策もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。