発電設備は私たちの生活に欠かせない電力を生み出す重要な設備です。中でも、電気工事士などの電気系資格の取得を目指す方にとって、発電設備の基本的な仕組みや種類の理解は欠かせません。
この記事では、発電設備の基本構造から各種発電方式の特徴、さらに関連する電気資格について詳しく解説します。電気業界への従事を検討されている方や資格取得を目指す方にとって重要な内容をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年9月30日 更新日:2025年9月30日
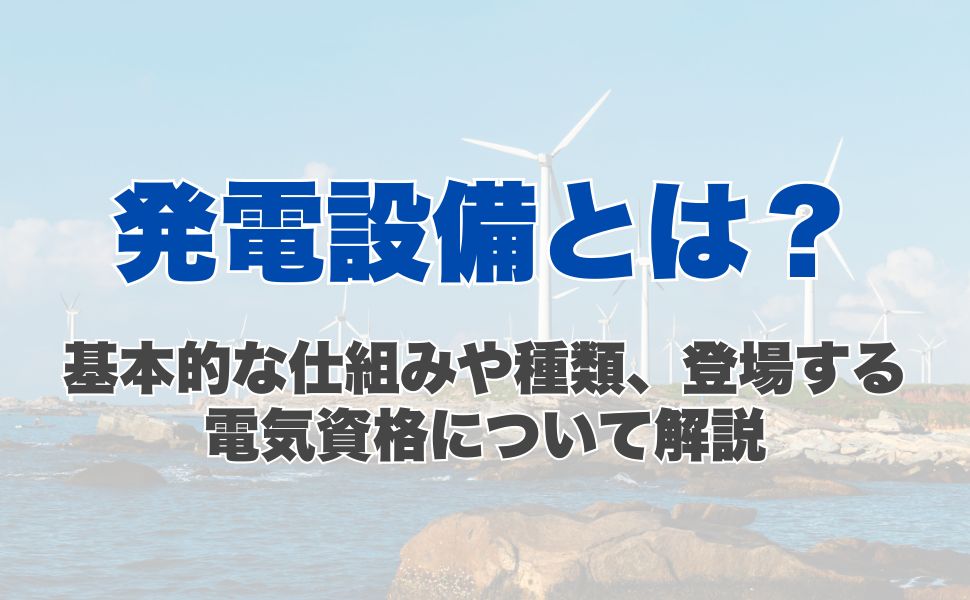
発電設備は私たちの生活に欠かせない電力を生み出す重要な設備です。中でも、電気工事士などの電気系資格の取得を目指す方にとって、発電設備の基本的な仕組みや種類の理解は欠かせません。
この記事では、発電設備の基本構造から各種発電方式の特徴、さらに関連する電気資格について詳しく解説します。電気業界への従事を検討されている方や資格取得を目指す方にとって重要な内容をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

発電設備とは、「何らかのエネルギーを利用して発電機を回し、電気を発生させる」設備のことです。発電機は、磁石の間でコイル(導線)を回転させると電気が発生する「電磁誘導」という現象を利用しています。
つまり、「いかにして効率よく発電機を回し続けるか」が重要であり、そのためのエネルギーとして水力や火力、原子力や太陽光など様々なものがあるというわけです。
発電設備は設置目的によって、「自家用発電設備」と「非常用発電設備」2つに分類されます。以下の表は、それぞれの違いをまとめたものです。
| 自家用発電設備 | 工場や病院、ビルなどが、自施設で使う電気をまかなうために設置する設備 |
|---|---|
| 非常用発電設備 | 災害などによる停電時に、最低限必要な電力を確保するために設置される設備。ディーゼルエンジンやガスタービンで発電機を動かすタイプが主流 |
自家用発電設備は、電力会社からの電力供給に加えて、またはそれに代わって電力を供給する役割を担います。一方、自家用発電設備は非常事態の発生によって停電した際でも、建物内に電気を供給するために設置されます。
発電設備は、様々な機器が組み合わさることで1つのシステムとして機能しています。ここでは、現在の日本で未だ多くの割合を占めている火力発電の発電システムを例に、主要な構成要素を解説します。以下の表は、火力発電の構成機器をまとめたものです。
| 構成機器 | 詳細 |
|---|---|
| ボイラー | 燃料を燃やし、水を熱して高温・高圧の蒸気をつくる巨大な「やかん」の役割を担う。 |
| タービン | ボイラーから送られてきた蒸気の力で高速回転する「羽根車」。この回転エネルギーが発電の源となる。 |
| 発電機 | タービンと直結しており、その回転エネルギーを「電磁誘導」の原理で電気エネルギーに変換する。発電所の心臓部分。 |
| 復水器 | タービンでの仕事を終えた蒸気を、海水などで冷却して水に戻す装置。この水を再びボイラーで利用することで、効率的なサイクルを生み出す。 |
| 送変電設備 | 発電された電気は、変圧器で超高電圧に変えられ、送電線を通じて各地に送られる。電圧を高くすることで、送電中のロスを少なくすることが可能。 |
火力発電は、燃料となる石油・石炭・LNG(液化天然ガス)をボイラーで燃やし、そこで生じた上記エネルギーをタービンに当てて回転させることで、タービンと直結した発電機が電気を生み出す仕組みです。その後、生み出された電気は、変圧器や送電線を通じて各建物まで送られます。
発電設備は、何らかのエネルギーを利用して発電機を回して電気を発生させる仕組みですが、火力発電であれば蒸気エネルギーというわけです。

電気工事士などの電気関連の資格では、様々な発電設備に関する問題が出題されます。ここでは、資格試験でも登場することの多い以下の発電設備について、それぞれの特徴と仕組みを詳しく解説します。
火力発電は、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料を燃焼させて発電する方式です。燃料の熱で水を沸騰させ、その蒸気でタービンを回して発電機を動かします。
日本の電力供給の約7割を担う主力電源であり、需要に応じた出力調整が比較的容易です。近年では発電効率を高めた「コンバインドサイクル発電」が主流となっています。
水力発電は、水の位置・運動エネルギーを利用しタービンを回して発電します。ダム式・流込み式・揚水式の3方式があり、それぞれ貯水・安定した発電、環境への配慮、蓄電池のような役割を担います。
水力発電は、二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーで、長期間発電可能です。電気工事士では、水車の種類や発電量の計算が出題されます。
原子力発電は、ウラン235の核分裂反応による熱で水を沸騰させ、その蒸気でタービンを回して発電します。火力発電と基本的な仕組みは同じですが、核燃料を使用する点が主な違いです。
日本では軽水炉が主流で、BWRとPWRの2種類があります。大量の電力を安定供給できる反面、放射性廃棄物の処理や安全性の確保が課題です。
太陽光発電は、太陽電池を用いて太陽光を直接電気に変換する発電方式です。回転機械を使わない点が特徴で、現在はシリコン系太陽電池が主流となっています。
システムは太陽電池モジュールやパワーコンディショナー等で構成され、発電された直流電力を交流に変換して電力系統に接続します。CO2排出のないクリーンなエネルギー源として、風力発電などと共に注目されています。
風力発電は、風の運動エネルギーを風車で回転エネルギーに変換し、発電機で電気を生み出す発電方式です。プロペラ型が一般的で、風速3〜4m/sで発電を開始し、25m/s程度で停止します。
また、風力発電には陸上と洋上があり、洋上は安定した強い風が得られます。風況に左右され出力が変動しやすいため、安定化させるために高い技術力が必要です。
そのほかの発電設備として、バイオマス発電や地熱発電などがあります。
バイオマス発電は、木材チップやもみ殻、家畜の糞尿などの生物由来の資源を燃料として発電する方式です。燃焼時に排出されるCO2は植物が成長過程で吸収したものとみなされ、カーボンニュートラルな発電方式として注目されています。
地熱発電は、地下の熱エネルギーを利用して発電する方式で、地下から取り出した蒸気や熱水でタービンを回します。日本は世界第3位の地熱資源量を有しており、24時間安定した発電ができるのも地熱発電の特徴です。
電気系の資格試験では、これらの再生可能エネルギーの特徴や系統連系時の課題などが出題されるケースもあります。
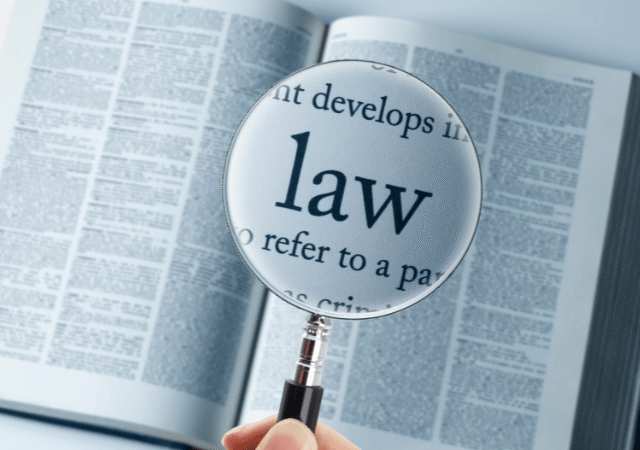
発電設備の設置や運用には、電気事業法をはじめとする各種法令の遵守が不可欠です。また、発電設備に関わる電気技術者には適切な資格が必要となります。
ここでは、発電設備に関する電気の法律と資格について詳しく解説します。
電気事業法は、電気の安全かつ安定的な供給を確保するための法律です。電気工作物は出力により、一般用(600V以下で系統連系する10kW未満未満の太陽光など)・自家用(50kW以上の太陽電池発電設備や高圧受電する建物など)・事業用(電力会社の発電所や変電所など)の3つに分類されます。
発電設備が問題として登場する電気の資格としては、以下のとおりです。
それぞれの資格について詳しくみていきましょう。
第一種電気工事士は、第二種電気工事士の範囲に加え、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事に従事できる国家資格です。発電設備における電気工事においても、第一種電気工事士の資格が必要になります。
筆記試験では発電設備の原理や特性、系統連系に関する問題が出題され、技能試験では実際の配線作業能力が問われます。近年の再生可能エネルギーの普及により、太陽光発電システムの施工技術を持つ第一種電気工事士の需要が高まっているため、取得することで技術者としての付加価値を高められるでしょう。
電験三種は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の保安監督業務に従事できる国家資格です。発電設備を含む自家用電気工作物の電気主任技術者として、電気技術者のキャリア形成において重要な位置を占めます。
特に、試験科目の1つである「電力」では、各種発電設備の原理・特性・運用方法に関する知識が多く問われます。火力発電の熱効率計算や水力発電の発電電力量計算、原子力発電の仕組みや再生可能エネルギーの系統連系など、実務に直結する内容が出題されるため、合格することで、より高度な知識を有していることを証明できるでしょう。
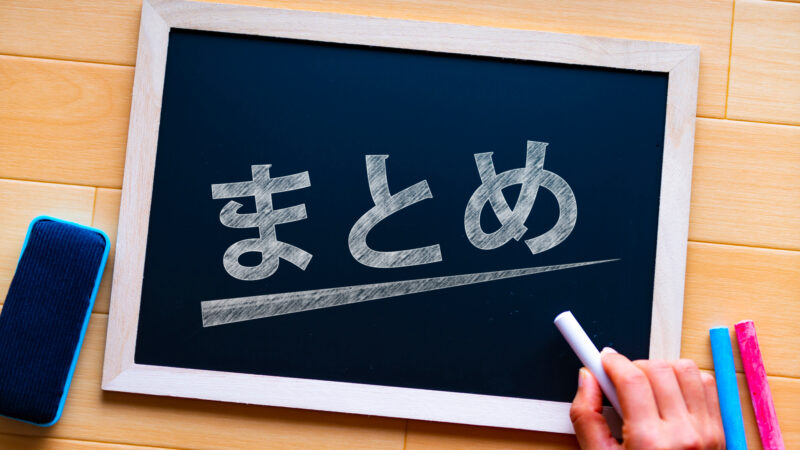
発電設備は、電磁誘導の原理に基づいて、多様なエネルギー源から電力を生み出す重要なインフラ設備です。現在、火力・水力・原子力に加え、太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電設備の重要性が増しています。
「第一種電気工事士」などの資格取得を目指す方にとって、発電設備の知識は必要不可欠です。各発電方式の特徴や仕組み、電気事業法などの関連法令を体系的に学ぶことで、試験合格や実務に役立ちます。
CIC日本建設情報センターでは、「電気工事士」を受験する方向けにWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら、効率的に学習できる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
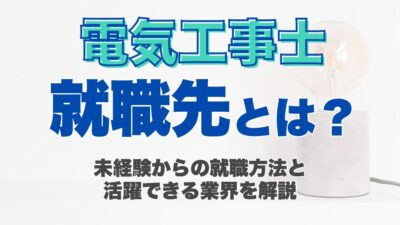
電気工事士の就職先とは?未経験からの就職方法と活躍できる業界を解説

電気工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士消防設備士工事担任者
電気系資格を徹底比較!活かせる仕事や取得難易度、将来性を解説

女性の電気工事士とは?活躍できる背景と資格取得のポイントを徹底解説
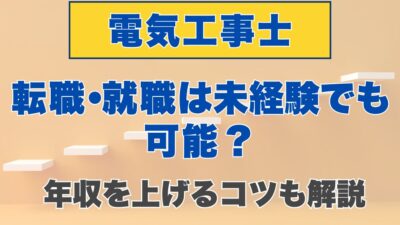
電気工事士への転職・就職は未経験でも可能?年収を上げるコツも解説
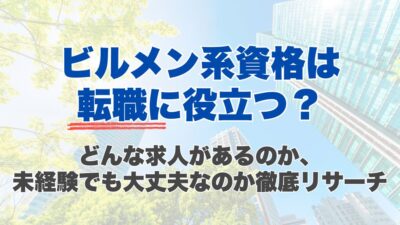
ビルメン系資格は転職に役立つ?どんな求人があるのか、未経験でも大丈夫なのか徹底リサーチ
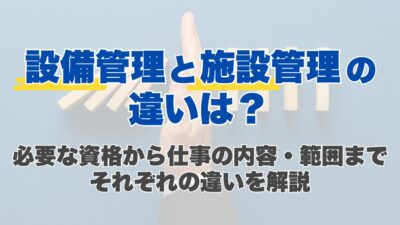
「設備」管理と「施設」管理の違いは?必要な資格から仕事の内容・範囲までそれぞれの違いを解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介

建設業の主な職種一覧!仕事内容や平均年収について解説 – 建設キャリア転職 –
