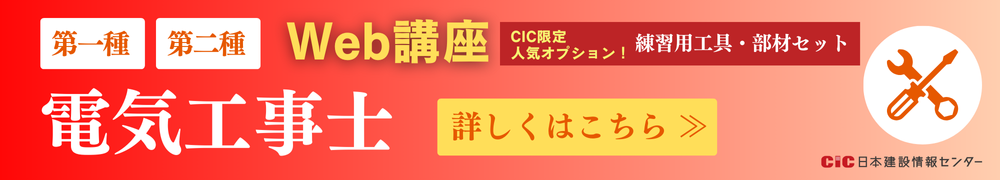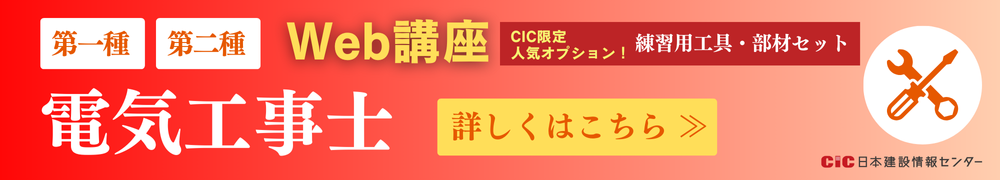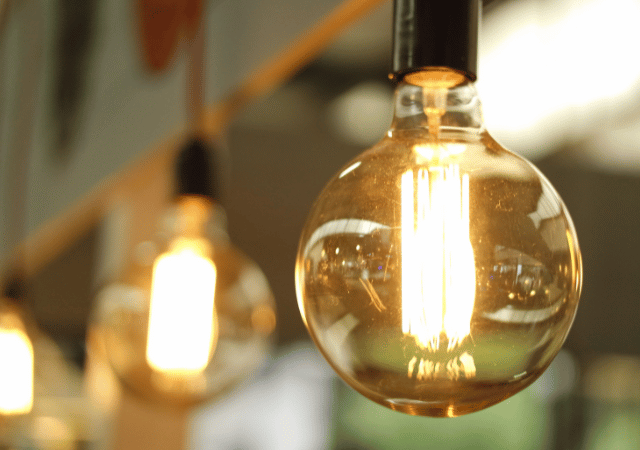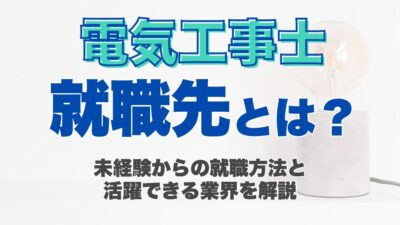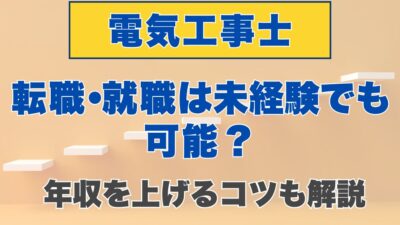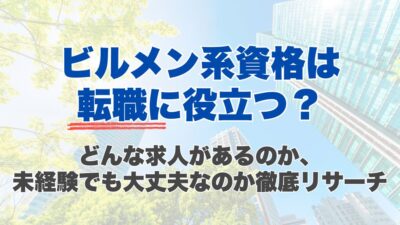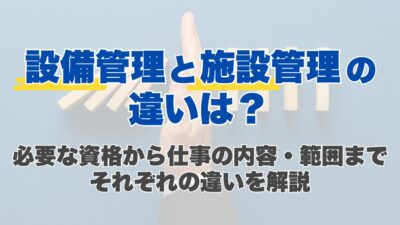建物の電気設備は、電力会社との「責任分界点」を境に管理責任が分かれており、需要家側の設備は「構内電気設備」と呼ばれています。構内電気設備は、受変電設備や配電設備、動力設備など多様な設備で構成され、受電・変圧・配電・保護管理という4つの重要な役割を担っているため、電気業界に従事していく中で理解が欠かせません。
この記事では、構内電気設備の基本的な仕組みから構成要素、関連する法律や資格まで、電気設備管理に必要な知識を詳しく解説します。電気の資格でよく出題されやすい内容なので、この機会にぜひ理解を深めてみてください。
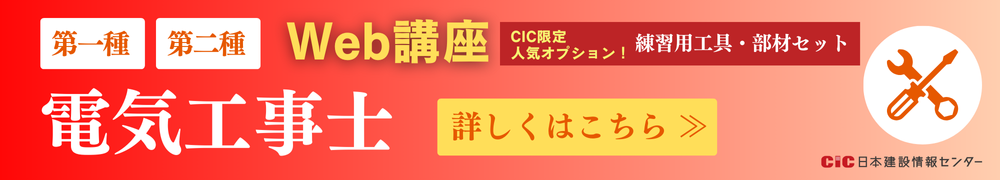
構内電気設備とは?電力会社の設備とどう違う?

構内電気設備とは、責任分界点から建物内におけるすべての電気設備を指す言葉です。受変電設備・配電設備・動力設備など多岐にわたる設備で構成されています。
まず、構内電気設備を理解する上で重要な要素が「責任分界点」です。
「責任分界点」とは、電気設備の維持・管理における「責任の境界線」を示す境界線のことで、電力会社側と施設側にわけられます。責任分界点を基準に、電力会社側が「供給設備」、需要家側の設備が「構内電気設備」に該当するわけです。
一般的に責任分界点は、電力会社の引込線と需要家の受電設備が接続される地点に設定されます。この境界を明確にすることで、事故や故障が発生した際の責任の所在が明らかになり、迅速な対応が可能となります。
また、供給側と需要家側は役割も違います。電力会社は発電所から変電所、配電線を経て責任分界点まで電気を供給する役割を担うのが特徴です。一方で需要家は責任分界点以降の設備について、自らの責任で管理・保守を行うため、発電・変電・配電には関わりません。違いを把握しておくことで、資格試験の勉強や仕事で従事する際の理解度が深まりやすくなるでしょう。
構内電気設備の主な役割

構内電気設備は、電力会社から供給される電気を建物内で安全かつ効率的に利用するために重要なものです。役割として、主に以下の4つがあります。
それぞれの内容についてみていきましょう。
役割1. 受電
電力会社の配電線から電気を受け取る最初の工程が受電です。一般的に、大規模施設では高圧(6,600V)、小規模施設では低圧(100Vまたは200V)で受電します。
受電設備には、引込開閉器や電力量計が含まれ、高圧受電の場合は断路器や遮断器などの保護装置も設置されます。これにより、異常時には瞬時に電気を遮断し、安定した電力供給を確保します。適切な受電設備の設置と管理は、電力供給の安定化に必要不可欠です。
役割2. 変圧
変圧とは、6,600Vなどの高い電圧を、施設内のコンセント(100V/200V)や動力設備(200V/400V)で使用できるよう、低い電圧に変換する作業のことです。変圧器(トランス)を使用し、電磁誘導の原理で電圧を変換します。
大規模施設では、受電した6,600Vを段階的に降圧した後に、各設備・部屋に配電されます。また、変圧器の容量は電力需要に応じて選定されるのが特徴で、適切な変圧によって各設備・部屋へ安全に電力を供給することが可能です。
役割3. 配電
配電とは、変圧された電気を照明、コンセント、空調、エレベーターといった施設内の設備へ送り届けることです。配電盤や分電盤を通じて各フロアや部屋へ電気を配ります。
また、幹線と分岐回路で構成される配電系統には、適切な容量の配線と保護装置が設置されています。用途ごとに各回路を別々にすることで、一部の設備に不具合が生じても他の設備への影響を最小限に抑え、建物全体への安定した電力供給を実現するというわけです。
役割4. 保護・管理(設備の維持)
電気設備の維持・保護・管理は「保安管理業務」とも呼ばれます。施設内の電気の流れを常に監視し、漏電や過負荷といった異常が発生した際、瞬時に電気を遮断して人や設備を感電や火災から守る保安の分野です。
漏電遮断器や配線用遮断器などの保護装置が異常電流を検知すると、自動的に回路を遮断します。また、定期的な絶縁抵抗測定や接地抵抗測定により設備の健全性を確認し、近年ではデマンド監視システムによる電力使用量のリアルタイム管理も増加しています。
適切な保護・管理により、電気事故の防止と設備の長寿命化が見込めるというわけです。
構内電気設備を構成する主要設備
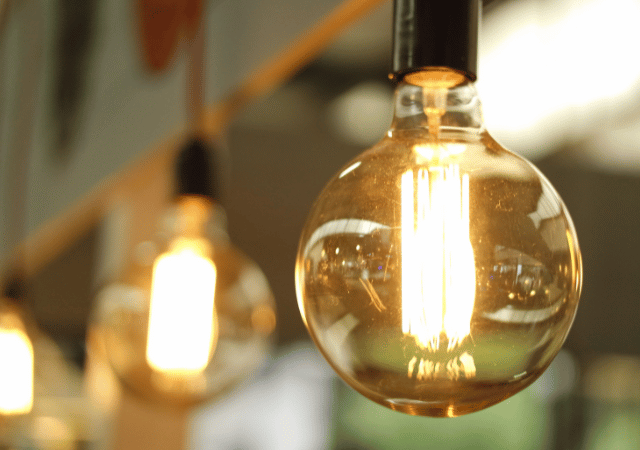
構内電気設備を構成する主要な設備は、主に大きく以下の4つに分類されます。
- 受変電設備
- 配電設備
- 動力設備
- 電灯・コンセント設備
ここでは、それぞれの設備について詳しく解説します。
1. 受変電設備
受変電設備は、電力会社から送電される高圧を施設で使用可能な電圧に変換する設備のことです。現在ではキュービクル式受変電設備が多く採用されており、断路器・遮断器・変圧器・保護継電器などが一体化されています。
受変電設備は、電気主任技術者が月次・年次点検と法定点検によって設備の安全性を維持します。停電や電気事故のリスクを最小限に抑え、電気の供給を安全・安定させる重要な設備です。
【こちらもチェック】受変電設備とは?役割や種類、構成機器や安全対策で必要なことまで解説!
2. 配電設備
配電設備は、受変電設備から各階の分電盤へ電力を送る主要な配線設備のことです。ケーブルラックやバスダクトを用いて、電気を各エリア・機器へ安全かつ効率的に配送します。
配送する際は配電盤が用いられており、いくつか種類があります。種類としては、主配電盤(建物全体に電気を分配する主の配電盤)・分電盤(主配電盤から送られた電気を各エリア・部屋に分配する配電盤)・動力盤(エレベーターや大型機械などを動かすための電気を供給する配電盤)の3つです。
3. 動力設備
動力設備は、エレベーターや空調機などの大型機器へ電気を供給する設備のことです。三相200Vや400V電源を使用し、機器の始動・運転電流に対応した配線と制御装置で構成されています。
電動機の始動方式には直入始動・スターデルタ始動・インバーター始動などがあり、機器の特性に応じて選定されます。これらは、動力制御盤にて機器の運転制御と保護を行います。最近では、省エネのためインバーター制御による回転数制御も広く採用され、電力消費削減に貢献しているのも特徴です。
4. 電灯・コンセント設備
電灯・コンセント設備は、照明やOA機器への電気の供給を担う身近な電気設備です。単相100V・200V電源を使用し、用途に応じた配線と器具で構成されています。
また、照明設備などは照明設備はLED化や人感センサーで省エネ化が進んでいます。コンセント設備は一般用と専用回路に分かれ、接地極付きで安全性が高められているのが現代の傾向です。
構内電気設備の保守・点検が重要な理由

構内電気設備の保守・点検は、法的義務だけでなく、施設の安全性と事業の継続性を確保する上で必要不可欠です。特に電気事故は、二次災害にもつながりやすく、人命に関わるため、設備の故障は事業に深刻な影響を与えます。
そこで電気事業法では、事業用電気工作物を設置する事業者には、電気主任技術者の選任と保安規程の作成・届出が義務付けられています。電験三種の有資格者が電気主任技術者として保安監督業務を行い、定期点検で異常を早期発見して事故を未然に防ぎます。
適切な保守・点検は単に設備の寿命を延ばすだけでなく、無駄なコストの発生を抑えたり労働災害・電気事故を防いだりする観点から大切というわけです。
構内電気設備に関わる法律と資格

構内電気設備の設置や維持管理には、電気事業法をはじめとする各種法令の遵守が求められます。また、これらの設備を適切に扱うためには、専門的な知識と技術力を証明する資格の取得が必要です。
ここでは、構内電気設備に関連する法律と主要な資格について解説します。
電気事業法について
電気事業法は、公共の安全と環境保全を目的に、電気事業と電気使用を規制する法律です。電気事業法では、構内電気設備は「一般用電気工作物」「自家用電気工作物」「事業用電気工作物」として分類され、設置者に保安責任が課されます。
中でも事業用電気工作物では、具体的な保安の責任として、電気主任技術者の選任や保安規程の作成・遵守、技術基準への適合維持などが義務付けられています。これらを怠ると罰則の対象となるため、工事計画の届出や使用前自主検査も必須です。
電気事業法は、事故防止と安定供給を両立させるための基本的な枠組みであり、定期的に法改正を行うことで、時代の変化にも対応しています。
構内電気設備が問題として登場する電気の資格
構内電気設備、特に事業用電気工作物ともなると、設計・施工・保守に対してより高度な専門知識と技術力が求められるため、関連する国家資格の取得が欠かせません。構内電気設備の内容が問題として出題される電気系資格は、主に以下の2つです。
- 第一種電気工事士
- 電験三種(第三種電気主任技術者)
それぞれの資格について詳しくみていきましょう。
第一種電気工事士
第一種電気工事士は、第二種電気工事士の上位資格で、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事に従事できる国家資格です。構内電気設備の多くがこの範囲に含まれるため、施工・改修工事では欠かせない資格となっています。
試験は学科試験と技能試験で構成され、高圧受電設備や動力制御回路など、第二種よりも高度な知識と技術が求められます。また技能試験合格後、実務経験3年以上で免状が交付され、5年ごとの定期講習受講が義務付けられているのも特徴です。
第一種電気工事士を取得すると、大規模施設の電気工事に携わることができるため、技術者としての活躍の場が大きく広がります。
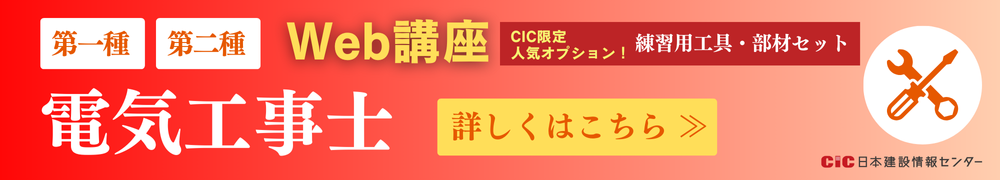
電験三種(第三種電気主任技術者)
電験三種は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の保安監督を行うための国家資格です。事業用電気工作物の維持管理には、この資格を持つ電気主任技術者の選任が法的に義務付けられています。
試験科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で、電気工学の幅広い知識が問われます。合格率が例年10%前後と難関ですが、科目合格制度により3年以内の合格が可能です。また、電験三種の合格者は、設備の保安監督という独占業務を担えるため企業からの需要が高く、安定したキャリアを築くことができます。
CIC日本建設情報センターでは、「第一種電気工事士」を含めたさまざまな資格のWeb講座を提供しています。受講者がモチベーションを維持しながら、最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
まとめ

構内電気設備は、電力会社の責任分界点から需要家側にある全ての電気設備を指す言葉です。受電・変圧・配電・保護管理の4つの役割を担っており、受変電設備や幹線設備、動力設備や電灯・コンセント設備などで構成されています。
構内の電気設備の設置・維持管理には電気事業法の順守が必要です。その際、「第一種電気工事士」は施工・改修工事に不可欠な資格となります。電気業界に従事する方であれば、非常に強い味方となる資格ですので、ぜひ取得を目指してみてください。