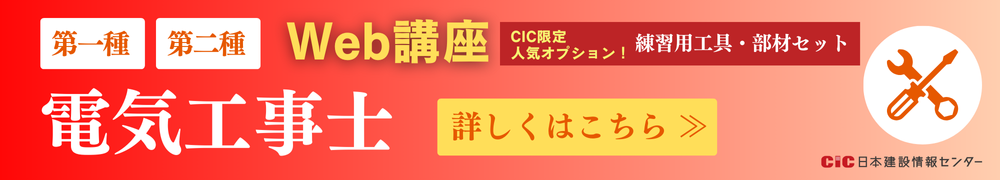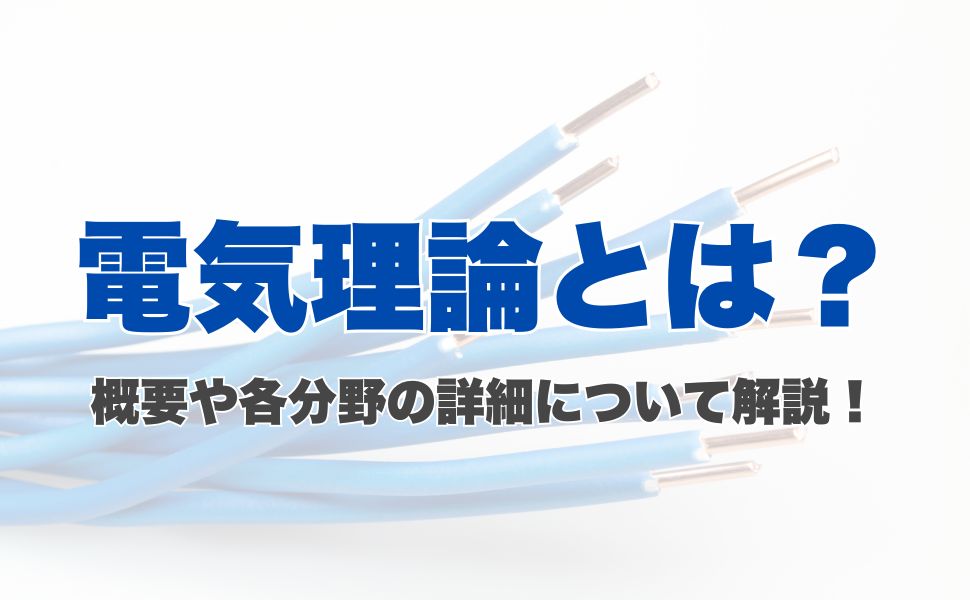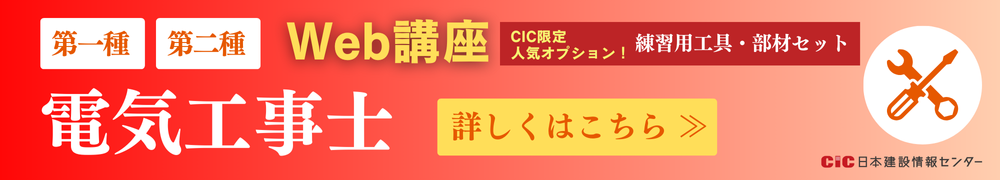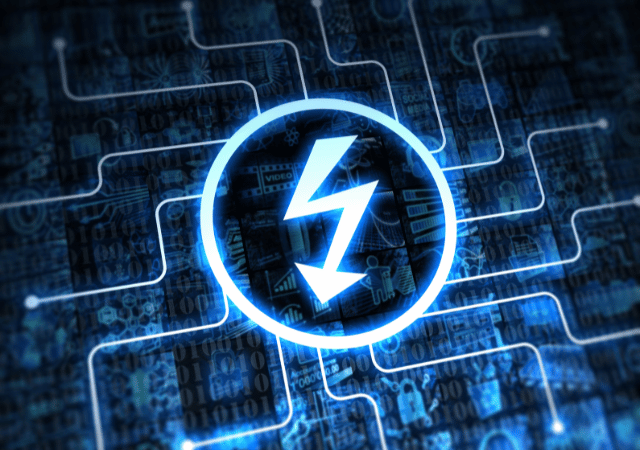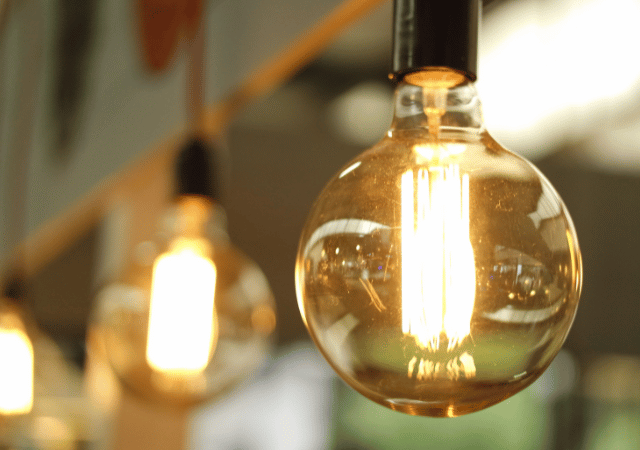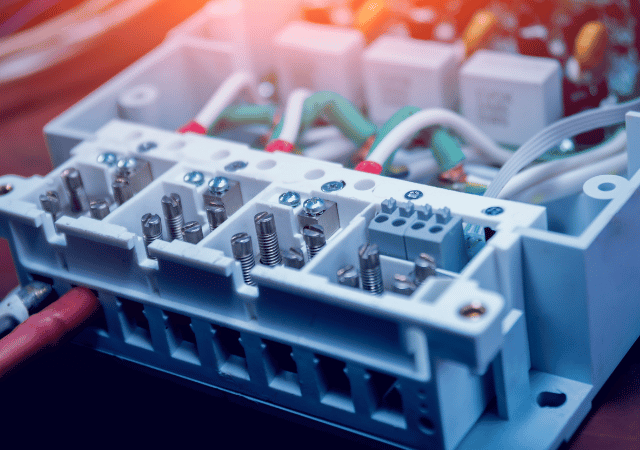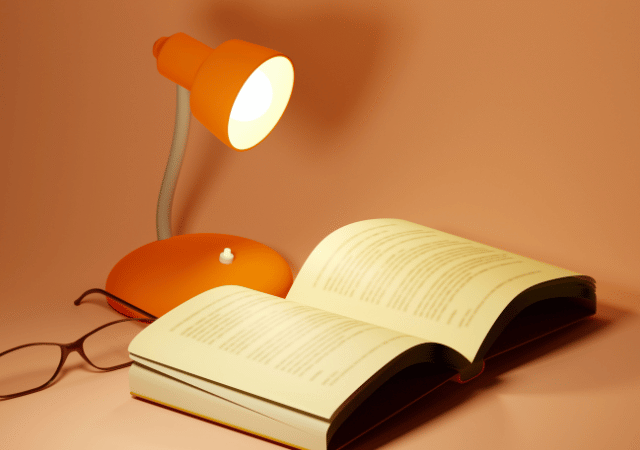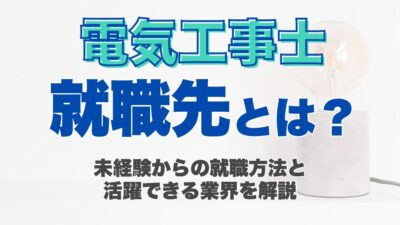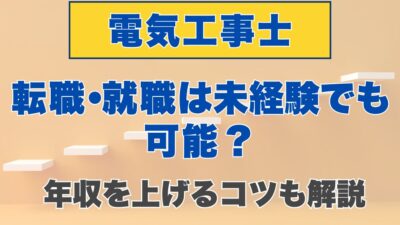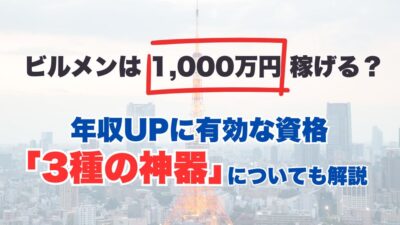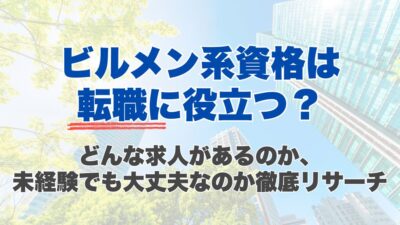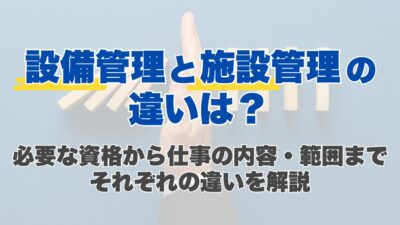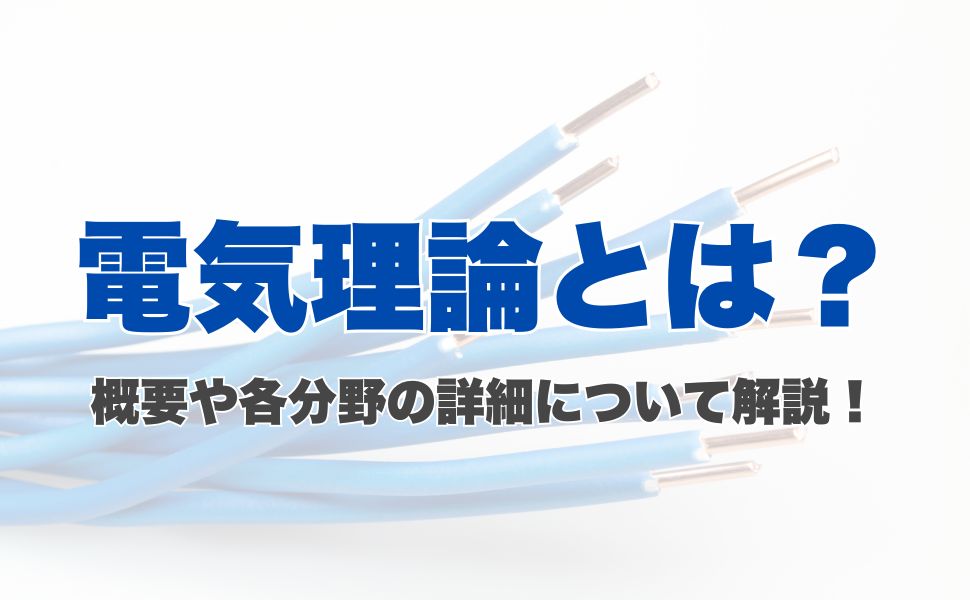
電気系の資格試験を含め、すべての電気技術の土台となる分野として「電気理論」があります。電気理論とは、電圧・電流・抵抗といった電気の基本要素の性質や、それらがどう影響し合うかを定めた法則・原理の総称のことです。
電気系の資格試験では、電気理論を土台として、さまざまな内容の問題が出題されるため、性質を正しく理解して基礎を身に付けることが大切となります。
この記事では、電気理論の概要や理解する上で最も重要な要素をご紹介します。電気理論が登場する資格や学習方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
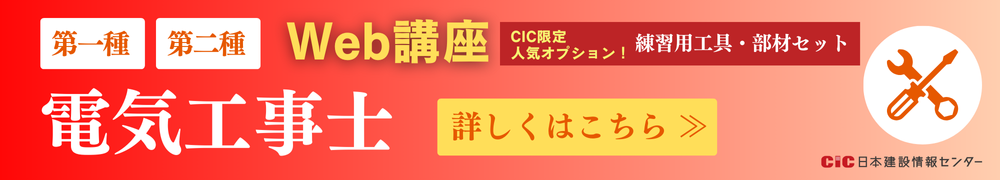
電気理論とは?すべての電気技術の土台となる分野
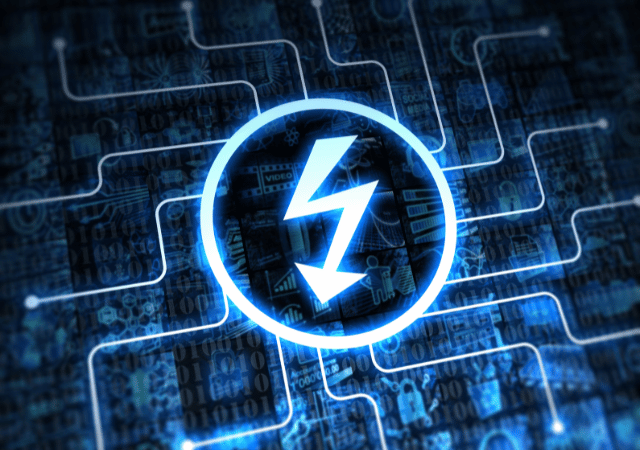
電気理論とは、電圧・電流・抵抗といった電気の基本要素の性質や、それらがどう影響し合うかを定めた法則・原理の総称を指します。あらゆる分野の技術者に必要な電気の基礎で、電気工事士や電験三種の理論分野などの資格試験では当たり前のように登場する分野です。
電気理論は、私たちの身の回りにあるスマートフォン・家電・照明・電車をはじめ、電気を作る発電所まで、ありとあらゆる電気設備・電子機器が電気理論の土台の上に成り立っています。
ここでは、なぜ電気理論の勉強が大切なのか必要性についてもみていきましょう。
なぜ電気理論の学習が必要なのか?
電気理論の学習が必要な理由は、電気を安全かつ効率的に利用するために不可欠だからです。電気理論をきちんと理解してない中で作業に従事してしまうと、自分や周囲の人間を巻き込んだ重大な電気事故につながる恐れがあります。
例えば、建物の電気配線を設計する際に電気理論を知らなければ、どれくらいの太さの電線を使えば良いか、どのくらいの電気を流せるかが分かりません。理解せず暗記だけしていても、もし間違いが生じそうなときに正しく気づくこともできないでしょう。
このように、電気理論は単なる座学にとどまらず、電気を扱うすべての技術者が必ず身につけるべき実践的な知識であるといえます。正しく学習し、技術者としての今後のキャリアにつなげることが大切です。
電気理論を理解する上で最も重要な3つの要素と法則
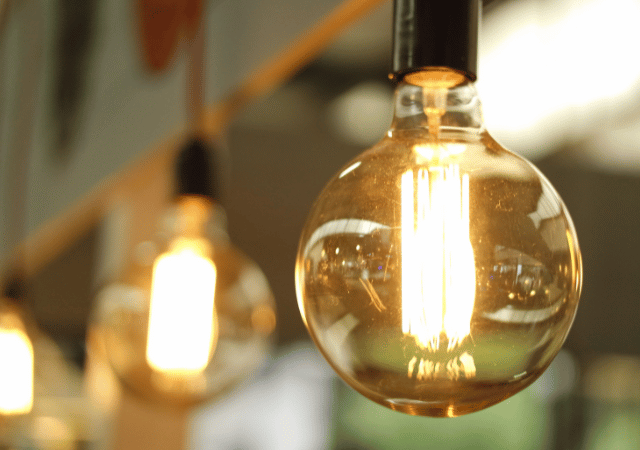
電気理論を学ぶ上で、最初のステップは主役となる3つの基本要素を理解することが大切です。基本的な要素とは、「電圧」「電流」「抵抗」のことを指します。
ここでは、電気の流れを「水の流れ」に例えて解説しますので、ぜひイメージを掴む際に役立ててみてください。
電圧(V)
電圧(V)とは、電流を流そうとする力の大きさのことです。単位は「V(ボルト)」で表されます。
電圧を水の流れに例えるなら、ポンプや蛇口が水を押し出す「水圧」に相当します。水圧が大きいほど水の勢いも強くなるように、電圧が高いほど電流を流す力は強くなります。実際、家庭用のコンセントは100Vが用いられていますが、電気を送り出している送電線には数万Vという非常に高い電圧がかかっています。
電流(A)
電流(A)とは、特定の時間内に導体を流れる電気の量のことです。単位は「A(アンペア)」で表されます。
電流を水の流れに例えるなら、水道管を流れる「水量」そのものです。管が太いほど多くの水が流れるように、多くの電流が流れるということは、それだけ多くの電力が生じていることを意味します。また、水圧が大きいほど一定時間に流れる水の量も増えることと同様に、電圧が大きいほど電流も大きくなるため、電圧と電流は比例の関係にあります。
抵抗(Ω)
抵抗(Ω)とは、その名の通り電流の流れにくさを表す指標のことです。単位は「Ω(オーム)」で表されます。
抵抗を水の流れに例えるなら、水道管の「細さ」や「ゴミの詰まり」に当てはまります。管が細ければ水は流れにくくなりますよね。電気の世界でも、物質や電線の太さによって電気の通しやすさは異なり、この「通しにくさ」が抵抗です。電気を用いることで電球が光ったり、電気ストーブが熱くなったりするのは、この抵抗に伴って生じる電気エネルギーを光や熱のエネルギーに変換しているためです。
また、抵抗が大きいほど電流が流れにくくなることから、電流と抵抗は反比例の関係にあります。
【最も基礎的な法則】オームの法則について
上記で解説した3つの要素「電圧・電流・抵抗」の関係性を示したものが、電気理論において最も基本的かつ重要な「オームの法則」です。これまで解説した電圧・電流・抵抗の関係性は、以下の式で表されます。
電圧 (V) = 電流 (A) × 抵抗 (Ω)
上記の式の要点をまとめると、以下のとおりです。
- 抵抗が一定の時、電圧を高くすれば、電流も多く流れる。(水圧を上げれば、流れる水の量が増える)
- 電圧が一定の時、抵抗を大きくすれば、電流は流れにくくなる。(水圧が同じなら、管を細くすれば水の量は減る)
この関係性は電気資格の試験問題で当たり前のように問われます。そのため、関係性を把握した上で、さまざまな問題が解けるように応用力を鍛えていくことが大切です。
電気工事士試験などで登場する主要な分野
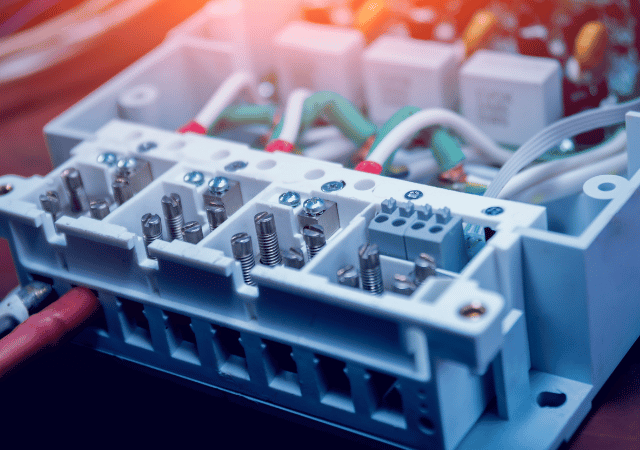
先ほど、電気理論の基本的な概要をご紹介しました。続いて、電気工事士試験などで電気理論が登場する主要な分野をご紹介します。以下の表は、主要な分野についてまとめたものです。
| 直流 (DC) と交流 (AC) |
電気の流れ方には、乾電池のように常に一定方向に流れる「直流」と、家庭のコンセントのように周期的に流れる向きが変わる「交流」がある。それぞれの性質や計算方法は異なり、どちらも重要な分野。 |
| 電力 (W) と電力量 (Wh) |
「電力」は、電気が1秒間あたりにする仕事の量を表し、「電力量」は、ある時間内に消費された電気の総量を表す。電気料金の計算など、実生活に密接に関わってくる分野。 |
| 静電気と磁気 |
静電気は物質内に溜まった電気であり、磁気は磁石の力のこと。電気と磁気は密接に関係しており(電磁気学)、モーターや発電機の原理に繋がる重要な分野。 |
| 電子回路 |
抵抗、コンデンサ、コイル、トランジスタといった電子部品を組み合わせた回路の動作を学ぶ。スマートフォンやコンピュータなど、現代の電子機器を理解するためには必須の知識。 |
表を見て分かるとおり、電気理論はさまざまな分野で用いられています。
各分野は、電気理論の土台の上で成り立っているものであり、その分野もまた、社会の至る所で活用されている技術を成り立たせていることから、電気理論は非常に重要であるといえるでしょう。
電気理論の学習方法
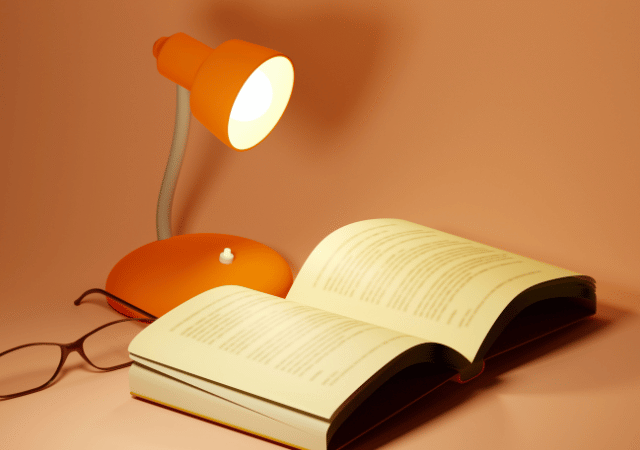
電気理論を学習する際、方法として主に以下の3つがあります。
- 参考書などで基礎から学習する
- 動画やWebサイトを活用して学習する
- 資格のWeb講座を通して学習する
それぞれの学習方法を理解しておくことで、どの方法が自分に適しているかを判断した上で学習に臨めます。ここでは、各方法について詳しくみていきましょう。
方法1. 参考書などで基礎から学習する
参考書を用いた学習は、電気理論の基礎を体系的に身に付けられる方法です。初心者向けの参考書から始めて、問題集などを活用しながら段階的にレベルアップしていくことで、コツコツと知識を積み上げられます。
また、図解・イラストが豊富に用いられている参考書であれば、文章だけでは理解が難しい部分も理解しやすいでしょう。ほかにも、自分のペースで何度も読み返せるため、じっくりと理解を深めたい方にもメリットのある方法です。
一方で、疑問点や不明点が生じた場合でも独学で解決しなければならない点やモチベーションの管理が自己管理となる点はデメリットといえます。無理のない学習計画を組み立てて、モチベーションを維持しながら勉強しなければならない点がこの方法の重要なポイントとなるでしょう。
方法2. 動画やWebサイトを活用して学習する
現在であれば、YouTubeやWebサイトを活用して学習する方法もあります。動画やWebサイトであれば、視覚・聴覚の両方を活用して情報を吸収できる点に加え、実際の映像やアニメーションなどで、電流の流れや回路の動作を理解できるのもメリットです。
また、動画であれば通勤時間やスキマ時間を上手く活用できるのもメリットです。忙しい方であっても、スキマ時間さえあればこまめに学習を継続できます。
ただし、情報の正確性にばらつきがあるため、信頼できる動画配信者のコンテンツを選ばなければなりません。参考書や問題集と併用しながら動画でもチェックしてみることで、より理解の定着度を深められるでしょう。
方法3. 資格のWeb講座を通して学習する
資格取得を目標としたWeb講座を受講するのもおすすめの方法です。Web講座は、プロの講師による体系的なカリキュラムで効率的に学習できる方法で、先ほどご紹介した参考書や動画環境など必要な教材がすべてそろいます。
また電気工事士や電験三種など、受験する資格試験に特化した内容で、出題傾向を踏まえた実践的な知識が身につくため、最短距離で合格を目指せるのがメリットです。加えて、質問サポートなどを受けられる講座も多くあり、独学では解決しづらい部分であってもモチベーションを維持したまま乗り越えやすいのが特徴です。
CIC日本建設情報センターでも、電気資格を含めたさまざまな資格のWeb講座を提供しておりますので、最短距離で効率よく合格を目指したい方は、ぜひ受講をご検討ください。
電気理論が登場する主要な電気資格

ここまで、電気理論の概要や最も重要な要素などをご紹介しました。電気技術のすべての土台となる電気理論ですが、主に以下の資格試験で登場します。
ここでは、それぞれの資格について詳しく解説します。
電気工事士
電気工事士は、住宅やビル、工場などの電気設備の工事を行うために必要な国家資格です。
第二種と第一種の2種類に分類されており、第二種では一般住宅や小規模店舗など600V以下で受電する設備の工事が可能です。一方で、第一種は第二種の範囲に加えて、高電圧で受電する小規模なビル、工場などの電気設備などの工事にも着手できます。
電気工事士の試験は学科試験と技能試験で構成され、学科試験では電気理論の基礎知識が必須です。特にオームの法則を使った計算問題や、直列・並列回路の電圧・電流・抵抗の関係を問う問題が多く出題されます。
受験資格に関しては特に制限がなく誰でも挑戦可能です。中でも第二種電気工事士の合格率は例年40〜60%ほどあるため、電気業界への入門資格として最適といえるでしょう。
CIC日本建設情報センターでは、第二種電気工事士の受験者向けに講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら効率的に学習できる内容となっておりますので、受験される際はぜひ受講をご検討ください。
電験三種(第三種電気主任技術者試験)
電験三種は、発電所や変電所、工場やビルなどの電気設備の保安監督を行うための国家資格です。
電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)における保安・監督を独占業務として担えるため、需要として非常に高いものとなります。
試験の科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で構成されています。中でも、「理論」科目では電気理論の深い理解が不可欠です。オームの法則はもちろん、交流回路理論、三相交流、過渡現象など、高度な電気理論の知識が求められます。
電験三種の合格率は例年10%前後と低く、難易度としては高いものの、科目合格制度があり3年以内に4科目合格すれば資格取得できます。年収アップや転職に有利で、電気のスペシャリストとして認められる価値の高い資格なので、電気業界に従事する上で将来的に取得しておきたい資格です。
まとめ

この記事では、電気理論の基礎知識から学習方法、関連資格まで幅広く解説しました。電気理論は、電圧・電流・抵抗という3つの基本要素とオームの法則を中心に構成され、すべての電気技術の土台となる重要な分野です。
電気理論の理解は、安全な電気工事の実施や、電気設備の適切な保安監督に不可欠です。この記事を参考に自分に合った学習方法を選択し、電気理論の習得と資格取得に向けた第一歩を踏み出してください。