建設現場では、機械や作業により大きな音が発生することがあります。騒音規制法は、これらの騒音から住民の生活環境を守るための重要な法律です。
また、騒音規制法は建築施工管理技士・土木施工管理技士などの資格試験で出題される分野でもあります。これから建設・土木業界への従事を考えている方は、勉強方法も踏まえた上で概要を把握しておきましょう。
この記事では、騒音規制法の概要について解説します。関連資格や効果的な勉強方法までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年10月30日 更新日:2025年10月30日
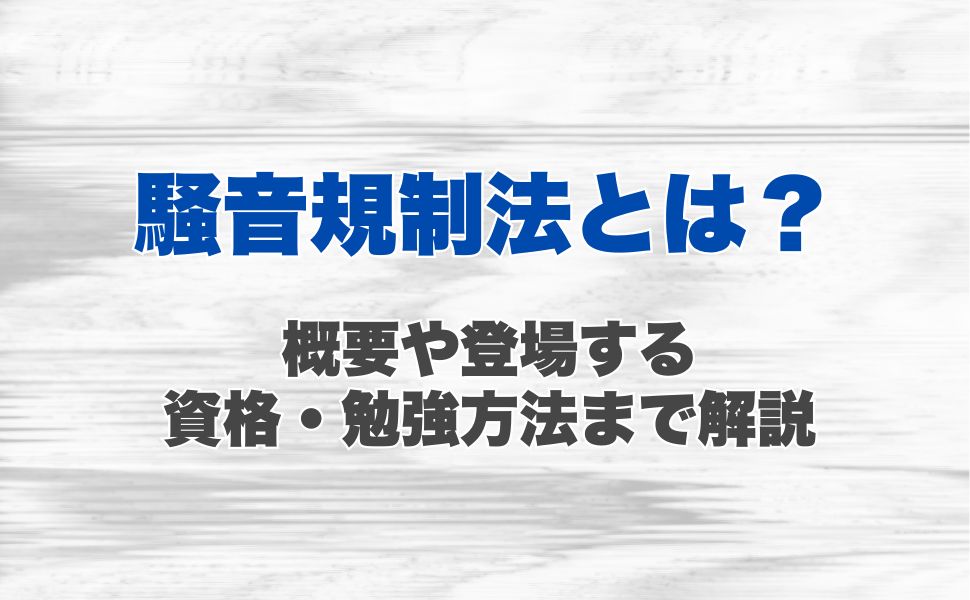

「騒音規制法」は、生活環境の保全と国民の健康保護を目的に、騒音問題に対応するため昭和43年に制定された法律です。工場・事業場、建設作業、自動車、深夜営業等から発生する騒音が規制対象となります。
この法律は国が大枠を定め、具体的な規制地域の指定や基準値の設定は都道府県知事や市区町村長に委ねられているのが特徴です。そのため、地域の実情に応じて柔軟に運用されます。
建設工事に伴う騒音のうち、特に著しい騒音を発生させる作業として法律で定められているのが「特定建設作業」です。騒音規制法において、以下の8種類の機械を使用する作業が特定建設作業として定められています。
特定建設作業を行う際には、作業開始の7日前までに、市区町村長に対して届出を行う義務があります。届出義務に加えて、現場では定められた騒音の基準値や作業時間、日数や曜日などを遵守しなければならず、違反した場合は改善勧告や改善命令、罰則の対象となります。
特定建設作業は、原則として夜間や日曜日・祝日には行えません。規制時間は区域により異なり、第1号区域(住居系)は午後7時~翌朝7時、第2号区域(工業系)は午後10時~翌朝6時です。
1日の作業時間は第1号区域で10時間以内、第2号区域で14時間以内、連続作業は6日以内と制限されています。敷地境界線の騒音レベルは85デシベル以下が必要です。これらの規制は周辺住民への配慮のため、遵守が重要です。ただし、災害時などの緊急時は適用が除外されるケースもあります。
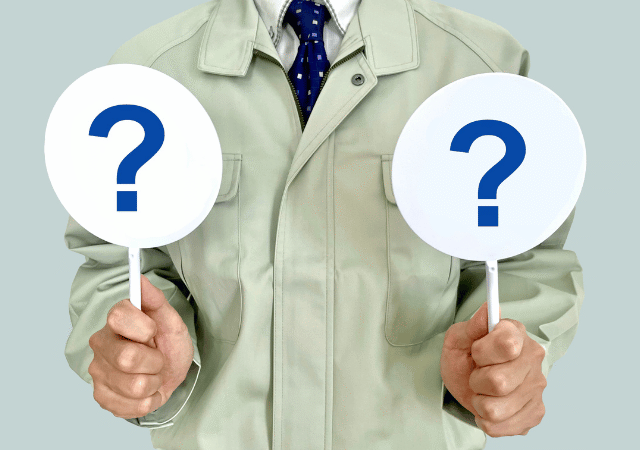
騒音規制法と類似した法律に「振動規制法」があります。両方とも建設工事や工場の操業に伴う公害を規制する法律としてかなり近いものとなりますが、明確な違いもあります。
以下の表は、振動規制法と騒音規制法の違いをまとめたものです。
| 項目 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
|---|---|---|
| 対象 | 騒音 | 振動 |
| 各対象の概要 | 騒音は空気を伝わって人の聴覚に影響を与える | 振動は地盤に伝わって建物や人体に影響を与える。 |
| 特定建設作業の対象となる作業内容 | ・くい打機を使用する作業 ・さく岩機・ブレーカーを使用する作業 ・鋼球を使用する破壊作業 ・舗装版破砕機を使用する作業 |
・くい打機を使用する作業 ・さく岩機・ブレーカーを使用する作業 ・鋼球を使用する破壊作業 ・コンクリートプラント等の作業 |
建設業の施工管理技士は、騒音と振動の両方について適切な管理を行い、関連規制に違反しないようにすることが大切です。騒音と振動に関する苦情は同時に発生しやすいため、両方に対応した対策を講じる必要があります。
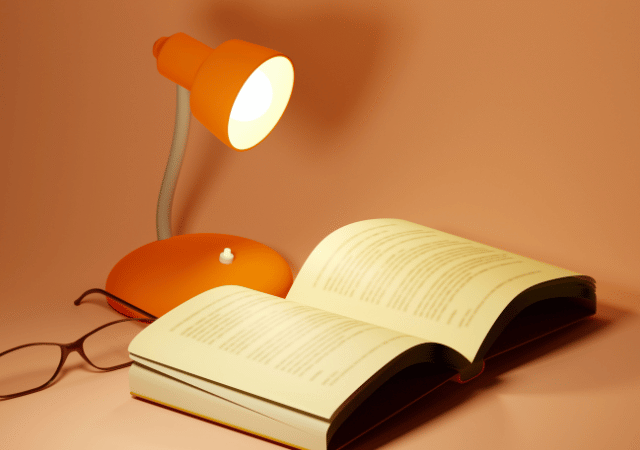
騒音規制法を勉強する方法として、主に以下の3つがあります。
それぞれの内容について詳しく解説します。
騒音規制法を学ぶには、参考書を使うのが一般的です。法律の条文は文章が中心ですが、図やイラストが豊富な参考書を選ぶことで、効率的に理解を深められます。
さらに、参考書で知識をインプットするだけでなく、問題演習も取り入れてみましょう。資格取得を目標に設定しつつ過去問題を解くことで、騒音規制法への理解を深めると同時に、学習のモチベーションも維持しやすくなります。
騒音規制法について学ぶ場合、現在ではインターネット上にもさまざまな情報源があります。特に動画コンテンツは、具体的な事例を通して理解を深めるのに効果的です。
また、騒音規制法に関するウェブサイトでは、最新の法令情報なども入手できます。ただし、情報の信頼性はサイトによって異なるため、公的機関や専門機関の情報源を優先して利用することが大切です。
資格試験で騒音規制法を学ぶ際は、合格を目標とした計画的かつ効率的な学習が大切です。社会人の方であれば、Web講座の活用もおすすめします。
Web講座は、時間や場所にとらわれずに、自分のペースで学習を進められます。また、質問対応や模擬試験などのサポートも充実しており、専門家による解説で効率的に知識を得られます。
CIC日本建設情報センターでも、騒音規制法が登場する建築施工管理技士・土木施工管理技士の受験者向けにWeb講座を提供しております。学習方法にお悩みの場合は、ぜひ受講をご検討ください。
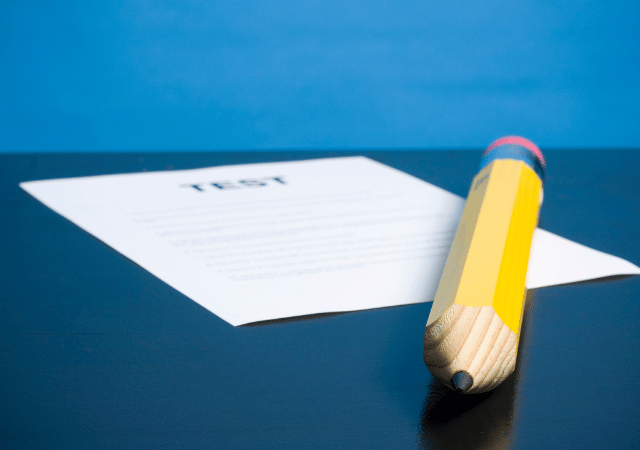
騒音規制法の知識が必要となる資格試験は、主に以下の2つです。
それぞれの資格で騒音規制法がどのように問われるのか解説します。
施工管理技士の資格のひとつである「建築施工管理技士」の「建築法規」分野では、振動規制法に関する問題が出題されます。出題内容は1級と2級で傾向が異なります。
また、2級では基本的な知識を問う問題が中心ですが、1級では実施の業務への適用を意識した応用問題も出題されます。特定建設作業の届出時期や作業時間制限に関する問題も出題されるため、十分な対策が必要です。
土木施工管理技士は、建築施工管理技士と同様に、1級と2級に分かれた国家資格です。この資格試験では、「施工管理法」や「法規」の分野で騒音規制法が出題されます。
道路工事や橋梁工事、トンネル工事など、大型重機を使用する土木工事では騒音問題への対応が必要不可欠です。試験では、くい打ち作業やコンクリート打設時の騒音対策、工事時間の制限などについて問われることが多く、実際の業務に即した知識が求められます。

騒音規制法は、建設工事による騒音から住民の生活環境を守るための法律です。特に特定建設作業については、8種類の作業内容と規制基準を正確に理解し、適切な届出と管理を行うことが施工管理者の責務となります。
また、施工管理技士試験では頻出分野となっているため、計画的な学習が必要です。参考書での基礎学習やWeb講座の受講など、自分に合った方法で効率的に学習を進めましょう。
CIC日本建設情報センターでは、建築施工管理技士・土木施工管理技士の受験者に向けたWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。

建設キャリア転職造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
施工管理技士の平均年収は?資格別や年代別の給与相場と年収1000万を目指す方法を解説
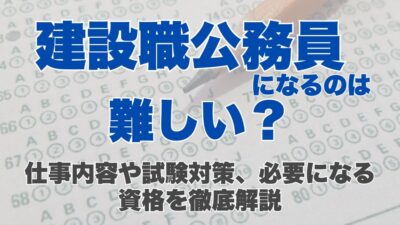
建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士消防設備士コンクリ技術士
建設職公務員になるのは難しい?仕事内容や試験対策、必要になる資格を徹底解説
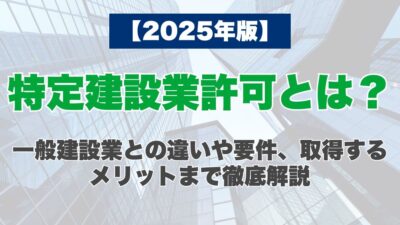
造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
【2025年版】特定建設業許可とは?一般建設業との違いや要件、取得するメリットまで徹底解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介
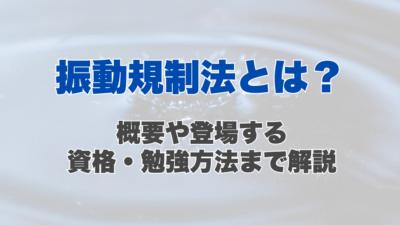
振動規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
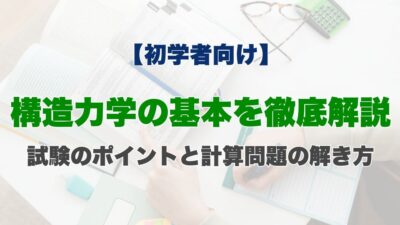
【初学者向け】構造力学の基本を徹底解説|試験のポイントと計算問題の解き方
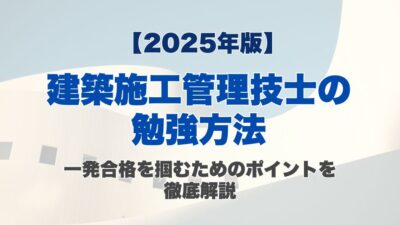
【2025年版】建築施工管理技士の勉強方法|一発合格を掴むためのポイントを徹底解説
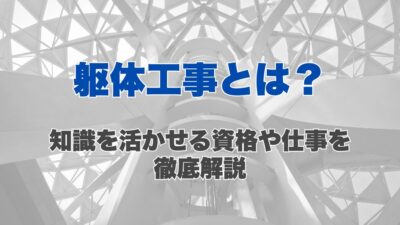
躯体工事とは?知識を活かせる資格や仕事を徹底解説
