公開日:2022年4月6日 更新日:2023年3月29日
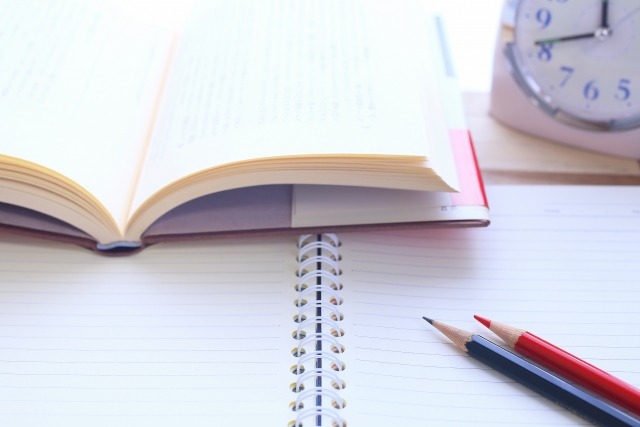
二級ボイラー技士に合格するためには、どのような勉強方法があるか。
またどのようにスケジュールを立てればよいか。このようなことにお悩みの方も、多いのではないでしょうか。
合格可能な勉強方法は複数ありますから、あなたに合った方法を選ぶことが合格への近道です。
加えて無理のないスケジュールを立て、効率的に学ぶことも欠かせません。
本記事では二級ボイラー技士に合格するための勉強方法と学習スケジュールの立て方を取り上げ、詳しく解説していきます。
二級ボイラー技士の合格に要する勉強時間は、多くの方が気になるポイントでしょう。
初心者と関連資格を取得済みの方に分けて、目安となる勉強時間を考えていきます。
初心者が独学で学ぶ場合、必要な勉強時間は100~200時間といわれています。
勉強時間が1日3時間ならば1カ月~2カ月、1日2時間なら1カ月半~3カ月必要です。
忙しい方ほど早めにターゲットとする試験日を決めたうえで、試験勉強をスタートしなければなりません。
もっとも学習方法によっては、勉強時間や期間を短縮できる可能性があります。
たとえばあなたに合った通信講座を選んだ場合は、50時間程度で合格することも可能です。
二級ボイラー技士を目指す方のなかには「危険物取扱者」など、関連する資格をお持ちの方もいることでしょう。
その場合の勉強時間は、50時間程度が目安です。
1日3時間なら2~3週間、1日2時間なら4週間程度を要します。
特に仕事に就いている方は、試験勉強にあてられる時間が限られるため、早めの準備がおすすめです。
二級ボイラー技士試験の合格率は、過去5年間で50%~60%となっています。
受験資格が無い試験であることを考慮すると、難易度の高い試験ではありません。
しっかり準備すれば、合格も十分に可能です。
また試験は、過去問に類似した出題がされやすい傾向があります。
試験勉強では数値や条件などを、正確に把握することが重要です。
加えて試験では、問題文を正しく読むことも欠かせません。
なぜなら問題文が少し変わるだけで、正解となる選択肢が変わる場合があるためです。
このため過去問の丸暗記はおすすめできません。
選択肢が問う内容を把握し、意味を理解することが重要です。
ここからは二級ボイラー技士試験に合格できる、代表的な4つの勉強方法を紹介します。
市販の参考書や問題集を使って学ぶことは、オーソドックスな学習方法です。
書店だけでなく、ネット通販でも購入可能。気になった点を、直接書き込むこともできます。
専門家が執筆・監修しているため、信頼できるメリットも見逃せません。
近年ではKindle版など、電子書籍も活用できます。
書き込みはできませんが、本の重さに悩まされずに済むことはメリットといえるでしょう。
インターネットには過去問サイトもあり、無料で活用できます。
スマートフォンでも確認できるため、細切れ時間で勉強できることもメリットに挙げられます。
もっともすべての過去問サイトで、専門家が関わっているとは限りません。
そのため、内容が誤っている可能性があることには留意が必要です。
通信講座の活用は、有効な学習方法の一つです。
合格に必要な内容を精選し、最短の時間で効率よく学べる工夫がされていることが特徴。
独学よりも少ない時間で合格レベルまで到達可能ですから、忙しい方でも資格を取得しやすくなります。
一方で、受講に数万円かかるケースも少なくありません。
しかしどの教材を使うべきか迷わずに済む点は、メリットといえるでしょう。
通信講座はさまざまな会社から提供されていますので、あなたに合った講座を選んでください。
テキストには文章だけでなくイラストも描かれていますが、一読しただけでは理解が難しいかもしれません。
特にボイラーは普段の生活になじみがないため、イメージがつきにくい方もいるでしょう。
この場合は、動画の活用も選択肢に入ります。
視覚と聴覚を活用することで、より理解しやすくなることは大きなメリット。
日本建設情報センターが提供する「二級ボイラー技士 受験対策講座」には、合計8時間の動画がついています。
WebだけでなくDVDも選べるため、インターネット回線が不安定な場所にいる方でも安心です。
試験勉強は、どのような方法でも同じように効果を挙げるわけではありません。
学習方法によって、合格しやすさは異なります。
どのような方法を取れば合格に近づけるのか、4つの視点から解説していきましょう。
ご自身に合った学習方法を選ぶことは、合格を勝ち取るうえで重要なポイントです。
一例として、以下の方法が挙げられます。
あなたの好みに合った方法を選びましょう。
学習に使う教材にも、以下のとおり多種多様なものがあります。
それぞれの教材には文字中心で情報を多く得られるものや、カラフルで見やすさを追求したものがあります。
好みの教材を選ぶことで勉強しやすくなり、合格へ近づけます。
テキストで一通り学習を進め、理解を深めることは重要です。
法令改正により変わっている場合もありますから、すべての項目について一度は目を通しておきましょう。
また学習を進める際、一字一句暗記する方法は非効率です。
疑問が出た場合はなぜそうなるのか、理由を把握しながら学習を進めるとよいでしょう。
覚えられなかった箇所は問題を解いた際に誤答となりますから、解答後にテキストで見直せばOKです。
テキストだけでなく問題集の活用も、合格につながる重要なポイントです。
1回解いただけでは、弱点を補強できません。
何度も解くことで正解率がアップし、合格へ近づけます。
また誤答した問題にどう対応したかは、合否を分ける重要なポイントです。
なぜ誤答したのか、解説を読んで理解することが重要。
そのうえで正解以外の選択肢がなぜ誤答なのか、理由も含めてテキストなどで調べておくと実力のアップにつながります。
合格にも大きく近づけることでしょう。
二級ボイラー技士の試験では、正答率が4割未満の科目があると不合格になってしまいます。
苦手な科目には特に重点をおき、学習に取り組みましょう。
二級ボイラー技士の合格基準は、以下の通りです。
試験当日には、上記の成績をあげる必要があります。
問題集を使った学習の段階では少なくとも7割から8割の得点を、コンスタントにあげられるよう実力を高めましょう。
なぜなら試験当日は以下の理由により、普段よりも得点が下がるリスクがあるためです。
問題集を解いて6割以上の得点を取ると、つい安心してしまいがちです。
しかし裏を返すと、4割は誤答ということ。
不正解の項目をチェックすることにより、合格へ近づけます。
二級ボイラー技士への合格は、日々の努力の積み重ねで成し遂げられるもの。
ここでは学習スケジュールの立て方について、詳しく解説していきます。
時間に余裕がある方は、以下のポイントを踏まえて学習スケジュールを立てるとよいでしょう。
漫然と時間をかけて学んでも、合格にはなかなかたどり着けません。
週ごと・月ごとに到達目標を決め、スケジュールを立てましょう。
その際には急用などが入った場合に備えて、予備日を設けるなど余裕を持たせることも重要です。
また毎日同じような時間帯に勉強することで、習慣にしやすくなります。
午前中や夕方など、学習しやすい時間を選んで勉強しましょう。
仕事で忙しい方の場合でも、週間・月間のスケジュールや到達目標を決めることは同じです。
一方で勉強は、どうしても休みの日にまとめて時間を取ることになりがち。
しかし仕事がある日でも、短時間でよいので毎日勉強時間を取るとよいでしょう。
特に公共交通機関を使って通勤・通学する場合は、移動中の時間を使って学ぶことをおすすめします。
これにより、時間の有効活用と実力アップの両立が可能です。
下車する時刻が決まっているため、集中力が高まりやすいこともメリットに挙げられます。
学習を進めていくと、どうしてもスケジュール通りには進まないものです。
しかし勉強を進めていくうえで、難しい項目に時間がかかることは当然ですから、気にする必要はありません。
進捗状況に一喜一憂せず、弾力的にスケジュールを見直すことが重要です。
あらかじめ予備日を設けておくことで、柔軟なスケジュール変更が可能となります。
二級ボイラー技士試験に合格しても、それだけでは資格を取得できません。
資格取得には、免許証の交付を受けることが必要です。
また免許を受けるためには、条件もあります。
本記事では最後に、資格取得までの注意事項を確認していきましょう。
二級ボイラー技士の免許を受けるためには、ボイラーを扱った実務経験が必要です。
実務経験が無い方は「ボイラー実技講習」を受講することで、実務経験として扱われます。
開催される日程は限られるため、早めの受講がおすすめです。
また「ボイラー取扱技能講習」など類似した講習があるため、間違えないように注意してください。
ボイラー実技講習は3日間、20時間のカリキュラムで行われます。
2日間の座学に加えて、1日間の実習があることが特徴。
実際のボイラーを見て操作できます。
一方で遅刻や早退があると、出席と認められないため注意が必要です。
ボイラー実技講習を終えた方には、「ボイラー実技講習修了証」が発行されます。
この書類は免許証発行に必要となるため、大切に保管しておきましょう。
合格後は以下の書類を用意のうえ、東京労働局免許証発行センターに郵送してください。
なお申請窓口は用意されていないため、対面での申請はできません。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 免許申請書 | – |
| 写真1枚(縦3cm、横2.4cm) | 免許申請書の表面に貼る |
| 1,500円分の収入印紙 | 免許申請書の裏面に貼る |
| 免許試験合格通知書 | 試験合格者に送付される。原本の提出が必須 |
| 実務経験を証明する書類 | ボイラー実技講習修了証など |
| 免許証送付用封筒 | 簡易書留料金分の切手を貼る(2021年11月現在では404円) |
免許申請書と送付用封筒は、以下の場所で受け取れます。
試験合格後に転居した方は、上記の書類に加えて住民票も必要です。
なおボイラー実技講習修了証を手元に残しておきたい場合はコピーを用意したうえで、免許証の申請前に労働基準監督署又は都道府県労働局へ出向き、原本確認を受けてください。
これによりコピーを送付することで、免許証の発行を受けられます。
二級ボイラー技士は、初心者でも3カ月程度で合格が可能な試験です。
悩んでいると時間はどんどん過ぎてしまいますから、早めに目標とする受験日と勉強方法を選び、スケジュールを立てることをおすすめします。
せっかく受験するならば、1回で合格したいもの。
日本建設情報センターでは、二級ボイラー技士の通信講座を用意しています。
効率のよい試験勉強と合格を勝ち取るために、ぜひ活用をご検討ください。
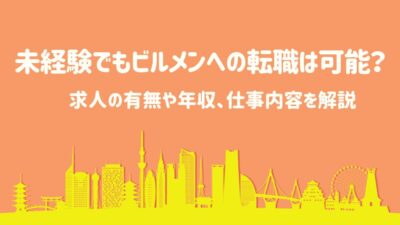
未経験でもビルメンへの転職は可能?求人の有無や年収、仕事内容を解説 – 建設キャリア転職 –

30代〜40代のビルメン転職は未経験でも売手市場!転職のポイントを解説 – 建設キャリア転職 –

建設キャリア転職ビル管電気工事士危険物消防設備士冷凍ボイラー
建設業の主な職種一覧!仕事内容や平均年収について解説 – 建設キャリア転職 –

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士冷凍ボイラー工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介

二級ボイラー技士の実技講習とは?受講のタイミングやどこで受けられるのか、資格習得までの流れも解説

ボイラー技士は転職に役立つ?どんな求人があるのか、未経験でも大丈夫なのか徹底リサーチ

ボイラー技士の合格発表はいつごろ? 免許申請の方法、合格率や合格基準まで紹介!

二級ボイラー技士とは?仕事内容や魅力、業界の将来性まで解説
