就職や転職に有利な「危険物取扱者」は、資格手当やキャリアアップにもつながるため、取得を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ勉強を始めようと思っても、「どのような問題が出るのだろう?」「どうやって対策すればいいの?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくありません。
この記事では、危険物取扱者試験の概要から、出題傾向、効率的な勉強方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。これから資格取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
公開日:2025年9月30日 更新日:2025年9月30日
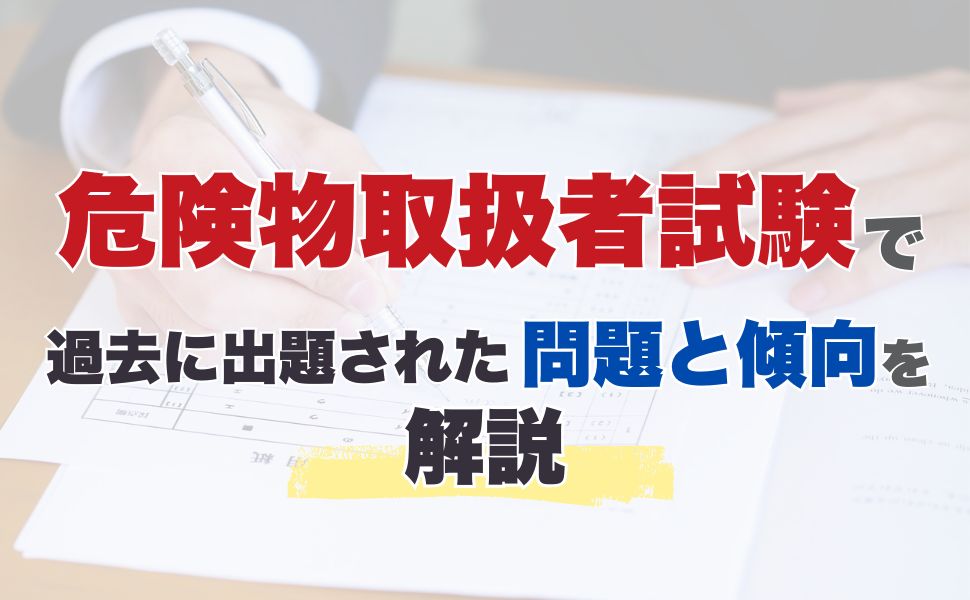
就職や転職に有利な「危険物取扱者」は、資格手当やキャリアアップにもつながるため、取得を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ勉強を始めようと思っても、「どのような問題が出るのだろう?」「どうやって対策すればいいの?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくありません。
この記事では、危険物取扱者試験の概要から、出題傾向、効率的な勉強方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。これから資格取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

危険物取扱者とは、消防法で定められた危険物を取り扱うために必要な国家資格を持つ人のことです。ガソリン・灯油・軽油などの液体燃料や、塗料、化学薬品など、私たちの身近には多くの危険物が存在します。これらの危険物は、火災や爆発などの事故につながる可能性があるため、安全に取り扱うためには専門知識を持つ人材が必要です。
危険物取扱者は、大きく分けて甲種・乙種・丙種の3つの区分があり、それぞれ扱える危険物の種類が異なります。
危険物取扱者試験は、マークシート形式で出題され、各科目で60%以上の正答率が合格基準となります。各区分の試験科目と問題数は、以下の通りです。
甲種危険物取扱者
| 科目 | 問題数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 15問 |
| 物理学および化学 | 10問 |
| 危険物の性質、火災予防、消火方法 | 20問 |
甲種の試験は総問題数45問で、試験時間は2時間30分です。回答は五肢択一式で行われ、出題範囲が広いため、計画的な学習が合格のポイントとなります。
乙種危険物取扱者
| 科目 | 問題数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 15問 |
| 基礎的な物理学および基礎的な化学 | 10問 |
| 危険物の性質、火災予防、消火方法 | 10問 |
乙種の試験は総問題数35問で、試験時間は2時間です。五肢択一式で回答し、各類の危険物に特化した知識が問われるため、受験する類の重点的な対策が重要です。
丙種危険物取扱者
| 科目 | 問題数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 10問 |
| 燃焼および消火に関する基礎知識 | 5問 |
| 危険物の性質並びに火災予防及び消火の方法 | 10問 |
丙種の試験は、総問題数が25問で、試験時間は1時間15分です。四肢択一式で回答する形式ですが、問題数が少ない分、一つのミスが合否に影響しやすいため、基礎知識を確実におさえる必要があります。
いずれの科目も、危険物を安全に取り扱うために不可欠な知識です。特に乙種第4類は、他の類と比較しても受験者数が非常に多く、ガソリンスタンドや化学工場などで需要が高い資格です。
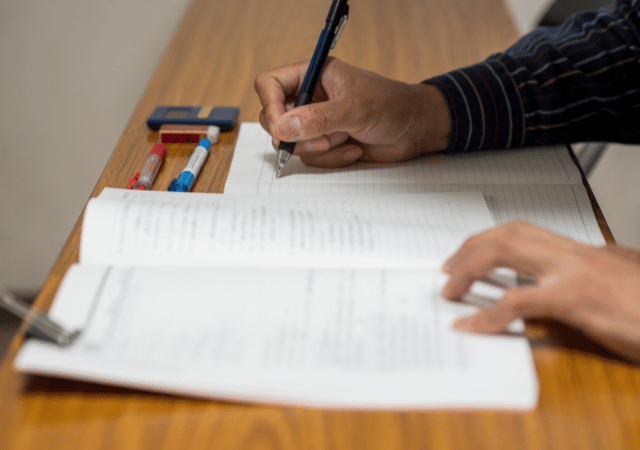
危険物取扱者試験は、過去問が公表されていません。試験終了後に問題用紙と解答用紙が回収されるため、問題を持ち帰ることはできないのです。このため、他の資格試験のように過去問を繰り返し解く勉強法は難しい現状があります。
しかし、市販の教材やウェブサイト、通信講座などでは、過去の出題傾向を分析して作成された「予想問題集」が主流となっています。これらの問題を解くことで、試験の傾向を掴み、効率的に学習を進めることが可能です。
ここでは、特に受験者数の多い乙種第4類と丙種の試験で、過去に多く出題されたテーマと問題例を紹介します。
引火性液体を扱う「乙種第4類」の試験では、危険物の性質や法令に関する問題が多く出題されます。
危険物に関する法令
基礎的な物理学および基礎的な化学
危険物の性質、火災予防、消火方法
「丙種」は、乙種第4類に比べて難易度は低いですが、問題数が少ないため一つのミスが合否に響く可能性があります。
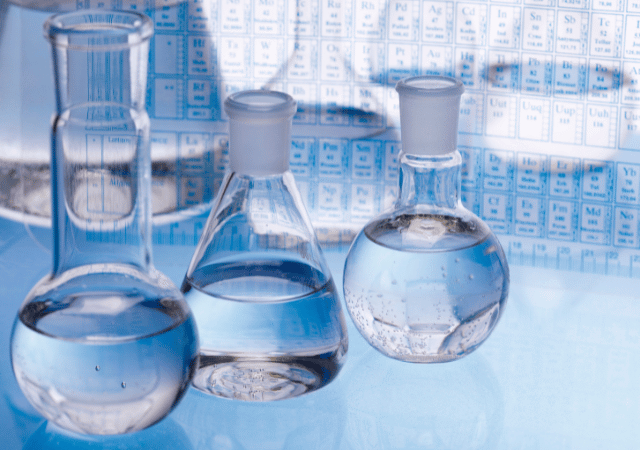
危険物取扱者試験の出題傾向は、毎年大きく変わることはありません。特に法令と危険物の性質に関する問題は、基礎知識を問うものが繰り返し出題される傾向があります。
| 法令 | 危険物の取り扱いに関するルールや規制。安全を確保するために最も重要な項目であるため、指定数量や施設の基準、保安講習など実務に直結する知識が重点的に問われる。 |
|---|---|
| 物理・化学 | 高校で学ぶ化学の基礎知識がベースとなっています。難しい計算問題よりも、物質の性質や変化に関する基本的な理解が問われることが多いです。 |
| 性質 | 危険物の特徴を正確に把握しているかが問われます。例えば、ガソリンの引火点が何度か、引火点と発火点の違いは何か、といった暗記系の問題が多くなります。 |
また、甲種、乙種、丙種の各区分で出題形式にも違いがあります。
丙種は選択肢が少ない分、比較的取り組みやすいと言えますが、前述の通り1問ごとの重みが増すため油断はできません。
試験対策においては、これらの出題傾向を理解し、効率的に学習を進めることが大切です。
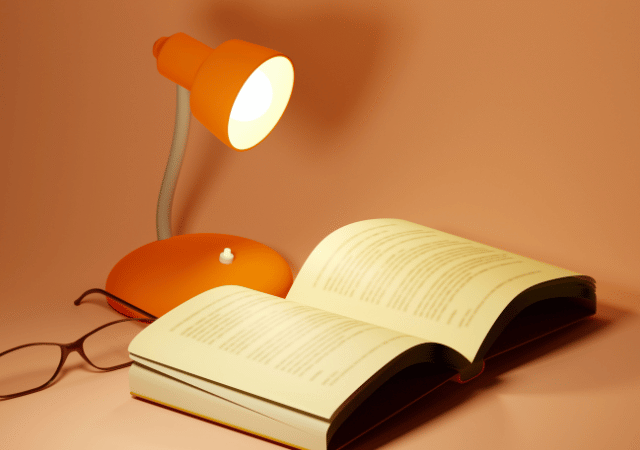
危険物取扱者試験の勉強は、ただやみくもに暗記するだけでは非効率です。以下に、合格への近道となる効果的な勉強方法をご紹介します。
まずは、試験の全体像を把握するため、最新のテキストを読み込みましょう。古いテキストは、法改正などに対応していない可能性があるため、必ず最新版を選んでください。
テキストを読む際は、単に内容を追うだけでなく、図や表、イラストが多く使われているものを選ぶのがおすすめです。特に物理や化学、危険物の性質に関する内容は、視覚的に理解することで知識が定着しやすくなります。
勉強する順番としては、まずは「物理・化学」の基礎を固め、次に「危険物の性質」、最後に「法令」を学ぶのがおすすめです。法令は、物理・化学や危険物の性質を理解していると、より内容が頭に入りやすくなります。
ある程度インプットが完了したら、実際に問題を解いてみましょう。前述の通り、試験問題は持ち帰ることができないため、市販の予想問題集を活用することが不可欠です。
問題を解くことには、主に二つの目的があります。一つは知識の定着、もう一つは出題傾向の把握です。
間違えた問題や、正解したものの自信がなかった問題については、必ず解説を読み込んで理解を深めましょう。なぜその答えになるのか、関連する知識は何があるのかを把握することで、応用力が身につきます。
また、問題を解くことで、自分の苦手な分野が明確になります。苦手分野を特定したら、テキストに戻って集中的に復習することで、効率的に弱点を克服できるでしょう。
独学での勉強が不安な方や、仕事と両立しながら短期間で合格を目指したい方は、通信講座やオンライン学習サービスの活用が有効です。
通信講座やオンライン学習サービスは、以下のようなメリットがあります。
自分に合った学習ツールを見つけることで、モチベーションを維持しながら、合格までの道のりをスムーズに進められるでしょう。
試験スケジュールや合格率については、こちらのページで詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

この記事では、危険物取扱者試験について、資格の概要から出題傾向、効果的な勉強方法までを解説しました。危険物取扱者の資格を取得すれば、専門知識が身につくだけでなく、就職やキャリアアップの大きな武器になります。
合格を目指すためには、単に暗記するだけでなく、出題傾向を把握し効率的に学習することが大切です。しかし、危険物取扱者試験の過去問は公開されていないため、独学だと不安に感じるかもしれません。
CIC日本建設情報センターでは、そんな方のために、過去の出題傾向を徹底分析したオリジナルの教材とカリキュラムで学べる対策講座を提供しています。プロの講師が合格に必要なポイントを絞り込んで解説するので、忙しい方でも最短ルートでの合格を目指すことが可能です。これから資格取得に挑戦したい方は、ぜひ「危険物取扱者」の詳細をご確認ください。
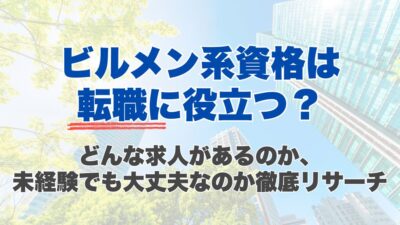
ビルメン系資格は転職に役立つ?どんな求人があるのか、未経験でも大丈夫なのか徹底リサーチ
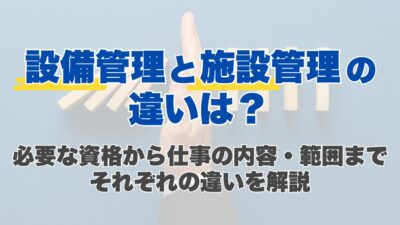
「設備」管理と「施設」管理の違いは?必要な資格から仕事の内容・範囲までそれぞれの違いを解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介

建設業の主な職種一覧!仕事内容や平均年収について解説 – 建設キャリア転職 –
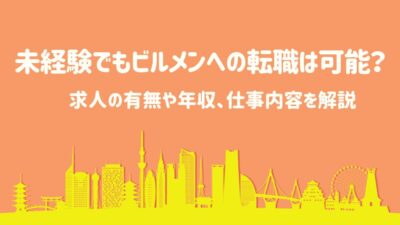
未経験でもビルメンへの転職は可能?求人の有無や年収、仕事内容を解説 – 建設キャリア転職 –
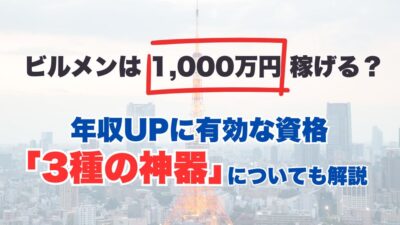
ビルメンは1,000万円稼げる?年収UPに有効な資格「3種の神器」についても解説

30代〜40代のビルメン転職は未経験でも売手市場!転職のポイントを解説

ビルメンを定年後のセカンドキャリアにおすすめする理由を徹底解説 – 建設キャリア転職 –
