公開日:2025年3月12日 更新日:2025年3月12日
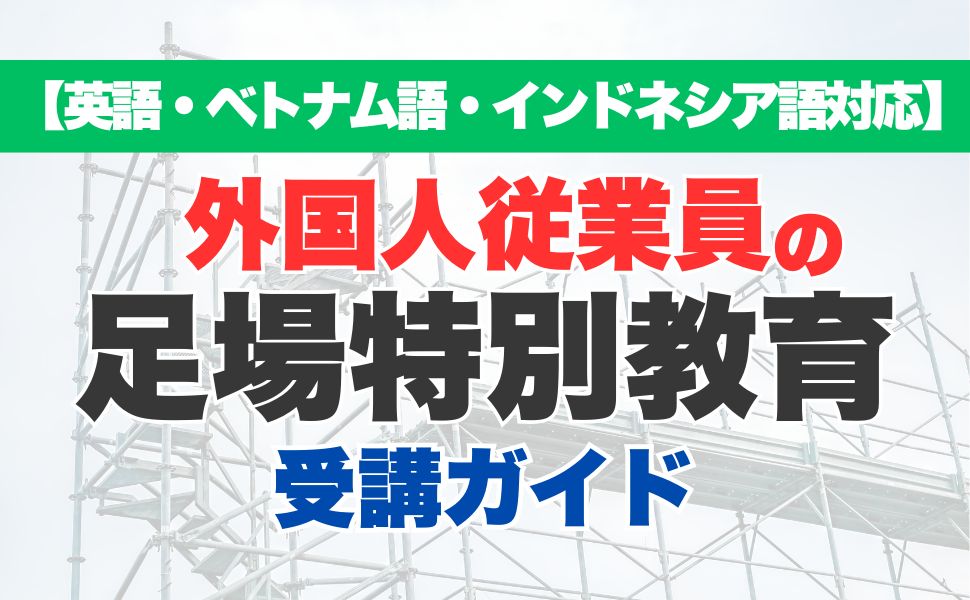
作業現場において、足場を組む必要がある場合、その業務に携わる作業員には「足場の組立て等の業務に係る特別教育(以下:足場特別教育)」を受講してもらう必要があります。
これは、日本人労働者はもちろんのこと、外国人労働者も同様です。外国人労働者を雇用している雇用者の方は、しっかりと受講方法を検討しなければいけません。
外国人労働者の方が足場特別教育を受講する方法や、受講に関する注意点などを詳しく解説していきます。

足場に関する基礎的な知識から、労働災害の防止に関する知識まで身に着ける教育が、足場特別教育です。
足場特別教育は受講義務があり、足場の組み立てに携わる外国人労働者も受講しなければいけません。
足場特別教育の受講義務があるのは、足場を組む作業に携わるすべての従業員です。業務上足場を組む機会がある業種の場合、原則全作業員に受講義務が発生します。たとえ外国人労働者の方でも、日本国内の作業現場で足場を建築する以上は足場特別教育を受講し、修了しなければいけません。
労働安全基準法で受講が義務付けられているため、受講しないまま業務に就いた場合は、従業員はもちろんのこと雇用者にも罰則が発生します。
足場特別教育の内容について紹介していきましょう。
| 受講科目 | 受講時間(最低限の目安) |
|---|---|
| 足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 30分 |
| 労働災害の防止に関する知識 | 1時間30分 |
| 関係法令 | 1時間 |
| 合計受講時間 | 6時間 |
定められた受講内容と受講時間は上記の通りです。講義はすべて学科科目のみです。
足場特別教育は、業務のために受講必須な講習となりますので、原則として就業時間内に受講することが求められます。作業員が受講している間は通常の業務ができないため、雇用者は自社の業務を調整しつつ受講してもらうことがポイントです。
足場特別教育の受講方法は、主に4つあります。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、雇用者側は自社にとって最適な方法を選ぶ必要があります。とくに外国人労働者は受講方法が限られますので、その点も考慮して考える必要があるでしょう。

足場特別教育の受講方法のなかでも、もっともおすすめの方法がWeb(オンライン)受講です。
Web(オンライン)受講であれば、何より自社内で完結可能です。外部の講習会に出席する場合は、講習会の会場までの移動を考える必要があります。外部の講習会といっても、自社の近隣で行われているとは限りません。場合によっては長い移動時間が必要なケースも考えられます。こうした時間的なロスもかからず、移動費用なども不要な点が、Web(オンライン)講習のメリットです。
さらに、外部の講習は自社のタイミングで受講が難しいデメリットもあります。外部講習会は常に開催されているわけではありません。講習会を実施する企業や団体の指定した日程でしか受講できません。そのタイミングが自社の業務が多忙なタイミングだった場合、受講が難しいでしょう。その点、Web(オンライン)受講であればクリアできます。
Web(オンライン)講座の場合、専門講師の良質な講義が受講できるメリットもあります。自社内で講師を選任する場合、講師役に選任した従業員は、足場の組み立てに関する知識はあっても、他人に講義をする専門家ではありません。どこまで講義の質を担保できるかが疑問です。
また、外部から講師を招いて開催する際に、自社で受講する従業員が少数の場合は一人あたりの費用が高くなる問題もあります。また、少人数の受講では講師の派遣が受けられない場合もあり、利用できる企業が限定されるのもデメリットでしょう。
デメリットが少なく、メリットが大きいという点で、Web(オンライン)講座を利用するのが、もっともおすすめの受講方法といえます。

外国人労働者の方に足場特別教育を受講してもらう場合、雇用者側が注意すべきは外国人労働者の日本語能力の把握です。日本にきて間もなく、日常会話すら難しいのでは、そもそも特別教育の受講自体が難しくなります。受講には最低でも日常会話程度の日本語能力は必要です。
外国人労働者の日本語能力によって、どのような受講方法を考えるべきか解説していきましょう。
日本語が問題なく理解できて、足場特別教育で使用される専門用語に関しても理解可能なレベルであれば、日本人労働者と同様に足場特別教育を受講が可能です。この場合は、外国人労働者に合わせて受講方法を考える必要はありません。
外国人労働者の日本語能力が、日常会話を理解できる程度の場合は受講方法を考慮しなければなりません。通常のコミュニケーションは取れるものの、専門用語などに関しては理解が難しいというのは、外国人労働者の平均的な日本語能力といえます。この場合考えられる受講方法は以下の通りです。
外部の講習会の中には、日本語以外の言語で講習を提供しているケースがあります。提供されているのはベトナム語やインドネシア語、中国語、英語などによる講習が中心です。こうした講習であれば、受講者の日本語能力を問わずに受講・修了が目指せるでしょう。ただし、実施している団体はそう多くありませんし、実施数も少ないのが問題です。
また、日本語で行う講習でも、通訳者の同席が認められているケースもあります。こうした講習であれば、日本語能力が不足している外国人労働者の方でも受講可能です。ただし、通訳者が通訳できるのは、専門用語に関してのみとなりますので、それ以外の日本語による解説を理解できなければいけません。かなり高いレベルの日本語能力がある方のみが利用できる方法といえます。
比較的利用しやすいのは字幕付きの講習でしょう。Web(オンライン)講習を受講した際に、外国人労働者が理解できる言語の字幕がついていれば、ある程度の日本語能力での受講が可能です。また、Web(オンライン)受講ですので、理解が難しい部分は一時停止などの対応も可能であり、現実的な受講方法といえます。

CIC日本建設情報センターでは、足場特別教育の字幕講習を提供しています。字幕に関するポイントやCIC日本建設情報センターの足場特別教育の特徴を紹介していきましょう。
CIC日本建設情報センターでは、英語・ベトナム語・インドネシア語字幕による足場特別教育のWeb(オンライン)講座を提供しています。日本で働くベトナム・インドネシアの方でも安心して受講できる講義となっており、多くの外国人労働者の方に対応できる講座です。
CIC日本建設情報センターでは、受講者個々にアカウントを発行しています。そのため受講者それぞれが、自身の業務の合間を使って効率的に受講できます。
また、字幕が読み取りにくい部分の一時停止なども、受講者それぞれのタイミングで活用できるため、内容をしっかりと理解できるという点でもおすすめです。
Web(オンライン)講座の数少ないデメリットとして、講師が不在という点が挙げられます。講師がいないため、受講者の受講中の様子を監視する存在がなく、受講者がきちんと受講しているか確認しづらい問題があるのです。
CIC日本建設情報センターでは顔認証システムを採用し、受講者の受講状況の確認を行っています。講義動画の再生中、画面の前に受講者がいないと判断したら自動的に講義動画が停止するシステムとなっていますので、確実に受講してもらえます。
CIC日本建設情報センターの足場特別教育は、修了証の発行にも対応しています。修了証はPDFタイプとカードタイプの2パターンがあり、それぞれ発行しますので、作業現場で資格の提示が必要な場合でも対応可能です。

足場特別教育は受講義務のある講習ですので、足場の組み立てに関わるすべての作業員が受講しなければいけません。これは外国人労働者も同様です。受講義務に違反した場合は雇用者側にも罰則がありますので、確実に受講してもらうようにしましょう。
外国人労働者の場合、日本語能力によって受講方法を検討する必要があります。外国人労働者の日本語能力に合わせて受講方法を検討してください。
おすすめはCIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座です。CIC日本建設情報センターの足場特別教育には、英語・ベトナム語・インドネシア語字幕がついていますので、多くの外国人労働者の方が受講可能です。
講義内容の質が高く、また受講確認の方法もしっかりしていますので、外国人労働者の方にもしっかりとした知識を身に着けてもらえるでしょう。
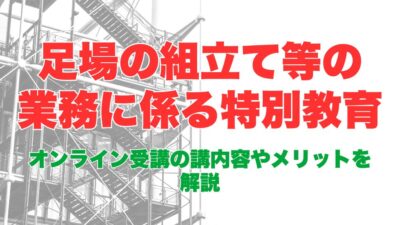
足場の組立て等の業務に係る特別教育はオンライン受講がおすすめ!受講方法から流れ、メリットまで解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介
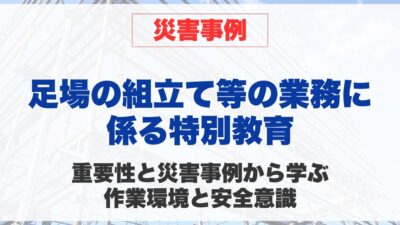
足場の組立て等の業務に係る特別教育の重要性と災害事例から学ぶ作業環境と安全意識
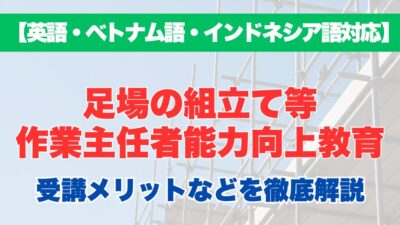
【外国語対応】足場の組立て等作業主任者能力向上教育の受講するメリットなどを徹底解説!
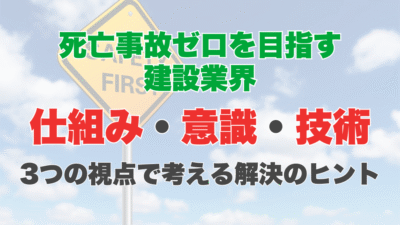
死亡事故ゼロを目指す建設業界 仕組み・意識・技術、3つの視点で考える解決のヒント
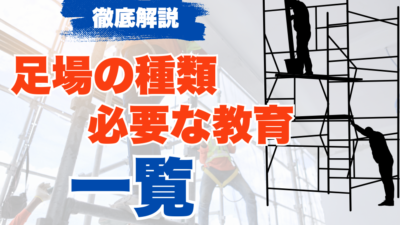
足場の種類と特徴を必要な教育と合わせて一覧で解説

足場組立作業の主任者と作業者の違い、特別教育と技能講習の違い、申し込み方法などを解説

高所作業は重大な労働災害が発生しやすい危険な作業!確実な安全対策を取ろう
