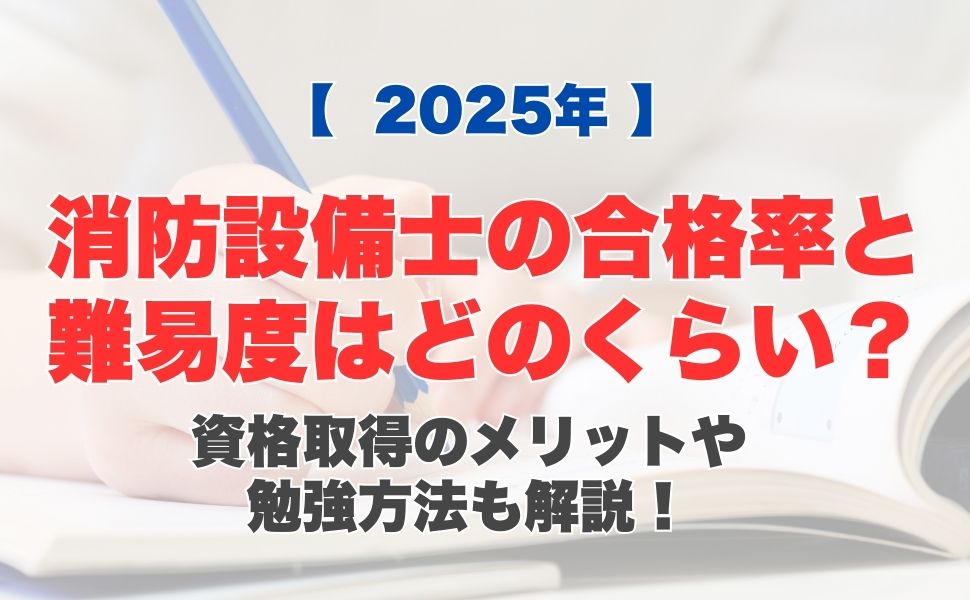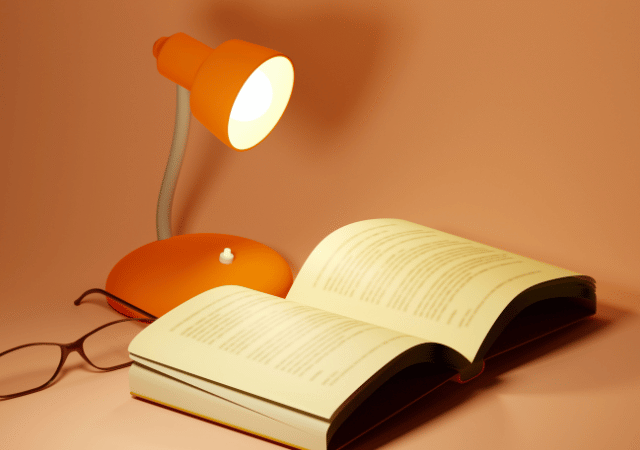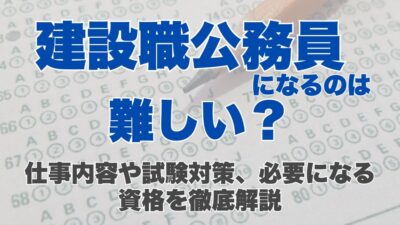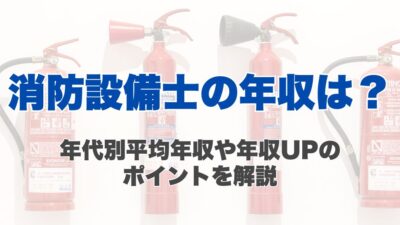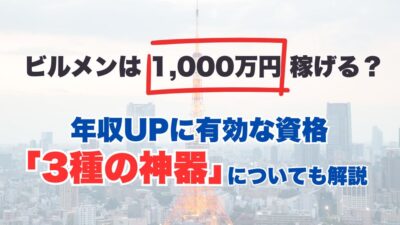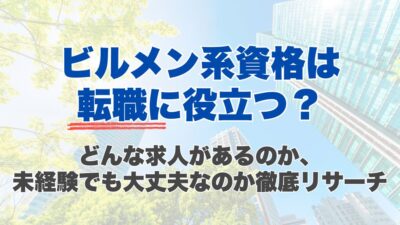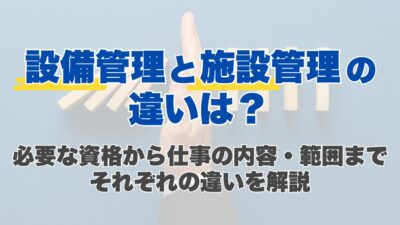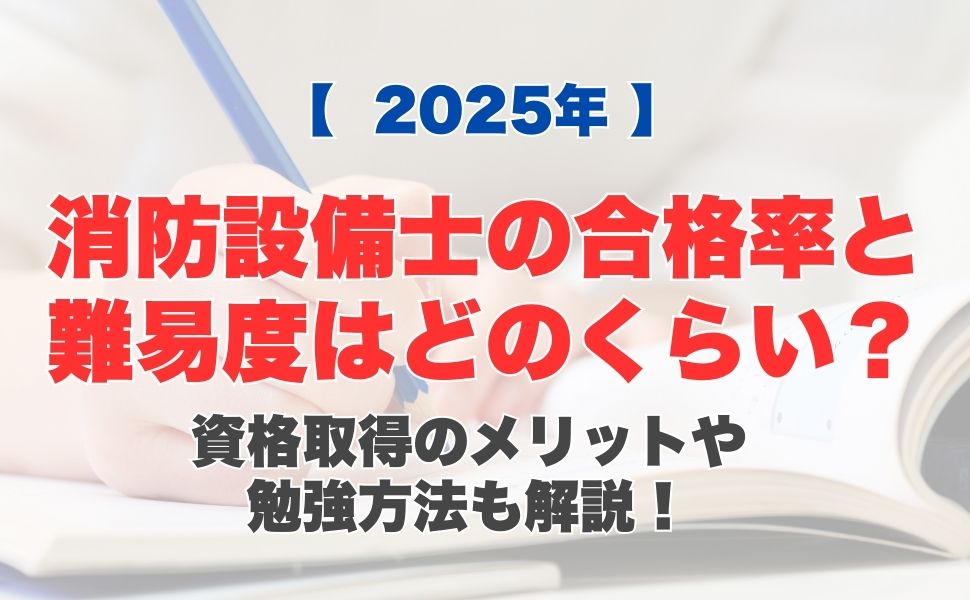
消防設備士試験では、甲種と乙種の2つに分類され、甲種は第1類から第5類まで、乙種は第1類から第7類までの区分が設けられています。それぞれの区分ごとに難易度が異なるため、受験する区分の合格率や難易度を把握した上で試験対策に臨むことが大切です。
また、試験の実施回数は地域ごとに異なります。多い地域になると1カ月に1回のペースで実施されますが、少ない場合は年1~2回しか実施されません。受験する地域の実施回数を把握し、申し込みに遅れないよう注意してください。
この記事では、消防設備士試験の難易度や合格率について解説します。試験の概要や試験対策のポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

消防設備士試験の概要

消防設備士試験は、消火器やスプリンクラー、火災報知器などの消防設備の点検・整備・工事を行えるようになる国家資格試験です。甲種と乙種の2つに分類され、甲種は第1類から第5類まで、乙種は第1類から第7類までの区分があります。
| 区分 |
取扱い設備 |
甲種(工事・整備・点検) |
乙種(整備・点検のみ) |
| 特類 |
特殊消防用設備など
(従来の消防用設備などに代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備など) |
〇 |
- |
| 第1類 |
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備
パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備 |
〇 |
〇 |
| 第2類 |
泡消火設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 |
〇 |
〇 |
| 第3類 |
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備 |
〇 |
〇 |
| 第4類 |
・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備
・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備 |
〇 |
〇 |
| 第5類 |
金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
〇 |
〇 |
| 第6類 |
消火器 |
- |
〇 |
| 第7類 |
漏電火災警報器 |
- |
〇 |
まずは、消防設備士試験の概要や日程についてみていきましょう。
消防設備士試験の概要
以下の表は、消防設備士試験の概要に関してまとめたものです。
| 項目 |
区分 |
詳細 |
| 試験方法 |
甲種 |
筆記:全区分の試験共通で四肢択一式
実技:写真・イラスト・図面等による記述式 |
| 乙種 |
| 問題数 |
甲種 |
筆記45問+実技7問 |
| 乙種 |
筆記30問+実技5問 |
| 試験時間 |
甲種 |
3時間15分(特類以外)
※特類:2時間45分 |
| 乙種 |
1時間45分 |
| 合格基準 |
甲種 |
・筆記:各科目ごとに40%以上、かつ全体で60%以上の正答率
・実技:60%以上の正答率
※甲種特類:各科目ごとに40%以上で全体の出題数の60%以上の正答率 |
| 乙種 |
| 受験資格 |
甲種 |
受験資格・学歴・実務経験で受験資格が分類されており、いずれかを満たす必要がある |
| 乙種 |
特になし |
試験は筆記試験と実技試験で構成されており、各試験で合格基準が異なります。また、乙種は誰でも受験可能ですが、甲種は実務経験や関連資格の保有など、一定の条件を満たす必要があります。
受験する区分の問題数や合格基準、受験資格などをチェックしておきましょう。
【令和7年度】試験日程
消防設備士の試験日程は、実施される地域によって異なります。多い地域になると1カ月に1回のペースで実施されますが、少ない場合は年1〜2回しか実施されません。
例えば、令和7年度における関東エリアの試験回数・直近の実施日に関して、以下の表をご覧ください。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 茨城県 |
9月5日 |
4回 |
| 栃木県 |
9月14日 |
2回 |
| 群馬県 |
8月30日 |
2回 |
| 埼玉県 |
6月15日 |
3回 |
| 千葉県 |
8月30日 |
2回 |
| 東京都 |
7月6日 |
各区分ごとに6回前後 |
| 神奈川県 |
6月22日 |
2回(乙6のみ4回) |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載
関東エリアだけでみても、地域によって試験回数が異なることが分かります。そのため、自分が受験する地域の試験回数や日程などを事前に確認しておくことが大切です。
各エリアの実施スケジュールや試験会場の傾向などは、こちらのページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
【こちらもチェック】【2025年】消防設備士試験の日程と申込み方法は?あわせて取得していると有利な他講座も紹介!
消防設備士試験の合格率と難易度

続いて、消防設備士試験の合格率と難易度について詳しく解説します。消防設備士試験がどの程度の難しさなのかをイメージしていきましょう。
合格率
以下の表は、消防設備士試験の中でも受験者の多い区分である、第4類・乙種6類における過去5年間の合格率をまとめたものです。
| 実施年度 |
乙種6類 |
乙種4類 |
甲種4類 |
| 2024年度(令和6年度) |
36.2% |
31.2% |
34.0% |
| 2023年度(令和5年度) |
38.1% |
34.4% |
32.3% |
| 2022年度(令和4年度) |
38.8% |
32.8% |
34.4% |
| 2021年度(令和3年度) |
39.9% |
35.0% |
37.1% |
| 2020年度(令和2年度) |
42.7% |
35.4% |
37.2% |
表を見ると、消防設備士試験の合格率は30%〜40%で推移していることがわかります。合格率が高いと40%を超えるケースはありますが、逆に30%を下回る年度は見られませんでした。
また、甲種と乙種で比較しても合格率は大きく変わりません。ただし、甲種は乙種と違って受験資格が求められたり問題数自体は多くなったりするため、難易度自体は甲種のほうが高いといえます。
難易度
消防設備士の合格率は30%〜40%が目安ですが、資格の難易度でいえば特別高いものでないといえるでしょう。難易度の高い資格になると合格率は10%前後であったり、20%を下回るケースが多く見られるためです。
例えば、電気系で難易度の高い資格に「電気主任技術者試験」、通称「電験」と呼ばれるものがありますが、その中の電験三種は例年の合格率が10%前後の資格です。逆に、電気系の中でも難易度のやさしい資格である「第二種電気工事士」は、例年の合格率が例年40%〜60%を推移しています。
このことから見ても、消防設備士の資格は決してやさしいとは言えないまでも、合格まで多くの時間を要したり例年の合格者が限りなく少なかったりするなどの高難易度の試験でないといえるでしょう。
ただし、闇雲に勉強して合格できるわけではありません。試験日までのスケジュールを立てて効率的に学習することは必要不可欠です。学習のポイントは後述しますので、ぜひ参考にしてみてください。
資格取得のメリット

消防設備士の資格を取得することで得られるメリットは、主に以下のとおりです。
それぞれのメリットについてみていきましょう。
転職に有利になる
消防設備士の仕事は法律で定められたものであり、あらゆる建物に消防設備が設置されていることから、消防設備士の資格は非常に需要の高いものであるといえます。将来的にも安定しているため、転職などでも有利に働くでしょう。
まずは、消防設備士の中でも需要の高い乙種6類や第4類(乙種・甲種)の取得を目指すのがおすすめです。その後、関連する資格も取得して活躍の場を広げることで、より付加価値の高い技術者となれます。
不可欠なことから、その需要は非常に高く、将来的にも安定しています。このため、消防設備士の資格を保有していることは、就職やキャリアチェンジにおいて大きな強みとなります。
ご自身のキャリアプランに応じて必要な資格を見極めながら、転職活動を進めてみてください。
資格手当がつく職場もある
企業によっては、消防設備士の資格を持つ技術者に毎月一定の資格手当を支給しています。支給額は勤務先で異なりますが、一般的に3,000円から5,000円が目安です。
さらに、消防設備士以外の資格も保有していれば、資格手当額が増額され、実質的な年収アップにつながることも珍しくありません。持っているだけで収入が上がる資格手当は、消防設備士試験の取得を目指す大きなメリットといえるでしょう。
合格を目指した勉強法

消防設備士試験の勉強方法は、主に参考書と問題集を併用して行うものとなります。参考書・問題集は何冊も購入する必要はなく、自分に適したものを1冊ずつ選んでやり込むのが費用的にもおすすめです。
また、学習する際はテキストを暗記するのではなく、1つずつ理解しながら進めることをおすすめします。その後、問題集を解きながらわからない問題や間違えた問題を再度参考書で確認し、知識を少しずつ定着させていきましょう。
消防設備士の試験は、全体60%の正答率以外に、科目ごとに40%以上の点数を獲る必要があります。そのため、得意科目はより正答率を高め、苦手科目は解けない問題を少しずつ減らして科目単位での正答率を高めるよう対策してみましょう。
試験に合格するためにはどの科目においても合格基準を満たせるよう、バランスよく勉強することが大切です。
試験対策講座の対策も
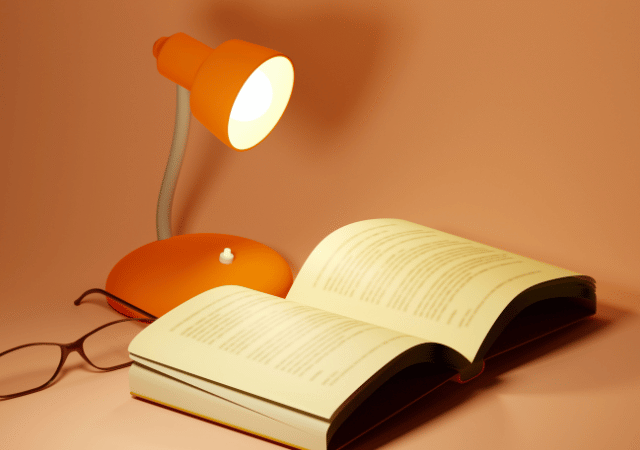
消防設備士試験は、独学以外にも通信講座などの試験対策講座の利用でも合格を目指せます。通信講座の利用は、独学ではどうもはかどらない、勉強する時間を確保できないくらい忙しい、より効率よく短時間で試験に合格したいという方におすすめです。
基本的に通信講座は、テキスト・問題集以外にも専門講師による動画講義で学習を進めます。専門講師による解説によって最短距離で合格を目指せるのがメリットです。また、わからないことはメール等で相談ができるなど、独学にはないサポートも受けられます。
CIC日本建設情報センターでも、消防設備士試験の通信講座を提供しております。受験者がモチベーションを維持しながら効率的に学習できる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
まとめ

この記事では、消防設備士試験の難易度や合格率について、試験の概要や試験対策のポイントと合わせてご紹介しました。
消防設備士試験の合格率は乙種や甲種、区分によって異なります。合格率の高い試験では40%付近、低い試験だと30%付近で推移している傾向です。受験する区分の合格率を把握し、自分に適した対策方法を実践してみましょう。
また、試験合格を目指す上で大切なのは計画的に対策を始めることです。試験日から逆算してスケジュールを立てて、参考書と問題集を併用しつつ、基礎的な内容から実践的な内容まで学びましょう。社会人の方でまとまった時間を確保しづらい方は、より効率的に学習できるWeb講座などの受講もおすすめです。
CIC日本建設情報センターでは、消防設備士試験のWeb講座を提供しております。受験者がモチベーションを維持しながら効率的に学習できる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。