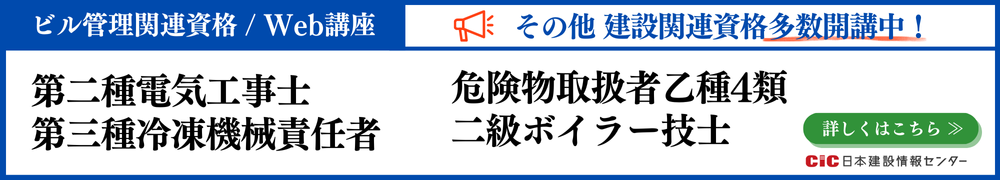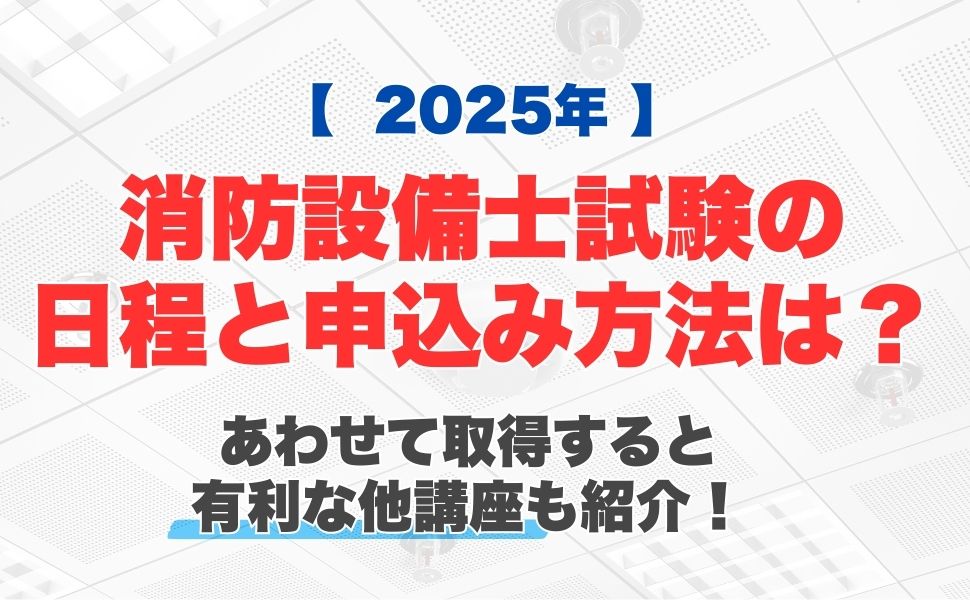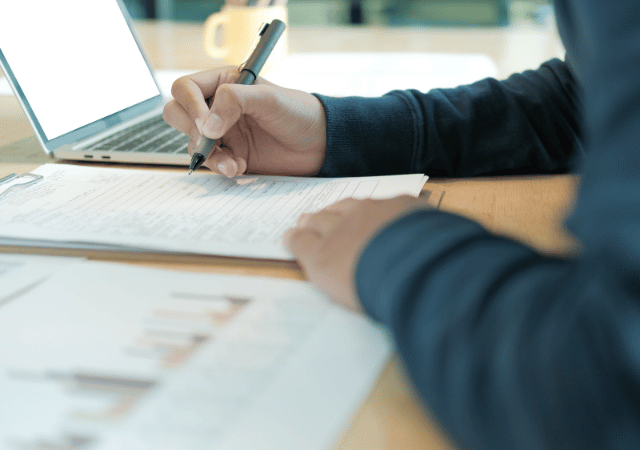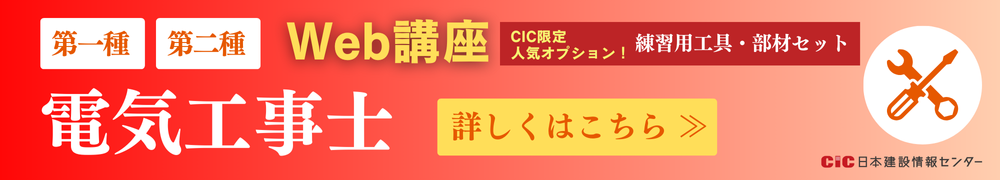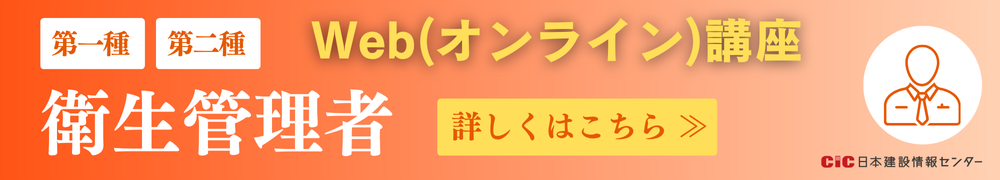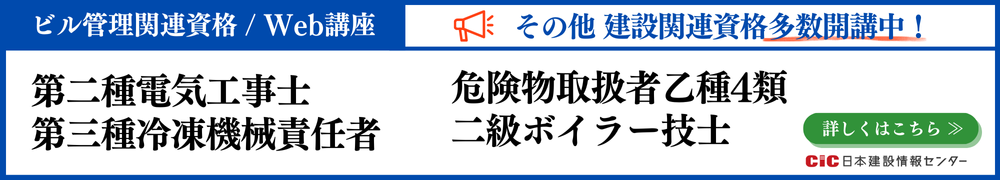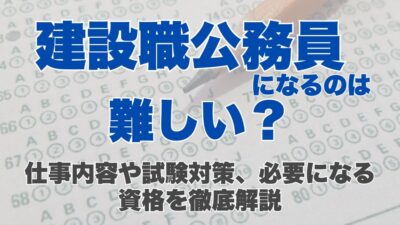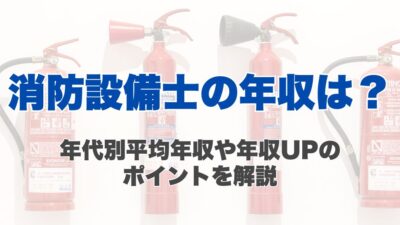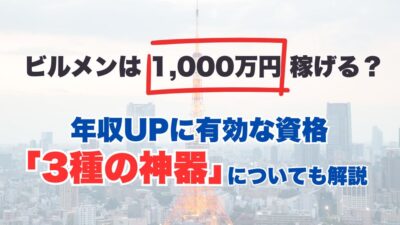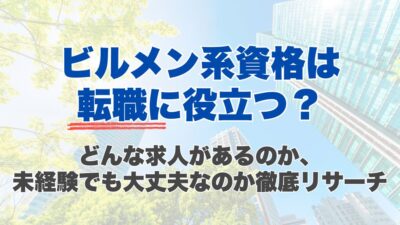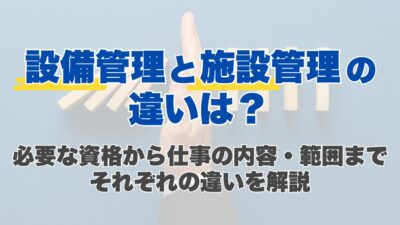【エリア別】消防設備士試験の試験会場と試験スケジュール

消防設備士試験は、全国47都道府県で実施されています。
- 北海道・東北エリア
- 関東エリア
- 甲信越・北陸エリア
- 東海エリア
- 近畿エリア
- 中国エリア
- 四国エリア
- 九州・沖縄エリア
お住まいの地域や通勤・通学先など、アクセスしやすい会場を選んでの受験が可能です。ただし、実施スケジュールも地域ごとに異なるため、申込みするよりも前に受験する地域の情報をチェックしておきましょう。
北海道・東北エリア
ここでは、北海道・東北エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
北海道・東北エリアの試験会場
北海道・東北エリアでは、各主要都市で試験が実施されています。北海道では札幌市、函館市、旭川市、北見市、苫小牧市、帯広市、釧路市などで試験が行われており、受験者の利便性を考慮した会場設定となっています。
東北エリアでは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の各県で試験が実施されています。各県の県庁所在地を中心に試験会場が設けられており、人口の多い箇所で受験が可能です。また、中心部以外でも試験会場が確保されて受験機会が確保されています。
北海道・東北エリアの試験スケジュール
以下の表は、北海道・東北エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 北海道 |
6月15日 |
9回 |
| 青森県 |
7月12日 |
6回 |
| 岩手県 |
8月23日 |
4回 |
| 宮城県 |
6月22日 |
3回 |
| 秋田県 |
8月17日 |
3回 |
| 山形県 |
5月24日 |
5回 |
| 福島県 |
8月30日 |
2回 |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
関東エリア
ここでは、関東エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
関東エリアの試験会場
関東エリアは全国でも特に試験実施回数が多い地域です。東京都では中央試験センターで試験が実施されており、受験者数の多さから頻繁に試験が開催されています。神奈川県では神奈川大学や専修大学が主な試験会場です。
埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県でも県庁所在地を中心に試験が行われています。
中でも東京都は、月1回のペースで試験が実施されているため、他県から受験するケースも珍しくありません。東京都で受験する場合は、交通のアクセスなどもチェックしておくと良いでしょう。
関東エリアの試験スケジュール
以下の表は、関東エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 茨城県 |
9月5日 |
4回 |
| 栃木県 |
9月14日 |
2回 |
| 群馬県 |
8月30日 |
2回 |
| 埼玉県 |
6月15日 |
3回 |
| 千葉県 |
8月30日 |
2回 |
| 東京都 |
7月6日 |
各区分ごとに6回前後 |
| 神奈川県 |
6月22日 |
2回(乙6のみ4回) |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
甲信越・北陸エリア
ここでは、甲信越・北陸エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
甲信越・北陸エリアの試験会場
甲信越・北陸エリアでは、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県の各県で試験が実施されています。
山梨県では甲府市、長野県では長野市や松本市などで試験が行われています。新潟県も同様、新潟市を中心に上越市や長岡市などで実施されています。富山県、石川県、福井県でも、各県の県庁所在地近辺で試験会場が設定されている傾向です。
また、甲信越・北陸エリアは全体的に実施回数が多く、3〜4回実施している県もあります。計画を立てながら受験するタイミングを決めると良いでしょう。
甲信越・北陸エリアの試験スケジュール
以下の表は、甲信越・北陸エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 山梨県 |
8月24日 |
2回 |
| 長野県 |
8月24日 |
4回 |
| 新潟県 |
6月21日 |
3回(特類のみ1回) |
| 富山県 |
8月16日 |
3回 |
| 石川県 |
5月18日 |
4回 |
| 福井県 |
8月31日 |
2回 |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
東海エリア
ここでは、東海エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
東海エリアの試験会場
東海エリアでは、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の各県で試験が実施されています。愛知県では名古屋市で試験が行われており、多くの受験者が集まります。
静岡県や岐阜県、三重県でもそれぞれの県庁所在地を中心に試験会場が設置されています。試験の実施回数としては愛知県が最も多く、岐阜県は年に1回と少ない傾向です。早めの準備・申込みを心がけておきましょう。
東海エリアの試験スケジュール
以下の表は、東海エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 岐阜県 |
7月20日 |
1回 |
| 静岡県 |
8月3日 |
2回 |
| 愛知県 |
5月25日 |
3回 |
| 三重県 |
7月27日 |
2回 |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
近畿エリア
ここでは、近畿エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
近畿エリアの試験会場
近畿エリアでは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県で試験が実施されています。大阪府では大阪大学で試験が行われており、多くの受験者を受け入れています。
京都府、兵庫県でも主要都市を中心に試験会場が設定されており、滋賀県、奈良県、和歌山県でもそれぞれの県庁所在地などで試験が実施されています。一方で試験回数は各府県で大きな差はありません。受験する場所で実施回数をチェックしておきましょう。
近畿エリアの試験スケジュール
以下の表は、近畿エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 滋賀県 |
6月14日~6月17日 |
各区分ごとに3~4回 |
| 京都府 |
7月13日 |
3回 |
| 大阪府 |
7月27日 |
2回 |
| 兵庫県 |
8月2日 |
各区分2回 |
| 奈良県 |
6月22日 |
3回 |
| 和歌山県 |
8月24日 |
2回 |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
中国エリア
ここでは、中国エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
中国エリアの試験会場
中国エリアでは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の各県で試験が実施されています。他のエリアと同様、県庁所在地を中心に試験会場が設定されている傾向です。
中でも、広島県や鳥取県は試験回数が多く、岡山県や山口県は年に1回程度と限られています。そのため、受験する県の回数をチェックして早めの準備を心がけましょう。
中国エリアの試験スケジュール
以下の表は、中国エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 鳥取県 |
7月20日 |
3回 |
| 島根県 |
7月27日 |
2回 |
| 岡山県 |
8月10日 |
1回 |
| 広島県 |
8月31日 |
4回 |
| 山口県 |
9月7日 |
1回 |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
四国エリア
ここでは、四国エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
四国エリアの試験会場
四国エリアでは、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の各県で試験が実施されています。各地域の県庁所在地近辺で試験会場が設定されている傾向です。
また、四国エリアは各県での試験実施回数が比較的少ないため、早めの申込みと計画的な準備が大切となります。
四国エリアの試験スケジュール
以下の表は、四国エリアの直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 徳島県 |
5月24日 |
2回 |
| 香川県 |
8月24日 |
2回 |
| 愛媛県 |
8月3日 |
2回 |
| 高知県 |
7月20日 |
2回 |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
九州・沖縄エリア
ここでは、九州・沖縄エリアの試験会場・試験スケジュールをご紹介します。
九州・沖縄エリアの試験会場
九州・沖縄エリアでは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の各県で試験が実施されています。福岡県では福岡市を中心に試験が行われており、九州エリアの中核として多くの受験者を受け入れています。
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県でもそれぞれ試験会場が設定されており、沖縄県でも西原町などで試験が実施されています。沖縄県においては、石垣市や宮古島島での受験にも対応しているのが特徴です。
九州・沖縄エリアの試験スケジュール
以下の表は、九州・沖縄の直近の実施日・令和7年度の試験回数をまとめたものです。
| 地域 |
直近の実施日※ |
令和7年度の試験回数 |
| 福岡県 |
7月20日 |
2回 |
| 佐賀県 |
7月20日 |
2回 |
| 長崎県 |
8月24日 |
2回 |
| 熊本県 |
8月31日 |
3回 |
| 大分県 |
8月24日 |
2回 |
| 宮崎県 |
8月17日 |
1回 |
| 鹿児島県 |
7月26日 |
1回 |
| 沖縄県 |
6月22日 |
3回(宮古島・石垣市は1回) |
※直近で実施された日にちを記載。実施されていない都道府県については直近で開催される日にちを記載。
消防設備士と相性のよい資格

消防設備士の資格と相性のよい資格は、以下のとおりです。
- 電気工事士(第一種・第二種)
- 危険物取扱者(甲種・乙種)
- 衛生管理者(第一種・第二種)
- ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
それぞれの資格について詳しく解説します。また、CIC日本建設情報センターでは、各資格の講座を提供しておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
電気工事士(第一種・第二種)
電気工事士は、電気設備の工事への従事が可能になる国家資格です。消防設備は電気設備とも関連性があるため、電気工事士の知識があると強みとしてアピールできます。電気系の企業の中には、消防設備の点検を扱うものもあるため、逆に消防設備士をアピールできる場合もあります。
より幅広い現場対応が可能になるため、独立や転職でも有利に働くでしょう。ぜひ取得をご検討ください。
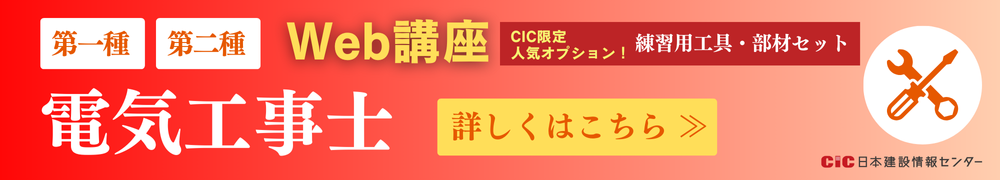
危険物取扱者(甲種・乙種)
消防設備と危険物は安全管理の両輪です。特に消防設備の設置や点検で、危険物の知識が役立つ場面が多くあります。
危険物に関わる施設の安全管理や法令遵守に関しても知識をつけることで、より専門性の高い技術者となれます。結果、技術者としての付加価値が高まり、職場での評価アップや転職でのアピールにつながるでしょう。

衛生管理者(第一種・第二種)
衛生管理者は、労働安全衛生の観点から施設全体の安全管理を担ううえで重要な資格です。消防設備士とも相性が良く、職場の安全管理体制を幅広くサポートできます。
消防設備士として働きつつも、キャリアプランとして管理職や安全衛生担当者を目指す方におすすめです。
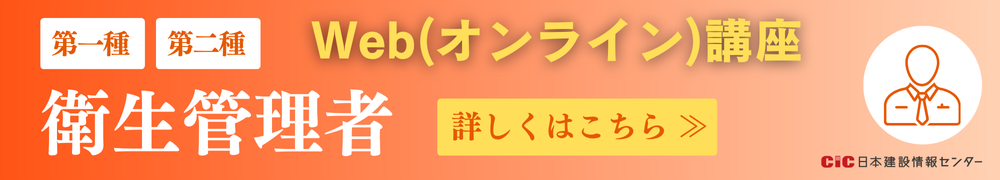
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
ビル管理技術者は、ビルの設備管理全般を担う国家資格です。消防設備の知識と組み合わせることでビル管理の専門性が高まります。
また、ビル管理の仕事においては第二種電気工事士や危険物取扱者乙種4類などの資格とも相性が抜群。複数資格の保有によって技術者としての付加価値も高まるため、転職でのアピール・キャリアアップにもつながるでしょう。