「労働安全衛生法とはどんな法律だろう」「労働安全衛生法の知識を活かせる仕事について知りたい」と考えている方は多いでしょう。
この記事では、労働安全衛生法とはどんな法律か、労働安全衛生法の知識が活かせる仕事、おすすめの勉強方法を詳しく解説します。さらに、建設業界における労働安全衛生法の重要性や、労働安全衛生法の知識が必要になる特別教育についてもご紹介するので、参考にしてみてください。
公開日:2025年10月24日 更新日:2025年10月24日
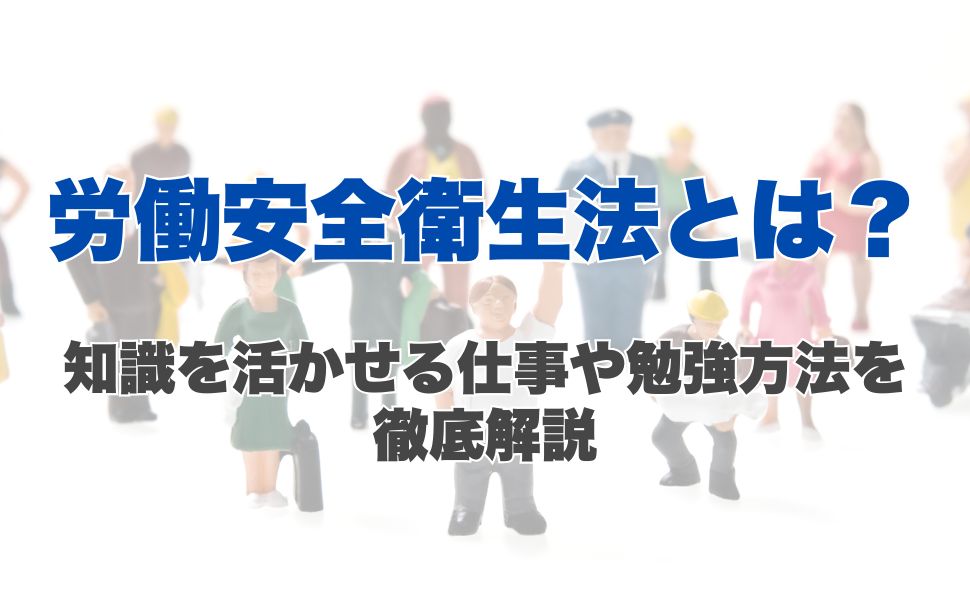
「労働安全衛生法とはどんな法律だろう」「労働安全衛生法の知識を活かせる仕事について知りたい」と考えている方は多いでしょう。
この記事では、労働安全衛生法とはどんな法律か、労働安全衛生法の知識が活かせる仕事、おすすめの勉強方法を詳しく解説します。さらに、建設業界における労働安全衛生法の重要性や、労働安全衛生法の知識が必要になる特別教育についてもご紹介するので、参考にしてみてください。

労働安全衛生法が労働者にとってどんな重要性があるのかを理解するためには、労働安全衛生法とはどんな法律かを知ることが大切です。
こちらでは、労働安全衛生法とはどんな法律か、労働安全衛生法が成立した背景、労働安全衛生法と労働基準法の違いについて解説していきます。
労働安全衛生法とは、「労働者の安全と健康を守る」「快適な職場環境をつくる」という2つの目的でつくられた法律です。
「第1章 総則」「第2章 労働災害防止計画」といった全12章から成り立っており、安全衛生対策を実施するために「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」などを定めています。また、現場での安全と衛生を守るため、一定規模などの条件を満たす事業場では、安全管理者や衛生管理者などのスタッフを配置することも義務付けられています。
労働安全衛生法が成立した背景として、高度経済成長期の大規模工事などで毎年6,000人以上の労働災害死亡者が発生したことが挙げられます。
当時も、「労働基準法」第五章で労働安全衛生関連の規定はありましたが、高度経済成長期の労働環境変化により労働災害が急増したため、法令が整備されて1972年に労働安全衛生法が成立しました。
労働安全衛生法と労働基準法の違いは、以下のとおりです。
| 法律の名称 | 概要 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康を守るため、労働災害の予防や、労働環境の改善を行うための法律 |
| 労働基準法 | 労働条件や労働環境を最低基準で保護するため、最低賃金や最大労働時間、休日などの権利を定める法律 |
上記のように、労働安全衛生法は労働災害を防ぐための法律ですが、労働基準法は労働者の基本的な権利を定める法律という違いがあります。

労働安全衛生法は、全12章によって労働者の安全を守るための規定が定められています。こちらからは、基礎知識として労働安全衛生法の中で事業者が特に注意するべき規定をご紹介していきましょう。
| 事業者が特に注意するべき規定 | 概要 |
|---|---|
| 事業者が守るべきこと | 労働安全衛生法の基準を守るだけでなく、労働者の安全と健康を守るための改善や、国の施策への協力をする必要がある |
| 責任者や委員会の配置 | 管理者や委員会を配置し、安全衛生のための責任体制を明らかにする必要がある |
| 労働者の危険や健康障害を防止するための措置 | 設備や引火、電気などによる危険、ガスや放射線、排気などによる健康障害を防止するための措置を行う必要がある |
| 機械等・危険物・有害物取り扱いの規制 | ボイラーや第一種圧力容器など特定の機械、労働者の大きな健康障害になる危険物や有害物は、製造を禁止するなどの規制がある |
| 安全衛生教育など | 業務の安全衛生のための教育を行う必要があることや、クレーンの運転といった危険性のある業務を行う際には免許などの資格が必要である |
| 健康診断やストレスチェック | 労働者の健康を守るため、医師による健康診断や、医師や保健師によるストレスチェックを行う必要がある |
| 職場環境や作業方法などの改善 | 労働者が快適に働くため、環境整備や作業方法改善などの措置に努めなければいけない |
| 労働基準監督官の立ち入り検査 | 労働基準監督官が必要に応じて事業場の検査などを行い、労働安全衛生法に違反していれば作業停止などが命じられる |
| 安全と健康を守るための内容を周知させること | 労働安全衛生法などの要旨を、作業場の見やすい場所に掲示したり、書面を交付したりなどで周知しなくてはいけない |
| 労働安全衛生法に違反したときの罰則 | 労働安全衛生法に違反する行為の一部を行った場合、罰則を受ける必要がある |
労働安全衛生法には、上記のように労働者の安全と健康や、快適な職場環境をつくるための様々な規定があることを理解しておきましょう。

建設業界において、労働安全衛生法が重要な理由は、以下の3つです。
こちらでは、上記3つの重要性について解説していきます。
建設現場では、高所作業・重量のある建材の運搬・重機の移動などの業務が不可欠なので、事故が発生しやすい環境と考えられます。このため、建設現場において事故から労働者を守るための労働安全衛生法の存在は、非常に重要だといえるでしょう。
建設現場では、粉塵・有害物質・騒音といった健康被害につながるリスクがあります。労働者の安全と健康を守るためにも、これらの健康被害リスクによる被害を防ぐために欠かせない労働安全衛生法が重要となります。
安全と健康のリスクが発生しやすい建設現場では、労働安全衛生法によって義務化されている様々な安全管理があります。例えば、現場の規模によって安全管理者・衛生管理者・産業医を選任し、安全衛生委員会を設置しなければならないといった規定もあります。
このように多様な義務を守り、労働災害を防止するという観点からも、建設業において労働安全衛生法が重要だといえるでしょう。

労働安全衛生法の知識が活かせる代表的な仕事は、以下の3つです。
| 労働安全衛生法の知識が活かせる仕事 | 概要 |
|---|---|
| 安全管理者 | 事業場における労働者の安全管理全般を担当する。建設業などの特定の業種、かつ50人以上の規模といった条件の事業場で選任する必要がある。 |
| 衛生管理者 | 労働者の健康を守るため、事業場の衛生管理や労働者の健康管理を行う仕事。50人以上の労働者数がいる全ての事業場で選任する必要がある。 |
| 総括安全衛生管理者 | 安全管理者や衛生管理者の指揮や、労働者の安全と健康のための措置を管理する仕事。建設業で100人以上の規模の事業場など、一定の条件で選任する必要がある。 |
上記3つの仕事は、労働安全衛生法の知識を活かして現場の労働災害を防ぐという重要な役割がある業務といえます。

労働安全衛生法の知識が必要になる特別教育には、以下のようなものがあります。
例えば、「騒音障害防止対策のための労働衛生教育」は、建設現場での重機の操作など、騒音が継続的に発生する現場で、労働者の安全と健康を守るための教育です。上記のような特別教育は、労働安全衛生法に基づいた受講義務があるうえ、関係法令のカリキュラムもあるため、労働安全衛生法とのつながりが深い特別教育といえます。

労働安全衛生法で義務付けられた特別教育を受けるなら、体系立てて勉強できるオンライン学習がおすすめです。オンライン学習であれば、最適化された学習支援によって少ない勉強時間でも効率的に学べるうえ、費用の負担も減らせるというメリットがあります。
建設業資格講座のパイオニアであるCIC日本建設情報センターのオンラインで受講できる特別教育なら、時間・労力・費用の無駄を徹底的に省いたカリキュラムで勉強を進めることができます。

この記事では、労働安全衛生法の概要や、労働安全衛生法の知識が活かせる仕事、おすすめの勉強方法を詳しく解説しました。
「労働安全衛生法で義務付けられた特別教育を受けたい」という方は、合格への最短ルートを歩める建設系資格試験対策講座を行い20年以上のキャリアをもつ「CIC日本建設情報センター」でオンライン受講を検討してみてください。
