構造力学は、建築物や土木構造物の安全性を確保するために不可欠な分野です。一見すると難しく感じそうな分野ですが、ポイントを押さえて勉強することで効率的に学習できます。
この記事では、構造力学の基本的な原理から重要用語、学習上のつまずきやすいポイントや乗り越え方まで、解説します。参考書やWebサイト、資格のWeb講座を活用した具体的な勉強方法などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年10月30日 更新日:2025年10月30日
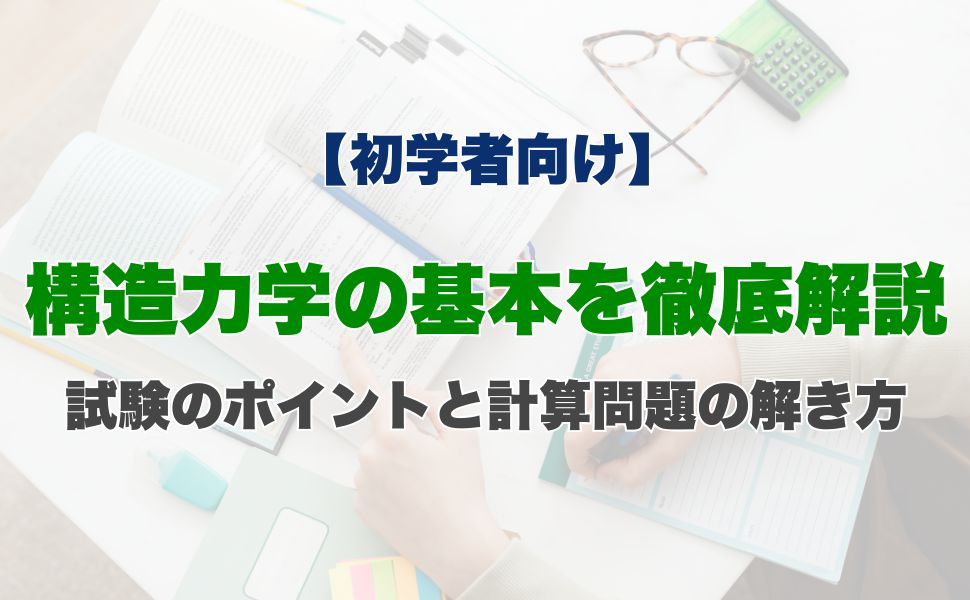
構造力学は、建築物や土木構造物の安全性を確保するために不可欠な分野です。一見すると難しく感じそうな分野ですが、ポイントを押さえて勉強することで効率的に学習できます。
この記事では、構造力学の基本的な原理から重要用語、学習上のつまずきやすいポイントや乗り越え方まで、解説します。参考書やWebサイト、資格のWeb講座を活用した具体的な勉強方法などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

構造力学とは、建築物や土木構造物がさまざまな力(荷重)を受けたときに、どのように挙動し、どうすれば安全性を保てるのかを科学的に解析・予測するための分野です。建築や土木の設計・施工において、構造力学の知識は構造物の「骨格」を理解する上で不可欠であり、建築系の技術者の根幹をなす知識といえます。
建築基準法第20条では「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない」と定められています。つまり、法律を遵守した安全な建設を実現するためには、構造力学の知識が必須であると法律面でも定められているというわけです。
構造物に作用する力として、まず「荷重(外力)」と、それを支える「反力(支持力)」があることを区別して理解する必要があります。建物に人が住んだり、風が吹いたりすることで発生するのが荷重であり、それに対して基礎や柱が押し返す力が反力です。
物体が静止しているための絶対条件が「力のつり合い」であり、具体的には「水平方向の力の合計がゼロ」「垂直方向の力の合計がゼロ」「任意の点を中心とした回転力(モーメント)の合計がゼロ」の3条件で表されます。
身近な例でいえば、シーソーが水平になっているときは左右の重さと支点からの距離の積が等しくなっており、綱引きで両チームが動かないときは引く力が完全に釣り合っています。このような日常的な感覚と構造力学の原理は一致しているため、数式への抵抗感を持つ必要はありません。
以下の表は、構造力学を学ぶ上で押さえておきたい重要用語をまとめたものです。
| 応力 | 部材内部で発生する抵抗力のこと。単位面積当たりの力で表され、材料が耐えられるかどうかの指標となる。部材の頑張り度と表現することが可能。 |
|---|---|
| ひずみ | 力による部材の変形の割合を示す用語。元の長さに対してどれだけ伸び縮みしたかを表し、部材の変形度と表現できる。 |
| 曲げモーメント | 梁などの部材を曲げようとする力のこと。梁のどの部分に最も大きな曲げの力がかかるかを示す重要な指標となる。 |
| せん断力 | 部材をずらし、断ち切ろうとする力。はさみで紙を切るときに紙の断面にかかる力をイメージすると理解しやすい。 |
上記以外にも重要な用語はあるものの、特に重要な用語として選定しております。まずは、特に押さえておきたい用語から把握し、徐々に知識の幅を広げていくと良いでしょう。

ここでは、構造力学でつまづきやすいポイントと乗り越え方をご紹介します。以下の表は、各ポイントと乗り越え方をまとめたものです。
| つまづきやすいポイント | 乗り越え方 |
|---|---|
| 物理的なイメージが湧かない | 数式を追う前に、身の回りの物(定規、消しゴムなど)を使って、力がかかるとどう曲がりどう抵抗するか手で感じてみることが有効。実際に定規の両端を持って曲げてみると、中央付近が最も曲がりやすいことが体感できる。 |
| 計算過程で符号(プラス・マイナス)を間違える | 「時計回りをプラス」など、自分なりの一貫したルールを最初に決め、常にそれに従う訓練が重要。問題を解くたびに同じルールを適用することで、符号ミスを大幅に減らすことが可能。 |
| 問題が少し複雑になると手も足も出なくなる | 複雑な問題は基本の組み合わせに過ぎないため、焦らずに問題を単純な要素に分解する思考法を身につけることが大切。まず全体像を把握し、次に個々の部分に分けて考える習慣をつけるのがおすすめ。 |
学習を継続するために、自分がどこでつまずいているのかを把握し、適切な対処法を身につけることが大切です。具体的な勉強方法に関しては後述します。

構造力学の勉強方法としては、主に以下の3つです。
それぞれの勉強方法について詳しく解説します。
構造力学に関する知識を効率的に習得するには、参考書を活用しつつ、基礎から順序立てて学習することが大切です。特に初心者には、図やイラストが豊富な教材をおすすめします。
また、資格試験に合格するなどの目標を立てることでモチベーションも維持しやすくなります。過去問題や参考書を併用しつつ、目標を見据えることで効率的な学習ができるでしょう。
構造力学に関する学習は、インターネット上の多様なコンテンツを通じて可能です。特に、動画であれば、実際の解説映像を通して理解を深めるのに役立ちます。
また、構造力学を含めた解説が掲載されているウェブサイトでは、最新の情報や事例紹介を得ることも可能です。ただし、情報の信頼性には差があるため、公的機関や専門団体の情報を優先して活用することが推奨されます。
資格試験の中で構造力学が登場する場合、資格試験に合格することが勉強の目的となるはずです。この場合、Web講座などを活用することで、より効率的に学習できます。
Web講座は、ご自身のペースで学習を進められるだけでなく、質問対応や模擬試験などのサポートも充実しています。プロによる解説や映像を活用した学習によって最短距離で知識が身につくもの魅力です
CIC日本建設情報センターでも、構造力学が頻出される土木施工管理技士・建築施工管理技士の受験者向けにWeb講座を提供しております。受験者がモチベーションを維持しながら、最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
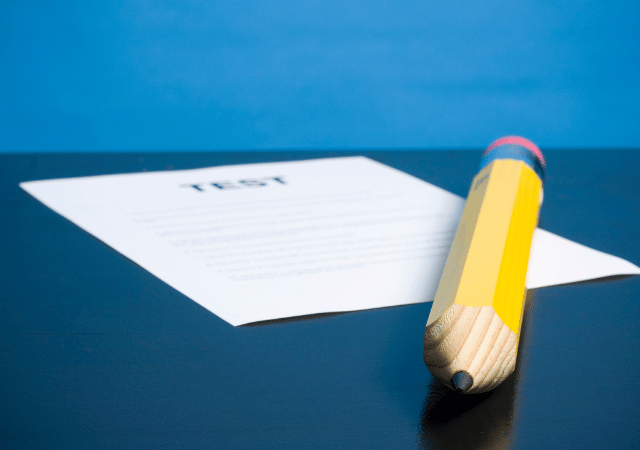
構造力学は多くの建設系資格試験で出題される重要科目です。特に施工管理技士の資格試験では、構造力学の知識が合否を左右する重要な要素となります。
ここでは、構造力学の知識が必要となりやすい建築施工管理技士・土木施工管理技士の特徴について解説します。
建築施工管理技士は、建設現場において施工計画の作成から工程、品質、安全、原価管理まで、工事全体を管理するための国家資格です。試験では、構造力学が学科試験の建築学等で出題されます。
1級建築施工管理技士では、より高度な構造計算問題が出題され、梁の曲げモーメント図やせん断力図の作成、トラスの解析などが頻出される傾向です。2級建築施工管理技士でも、基本的な力のつり合いや反力の計算問題は必須となっています。
第二次検定においても、施工計画を立てる際に構造物の力学的な理解が求められるため、構造力学の知識は欠かせません。
土木施工管理技士は、土木工事の施工計画から品質、安全、工程、原価管理まで、工事全体を監督・管理するための国家資格です。試験では、構造力学が土木一般の科目で重要な位置を占めています。橋梁、ダム、トンネルなどの土木構造物の設計・施工には、構造力学の深い理解が不可欠です。
1級土木施工管理技士では、連続梁の不静定構造物の解析や、土圧・水圧を考慮した構造計算が出題されます。2級土木施工管理技士でも、単純梁や片持ち梁の基本的な計算問題は確実に解けるようにしておく必要があります。

構造力学は建築物や土木構造物の安全性を確保するために必要不可欠な学問です。初めて勉強される方にとっては難しく感じられるかもしれませんが、基本原理を理解し、重要用語を押さえることで、着実に知識を身につけられます。
つまずきやすいポイントを認識し、適切な対策を講じながら学習を進めることが大切です。参考書、動画、Web講座など、自分に合った学習方法を選択し、建築施工管理技士や土木施工管理技士といった資格取得を目指して、計画的に学習を進めていきましょう。
CIC日本建設情報センターでは、建築施工管理技士や土木施工管理技士の受験者に向けたWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。

建設キャリア転職造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
施工管理技士の平均年収は?資格別や年代別の給与相場と年収1000万を目指す方法を解説
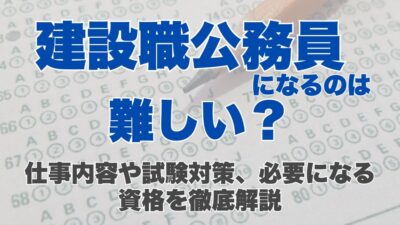
建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士消防設備士コンクリ技術士
建設職公務員になるのは難しい?仕事内容や試験対策、必要になる資格を徹底解説
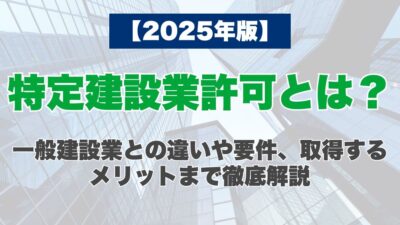
造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
【2025年版】特定建設業許可とは?一般建設業との違いや要件、取得するメリットまで徹底解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介
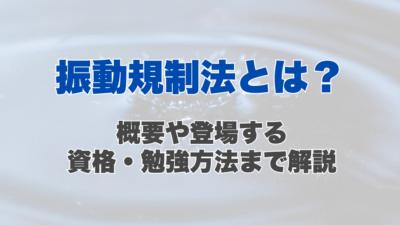
振動規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
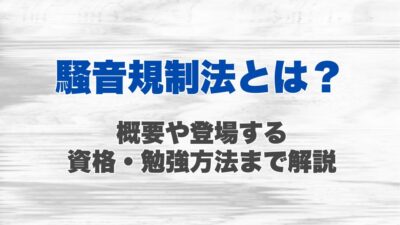
騒音規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
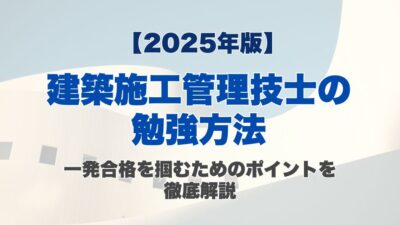
【2025年版】建築施工管理技士の勉強方法|一発合格を掴むためのポイントを徹底解説
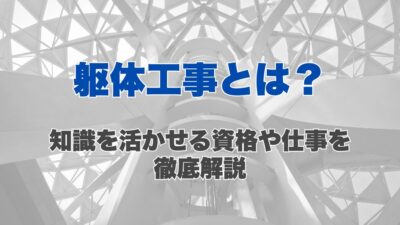
躯体工事とは?知識を活かせる資格や仕事を徹底解説
