玉掛けの業務に係る特別教育は、「労働安全衛生規則第36条」に基づく法定教育で、玉掛け業務従事者に対して事業者が実施する義務があります。クレーンでの荷の吊り上げ作業において、荷をフックに掛ける玉掛け作業は重大な労働災害につながる可能性が高い作業です。
教育では玉掛け用具の取り扱い、作業方法、関係法令について学習します。厚生労働省の基準により教育時間は、学科10時間、実技4時間の合計14時間以上で、修了者にはPDFタイプやカードタイプの修了証が交付されます。
公開日:2025年8月27日 更新日:2025年8月27日
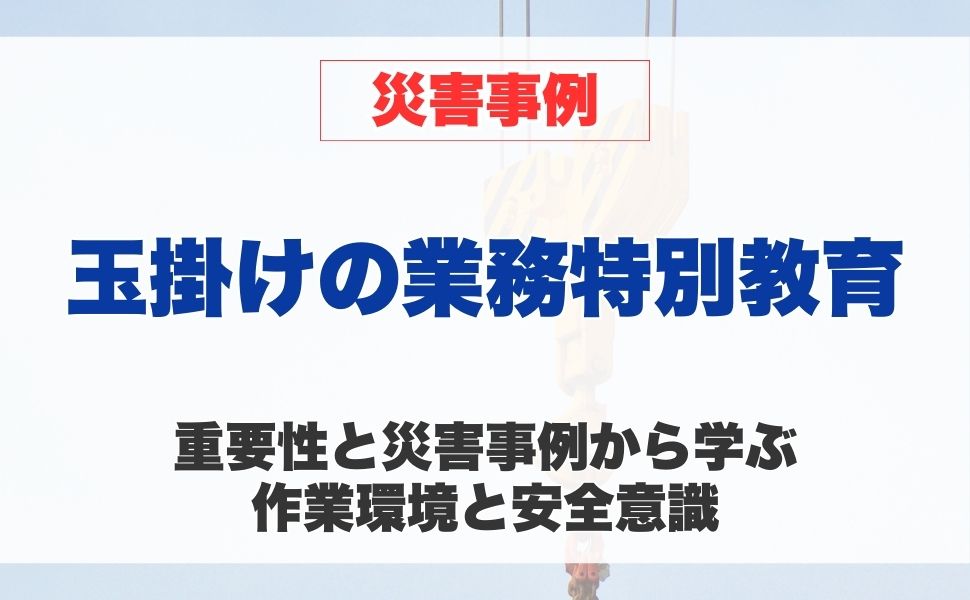
玉掛けの業務に係る特別教育は、「労働安全衛生規則第36条」に基づく法定教育で、玉掛け業務従事者に対して事業者が実施する義務があります。クレーンでの荷の吊り上げ作業において、荷をフックに掛ける玉掛け作業は重大な労働災害につながる可能性が高い作業です。
教育では玉掛け用具の取り扱い、作業方法、関係法令について学習します。厚生労働省の基準により教育時間は、学科10時間、実技4時間の合計14時間以上で、修了者にはPDFタイプやカードタイプの修了証が交付されます。

玉掛けの業務に係る特別教育は、「労働安全衛生規則第36条」に基づく法定教育で、玉掛け業務従事者に対して事業者が実施する義務があります。クレーンでの荷の吊り上げ作業において、荷をフックに掛ける玉掛け作業は重大な労働災害につながる可能性が高い作業です。
教育では玉掛け用具の取り扱い、作業方法、関係法令について学習します。厚生労働省の基準により教育時間は、学科10時間、実技4時間の合計14時間以上で、修了者にはPDFタイプやカードタイプの修了証が交付されます。
玉掛け作業は重量物をクレーンで吊り上げる工程で、不適切な操作が死亡・重傷事故につながる高リスク作業です。適切な知識と技能により、作業者自身と周囲の安全確保、設備損傷防止、工期遅延回避が可能です。一般社団法人日本クレーン協会によると、クレーン等による災害での死傷者数は建設業が年間447人にのぼり、死亡者数では最も多い26人を記録しています。その中でも玉掛け関連事故は多くの割合を占め、重大災害につながる要因の一つとされており、特別教育の重要性を示しています。

玉掛け作業における災害事例を分析することで、事故の発生パターンや原因を理解し、同様の災害を防ぐ知識を得ることができます。以下に実際に発生した代表的な災害事例を紹介します。
発生状況: 建設現場で長さ12m、重量約3トンのH鋼を4点つりで吊り上げ中、高さ約5mでワイヤロープが切断。H鋼が落下し、下で合図作業中の作業者が下敷きになりました。
事故の原因: 使用ワイヤロープに多数の素線切れがあり安全荷重を大幅に下回る状態。点検記録が不十分で交換時期が適切に管理されず、H鋼の重心位置を正確に把握せず一部ロープに過度な負荷がかかっていました。
結果(けが・死亡・周囲への影響): 作業者は頭部外傷により死亡。周囲2名が軽傷。工事1週間中断、労働基準監督署調査実施。安全管理体制見直しと全現場緊急安全点検が実施されました。
防げたポイント: 定期的なワイヤロープ点検と交換、荷の重心位置把握と適切な玉掛け方法選択、作業前安全打合せ徹底、吊り荷下からの退避徹底が重要でした。
発生状況: 配管工事現場で直径300mm、長さ6mの鋼管を2点つりで吊り上げ中、約3mの高さでワイヤロープから鋼管がずり落ち、受け取り準備中の作業者の足に直撃しました。
事故の原因: 鋼管表面が雨で濡れワイヤーロープとの摩擦力が低下。2点つりの玉掛け位置が重心から離れ、つり上げ時に鋼管が傾斜しロープから滑り落ちやすい状態。滑り止め措置も未実施でした。
結果(けが・死亡・周囲への影響): 被災者は右足首複雑骨折により約3ヶ月入院。現場での安全教育見直しと濡れた荷物への玉掛け手順策定。他現場でも緊急安全対策点検が実施されました。
防げたポイント: 荷物表面状態確認と滑り止め措置、重心位置を考慮した玉掛け位置設定、天候条件を考慮した作業計画、合図者と受け取り作業者の安全配置が重要でした。
発生状況: 倉庫内で重量約1.5トンの機械部品をロッキングフック付きワイヤロープで玉掛けし天井クレーンで吊り上げ中、高さ約4mで突然フックから荷が外れ、真下の作業者上に落下しました。
事故の原因: ロッキングフックの安全装置(ラッチ)が正常作動せず、定期点検で異常発見も修理が先送り。作業者はフックの向きや荷の掛け方の適切な知識がなく不安定な状態で玉掛けしていました。
結果(けが・死亡・周囲への影響): 被災者は胸部圧迫により死亡。会社全体で玉掛け用具総点検実施、不良品廃棄と新品交換。全作業者への緊急安全教育が実施されました。
防げたポイント: 玉掛け用具の定期点検と不良品の即座使用停止、ロッキングフック正しい使用方法教育、作業前用具点検徹底、吊り荷直下立ち入り禁止徹底が重要でした。

災害事例を分析すると共通する背景や原因が見えてきます。
玉掛け作業の事故には、人的・設備・管理・作業方法といった多面的な要因が関係しています。
人的要因として、玉掛け作業に関する知識・技能不足や危険に対する感受性の低さがあります。設備・用具では定期点検の不備や不良品の継続使用が多く、コスト削減圧力により安全対策が後回しにされるケースもあります。
また、管理体制では安全教育の形骸化、危険予知活動の不徹底、作業手順の未整備が問題が見られます。作業方法においても、作業前打合せ不足や適切な合図方法の未実施、危険区域設定不備などが事故発生につながっています。
これらの要因は相互に関連し合っており、総合的かつ継続的な安全対策の実施が必要です。

効果的な災害防止にはハード面とソフト面両方のアプローチが必要です。
玉掛け用具の適切な選定と管理が基本で、ワイヤロープ、チェーン、フック等は定期点検を実施し、摩耗や損傷発見時は即座に交換します。作業環境整備では適切な照明確保、作業エリア整理整頓、危険区域の明確表示が必要です。労働安全衛生規則第151条の42などにより「定期自主点検の実施義務」があります。
継続的な安全教育が最重要で、特別教育受講だけでなくOJTや定期安全講習、危険予知訓練、事故事例共有により作業者の安全意識と技能向上を図ります。現場では作業開始前の安全打合せ徹底、適切な合図方法統一、吊り荷直下立ち入り禁止徹底が重要です。
安全管理責任者の明確化、事故発生時対応手順策定、安全パトロール定期実施が必要です。50人以上の現場では安全管理者選任が法定義務となります(労安法第11条)
実技訓練重視で様々な条件下での玉掛け作業体験と、過去事故事例を活用した危険感受性向上が効果的です。実際に「体験型研修(VR訓練含む)」や「ヒヤリ・ハット報告の活用」が労災削減に有効です。
玉掛け作業の災害防止に向けた 「ハード対策+ソフト対策+教育+管理体制」 の多角的アプローチは、現場安全の基本です。

玉掛けの業務に係る特別教育は、重大な労働災害を防ぐ不可欠な法定教育です。紹介した災害事例からも、適切な知識・技能・安全意識の不足は取り返しのつかない結果を招きます。
事故の多くは玉掛け用具の点検不備、不適切な作業方法、安全教育の不徹底などの複合的要因により発生します。これらを防ぐには組織全体での安全意識向上と継続的な教育・訓練実施が必要です。
特別教育受講は法的義務であると同時に、作業者自身と周囲の安全を守る重要な投資です。単なる資格取得でなく、現場での実践的安全対策と組み合わせることで真に効果的な災害防止を実現できます。安全は日々の積み重ねと継続的改善により、誰もが安心して働ける職場環境を構築することがすべての関係者に求められています。まずは、適切な教育を必ず受講しましょう。

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育クレーン安全教育ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育ゴンドラ取扱い業務特別教育巻上げ機の運転の業務に係る特別教育移動式クレーンの運転特別教育移動式クレーン運転士安全衛生教育フォークリフト玉掛け特別教育玉掛け安全教育高所作業車クレーンローラー特別教育小型車両特別教育
重機・建設機械の免許を徹底解説!種類や取得費用・期間をご紹介!
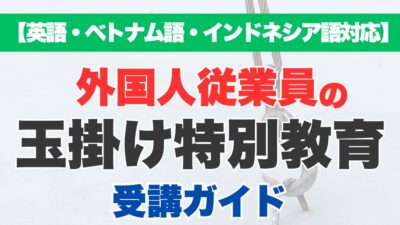
【英語・べトナム語・インドネシア語対応】外国人労働者の方に玉掛け特別教育を受講してもらう最適な方法は?
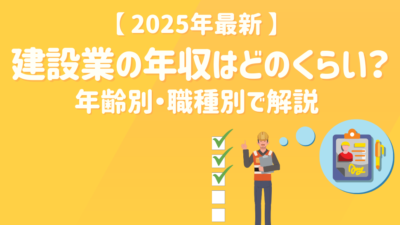
【2025年最新】建設業の年収はどのくらい?年齢別・職種別で解説

クレーンの玉掛け作業に資格は必要?玉掛け特別教育と技能講習について解説
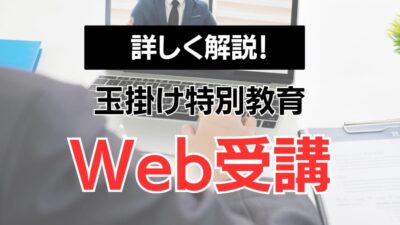
玉掛け特別教育はWeb受講がおすすめ!メリットや注意点などていねいに解説

玉掛けの業務に係る特別教育の修了証は必ず必要?修了証の期限や記載事項もていねいに解説

玉掛け特別教育って何?講習の内容や受講方法を解説!
