フルハーネスが必要となる具体的な高さをご存じでしょうか。「フルハーネスの着用義務化」が施行されたことにより、今までの作業とは異なる変更点も出ていますので、この機会にぜひ確認してみましょう。
この記事では、フルハーネスの着用が義務付けられている高さ、墜落制止用器具の選定について詳しく解説します。さらに、フルハーネス特別教育の講習内容と受講方法、特別教育の受講はWeb講座がおすすめの理由についてご紹介しますので、参考にしてみてください。
公開日:2025年4月28日 更新日:2025年5月8日
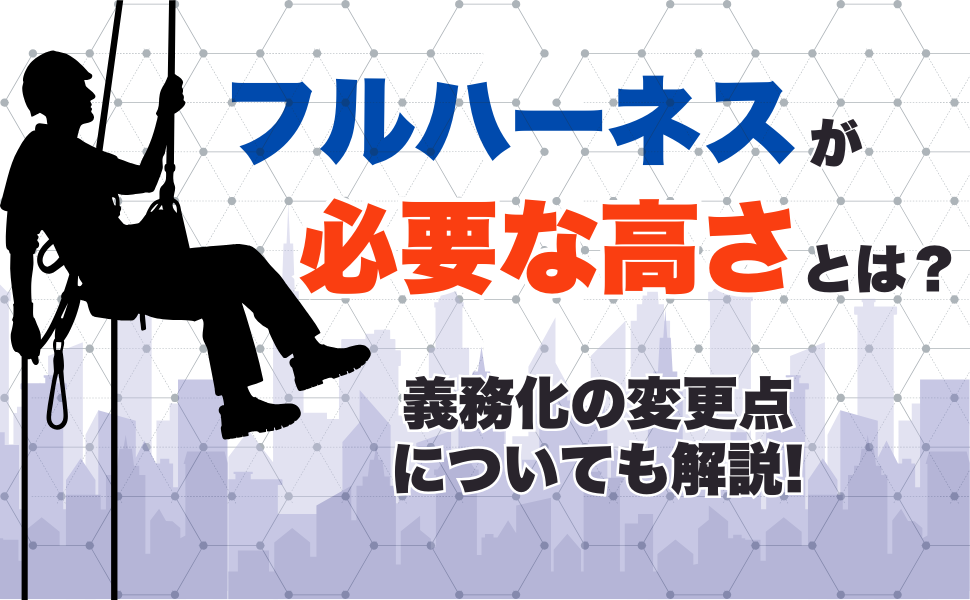
フルハーネスが必要となる具体的な高さをご存じでしょうか。「フルハーネスの着用義務化」が施行されたことにより、今までの作業とは異なる変更点も出ていますので、この機会にぜひ確認してみましょう。
この記事では、フルハーネスの着用が義務付けられている高さ、墜落制止用器具の選定について詳しく解説します。さらに、フルハーネス特別教育の講習内容と受講方法、特別教育の受講はWeb講座がおすすめの理由についてご紹介しますので、参考にしてみてください。

こちらからは、フルハーネスの着用が義務付けられる高さについて詳しく解説します。
フルハーネスの着用は、6.75mより高い箇所で義務化されています。6.75m以下の場合であれば、胴ベルト型(一本つり)の着用も選択できますが、原則的に墜落制止用器具はフルハーネスを着用することが義務づけられているのです。
また、建設業であれば5m、柱上作業などであれば2m以上でフルハーネスの着用が推奨されています。ただ、実際にどのような墜落制止用器具を着用するかは、作業現場の高さなどによっても変化することを押さえておきましょう。
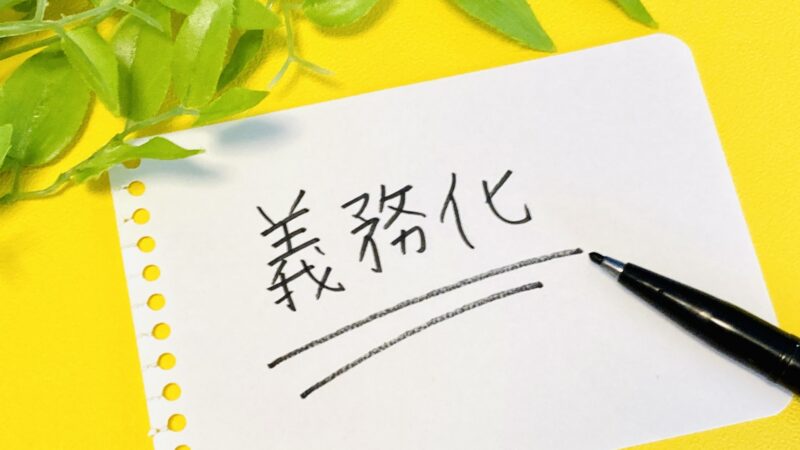
フルハーネス着用義務化は、2022年1月から施行されています。こちらからは、フルハーネス着用義務化が施行された背景や変更点について詳しく解説していきましょう。
フルハーネス着用義務化に至った背景は、胴ベルト型安全帯の安全性が危惧されていたからです。
胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部などの圧迫による危険性が指摘されているうえ、実際に胴ベルト型の使用に関わる災害も確認されています。加えて、国際規格などではフルハーネス型安全帯が採用されているため、政令などの改正が行われました。
フルハーネス着用義務化の変更点については、以下のとおりです。
フルハーネス着用義務化により、胴ベルト型(U字つり)は墜落を制止する機能が備わっていないことから、墜落制止用器具とは認識されないことが定められています。
また、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型のものを用いて行う作業を行う方は、「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」の受講が義務化されました。
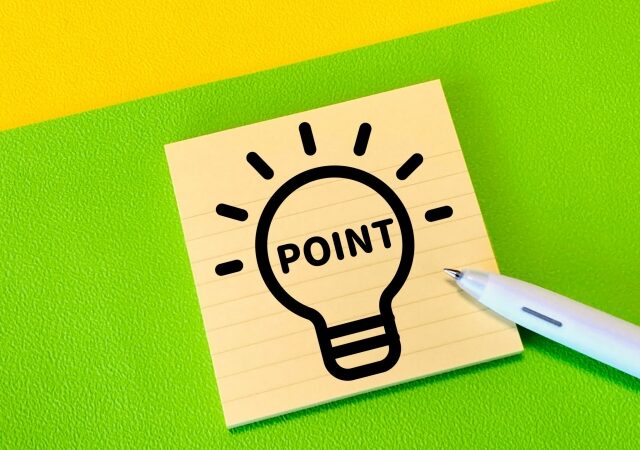
墜落制止用器具の選定をする際は、以下4つのポイントを押さえておきましょう。
上記4つのポイントについてご紹介します。
フルハーネス着用義務化により、墜落制止用器具として認められているものは「フルハーネス安全帯」または「胴ベルト安全帯」です。6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定し、高さが6.75m未満であれば胴ベルト安全帯の選択も可能です。
一方で、柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトを着用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要です。
以前の法令に基づいて作られた胴ベルト型・フルハーネス型ではなく、規格変更に基づいて製造された墜落制止用器具を選びましょう。
旧規格と新規格の胴ベルト型・フルハーネス型を見分けるには、販売されている名称を確認することがおすすめです。フルハーネス着用義務化の施行によって名称が変更されたので、「安全帯」ではなく「墜落制止用器具」と記載されているものを選びましょう。
墜落制止用器具は、作業者の体重や装備品の合計重量に適したものを選びましょう。墜落制止用器具に定められている使用可能な最大重量を超えてしまうと、新規格のものを着用していたとしても危険性は拭えません。
作業者の体重よりもゆとりのある耐荷重のものを選び、安全に作業を進めていきましょう。
墜落制止用器具を選ぶときは、作業場所を考慮することもポイントです。万が一落下した際、身の安全を守れるように、作業場所は墜落制止用器具のショックアブソーバに表示された落下距離以上の高さかどうかを確認しましょう。
また、腰の高さ以上にフックなどを掛けて作業を行うことが可能な場合は「第一種ショックアブソーバ」、足下にフックなどを掛けて作業を行う必要がある場合は「第二種ショックアブソーバ」を選定してください。
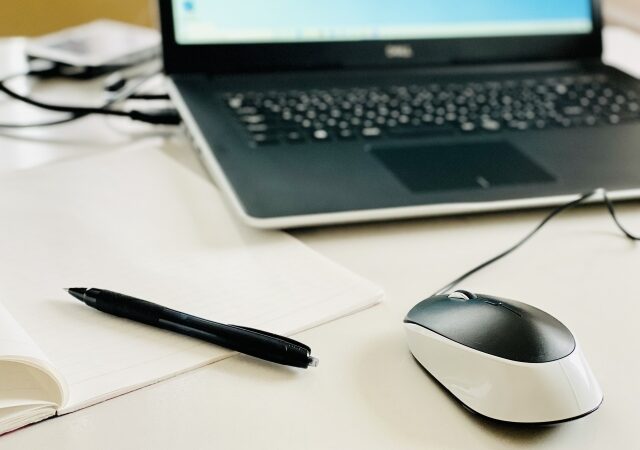
墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を実施することが義務付けられています。
こちらでは、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の概要や講習内容、受講方法について詳しく解説していきましょう。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、作業者がフルハーネス型墜落制止用器具の安全な使い方を学ぶための講座です。
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に従事する場合は、受講が義務付けられています。対象者が受講を行わなければ、「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に課せられるので、十分注意しましょう。
建設業界歴26年のCICがご提供する「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」の講習内容は、以下のとおりです。
【学科】
| 区分 | 科目 | 講習時間 | |
|---|---|---|---|
| Web講座 | 通学講座 | ||
| 学科 | 作業に関する知識 | 1時間 | 1時間 |
| フルハーネスに関する知識 | 2時間 | 2時間 | |
| 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | 1時間 | |
| 関係法令 | 30分 | 30分 | |
| 実技 | 墜落制止用器具の使用方法等 | - | 1時間30分 |
| 合計 | 4.5時間 | 6時間 | |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、建設業関連の一般社団法人などの団体で受講することが可能です。
一般的な流れとしては、該当の講座に申し込み、入金をしてから受講をすることができます。受講が完了した後、修了証を発行してもらうことが可能です。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講を検討しているなら、Web講座がおすすめです。
会場に足を運ぶことなく、自宅で好きな時間に受講できるため、なかなか受講の時間をとりづらい方にもぴったりでしょう。建設業界歴26年のCICがご用意している「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」のWeb講座であれば、受講後に即時で修了証(PDF)をダウンロードいただけます。
いつでも受講できるWeb講座で、スキマ時間に受講してみましょう。

この記事では、フルハーネスの着用が義務付けられている高さ、墜落制止用器具の選定について詳しく解説しました。
フルハーネス義務化により、6.75mより高い箇所でフルハーネスの着用が必須とされています。
さらに、特に危険性の高い業務を行う作業者は「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」の受講が義務付けられていることも、忘れずに押さえておきましょう。
