公開日:2024年7月22日 更新日:2025年11月10日
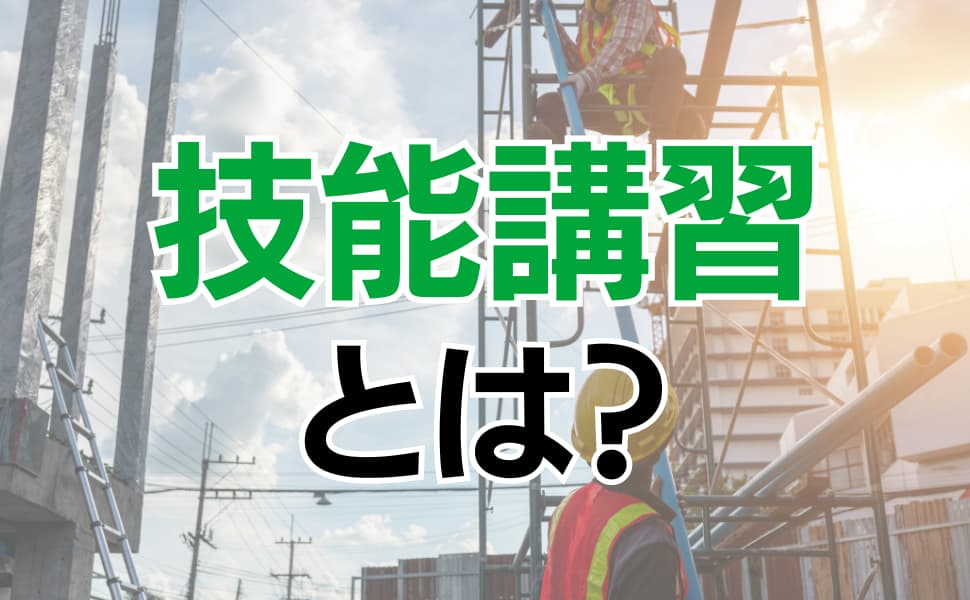
特定の業務に関しては、指定された講習を受講しないと従事できない業務があります。こうした講習の中に「技能講習」という講習がありますが、この技能講習とはどのようなものなのでしょうか。
この記事では技能講習を修了することでできることや、ほかの講習との違いなどに関して解説していきます。

技能講習とは、その講習を受講することで特定の業務に就くことができるようになる講習です。特に知識が求められる業務や、危険性の高い業務に関して設定されているケースが多く、労働安全衛生法という法律で受講が義務付けられています。
こうした特定の業務に関する講習には、「安全衛生教育」や「特別教育」、そして技能講習があります。さらにこの上に「免許」というものがあるケースも存在します。
免許を持っていれば、その業務に関するすべてのことの関わることができます。技能講習を修了している場合、一部対応できないことがあるものの、ある程度の業務にかかわることができるといった具合です。
免許ほどの幅広い業務に対応できる資格ではないものの、技能講習を修了することで、より幅広い業務に就くことができるようになるということです。
この技能講習には主に2つのタイプがありますので、それぞれのタイプを紹介していきます。
1つ目のタイプは、作業現場で作業主任者に選任されるための技能講習です。これは労働安全衛生法第14条に規定されています。
労働災害などが発生する可能性が高い一部の業務に関しては、その業務を行う作業現場において、作業主任者の設置が義務付けられています。この作業主任者に選任されるための要件が、技能講習の修了となっているわけです。
2024年現在、作業主任者に選任されるために取得が必要な技能講習は、以下の27種類です。
上記の業務にあたる作業現場においては、技能講習を修了している作業主任者の設置が義務となっています。
もう1つのタイプが、業務の制限の上限が上がるタイプの技能講習です。こちらは労働安全衛生法第61条に規定されています。
2024年月現在、このタイプの技能講習は12種類存在します。
| 技能講習 | 制限等 |
|---|---|
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業 |
| ガス溶接技能講習 | アセチレンガスなどの可燃性ガス及び酸素を使用して行うガス溶接・溶断の業務 |
| フォークリフト運転技能講習 | 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転作業 |
| ショベルローダー等運転技能講習 | 最大荷重1t以上のショベルローダーの運転作業 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業 |
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 機体重量3トン以上の車両系建設機械(基礎工事用)のくい打機業務 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業 |
| 不整地運搬車運転技能講習 | 最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転作業 |
| 高所作業車運転技能講習 | 作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業 |
同じ小型移動式クレーンの操縦をする場合でも、吊り上げ荷重が5t以上のクレーンを操縦する場合は技能講習の修了が必須など、技能講習を修了することで、従事できる作業の上限が上がるというタイプとなります。
技能講習は上記の通り40種類近い講習があります。それぞれその業務に関する知識などを身に着けるために講習を受講しますが、講習の受講修了後には認定試験があります。技能講習の資格を取得するためには、指定された講習を受講したうえで、認定試験に合格しなければいけません。

こうした業務にかかわる講習には、ほかにも特別教育や安全衛生教育などがあります。特別教育などに関しては、その業務の経験や知識を持っている方であれば、講師に選任できます。つまり講師に関して選任要件が存在しないため、自社内で講師役を選任し、自社内でも講習を行うことが可能ということです。
しかし、技能講習の場合、実施できる方に条件が加わります。技能講習を実施できるのは、各都道府県の労働局長に登録を行っている「登録教習機関」だけです。技能講習に関しては、自社内で完結することができず、登録教習機関として登録されている団体や企業が実施する講習を受講しなければいけません。

記事内でもたびたび出てきている「安全衛生教育」と「特別教育」に関しても簡単に説明しておきましょう。技能講習との違いも合わせて解説していきます。
安全衛生教育とは、特定の業務に関する講習の中ではもっとも下に位置する講習です。そのため講習自体に受講義務はありません。受講が強く推奨されているものです。仮に安全衛生教育を受講していない方が業務に従事しても、罰則等はありません。
安全衛生教育は、講師の選任要件がありませんので、指定されているテキストさえ用意すれば、自社内の従業員から講師役を選任し、自社内で完結できる講習となります。講習受講後の認定試験もありません。
特別教育とは、特定の業務に従事するすべての方に受講が義務付けられている講習です。受講が義務付けられているため、未受講の方がその業務に従事した場合、罰則が与えられます。この罰則は、従事した従業員だけではなく、特別教育を受講させる義務を怠った事業者にも与えられますので注意が必要です。
特別教育で得られる資格は、あくまでもその業務に従事する資格までです、技能講習のように作業主任者にはなることができません。
また、技能講習同様に、従事できる作業の制限に関する特別教育もあります。上で、「小型移動式クレーンの技能講習」を修了すると、吊り上げ荷重5t以上のクレーンの操縦ができると書きましたが、「小型移動式クレーンの特別教育」を修了した方は、吊り上げ荷重1t未満のクレーンまでしか操縦できません。技能講習と特別教育にはこうした差があるわけです。
特別教育に関しても、講師の選任要件がありませんので、自社内でも完結可能です。また、講習の受講が修了条件であり、認定試験は存在しません。

労働安全衛生法で制定されている各種講習は、労働災害を未然に防ぐために行われています。そのもっとも下位の講習が安全衛生教育であり、その上に特別教育、技能講習があるという形になります。
そして技能講習には講習を実施する者にも条件があり、その条件が都道府県労働局長に登録をしている、登録教習機関であるということです。
CIC日本建設情報センターは、東京都と大阪府において登録教習機関として登録を行っています。
実際にCIC日本建設情報センターでは2つの技能講習を定期的に開催しています。
金属アーク溶接の技能講習に関しては、2024年1月1日に制定された新しい技能講習であり、まだ実施している団体が少ない技能講習です。
安全衛生教育や特別教育の場合、講習の受講が修了条件ですが、技能講習の場合は、講習終了後に認定試験を実施する必要があります。そのためオンライン(Web)講座での受講が難しいのが現状です。上記の2つの技能講習に関しても、東京や大阪で定期的に講習を実施し、認定試験まで受験できるようになっています。

作業現場で行われる業務の中で、特に労働災害の危険性が高い業務に関しては、講習の受講が推奨もしくは義務付けられています。労働災害を未然に防ぐために、必要な知識を身に着けるための講習です。
こうした業務に関する講習には段階があり、安全衛生教育、特別教育、そして技能講習があります。特定業務に関する講習の中では、最上位に位置するのが技能講習ということです。
技能講習には、作業主任者に選任されるためのものと、作業の制限が緩和されるものがあります。事業者の方は、特定の業務に就く従業員に、技能講習を受講してもらう義務がありますので、自社の業務を確認し確実に受講してもらえるようにしましょう。
CIC日本建設情報センターは、登録教習機関として登録を行っており、技能講習の実施が可能です。技能講習の受講を考えている事業者の方は、ぜひ受講を検討してみてください。
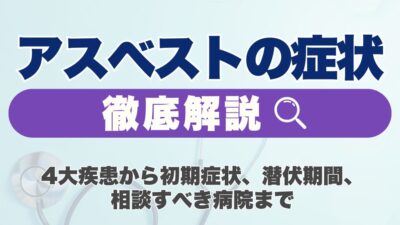
アスベストの症状を徹底解説!4大疾患から初期症状、潜伏期間、相談すべき病院まで
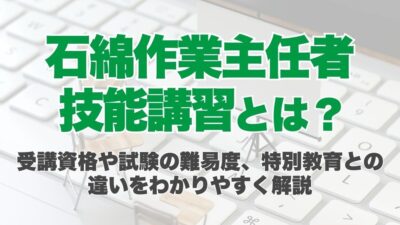
石綿関連石綿特別教育石綿技能講習建築物石綿含有建材調査者講習
石綿作業主任者技能講習とは?受講資格や試験の難易度、特別教育との違いをわかりやすく解説

石綿関連石綿特別教育石綿技能講習建築物石綿含有建材調査者講習
【2026年】アスベスト関連資格一覧!資格取得の難易度や費用を法改正と合わせて解説

【2026年最新】アスベスト事前調査とは?対象となる工事・費用相場・義務化された報告ルールを徹底解説
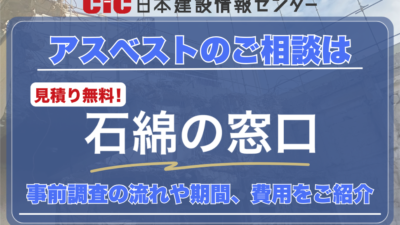
アスベストのご相談は「石綿の窓口」へ!事前調査の流れや期間、費用をご紹介
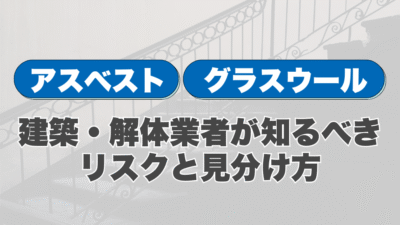
アスベストとグラスウールの違い|建築・解体業者が知るべきリスクと見分け方
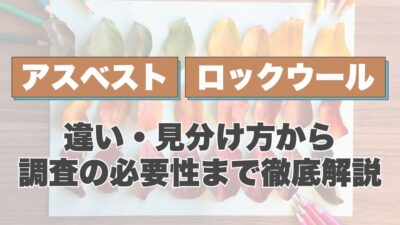
アスベストとロックウールの違いを徹底解説!見分け方から調査の必要性まで
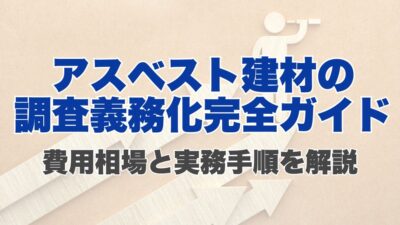
アスベスト建材の調査義務化完全ガイド|費用相場と実務手順を解説
