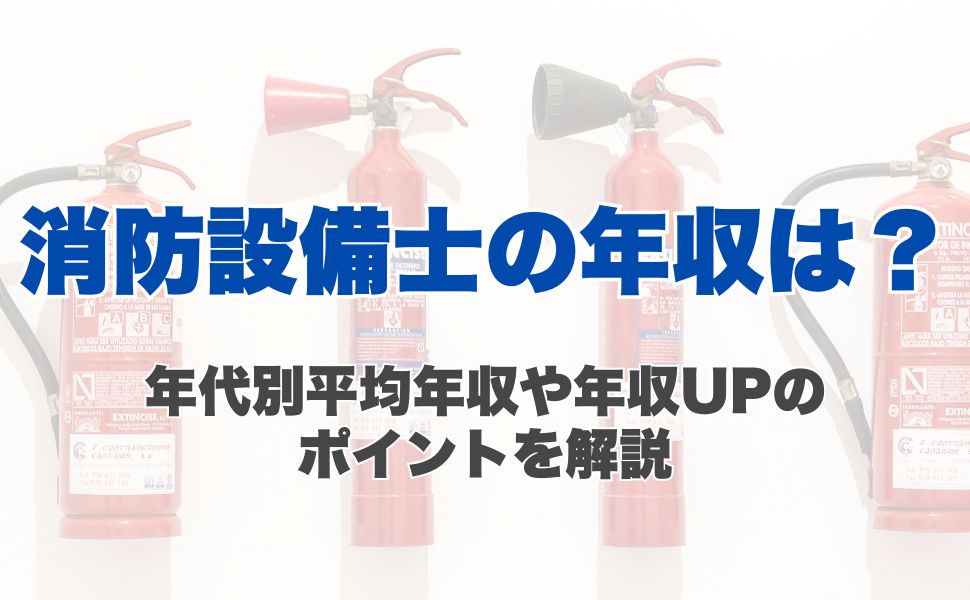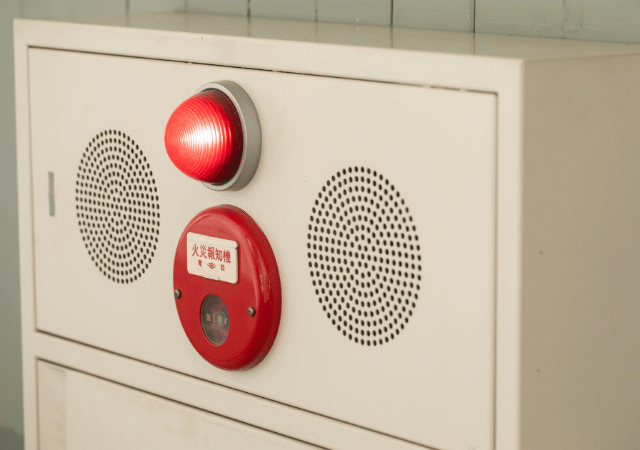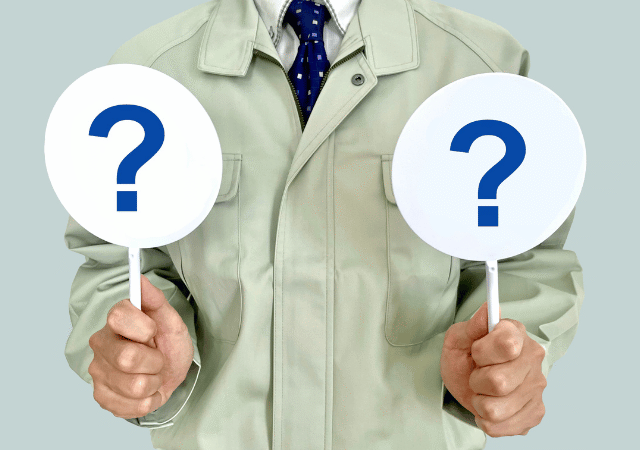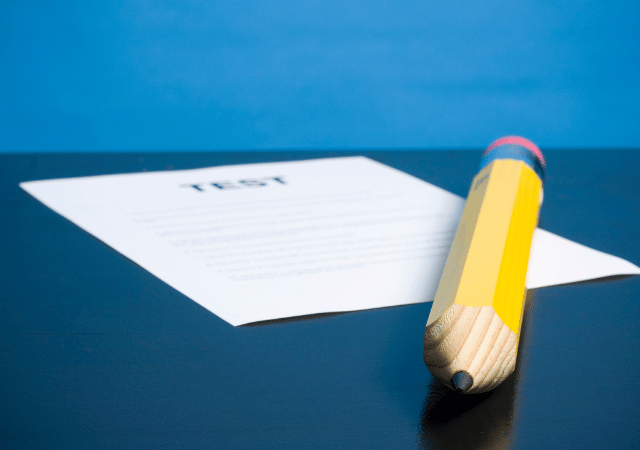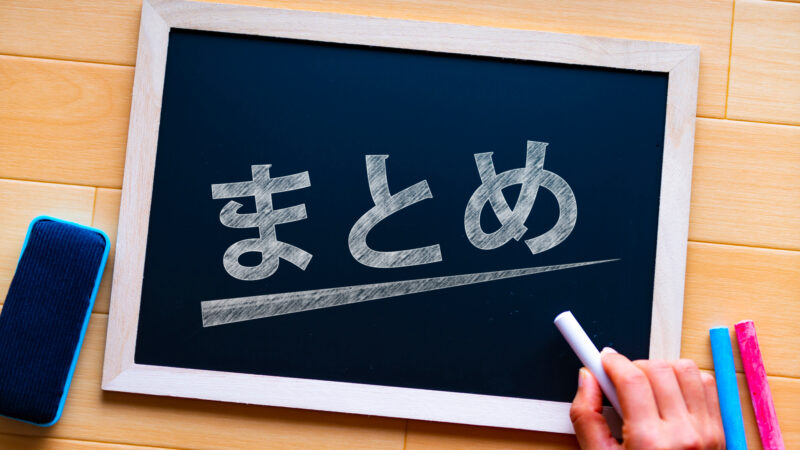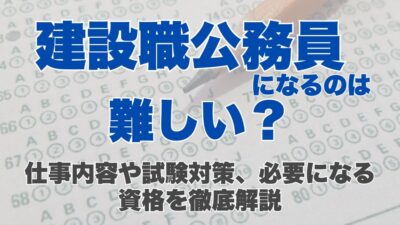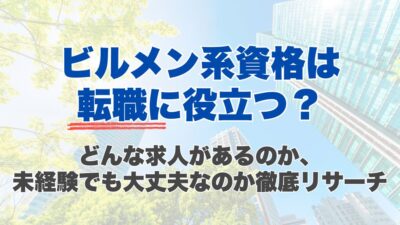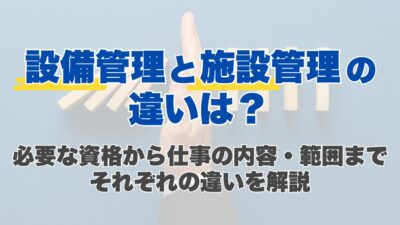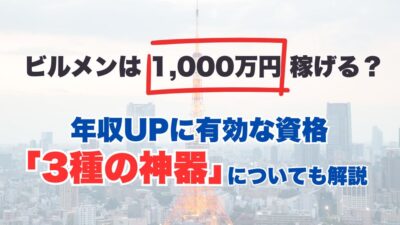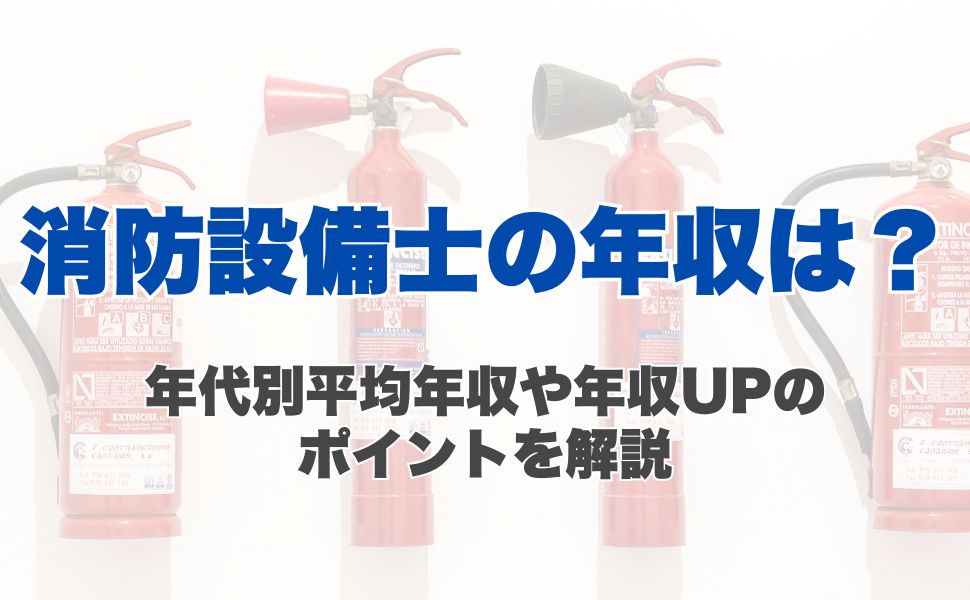
私たちの日々の安全は、建物に設置されたさまざまな消防設備によって守られています。火災報知器・スプリンクラー・消火器などがいざという時に正しく機能しなければ、人命に関わる大事故につながりかねません。
消防設備士は、まさにこれらの重要な設備を点検・整備・工事できる国家資格を持った、「安全のプロフェッショナル」です。建物のオーナーや管理者にとって、法令順守と安全確保のために欠かせない存在となっています。
専門性の高い国家資格である消防設備士ですが、これから資格取得を目指す方の中には「実際の年収はどれくらいなのか」「頑張り次第で収入アップは見込めるのか」と疑問に思う方も多いことでしょう。
この記事では、消防設備士の平均年収を年代別や企業規模別に詳しく分析し、年収を大きく引き上げるための具体的なポイントや、有利な資格の種類について徹底的に解説します。

消防設備士とは
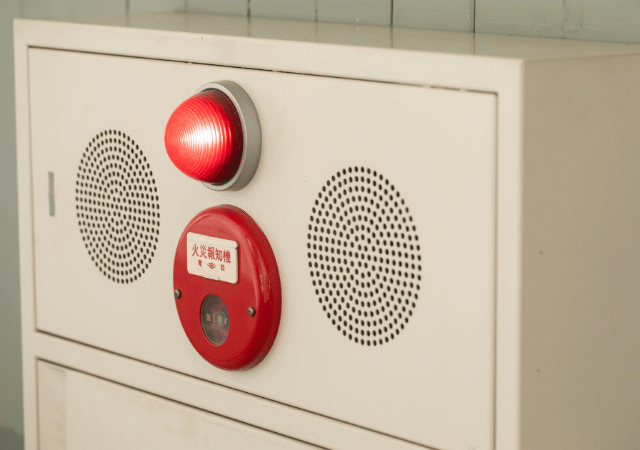
消防設備士とは、消火器・火災報知設備・スプリンクラー設備といった、建物に設置されている消防用設備等の点検、整備、または工事を行うことができる国家資格保有者です。
消防法に基づき、特定の建物にはこれらの設備の設置が義務付けられていますが、設備の工事や点検・整備を行うには、消防設備士の資格が必要となります。
消防設備士の資格は、取り扱う設備の種類や業務範囲によって分類されており、「甲種」と「乙種」の二種類があります。
- 甲種:消防設備の工事、点検、整備が可能
- 乙種:消防設備の点検、整備のみ可能
甲種は工事を含む幅広い業務を担うため、より高度な専門知識と、後述する実務経験や関連資格が受験資格として求められます。人々の命と財産を守る、非常に社会貢献度と責任感の大きい仕事です。
消防設備士の詳しい仕事内容や、資格の種類についての詳細な情報は以下の記事もぜひ参考にしてください。
関連記事:消防設備士とは?試験概要から仕事内容、年収までまとめ
消防設備士の平均年収

消防設備士の年収は、その専門性から一定水準を保っていますが、統計データでは「その他の保安職業従事者」などの括りで集計されることが多く、正確な平均額を把握するのが難しい側面もあります。
しかし、実際の求人情報や関連データから判断すると、消防設備士の平均年収は約350万円〜450万円程度が相場です。これは、経験年数や勤務先の企業規模、そして最も重要な保有資格によって大きく左右されます。
年代が上がるにつれて年収は上がる傾向にありますが、経験と実績を積んでも、資格や役職が伴わなければ収入の伸びが頭打ちになる特徴があります。
令和3年の統計調査から推計した年代別の平均年収の目安は、以下の通りです。
| 年齢 |
役職・役割の目安 |
平均年収(目安) |
| 20代 |
見習い、実務経験を積み始めた若手 |
350万円前後 |
| 30代 |
独り立ち、現場責任者・主任クラス |
400万円前後 |
| 40代 |
複数の現場統括、課長代理・係長クラス |
450万円前後 |
| 50代 |
管理職・部門長クラス、豊富な経験者 |
500万円前後 |
| 60代 |
再雇用・顧問、ベテラン技術者 |
400万円前後 |
参考:賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査
20代の平均年収
20代の平均年収は、310万円〜360万円程度が一般的です。この年代は、未経験から入社し、まずは甲種の受験資格のない乙種の資格取得を目指しながら、現場で見習いとして経験を積む時期にあたります。
まだ実務経験が浅いため全体の年収水準は低めですが、この期間にどれだけ多くの資格を取得し技術を身につけられるかが、将来の年収に直結します。
30代の平均年収
30代になると、十分な実務経験を積み、甲種の資格を取得する方が増えてきます。現場での責任者や、小規模なプロジェクトの主任クラスを任されるようになり、平均年収は360万円〜430万円程度に上昇します。
資格手当も加算され、給与の伸びを感じられる時期です。
40代の平均年収
40代は長年の経験から複数の資格を保有し、技術者として信頼を確立する時期です。複数の現場を統括したり、企業の課長代理・係長といった管理職に昇進したりするケースが増え、平均年収は390万円〜470万円程度が目安となります。
この時期に年収の伸びが停滞しないよう、新しい資格取得やマネジメントスキルを磨くことが重要です。
50代の平均年収
50代は部門長や幹部クラスといった管理職として活躍する方が増えるため、年収も高くなる傾向があります。平均年収は450万円〜550万円程度が見込めます。
豊富な経験を持つベテランとして、若手の指導育成や、企業の技術的な判断を担う重要な役割を果たす時期です。
60代の平均年収
消防設備士は、体力的負担が比較的少ない業務が多いため、定年後も再雇用や顧問として長く働くことが可能です。60代の再雇用後の平均年収は、350万円〜450万円程度が相場となります。
長年の経験とノウハウを活かし、安定した収入を得続けられるのが、この仕事の大きな魅力の一つです。
消防設備士の年収が決まる3つの要因

消防設備士の年収は、ただ長く働くだけではなかなか上がりません。個人の収入を大きく左右する、決定的な3つの要因を理解しておくことが重要です。
①保有資格の種類と数(甲種・乙種、特類など)
年収を決定する最大の要因は、保有している消防設備士資格の種類と数です。
甲種は乙種に比べて仕事の範囲が広く、特に「工事」ができることが大きなアドバンテージになります。さらに、甲種の中でも需要の高い甲種1類(屋内消火栓・スプリンクラー設備)や甲種4類(自動火災報知設備)は、多くの建物に設置義務があり、資格の希少性が高いため、企業からの評価や資格手当が厚くなります。
すべての甲種・乙種を制覇し、さらに難易度の高い特類まで取得すれば、資格手当だけで毎月数万円、年間で数十万円の増収も可能です。
②勤務先の事業内容(点検・工事・設計など)
勤務先の事業内容によっても、年収水準は大きく異なります。
- 点検専門業者:点検業務が中心で、比較的給与水準は安定しているものの、高収入は望みにくい傾向があります。
- 工事・設計業者:消防設備の設計や大規模な設置工事を請け負うため、単価の高い仕事が多く、全体的に給与水準が高い傾向にあります。特に防災設備メーカーや大手ゼネコン系の企業は、高額な年収が期待できます。
甲種資格を活かし、工事や設計に携われる環境を選ぶことが、年収アップのポイントです。
③雇用形態(正社員・契約社員・独立)
働き方も収入に直結します。特に、企業に雇用されるか、独立するかで、収入の安定性や上限は大きく変わってきます。具体的な働き方と収入の特徴は以下の通りです。
- 正社員:安定性は抜群ですが、年功序列や会社の給与規定に縛られることもあり、収入の上限があります。
- 契約社員:即戦力となる経験者や有資格者が、期間を定めて高い専門性を活かす場合に採用されやすい形態です。正社員より柔軟な働き方ができる反面、昇給や賞与の幅が制限されるなど、契約更新の不安が伴うことがあります。
- 独立開業:最も年収の上限がなく、成功すれば年収1,000万円以上も狙えます。ただし、営業や経理といったビジネススキルも必要となり、収入が不安定になるリスクもあります。
特に経験豊富な技術士は、フリーランスのコンサルタントや個人事業主として独立することで、大幅な収入増を実現しているケースも多く見られます。
消防設備士の種類と種別
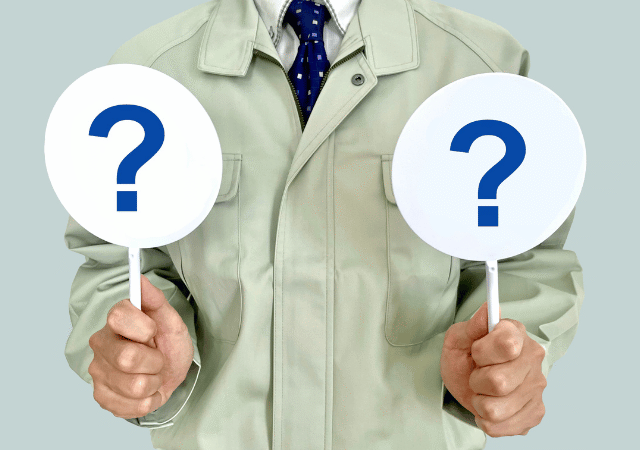
消防設備士の資格は、取り扱う消防設備の種類によって、特類、甲種1〜5類、乙種1〜7類に細かく分類されています。
| 消防設備士の種別 |
業務範囲 |
主に取り扱う設備 |
| 特類(甲種のみ) |
特殊な消防用設備の工事・点検・整備 |
特殊な技術が必要な設備(特定防火対象物など) |
| 甲種・乙種1類 |
工事(甲種のみ)、点検・整備 |
屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など(水系消火設備) |
| 甲種・乙種2類 |
工事(甲種のみ)、点検・整備 |
泡消火設備、パッケージ型消火設備など |
| 甲種・乙種3類 |
工事(甲種のみ)、点検・整備 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備など |
| 甲種・乙種4類 |
工事(甲種のみ)、点検・整備 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置など(電気系統) |
| 甲種・乙種5類 |
工事(甲種のみ)、点検・整備 |
避難はしご、救助袋、緩降機など |
| 乙種6類 |
点検・整備のみ |
消火器 |
| 乙種7類 |
点検・整備のみ |
漏電火災警報器 |
このうち、年収アップに特に直結しやすいのは、建物への設置義務が最も広く、工事の需要も高い「甲種1類(水系)」と「甲種4類(電気系統)」です。これらは「ダブルライセンス」としてセットで取得する価値が高いとされています。
参考:消防設備士試験|一般財団法人 消防試験研究センター
年収1,000万円以上を狙いやすい種類

消防設備士の年収は日本の平均を下回ることが多いですが、年収1,000万円以上を狙うことは、特定の戦略と資格があれば十分に可能です。
年収1,000万円を目指す上で、特に重要となるのは以下の資格の組み合わせです。
- 甲種1類(水系消火設備)
- 甲種4類(自動火災報知設備)
- 電験三種(第三種電気主任技術者)や電気工事士
甲種1類と4類は、消防設備の中でも工事の規模が大きく、需要が最も高い設備を扱えます。この2つを保有することで、建物の消防設備工事のほとんどに対応できるようになり、市場価値が飛躍的に高まります。
さらに、年収1,000万円を現実にするためには、関連する設備系の資格、特に電気設備の知識が必須です。消防設備は、電気系統と密接に関わっているため、「電験三種」や「電気工事士」などの資格を併せて保有することで「消防設備だけでなく、電気設備全般を管理できる」という高い付加価値を生み出せます。
これらのハイレベルな資格を保有し、大手防災メーカーや大手ゼネコン系の管理職に就く、あるいは独立して大規模な工事案件を請け負うことが、年収1,000万円という目標達成につながるでしょう。
消防設備士試験の受験資格
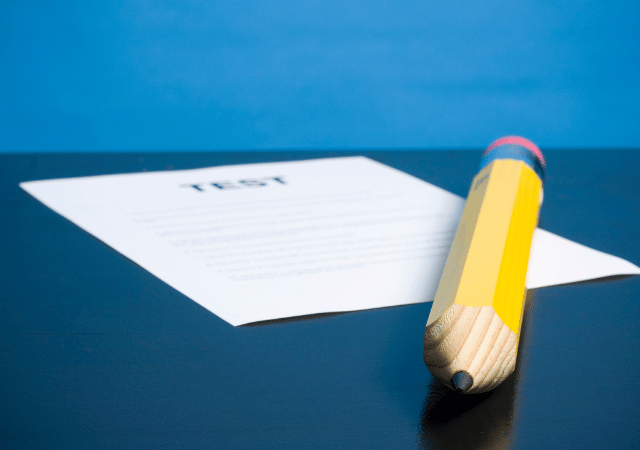
消防設備士試験は、業務範囲が広い甲種と、比較的制限が緩やかな乙種で、受験資格が大きく異なります。
乙種の受験資格
乙種の消防設備士試験には、学歴や実務経験、保有資格などの制限は一切ありません。誰でも受験することが可能です。
そのため、未経験者が最初に取得を目指すには最適な資格であり、実務経験を積みながら上位の甲種資格の受験資格を満たすための第一歩となります。
甲種の受験資格
甲種の受験資格を得るには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 関連資格の保有:電気工事士や電気主任技術者、管工事施工管理技士など、消防設備に関連する国家資格を保有していること
- 学歴要件:大学や高等専門学校などで、機械・電気・工業化学などの関連学科を卒業していること
- 実務経験:乙種の資格を取得し、その後に2年以上の消防用設備等の整備または工事の実務経験を積んでいること
甲種特類に関してはさらに厳しく、甲種1類から5類のうち、4種類以上の免状を交付されていることが求められます。この厳しい受験資格が、甲種資格の価値と専門性を高めているのです。
消防設備士として年収を上げるためのポイント

消防設備士として平均年収を超える収入を得るためには、自身の価値を高めるための戦略的な行動が必要です。特に「どこで働くか」は年収に大きく影響します。
都市部で仕事をする
一般的に、都市部(特に東京・大阪・愛知などの大都市圏)は、地方と比較して消防設備士の年収水準が高い傾向があります。
都市部には、特定防火対象物となる大規模な商業施設・オフィスビル・高層マンションが集中しており、消防設備士の需要が非常に高いため、人材確保のために給与が高く設定されやすいのです。
また、都市部の再開発や新規建設プロジェクトは規模が大きいため、工事単価や点検費用も高くなります。企業の収益が上がりやすいため、従業員に還元される報酬も多くなります。
年収アップを目指すなら、多少の通勤や転居の労力をかけてでも、需要と給与水準の高い都市圏での就職・転職を検討する価値は十分にあるでしょう。
できるだけ規模の大きい企業に所属する
年収を上げるためには、勤務先の企業規模も重要な判断基準となります。
統計データを見ても、従業員が100人未満の中小企業に比べて、従業員が1,000人を超える大企業の方が、平均年収が100万円以上高い傾向が明確に見られます。
大企業は、高単価で安定した大規模案件を継続的に受注できるため、収益性が高いです。賞与や福利厚生も手厚く設定されていることが多く、資格手当や役職手当といった諸手当も充実しています。
大手防災メーカーや、大手ゼネコン・デベロッパー系のグループ企業など、規模の大きい企業に所属することで、安定した環境で高い年収を目指せるでしょう。
まとめ
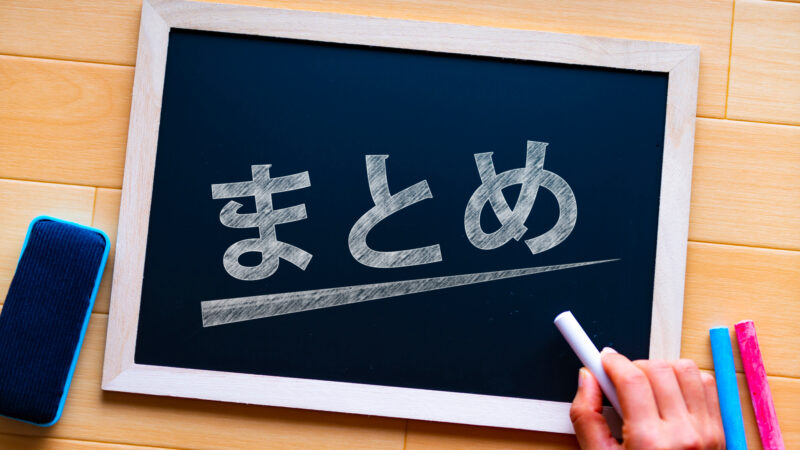
消防設備士は、建物利用者の安全を守る上で不可欠な業務独占資格であり、甲種を取得して工事に携われれば、高収入と安定したキャリアが見込めます。特に甲種4類は、火災報知機などを扱い需要が高く、年収アップにも直結するでしょう。
しかし、消防設備士の試験の合格率は30〜40%前後と決して易しくなく、効率的な対策が不可欠です。
消防設備士(甲種4類・乙種4類)試験の合格を目指すなら、CIC日本建設情報センターの「消防設備士」対策講座をぜひご検討ください。過去問分析と短期集中カリキュラムで、忙しい社会人の方でも最短ルートで合格する実力を養えます。ぜひ一度、詳細をご確認ください。