自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育は、自由研削といしの取付けや試運転などで必要な知識・技術力を身につけるための講習です。国籍・雇用形態に関係なく受講が義務づけられており、未受講者を従事させると罰則が適用される恐れがあります。
この記事では、自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育の概要や外国人労働者に受講してもらう方法を解説します。受講してもらう際の注意点などもご紹介しますので、「外国人労働者がスムーズに受講できる方法を見つけたい」場合はぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年8月27日 更新日:2025年8月27日
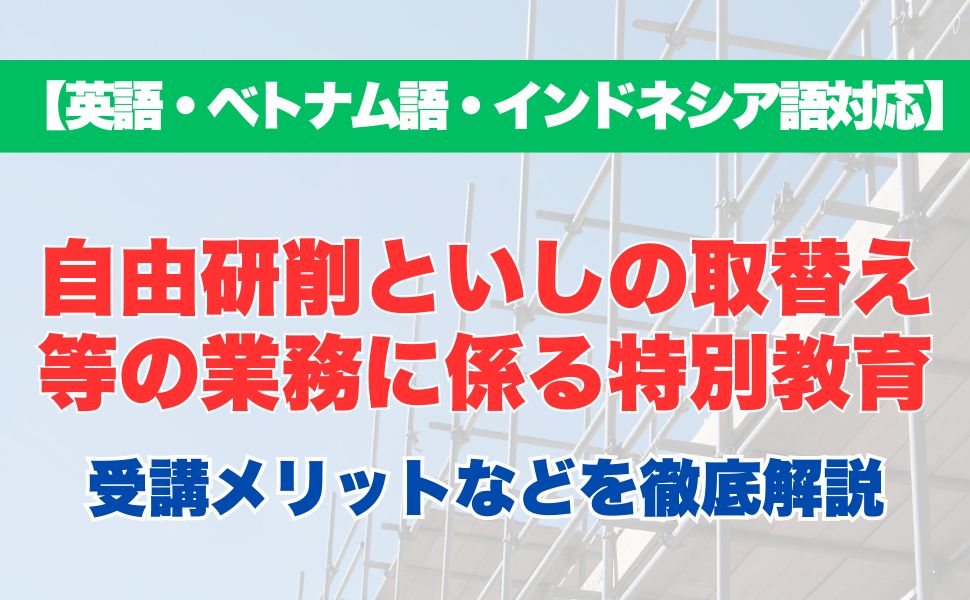
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育は、自由研削といしの取付けや試運転などで必要な知識・技術力を身につけるための講習です。国籍・雇用形態に関係なく受講が義務づけられており、未受講者を従事させると罰則が適用される恐れがあります。
この記事では、自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育の概要や外国人労働者に受講してもらう方法を解説します。受講してもらう際の注意点などもご紹介しますので、「外国人労働者がスムーズに受講できる方法を見つけたい」場合はぜひ参考にしてみてください。

自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育とは、その名の通り自由研削といしの取付けや試運転などで必要な知識・技術力を学ぶための講習です。特別教育なので受講が義務づけられており、未受講者が作業に従事することで罰則が適用される恐れがあります。
自由研削といしを使用する作業は、重大な労働災害につながりかねない多くの危険を伴います。中でも注意すべきは、高速で回転する研削といしが破損し、その破片が飛散することで生じる事故です。この事故は時として、作業者の命に関わる可能性があります。
このような労働災害を防止するため、労働安全衛生法に基づいて「自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」が義務づけられているというわけです。
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育の受講対象者は、「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に携わるすべての人です。国籍などは関係なく、外国人労働者であっても受講の対象となります。
特別教育は、受講が推奨ではなく義務付けられているものなので、未受講者の従事は認められていません。労働災害の観点から見ても非常に危険で、なおかつ事業者側にも罰則が適用される恐れがあります。業務に従事する方には、必ず特別教育を受講してもらいましょう。
以下の表は、自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育をまとめたものです。
| 科目・範囲 | 講習時間 | |
|---|---|---|
| 学科 | 自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 | 2時間 |
| 自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 1時間 | |
| 関係法令 | 1時間 | |
| 学科合計 | 4時間 | |
| 実技 | 自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 | 2時間以上 |
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育は、学科・実技講習の両方が実施されます。学科講習では、自由研削といしに関する基本的な知識や関係法令、実技では実際に取り扱う際の技術力を養うのが特徴です。
ただし、上記の受講時間は最低受講時間となります。実際の受講時間は、講習機関によって異なるため、気になる方は公式サイトなどからカリキュラム・受講時間をチェックしてみるとよいでしょう。

自由研削といし特別教育は、主に以下3つの受講方法があります。
一般的な受講方法は、各講習機関が開催する講習への参加です。講師の確保などが不要であるため、スムーズに受講できる点がメリットとなります。ただし、講習会場への移動が必要となるため、交通機関に不慣れな外国人労働者にとっては移動面での困難が生じる可能性があります。状況によっては、企業側での送迎対応が必要となるケースもあるでしょう。
また、講師を職場に呼んで行う出張講習の実施も方法の1つです。受講者が移動する必要がないため、リラックスした環境で講習に専念できます。一方で、講師の交通費や宿泊費が生じる可能性があり、受講者数が少ない場合は実施が困難な場合もあります。
受講者・事業者双方の負担を軽減できる方法がWeb(オンライン)講座です。Web講座であれば、受講者は自身の都合に応じて学習を進行できます。また、会場への移動や送迎の調整、出張経費の負担も不要です。効率と経済的な懸念を同時に解決できることが大きなメリットといえるでしょう。
Web講座講座には多言語字幕に対応したものもあるため、外国人労働者も不安なく受講できます。CIC日本建設情報センターでは、英語・ベトナム語・インドネシア語の字幕付き講座を提供しておりますので、ぜひご利用ください。

外国人労働者が自由研削といし特別教育を受講する際、受講できるかどうかは、主に以下2つの基準に基づいて判断されます。
| 1. 日常生活に必要な日本語の理解力がある | ・講習に関する読み書きや会話において、日本人労働者と同程度の日本語力があること |
|---|---|
| 2. 専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分ある | ・講師の説明のうち、専門用語以外の内容を概ね理解できること ・ひらがなやカタカナを読むことができる程度の日本語力があること |
これらの基準を満たしていないと判断されると、受講途中でも退室を要求されたり、修了しても修了証が交付されなかったりする可能性があります。
もし、日本語能力に懸念がある場合は、Web(オンライン)講座の活用を検討してみてください。Web講座であれば、事業者の監督のもとで受講・修了が可能であり、受講修了後に修了証を取得できます。
受講開始前に、外国人労働者の日本語理解力を十分に把握し、適した受講方法を選択することが大切です。
※なお、多言語字幕対応のWeb講座は、あくまで一定程度の日本語能力を持つ受講者(上記表①に該当)を対象としたサポートであり、翻訳内容の完全な正確性を保証するものではありません。
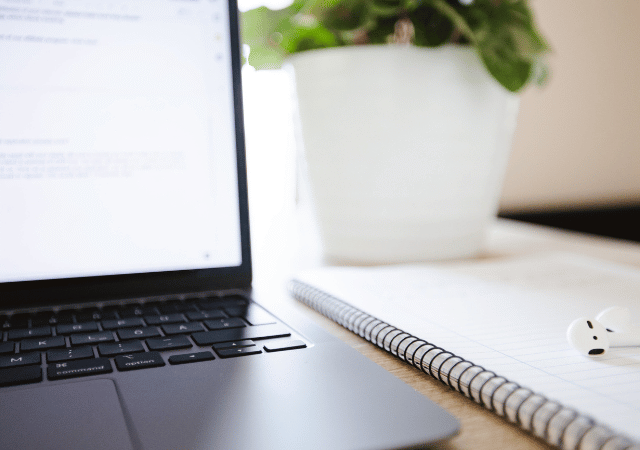
日本語を理解できる外国人労働者が自由研削といし特別教育を受講する場合、Web(オンライン)講座の活用がおすすめです。Web講座には、次のようなメリットがあります。
各講習機関の講習の場合、日本語をある程度習得している受講者でも、講師の説明速度が速いことで内容の理解・把握に時間を要したり、聞き逃したりするケースがあります。
Web講座であれば、一時停止や巻き戻しが可能であるため、受講者一人ひとりの理解力に合わせて学習を進行できます。受講者が自分のペースで学習できることは、大きなメリットといえるでしょう。
また、Web講座は移動時間や休憩時間といった空き時間を有効活用して受講できることも、魅力です。ただし、就業時間外に受講を実施する際、事業者側が受講を強制できません。時間外での受講を依頼する際は、時間外手当の支払いなど柔軟な対応が求められます。

自由研削といし特別教育を外国人労働者が受講する際、注意点は以下のとおりです。
それぞれの内容について詳しく解説します。
自由研削といし特別教育は日本語で行われるため、受講者には一定レベルの日本語の読み書き能力が必要です。
例として、「特定技能」の在留資格を有する外国人労働者のケースでは、日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が取得要件となっており、基本的な日本語能力を有すると認められやすく、特別教育の受講条件をほぼ満たしていると評価される可能性が高いです。
一方、日本語の理解度が不足していると判断されたケースでは、受講を断られる場合もあるため留意が必要です。加えて、所定の日本語能力を持たない受講者を修了させてしまった場合、事業者側に責任が発生する危険性もあります。
したがって、受講開始前に日本語能力の検証を実施している講習機関へ問い合わせるなど、状況に合わせて適切に対処することが重要です。
日本語で実施される特別教育は、通訳の同伴が許可されるケースもあります。ただし、通訳が担当できる範囲には制約があり、講義内容すべての翻訳はできません。
通常、通訳が認められるのは、専門用語といった技術的な箇所に限定されます。追加的な説明や全般的な解説については対象外となるケースが大半です。
また、通訳が同伴していても、受講者の日本語の理解力が不十分だと判断されると、受講自体が認められない可能性があります。受講が認められないケースも考慮し、多言語対応のWeb講座での受講など、別の受講方法を検討することをおすすめします。
外国人労働者向けの講習を開催している講習機関も一定数存在しますが、あらゆる言語に対応しているわけではありません。
例えば、英語に対応している講習機関は比較的多く見られますが、フランス語やイタリア語、中国語の方言(北京語・上海語等)まで網羅しているケースは限りなく少ない傾向です。希望する言語で必ず受講できるわけでない点は、十分に注意すべきでしょう。
そのため、講習を受講する前に、受講者の理解できる言語や日本語の理解力などをチェックしておく必要があります。
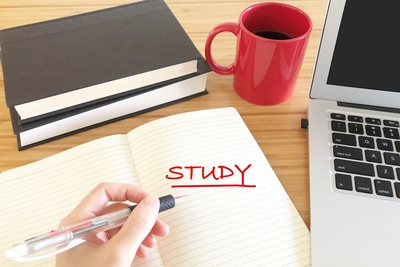
CIC日本建設情報センターでは、外国人労働者の方でも受講できる自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育のWeb講座を提供しております。ここからは、CIC日本建設情報センターのWeb講座の特徴を詳しく解説します。
日本で働く外国人労働者の多くは、ベトナムやインドネシア出身者です。CIC日本建設情報センターが展開するWeb講座は、このような状況を踏まえて、ベトナム語やインドネシア語に対応した講座を用意しています。
そのため、受講者は慣れ親しんだ言語で、安心して学習に取り組めます。また、受講者によっては、母国語より英語での理解を好む方も存在します。このような要望にも応えられるよう英語字幕版も準備しており、幅広い言語ニーズに対応する充実したサポート環境を実現しているのが魅力です。
CIC日本建設情報センターのWeb講座は、受講者一人ひとりに専用のアカウントが発行されます。学習の進行度や過去の受講記録については、管理画面から常に確認できるため、学習計画の立案や復習にも活用できます。
自身のペースで確実に習得したい受講者に対して、利用しやすく続けやすい学習環境が提供されるのも魅力です。
CIC日本建設情報センターのWeb講座は、受講者が確実に画面の前で学習しているか確認できるよう、顔認証システムを採用しています。
この顔認証システムにより、受講者が画面から離れた際には講座が自動停止する仕様ですす。修了証発行時には、間違いなく本人が受講を完了したことが保証されます。事業者側から見ても安心できるシステムといえるでしょう。
CIC日本建設情報センターのWeb講座を修了すると、修了証が交付されます。修了証のタイプは、PDF版とカード版の2つです。
PDF版は、修了と同時にダウンロードできます。一方で、カード版は持ち歩きに適しており、現場で修了証の提示が必要な際にも迅速に対応可能です。現場での業務を想定すると、携帯性に優れたカード版での発行をおすすめします。
講座の受講を申し込む際にご希望のタイプを指定できるため、用途に応じて適した修了証をお選びください。

この記事では、自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育を受講する方法について詳しく解説しました。
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育は、自由研削といしの取付けや試運転などで必要な知識・技術力を身につけるための講習です。国籍・雇用形態に関係なく受講が義務づけられているため、受講者に適した方法で修了する必要があります。
受講方法にはいくつか種類がありますが、事業者と受講者の両方にメリットがある受講方法として、Web講座がおすすめです。Web講座であれば、日本語が聞き取れなかった箇所や分からない部分を巻き戻しや一時停止するなど、受講者のペースでじっくりと理解を深められます。
CIC日本建設情報センターでは、英語・ベトナム語・インドネシア語字幕に対応した自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育のWeb講座を用意しております。外国人労働者の方でもモチベーションを維持しながら計画的に学習を進められる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
