技術士は、科学技術に関する高い専門性と応用能力を持つ技術者の国家資格です。試験は第一次試験と第二次試験の2段階で構成され、特に第二次試験は合格率が約10%前後と非常に難関です。
対策としても、第一次試験・第二次試験それぞれで行う必要があります。闇雲に勉強を始めるのではなく、ポイントを押さえた上で対策をスタートしましょう。
この記事では、技術士試験の特徴を踏まえた効果的な対策方法を詳しく解説します。独学での勉強法からWeb講座の活用までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年10月30日 更新日:2025年10月30日
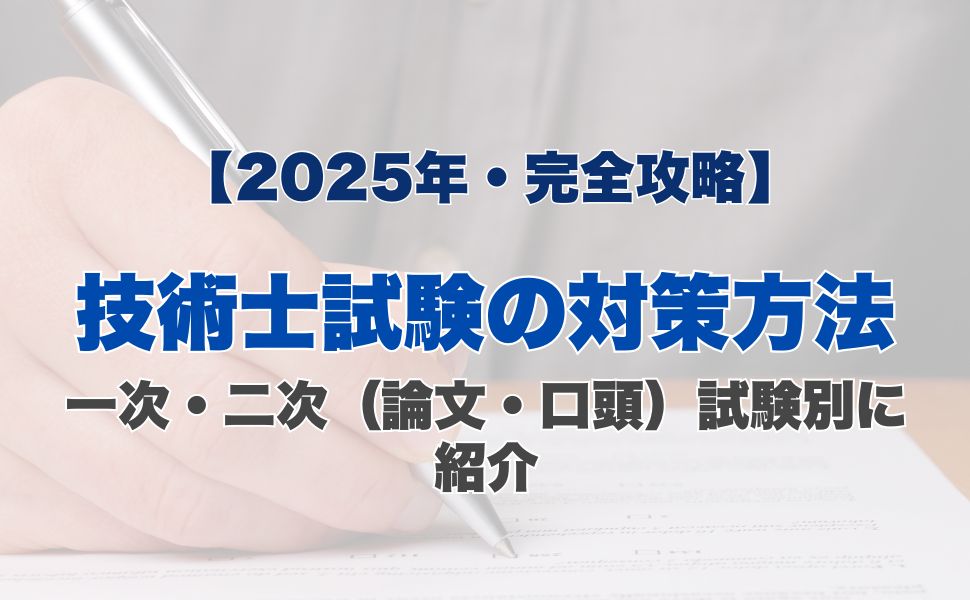
技術士は、科学技術に関する高い専門性と応用能力を持つ技術者の国家資格です。試験は第一次試験と第二次試験の2段階で構成され、特に第二次試験は合格率が約10%前後と非常に難関です。
対策としても、第一次試験・第二次試験それぞれで行う必要があります。闇雲に勉強を始めるのではなく、ポイントを押さえた上で対策をスタートしましょう。
この記事では、技術士試験の特徴を踏まえた効果的な対策方法を詳しく解説します。独学での勉強法からWeb講座の活用までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
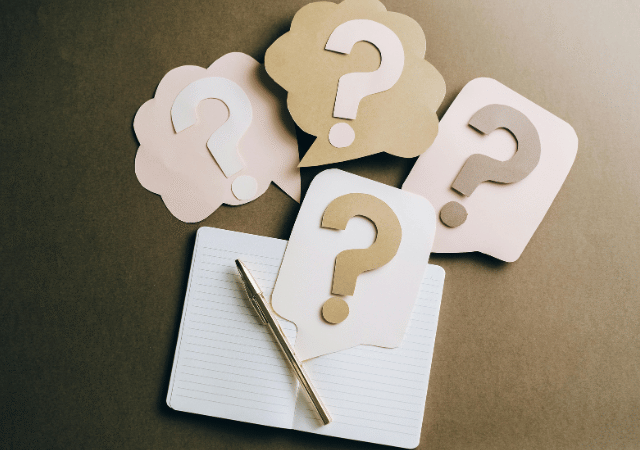
技術士試験は「第一次試験」と「第二次試験」の2段階で構成されている国家資格です。建設部門や上下水道部門など、21ある技術部門から自分の専門分野を選択して受験します。合格すると、各部門において技術に関する高い専門性と応用能力を持つ技術者として証明が可能です。
試験では、第一次試験合格後、一定の実務経験を積んだ後に第二次試験の受験資格を得られます。第二次試験の合格率は約10%前後と非常に低く、多くの受験者にとって大きな壁となっている傾向です。
第二次試験は単なる専門知識だけでなく、技術士としての資質能力が重視されます。具体的には、問題解決能力、マネジメント能力、コミュニケーション能力、技術者倫理などのコンピテンシーが評価軸です。
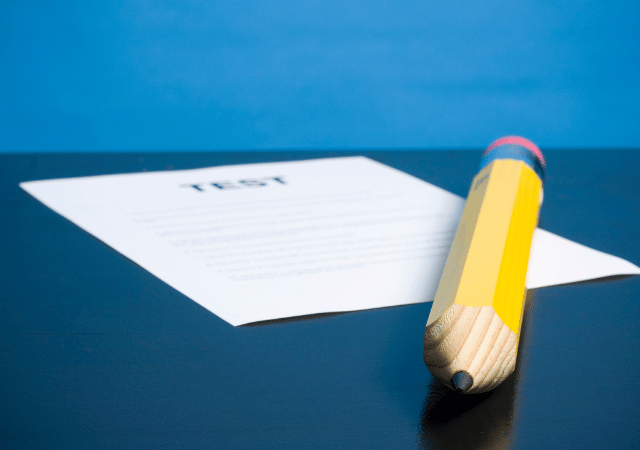
第一次試験は、科学技術全般にわたる基礎知識と技術士法への理解を問うマークシート形式の試験です。「基礎科目」「適性科目」「専門科目」の3科目で構成されており、それぞれ50%以上の正答率が合格基準となります。
第一次試験の対策の基本は、過去問題を徹底的に解くことです。最低でも過去5年分を3回以上繰り返し解き、出題傾向を把握することが最も効率的な学習方法となります。
中でも基礎科目では設計・計画、情報・論理、解析、材料・化学・バイオ、環境・エネルギー・技術の5分野から出題されます。適性科目では技術士法や技術者倫理に関する知識が問われます。
専門科目は自身が選択する技術部門の基礎となる内容が出題されます。ここでしっかりと知識を固めておくことで、第二次試験の土台となる専門的学識を身につけることが可能です。過去問と専門書・参考書を併用しながら効果的に学習を進めてみましょう。
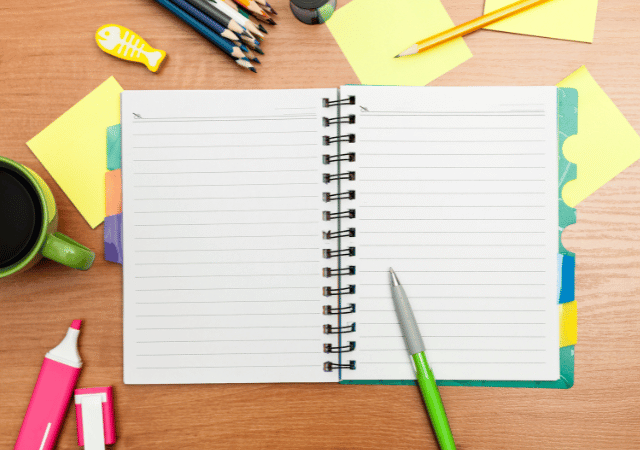
技術士試験の合否を分ける関門のひとつが、第二次試験の筆記における論文(記述式問題)です。この試験では単なる知識量ではなく、技術士として求められるコンピテンシー(特性)を文章で表現できるかが評価されます。
必須科目では技術部門全般の専門知識と応用能力、選択科目では専門分野における問題解決能力とマネジメント能力が問われます。
筆記試験の効果的な対策として、まず出題テーマに関する情報収集を行い、論文の土台を作成します。次に実際に時間を計って答案を作成し、第三者による添削を受けるというサイクルを繰り返すことが大切です。特に論理的な文章構成、専門用語の適切な使用、具体的な解決策の提示などがポイントとなります。
独学では客観的な評価を得にくいため、CIC日本建設情報センターの「技術士受検対策講座」などを活用し、プロの講師による論文添削指導を受けて合格レベルの答案作成能力を効率的に身につけましょう。

技術士試験の関門2つ目が、第二次試験の口頭試験です。
口頭試験は、筆記試験で提出した論文と業務経歴票を基に行われる約20分間の面接形式の試験で、受験者が技術士にふさわしいコンピテンシー(特性)と技術者倫理を体得しているかを、対話を通じて最終確認されます。
口頭試験の対策として重要なのは、自身の業務経歴と作成した論文の内容を完璧に説明できるよう準備することです。特に業務経歴については、技術的な課題をどのように解決したか、その際にどのような判断をしたかを具体的に説明できる必要があります。
また、技術者倫理に関する質問にも的確に答えられるよう、さまざまな観点から自身の業務を振り返っておくことが大切です。模擬面接を繰り返し行い、緊張感のある環境で的確に回答する練習をしておきましょう。

技術士試験の勉強方法としては、独学もしくは受験対策講座の利用が挙げられます。
独学は費用を抑えられるのがメリットです。ただし、第二次試験の論文・口頭試験対策において客観的な評価を得にくく、モチベーション維持が難しいというデメリットがあります。
一方、Web講座のような受験対策講座であれば、体系化されたカリキュラムと最新の試験情報、論文添削や模擬面接といった合格に直結するサポートを自分のライフスタイルに合わせながら受けられます。費用はかかるものの、最短距離で合格を目指せるのがメリットです。
CIC日本建設情報センターでは、技術士試験の受験者に向けた「受験対策講座」を提供しております。受講方法にお悩みの場合は、ぜひ一度ご検討ください。

ここでは、技術士試験の対策に関するよくある質問についてまとめました。
技術士の勉強時間に関して、第一次試験は約400時間以上、第二次試験は600〜1000時間以上が目安となります。
ただし、実務経験や基礎知識のレベルによって個人差があります。そのため勉強時間はあくまでも目安にとどめ、自分の現状の実力と試験日までの期間から学習計画を立てて、継続的に勉強することが大切です。
特に第二次試験は論文作成の練習に多くの時間を要するため、早めの対策を開始することをおすすめします。
技術士の専門科目は、自身の実務経験が最も豊富な分野、または将来的に専門としたい分野を選択するのがおすすめです。実務経験と関連性の高い科目を選ぶことで、第二次試験の業務経歴票作成や口頭試験でも有利になります。
また、選択した部門の過去問題を確認し、自分の知識レベルと出題傾向がマッチしているか事前に確認することも大切です。
第一次試験の受験手数料は11,000円、第二次試験は14,000円です。これに加えて、参考書や問題集の購入費用、受験対策講座を利用する場合はその受講料が必要となります。
また、いつから施行されるかは不明ですが、現在技術士試験の受験料改定が検討されています。もし改定された場合、第一次試験の受験手数料は13,000円、第二次試験は20,500円です。

技術士試験は第一次試験と第二次試験の2段階で構成される国家資格です。第一次試験は過去問題の徹底演習が基本となり、第二次試験では論文作成能力とコンピテンシーの表現力が問われます。
中でも第二次試験は合格率が約10%と難関であり、筆記試験の論文対策と口頭試験の面接対策が合否を分ける重要なポイントです。学習方法としては、独学やWeb講座の利用などがありますが、自分に適したものを選ぶと良いでしょう。
CIC日本建設情報センターでは、技術士試験の受験者に向けて「技術士受検対策講座」のWeb講座を提供しております。受験者がモチベーションを維持しながら最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
