建設現場において、道路に関する工事を行う際には必ず関わってくるのが「道路法」です。土木施工管理技士を目指す方にとって、道路法の理解は避けて通れません。
過去問をはじめ、頻出されやすい分野であるため、勉強方法などを含めて把握しておくことが大切です。
この記事では、道路法の概要から具体的な規制内容、道路交通法との違いを詳しく解説します。勉強方法や関連資格までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年10月31日 更新日:2025年10月31日
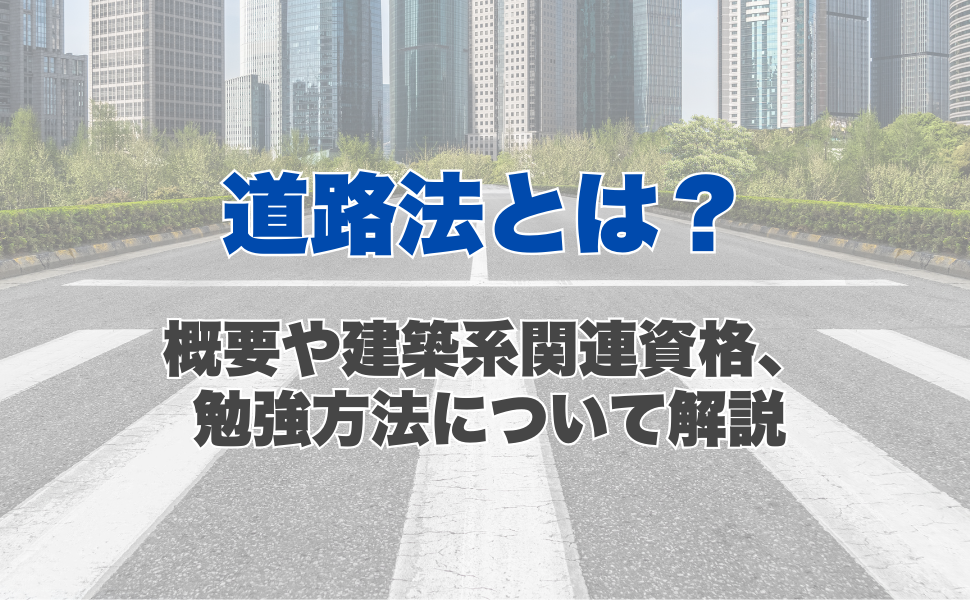
建設現場において、道路に関する工事を行う際には必ず関わってくるのが「道路法」です。土木施工管理技士を目指す方にとって、道路法の理解は避けて通れません。
過去問をはじめ、頻出されやすい分野であるため、勉強方法などを含めて把握しておくことが大切です。
この記事では、道路法の概要から具体的な規制内容、道路交通法との違いを詳しく解説します。勉強方法や関連資格までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

道路法は1952年に制定された法律です。道路網の整備と適正な管理を通じて、交通の発展と公共の福祉増進を目的としています。
道路法における「道路」は路面だけでなく敷地や橋、トンネルや付属物など、道路と一体となる施設全てを含みます。道路は「高速自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」の4種類に分類され、それぞれ国土交通大臣や都道府県、市町村が管理しているのが特徴です。
道路の占用とは、道路に一定の工作物や物件、施設を設け、継続して道路を使用することです。道路法第32条では、電柱・水管・ガス管・地下街・露店・商品置場など、道路の構造または交通に支障を及ぼす恐れのある工作物等を道路に設置する場合、道路管理者の許可が必要と定めています。
建設工事における具体的な占用例としては、工事用の足場や仮囲い・現場事務所・資材置場・工事用車両の出入りのための鉄板設置などが挙げられます。これらは工事期間中、道路を継続的に使用することになるため、占用許可の対象となります。
(参考:国土交通省「道路占用制度」)
道路法第24条は、道路管理者以外の者が、自己の都合で道路に関する工事を行う場合に、道路管理者の承認を受けて実施できることを定めています。この承認は「道路工事施行承認」や「24条工事」と呼ばれています。
建設工事における具体的な例として、工事車両の出入りのための歩道の切り下げやガードレールの撤去・復旧、側溝の付け替え工事などがあります。店舗や住宅への車両乗り入れ口を設置する際の縁石切り下げも、この承認が必要な典型例です。
「占用許可(32条)」が道路を”借りて使う”イメージであるのに対し、「工事施行承認(24条)」は道路そのものに”手を入れる”工事となります。
建設工事で用いられる特殊車両(幅2.5m・高さ3.8m・長さ12m・総重量20トンなどの一般的制限値を超える車両)が道路を通行するには、道路法第47条に基づき、道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要です。
これは道路の構造保全と交通の危険防止が目的です。無許可通行は、道路や橋の損傷、重大事故のリスクがあり、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

道路法と混同されがちな法律には「道路交通法」があります。これらの法律は、目的と規制対象が主な違いです。
道路法は、「道路の管理・保全」が目的で施設そのものを規制し、国土交通省が管轄しています。一方、道路交通法は「交通の安全と円滑」が目的で人や車を規制し、警察庁が管轄しています。
建設工事では、足場設置に道路法に基づく道路占用許可が、交通整理には道路交通法に基づく道路使用許可が必要になるなど、同じ現場でも複数の許可が必要な場合があります。施工管理者は両法律を理解し、適切な手続きを行うことが大切です。

道路法を勉強する場合、主な手段は以下の3つです。
それぞれの内容について詳しく解説します。
道路法について効率的に学びたい場合、参考書等を用いて知識を習得することが大切です。法律に関する内容は文章が中心なので、可能な限り図解などを用いながら解説されている教材をおすすめします。
また、資格取得のような具体的な目標を設定するのもおすすめです。目標があることで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。過去問や参考書を併用しながら道路法に関する内容を学び、目標を見据えて効率的な学習を実現しましょう。
道路法に関する学習は、インターネット上の多様なコンテンツを通じて行うことも可能です。特に動画であれば、実際の解説映像を通して理解を深めるのに役立ちます。
また、道路法を含めた解説が掲載されているウェブサイトでは、最新の内容や関連する情報なども含めて学ぶことも可能です。ただし、ウェブサイトの情報は、信頼性が異なるため、公的機関や政府の情報などを優先して活用しましょう。
土木施工管理技士の受験対策として、Web講座を受講する方法があります。
Web講座の利点は、講師による詳しい解説が受けられることと、質問対応などのサポートが受けられることです。独学では理解しにくい部分も専門講師の解説により、スムーズに理解が深まります。また、学習スケジュールが組まれているため、計画的な学習を進めやすいというのもメリットです。
CIC日本建設情報センターなどの専門機関では、道路法などが出題される土木施工管理技士のWeb講座を提供しています。豊富なノウハウを活かして、受講者のモチベーション維持、試験に出題されやすいポイントの効率的な学習がしやすい内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。
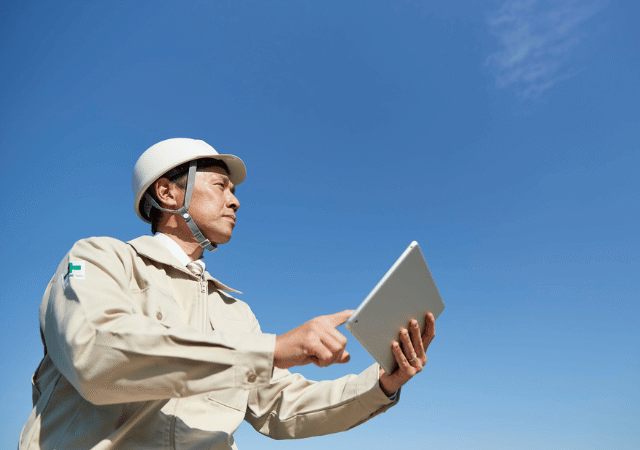
道路法の内容が出題される資格には、土木施工管理技士試験が挙げられます。土木施工管理技士は1級・2級に分類されていますが、ともに第一次検定で必ず出題される科目です。
具体的には、道路占用許可・道路工事施行承認・特殊車両通行許可などの内容が頻出しています。過去問題を分析すると、毎年類似する問題が繰り返し出題される傾向があるため、基本的な知識をしっかり押さえることが合格への近道といえます。
また、実際の業務においても、道路法の知識は不可欠です。工事現場では道路占用許可申請や道路工事施行承認申請などの手続きを適切に行う必要があり、これらの手続きを怠ると工事の中断や罰則の対象となる可能性があります。
施工管理技士として責任ある立場で現場を管理するためには、道路法の正確な理解と適切な運用が求められます。

道路法は、道路の適正な管理と交通の発達を図るための重要な法律です。建設工事において道路を使用する際は、道路占用許可や道路工事施行承認など、必要な手続きを確実に行わなければなりません。
また混同されやすい「道路交通法」との違いを理解し、両方の要求事項を満たすことが、施工管理者の大切な責務となります。
道路法は、土木施工管理技士などの資格試験で出題される分野です。土木施工管理技士を目指す方は、参考書やWeb講座などを活用して道路法の知識を身につけ、試験対策と実務能力の向上を図りましょう。
CIC日本建設情報センターでは、土木施工管理技士の受験者に向けたWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。

建設キャリア転職造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
施工管理技士の平均年収は?資格別や年代別の給与相場と年収1000万を目指す方法を解説
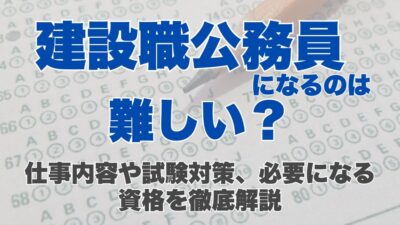
建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士消防設備士コンクリ技術士
建設職公務員になるのは難しい?仕事内容や試験対策、必要になる資格を徹底解説
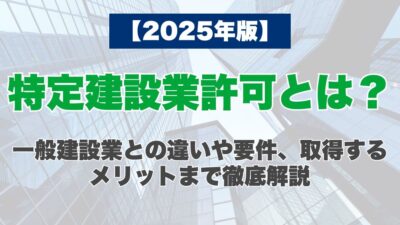
造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
【2025年版】特定建設業許可とは?一般建設業との違いや要件、取得するメリットまで徹底解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介
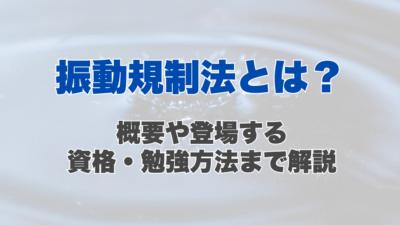
振動規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
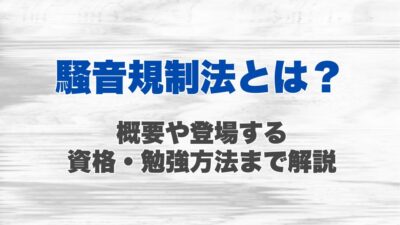
騒音規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
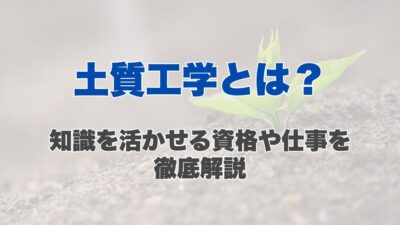
土質工学とは?知識を活かせる資格や仕事を徹底解説
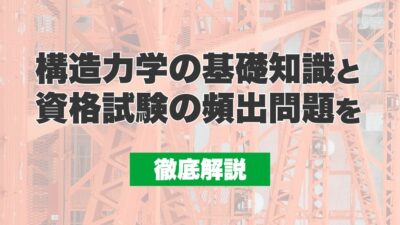
構造力学の基礎知識と資格試験の頻出問題を徹底解説
