建設業界では、「施工管理」と「設計」が代表的な技術職として知られています。どちらも建物づくりに欠かせない役割ですが、業務内容や求められるスキル、資格にはそれぞれ違いがあります。
この記事では、施工管理と設計それぞれの仕事内容や共通点、異なる資格が求められること、両方のスキルを持つことによるキャリアの可能性について解説します。未経験者はもちろん、設計から施工管理への転職を考えている方、逆に現場経験を活かして設計に携わりたい方も有益な情報ですので、ぜひ参考にしてください。
公開日:2025年5月13日 更新日:2026年1月7日

建設業界では、「施工管理」と「設計」が代表的な技術職として知られています。どちらも建物づくりに欠かせない役割ですが、業務内容や求められるスキル、資格にはそれぞれ違いがあります。
この記事では、施工管理と設計それぞれの仕事内容や共通点、異なる資格が求められること、両方のスキルを持つことによるキャリアの可能性について解説します。未経験者はもちろん、設計から施工管理への転職を考えている方、逆に現場経験を活かして設計に携わりたい方も有益な情報ですので、ぜひ参考にしてください。
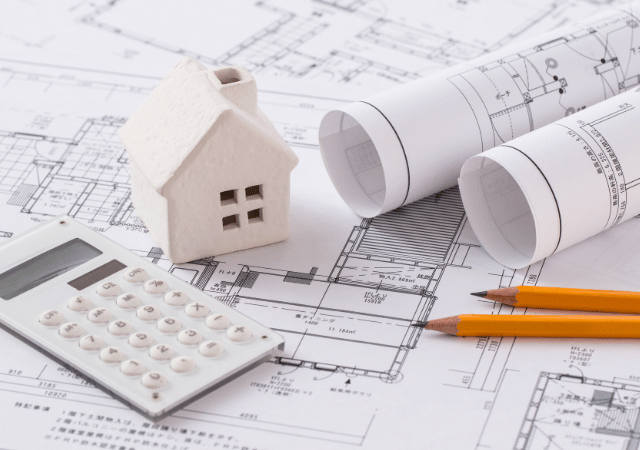
施工管理と設計は、どちらも建設関係の仕事ではありますが、建物が完成するまでの工程において異なる活動の仕方をするのが主な違いです。設計は「建てる前」、施工管理は「建てている間」を担当するイメージとなります。
一方で設計職は、施主の要望や法規・環境条件などを考慮して、図面や仕様書などの「計画」を立てます。
施工管理技士は、その図面に基づいて実際の現場がスムーズに進行するように、品質・工程・安全・原価を管理する現場の監督者です。
どちらも建設プロジェクトの成功に不可欠な存在であり、それぞれに専門的な知識と経験が求められます。
まずは施工管理と設計の違いを簡単に把握するため、以下の比較表を参考にしてみましょう。
| 施工管理 | 設計 | |
|---|---|---|
| 主な仕事場 | 工事現場 | オフィス |
| 役割 | 図面通りに作る | クライアントの要望を描く |
| 年収傾向 | 若手は平均より高め(残業・手当が多い) | 初任給は低めだが、上限値は高め |
| 体力・環境 | 体力勝負、夏暑く冬寒い | 体力は不要だが、長時間の座り仕事 |
| 求められる資格 | 施工管理技士 | 建築士(一級・二級) |
施工管理は工事現場での仕事が主になるため、外作業で体力勝負のところがありますが、建築物が形になっていくときに得られる満足感が高い仕事です。一方、設計はオフィスを仕事場としてクライアントの要望を描くのが仕事となるため、お客様の希望を汲み取って図面にするというやりがいがあるでしょう。
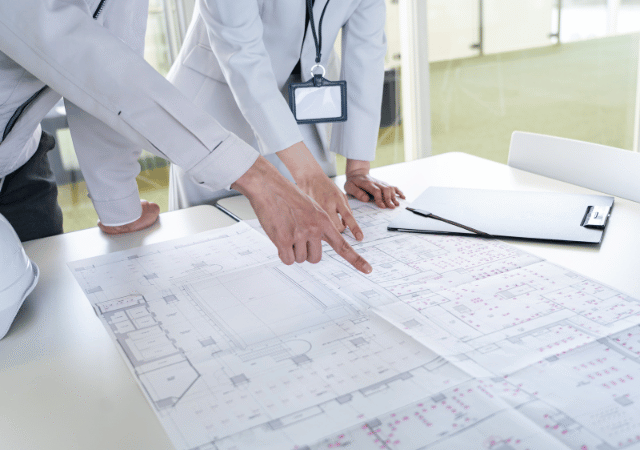
続いて、施工管理と設計の基本的な違いについて解説します。それぞれの基本業務や共通点から違いを把握していきましょう。
施工管理技士は、建設現場における管理業務を担います。「遅れず・安全に・品質良く・無駄をなくして」建物を完成させることを目的に、さまざまな仕事内容を担うのが特徴です。
業務内容には、主に以下4つの管理業務があります。
| 工程管理 | 工期内に建物を完成させるためのスケジュール管理 |
|---|---|
| 品質管理 | 設計図や施工仕様に沿った品質の確保 |
| 安全管理 | 作業員の安全確保、事故防止対策 |
| 原価管理 | 予算内に工事を完了させるためのコスト調整 |
施工管理技士は上記の管理業務を通じて、現場のリーダーとして各専門業者や作業員の調整役を担い、作業現場全体を統括します。スムーズに工事を進めるために大切な仕事です。
建築業界における設計の基本業務は、建物を「形にする」ための計画立てから始まります。設計者は、施主(クライアント)の要望をもとに、法律・安全性・利便性・美しさなどを総合的に考慮しながら図面を作成します。
以下の表は、設計業務を段階・進行別にまとめたものです。
| 基本計画・基本設計 | 建物の大まかな形や配置、面積構成などを定める段階。施主との打ち合わせを重ねながら、イメージを視覚化して建物の方向性を定める。 |
|---|---|
| 実施設計 | 基本設計をもとに、施工会社が実際に工事を進められるよう詳細な図面や仕様書を作成する。材料の選定や構造計算、設備の配置などもこの段階で細かく詰められる。 |
| 確認申請 | 設計した建物が建築基準法や条例に適合しているかを審査機関に提出して、建築許可を得るための手続きを行う。 |
また、設計の業務には専門分野ごとの役割分担があるのも特徴です。
| 意匠設計 | 建物のデザインや間取り、空間構成などを計画する業務 |
|---|---|
| 構造設計 | 建物の強度や安全性を担保する構造的な計画 |
| 設備設計 | 空調、電気、給排水など生活インフラに関わる設計 |
設計者は、これらの業務を遂行する中でCADやBIMといったソフトウェアを活用し、施主・施工業者・行政との調整役も果たします。工事するまでの多くの作業を担う仕事です。
施工管理と設計は、担当する業務内容やタイミングこそ異なるものの、建築物を完成させるという共通のゴールに向かって連携する大切な職種です。以下の表に、施工管理と設計の共通点をまとめました。
| 建物づくりに対する総合的な知識が必要 | 設計・施工管理ともに、建築基準法をはじめとする法律や、構造・材料・設備に関する知識が求められます。設計者は図面上でその知識を活かし、施工管理者は現場で安全かつ効率的に実現するために活用します。知識のベースで共通点が多いのも特徴です。 |
|---|---|
| 多くの関係者との調整力が求められる | どちらの職種も、施主・社内の関係部署・協力会社・行政など、さまざまな関係者とのコミュニケーションが必要不可欠です。設計者は「計画段階の調整」、施工管理者は「実行段階の調整」の役回りが多く、スケジュール管理力や柔軟な対応力が求められます。 |
| 最終的な目的である「建物の完成と品質確保」 | 設計者がいくら素晴らしい図面を描いても、施工管理が不十分では建物は理想通りに完成しません。逆に、現場での施工に無理がある設計では、工期や予算のトラブルが生じます。ともに、「品質の高い建築物をつくる」という同じゴールに向かって業務を遂行しているのも特徴です。 |
立場こそ違えど、ともに同じゴールに向かって重要な仕事を担っています。どちらが良いかではなく、どちらも重要な役割である点は把握しておきましょう。
施工管理と設計では、以下のように取得すると役立つ資格が異なります。
このため、例えば年収アップを目指してキャリアチェンジをする場合、新しく資格を取得する必要があります。資格を取得しないまま転職活動をしてしまうと、即戦力を求める多くの企業では未経験者とみなされてしまうこともあり、採用されづらくなってしまうでしょう。
特に、建築士資格の取得難易度は比較的高いため、設計への転職は簡単ではないといえます。

設計と施工管理は本来別の職種となりますが、実際の現場では「設計と施工を兼務する」という働き方も珍しくありません。特に企業規模や業態によって、その分業の程度や求められるスキルに大きな違いがあります。
ここからは、施工管理と設計における兼務の実態や企業規模・業態で変わる役割について詳しく解説します。
大手ゼネコンや設計事務所では、業務効率と品質管理の観点から、設計と施工管理は明確に分かれています。例えば、意匠設計・構造設計・設備設計といった各分野がさらに細分化され、それぞれが専門性を活かして業務を進めるスタイルが一般的です。
一方、中小建設会社では、人員や予算の都合から一人の担当者が設計と施工管理の両方を担うケースも見られます。そのため、施主との打ち合わせから設計、そして現場監督まで一貫して担当することがあり、柔軟な対応力と広範な知識が求められるのが特徴です。
兼務は負担が大きい反面、現場のリアルを設計に反映しやすいというメリットもあります。設計段階で「現場で施工しやすいか」を意識できるようになり、無駄のない計画が立てられるため、結果的に施主満足度や工期短縮にもつながる可能性があります。
現在の建設業界では、設計と施工のどちらにも精通したハイブリッドな人材の付加価値が高まっています。例えば、建築士と施工管理技士の両資格を保有し、設計と現場監督の両面に対応できる人材は、中小企業や設計施工一貫型の企業などで重宝されるでしょう。
重宝される主な理由は、以下のとおりです。
現場を理解している設計者は、現場の方に配慮した施工しやすい図面を作成できるだけでなく、手戻りやミスを減らせます。一方、図面を読み解く力がある施工管理者は、設計とのずれが起きたときにも臨機応変に対処可能です。
また、設計と施工をデジタル上で連携するBIM/CIM技術が普及しており、両方の知識がある人材がプロジェクトの要となりつつあります。建築士と施工管理技士のスキルセットを持つ技術者は業界内での市場価値が高く、転職市場でも非常に有利です。
将来的に「どちらかだけでなく両方できる人」が評価される時代になっていくことも考えられるでしょう。

ここまで見ると、一見別の職種に思える施工管理と設計の仕事が、実際は密接な関係があることが分かりました。とはいえ、「本当に両方のスキルが必要なの?どちらか片方だけでも生き抜けない?」と思う方もいるのではないでしょうか。
もちろん、片方のスキルだけでも仕事をこなすことは可能です。しかし、どちらかの職種を経験した人がもう一方の業務に携わることで自分自身の強みになり、キャリアアップやより待遇の良い職場への転職で有利に働く可能性は十分に考えられます。
それぞれの現場経験だけでなく共通のスキルであるCAD・法規・構造なども、互いの仕事で十分に活用できるでしょう。ここからは、施工管理と設計における互換性について深掘りします。
設計職に就いている人が施工管理の現場経験を持っていると、より現場の作業者が施工しやすい図面を描けるようになります。現場の動線や作業工程、資材の搬入経路などを具体的に理解している設計士は、図面上の細かな納まりや施工手順まで想定できるためです。結果として手戻りの少ない設計になるでしょう。
また、設計段階で現場作業の負担や安全性を配慮したプランを立てられるため、施工側とのコミュニケーションも円滑になります。これはBIM(Building Information Modeling)を活用する企業などでも重視されており、「施工を理解した設計」がプロジェクトの効率化に直結する重要なポイントとなっています。
現場を知っている設計士は非常に強い存在といえるでしょう。
逆に、設計の知識を持つ施工管理者も同様、設計図面の意図を深く理解できるため現場での対応力に優れます。細部の寸法や設計意図を正しく把握することで、現場での誤施工を防いだり協力業者への指示が的確に出せたりするなど、マネジメント面で大きなメリットがあります。
また、施工中に発生する設計変更にも柔軟に対応できるため、全体のスケジュールや予算の調整もしやすくなるでしょう。施工と設計の両視点を持つ人材は、現場の「判断力」や「交渉力」が高く、プロジェクトのキーマンとして重宝されます。

最後に、どんな人が施工管理・設計両方のスキルを有することで武器につながるのか解説します。該当するのは、主に以下の方です。
それぞれの内容について詳しく解説します。
将来的に建築士事務所や工務店を立ち上げたいと考えている人にとって、設計と施工管理のスキルは欠かせない要素です。両方の知識があれば、施主との打ち合わせから設計・申請・現場管理・引き渡しまでを一貫して請け負うことができ、フリーランスや一人親方としても高い信頼を得やすくなります。
設計から施工まで一括管理したい、設計・施工両方の視点を持つ人は業界からも重宝されるでしょう。
地域に根ざした建設会社や工務店では、1人の技術者が複数の業務を兼任することが日常的です。顧客との距離が近く、小回りの利く対応が求められるため、「設計もできる現場監督」や「現場をわかっている設計士」が高く評価されます。
また、地域密着型の業態では、継続的な信頼関係が大切です。現場対応力と提案力の両方を兼ね備えた人材だけでなく、コミュニケーションも重視して「相談しやすいパートナー」として選ばれやすくなります。
キャリアの幅を広げたい・収入アップを狙いたい人にとっても設計・施工管理の両方担えることがメリットにつながります。設計と施工管理の両方を理解している人は、転職市場でも高い評価を受け、キャリアアップにつながるためです。
企業側から見ても「どちらでも任せられる人材」は非常に貴重であり、育成コストも低く、即戦力として活躍を見込めます。年収アップや職種の選択肢を増やしたい人には、大きなアドバンテージとなるでしょう。

この記事では、施工管理と設計の違いについて、キャリアを広げる方法と併せて解説しました。
施工管理と設計は、どちらも建設関係の仕事ですが、建物が完成するまでの工程における立場や業務内容、役立つ資格が異なります。
施工管理技士は、建設現場における管理業務を担います。
一方で、設計者は、施主(クライアント)の要望をもとに、法律・安全性・利便性・美しさなどを総合的に考慮しながら図面を作成する仕事です。
両方の仕事の経験・スキルを有することで、キャリアの幅を広げたり独立を有利にできたりします。
CIC日本建設情報センターでは、転職支援サービス「建設キャリア転職(運営会社:CIC日本建設情報センター)」を提供しております。長年のキャリアがあるからこそ実現できる独自の強みを活かし、さまざまな希望条件に適した求人をご紹介しますので、求人選びでお悩みの方は、ぜひ利用をご検討ください。

建設キャリア転職造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
施工管理技士の平均年収は?資格別や年代別の給与相場と年収1000万を目指す方法を解説

建設業の主な職種一覧!仕事内容や平均年収について解説 – 建設キャリア転職 –

【静岡県】地場ゼネコンの売上高ランキングTOP7 – 建設キャリア転職 –

【兵庫県】地場ゼネコンの売上高ランキングTOP8 – 建設キャリア転職 –
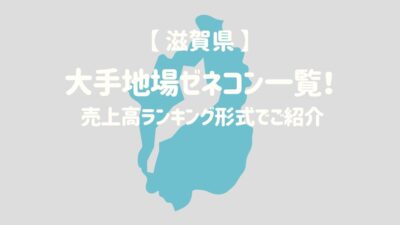
【滋賀県】大手地場ゼネコン一覧!売上高ランキング形式でご紹介 – 建設キャリア転職 –
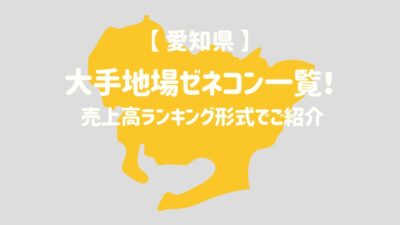
【愛知県】大手地場ゼネコン一覧!売上高ランキング形式でご紹介 – 建設キャリア転職 –

【石川県】地場ゼネコンの売上高ランキングTOP4 – 建設キャリア転職 –

【富山県】地場ゼネコンの売上高ランキングTOP5 – 建設キャリア転職 –
