賃金や労働時間など、労働条件に関する最低基準を定めた「労働基準法」。労働者が不当な条件で働くことを防ぎ、自身の生活保障を図るためには、必ず把握しておきたい法律です。
この記事では、労働基準法とは何か、労働基準法の3大要素、年次有給休暇のルールを詳しく解説します。さらに、違反した場合の罰則、建設業における注意点、2024年4月の改正についてもご紹介するので、参考にしてみてください。
公開日:2025年10月24日 更新日:2025年10月24日
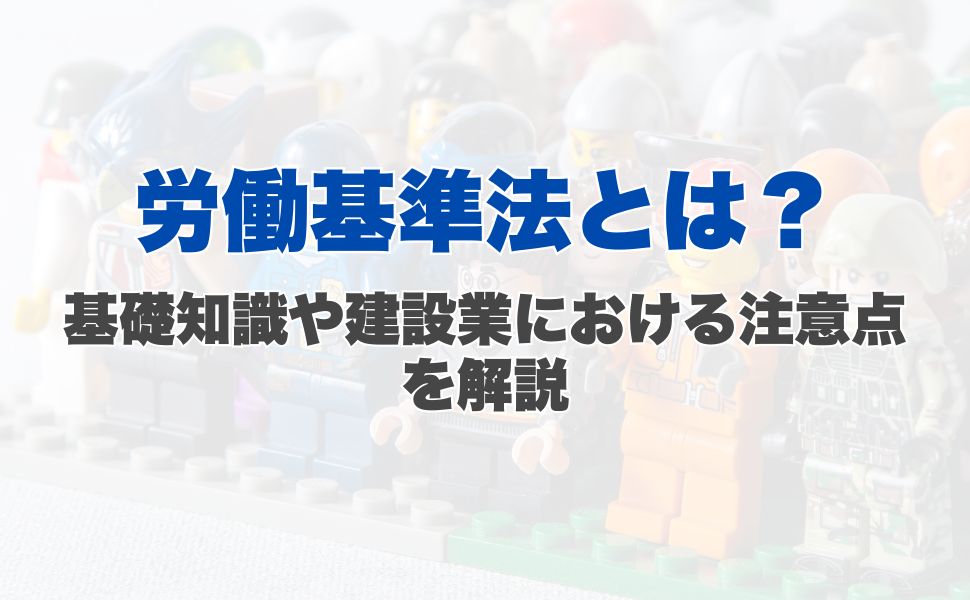
賃金や労働時間など、労働条件に関する最低基準を定めた「労働基準法」。労働者が不当な条件で働くことを防ぎ、自身の生活保障を図るためには、必ず把握しておきたい法律です。
この記事では、労働基準法とは何か、労働基準法の3大要素、年次有給休暇のルールを詳しく解説します。さらに、違反した場合の罰則、建設業における注意点、2024年4月の改正についてもご紹介するので、参考にしてみてください。

労働基準法とは、事業主が労働者の雇用において守らなければならない、労働条件の最低基準を定めた法律です。こちらでは、労働基準法の「目的」 や「対象者」、会社ルール(就業規則)との関係について詳しく解説していきます。
労働基準法の目的は、労働者の生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)を保障することです。
労働者は雇用主から支払われる給与で生活をしていることから、雇用主よりも弱い立場になりやすいため、不公平な条件で働くことを防ぐ必要があります。「低賃金」「長時間労働」など、劣悪な労働条件になることを阻止し、生活と権利を保護できる最低基準まで条件を引き上げるためにも、労働基準法の存在は重要なのです。(参考:労働基準法の概要)
労働基準法の対象者は、日本国内で雇用主に雇われて働いている全ての人です。
大企業や中小企業といった企業の規模や、契約社員・パート・アルバイトなど就業形態に関わらず労働基準法が適用されます。また、国籍・身上・性別なども問わず権利が保障されます。
一方、雇用されずに仕事をする「個人事業主」や、一斉に有給休暇を取得すると役所が機能しなくなる「国家公務員(一般職)」など、労働基準法が適用されないケースもあります。(参考:労基法は、働く人みんなに適用されるのですか。)
会社ルール(就業規則)の労働条件は、労働基準法の規定を下回っていてはいけません。
仮に下回っている場合、労働基準法の基準が優先して適用されます。一方、労働基準法の規定を上回っている労働条件を就業規則で定めている場合は、就業規則の定めが適用されることとなります。(参考:就業規則を作成しましょう)

「労働時間」「休日」「賃金」 は労働基準法の3大要素であり、雇用されて仕事をしている人が知っておきたい基礎知識といえます。こちらでは、労働時間の上限と休憩のルール、休日のルール、賃金のルールについて、それぞれ詳しく解説していきます。
労働基準法では「法定労働時間」が定められており、労働時間の上限は原則として「1日8時間・週40時間」です。また、企業が独自に定める「所定労働時間」は、法定労働時間の範囲内で決定されなければいけません。
企業が法定労働時間を超える時間外労働(残業)をさせる際は、労働者と「36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)」を結ぶ必要があります。しかし、36協定を締結したとしても、無制限に時間外労働が指示されるわけではなく、原則として「1ヶ月につき45時間」「1年につき360時間」という決まりがあります。
加えて休憩のルールとして、「労働時間が6時間を超える場合、45分以上の休憩」「労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩」が義務付けられているのです。(参考:労働時間・休日)
休日のルールとしては、「週に1日、または4週に4日の休日が義務」という、企業が労働者に与えなければならない最低限の休日である「法定休日」が定められています。このため、「週休2日以上」という会社の場合、週に1日は法定休日で、それ以外の休日は「法定外休日」です。
一方で、36協定が締結されていれば、休日労働の指示を受けることがあります。
もし、法定休日に休日労働をする場合「通常賃金の35%以上の割増賃金」が発生します。一方、法定外休日に休日労働をする場合「時間外労働」となり、週40時間の労働時間を超過した場合「25%以上の割増賃金」、60時間を超える時間分は「50%以上の割増賃金」が適用されるのです。(参考:労働時間・休日、しっかりマスター労働基準法割増賃金編)
賃金のルールとしては、以下のような「賃金支払いの5原則」というものがあります。
| 原則の名称 | 概要 |
|---|---|
| 通貨払いの原則 | 賃金は現物支給や小切手ではなく、通貨で支払わなければならない。 |
| 直接払いの原則 | 賃金は代理人への支払いではなく、労働者本人に直接支払わなければならない。 |
| 全額払いの原則 | 法令で規定された「社会保険料」や「税金」など以外は賃金から天引きすることはできず、全額を労働者へ支払う必要がある。 |
| 毎月1回以上払いの原則 | 賞与などの例外を除き、賃金は毎月1回以上支払う義務がある。 |
| 一定期日払いの原則 | 「月末締め翌月25日払い」のように一定の期日に賃金を支払う必要がある。 |
(参考:賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。)
また、「時間外労働(法定外休日)」と「法定休日労働」における割増賃金の計算方法については、以下のとおりです。
【時間外労働(法定外休日)の場合】
| 時間(例:所定労働時間が9時から17時の場合) | 割増賃金の計算方法 |
|---|---|
| 17~18時 | 法定時間内残業として1時間あたりの賃金×1.00×1時間 |
| 18~22時 | 法定時間外残業として1時間当たりの賃金×1.25×4時間 |
| 22時~5時 | 法定時間外+深夜残業として1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間 |
(参考:しっかりマスター労働基準法割増賃金編)
【法定休日労働の場合】
| 時間(例:9時から24時まで労働した場合) | 割増賃金の計算方法 |
|---|---|
| 9~22時 | 休日労働として1時間当たりの賃金×1.35×12時間 |
| 22~24時 | 休日労働+深夜労働として1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 |
(参考:しっかりマスター労働基準法割増賃金編)
ちなみに、労働者の賃金最低額は「最低賃金制度」というルールに基づいており、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に定められた高い水準の最低賃金「特定(産業別)最低賃金」のどちらか高い方の賃金が適用されます。

年次有給休暇が付与される条件としては、「6ヶ月以上継続して雇用されている」「所定労働日の8割以上出勤している」の2つを満たしている必要があり、通常の労働者に付与される日数は以下のとおりです。
| 継続勤務年数(年) | 年次有給休暇の付与日数(日) |
|---|---|
| 0.5 | 10 |
| 1.5 | 11 |
| 2.5 | 12 |
| 3.5 | 14 |
| 4.5 | 16 |
| 5.5 | 18 |
| 6.5以上 | 20 |
また、年5日の年次有給休暇を確実に取得するため、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日は雇用主が時季を指定して取得させる義務が発生しています。
有給休暇は雇用形態に関係なく付与されるため、パートやアルバイトでも年次有給休暇が付与されますが、短時間従業員の場合、勤務年数と所定労働日数によって有給休暇の付与日数が変化します。

労働基準法に違反した疑いが発覚した場合、労働基準監督署による調査が行われ、違反が認められると是正勧告があり、司法処分を受けることになります。
罰則の例として、「労働者に休憩をとらせなかった場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」や「残業代未払いの場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるなどのケースがあります。(参考:休憩時間が取れない! 法律上のルールや違法となるケース、残業代の未払いがあるときに、使用者は罰則を受ける?また、その他の影響は?)

建設業における労働基準法の注意点として、「特定の業務で特別教育を受けることが義務付けられている」ということを押さえておきましょう。特別教育が必要な作業者が、その教育を受けずに該当の業務を行った場合、法令違反として罰則が課せられる可能性があります。
建設業で特別教育の受講を検討している方は、「CICの特別教育・安全衛生教育」の受講がおすすめです。CICの特別教育はWeb講座であるため、会社以外の場所からでも24時間好きな時間にPCやスマホから手軽に受講でき、忙しい方にも最適です。
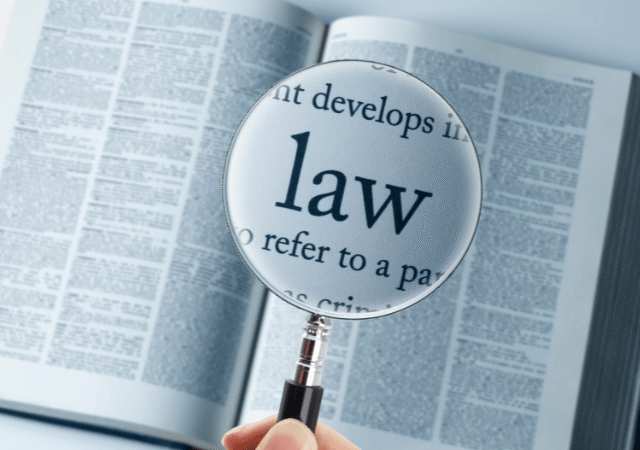
労働基準法の改正に伴い、2024年4月から「時間外労働の上限規制」が建設業に適用されています。このため、時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間(限度時間)」となり、特別な事情がない限りこれを超えることはできません。(参考:建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説)
法改正により長時間労働の常態化を改善する必要があるため、工期の適正化を図ったり、人材の確保に力を入れたりなどの対策を行うことが重要になるでしょう。

この記事では、労働基準法とは何か、労働基準法の3大要素、年次有給休暇のルールを詳しく解説しました。
「特別教育の実施を検討している」という方は、特別教育をオンラインで受講できる「CICの特別教育・安全衛生教育」を検討してみてください。
