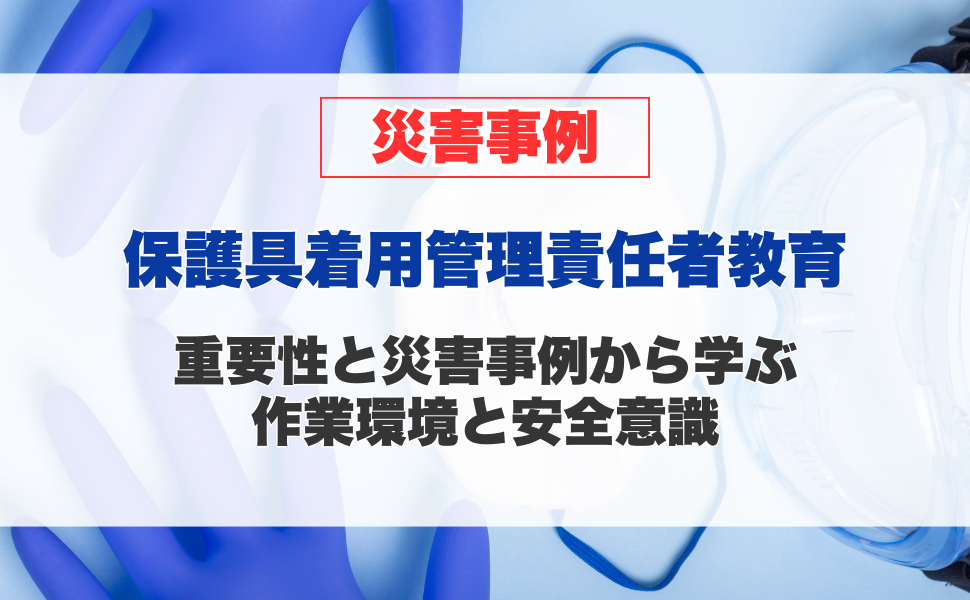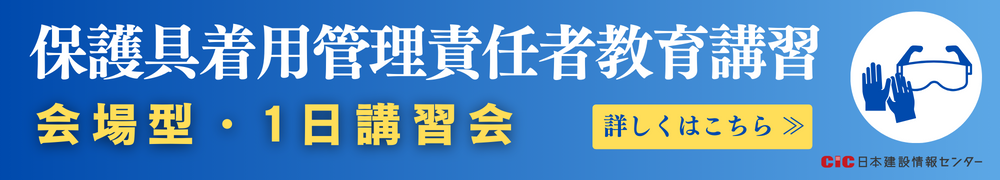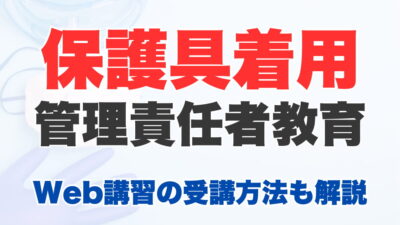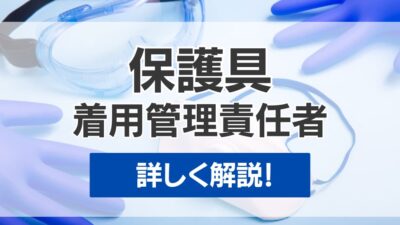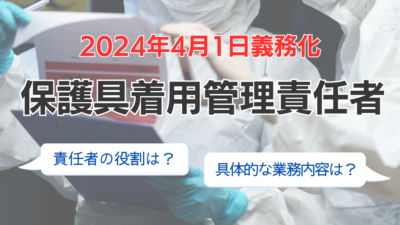近年、保護具を正しく着用しなかったことによる労働災害が後を絶ちません。災害の結果、健康障害や、死に至るケースもあるため、これまで努力義務であった保護具の着用が、2024年4月から原則として義務化されました。
これにより事業者は、労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。
今回は保護具に関わる過去の労働災害事例をご紹介します。最後まで読めば保護具着用管理責任者の重要性が理解できるでしょう。特に受講を考えている事業者の方は必見です。