建物が安全に建ち続けるためには、美しいデザインだけでなく、しっかりとした「構造」が必要となります。この構造の安全性を計算し、証明するのが「構造力学」です。
構造力学とは、建物にかかるさまざまな力(荷重)を分析し、それに耐えうる設計を導き出す学問を指します。
この記事では、構造力学の基礎をわかりやすく解説し、建築士などの資格試験で頻出する問題の解き方や、効率的な勉強法をご紹介します。
公開日:2025年10月24日 更新日:2025年10月24日
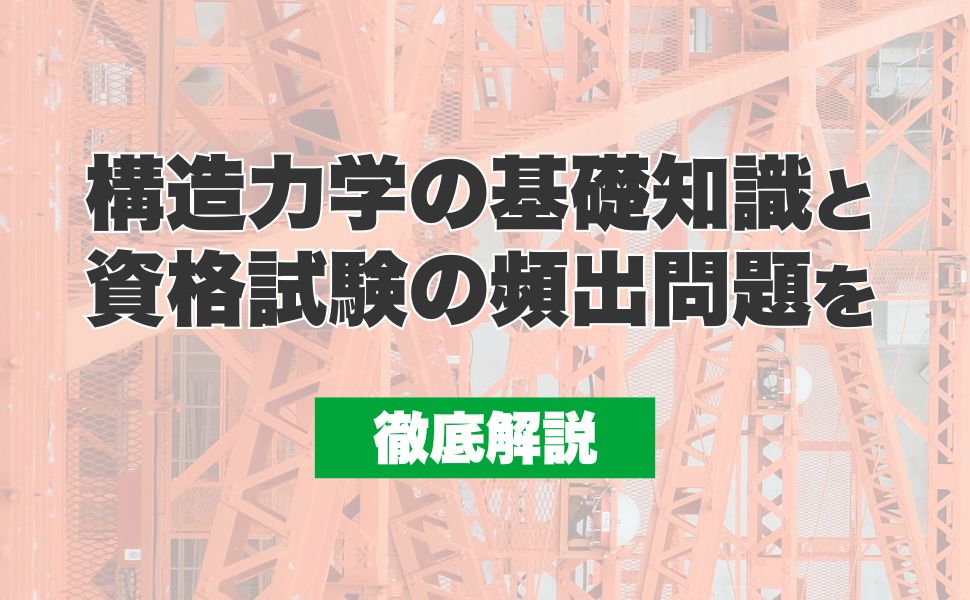
建物が安全に建ち続けるためには、美しいデザインだけでなく、しっかりとした「構造」が必要となります。この構造の安全性を計算し、証明するのが「構造力学」です。
構造力学とは、建物にかかるさまざまな力(荷重)を分析し、それに耐えうる設計を導き出す学問を指します。
この記事では、構造力学の基礎をわかりやすく解説し、建築士などの資格試験で頻出する問題の解き方や、効率的な勉強法をご紹介します。

構造力学とは、「建物・橋・船舶といった構造物が、その重さや外部からの力によってどのように変形し、内部にどのような力が働くか」を解析する応用力学の一分野です。
私たちが日常生活を送る建物には、常にさまざまな力が作用しています。
これらの力が構造物にどう影響するかを予測し、安全な状態を保つための設計基準を数値化するのが、構造力学の役割です。
構造力学の知識なしには、人々が安心して暮らせる建物は造れません。万が一、不十分な設計のまま建ててしまうと、建物が傾いたり、ひび割れが生じたり、最悪の場合には倒壊する危険性もあります。
構造力学は、こうしたリスクを未然に防ぎ、建物の安全性を科学的に保証するための基準となる学問なのです。
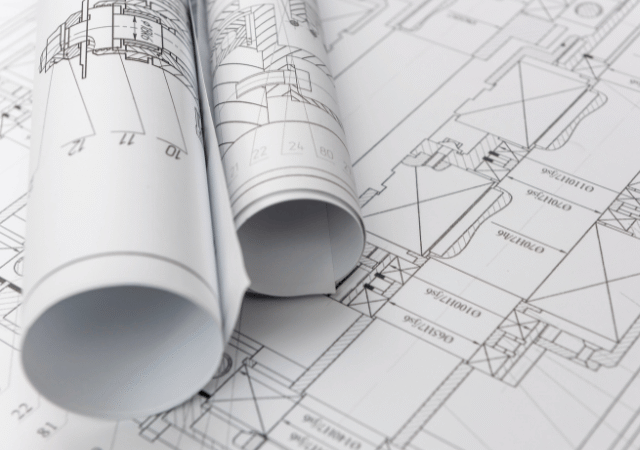
構造力学は、安全な建物を設計・施工するために必須の知識です。そのため、建築や土木関連の多くの国家資格や民間資格で、その知識が問われます。
建築士の試験では、「構造」という科目で構造力学の問題が必ず出題されます。一級建築士の試験では、30問中6〜7問、二級建築士では25問中6問程度が構造力学からの出題とされています。
内容は、断面の性質や応力度、静定構造物の応力解析など多岐にわたります。建築士として活躍するには、この学問の深い理解が必須です。
コンクリート技士は、高品質なコンクリート構造物を施工するために必要な知識と技術を証明する資格です。コンクリートの強度や性質を正確に把握し、設計基準を満たすためには、構造力学の知識が欠かせません。
その他にも、以下のような資格で構造力学の知識が必要となります。

構造力学を学ぶ上で、避けて通れないのが以下の基本的な概念です。これらを理解することが、問題解決への第一歩となります。
物体が静止している状態を「平衡状態」といい、その物体に働くすべての力の合計がゼロになることを「力のつり合い」と言います。力のつり合い(平衡)条件は、構造力学のすべての計算の土台となります。
物体を回転させようとする力を「モーメント」と呼びます。これは、力(P)と、その力が作用する点から回転の中心までの距離(L)の積(P×L)で表されます。時計回りの回転を正、反時計回りを負として計算します。
構造物が外部からの力を受けるとき、それを支える支点から生じる抵抗力を「反力」と呼びます。反力を正しく計算することで、構造物の安定性を確保できます。
部材の内部に生じる力で、外部からの力に抵抗しようと働きます。断面力には、引っ張る力(軸力)・ねじる力(ねじりモーメント)・曲げる力(曲げモーメント)などがあります。これらの力を求めることが、部材の安全性を検討する上で重要です。
三角形の集合体で構成される、軽量で強度に優れた構造です。橋や屋根などでよく見られます。各部材には引っ張る力または圧縮する力のみが働き、曲げモーメントは生じないという特徴があります。
部材の形や大きさ(断面)が、力に対してどのように影響するかを表す指標です。
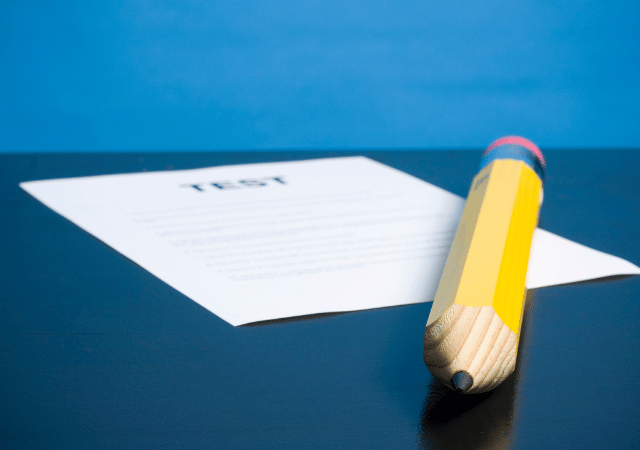
ここでは、構造力学の基礎知識を応用した、資格試験でよく出題される問題の例をいくつかご紹介します。
問題:
長さ6mの梁の左端にA、右端にBの支点があります。中央の3mの位置に鉛直下向きに10kNの力が作用するとき、支点AとBに生じる反力を求めなさい。
解答:
支点Aの反力:5kN
支点Bの反力:5kN
解説:
鉛直方向の力のつり合い:支点Aの反力(RA)と支点Bの反力(RB)の合計が、作用する力10kNとつり合います。「RA+RB=10」
モーメントのつり合い:支点A回りのモーメントの合計を考えます。作用する力10kNはAから3m離れているため、時計回りのモーメントは10×3=30となります。一方、支点Bの反力RBはAから6m離れており、反時計回りのモーメントは$-RB \times 6$です。この合計がゼロになるので、30−RB×6=0。これを解くと、「RB=5」となります。
RA+5=10より、RA=5となります。
問題:
片持ち梁(一端が固定された梁)に、自由端に鉛直下向きに10kNの力が作用します。梁の長さが3mのとき、固定端から1m、2m、3mの位置に生じる曲げモーメントを求めなさい。
解答:
1mの位置:20kNm
2mの位置:10kNm
3mの位置:0kNm
解説:
片持ち梁の自由端に力がかかっている場合の曲げモーメントを求める問題です。曲げモーメントは固定端から自由端に向かうにつれて小さくなり、力がかかる点(自由端)でゼロになります。
問題:
二等辺三角形の単純トラス構造を考えます。底辺は6m、高さは4mで、頂点の節点Cに鉛直下向きに10kNの荷重が作用しているとします。このとき、斜めの部材ACおよびBCに生じる軸力をそれぞれ求めなさい。
解答:
部材ACの軸力:6.25kN(圧縮力)
部材BCの軸力:6.25kN(圧縮力)
解説:
この問題は、力のつり合いを考えて解きます。まず、三平方の定理より斜辺の長さは5mです。
荷重10kNは左右の斜辺に均等に分担されるため、それぞれの斜辺が負担する鉛直成分は5kNとなります。軸力は、この鉛直成分を$\sin\theta$(0.8)で割ることで求められ、6.25kNとなります。荷重が下向きのため、部材には圧縮力が生じます。
問題:
幅10cm、高さ20cmの長方形断面の断面二次モーメントを求めなさい。
解答:
6,666.67cm⁴
解説:
長方形断面の断面二次モーメントIは、I=(幅×高さ3)/12という公式で求められます。
I=(10×203 )/12=80000/12≒6666.67cm4
問題:
部材に圧縮力が作用したときに、部材が横にたわんで崩壊する現象の名称を答えなさい。
解答:
座屈
解説:
座屈とは、部材が持つ強度に対して、横方向へのたわみによって急激に耐力が低下し、破壊に至る現象です。柱のように細長い部材に圧縮力が加わると発生しやすいため、構造設計において重要な検討項目となります。
問題:
一定の曲げ剛性EIを持つ片持ち梁に、集中荷重Pが作用するとき、自由端のたわみδを求める式を書きなさい。
解答:
δ=PL3 /(3EI)
解説:
たわみとは、構造物が力によって変形する量を指します。この問題では、代表的な梁のたわみの公式が問われています。公式を暗記しておくことで、問題を素早く解くことができます。
問題:
連続梁のように、力のつり合いの式だけでは反力を求められない構造物を何と呼びますか?
解答:
不静定構造物
解説:
不静定構造物は、未知の反力の数がつり合いの式の数よりも多い構造です。これを解くには、たわみや応力といった変形に関する知識を組み合わせる必要があります。

構造力学は、公式を覚えるだけでは通用しません。なぜその公式が成り立つのかを理解し、さまざまな問題に応用できる「解く力」を身につけることが大切です。
ここでは、構造力学対策の3つのポイントをご紹介します。
資格試験の出題傾向は、毎年大きくは変わりません。過去問題を繰り返し解くことで、出題形式や問われ方のパターンに慣れてきます。ただ解くだけでなく「なぜその答えになるのか」「他の選択肢がなぜ間違いなのか」を説明できるようになるまで深く掘り下げてみましょう。
応用問題が解けないのは、基礎知識が曖昧なためです。力のつり合いやモーメントの概念をしっかり理解すれば、応用問題も怖くありません。特に、計算ミスを防ぐために、単位の確認を怠らないようにしましょう。
独学では限界を感じる方もいるかもしれません。特に、働きながらの学習は時間との戦いです。そのような場合は、専門の講座を受講することをおすすめします。プロの講師が要点を絞って教えてくれるため、効率的に学習を進められるでしょう。
資格試験では、限られた時間内で合格点を取る必要があります。要点に絞って効率的に対策を進めるためにも、専門の講座を活用することをおすすめします。

構造力学は、建築や土木の世界で活躍するために不可欠な、安全性を支える重要な学問です。
一見難しそうに見えますが、基礎から丁寧に学び、繰り返し問題を解くことで必ず習得できます。公式をただ暗記するのではなく、その意味を理解することが、応用力を高めるためのポイントです。
この記事でご紹介した基礎知識と頻出問題を参考に、ぜひ学習を始めてみてください。構造力学の知識は、将来的に多くの人々の安全を守る力となります。
構造力学の学習内容は、コンクリート技士や土木施工管理技士の資格試験でも役立ちます。試験範囲の多くが構造物や材料の特性に関わるため、学習の相乗効果が期待できるでしょう。効率的に短期集中で合格を目指したい方は、「土木施工管理技士」の資格取得を目指せるCIC日本建設情報センターの講座もぜひご覧ください。質の高いプロの講座を、ご自分のペースで無理なく受講できます。

建設キャリア転職造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
施工管理技士の平均年収は?資格別や年代別の給与相場と年収1000万を目指す方法を解説
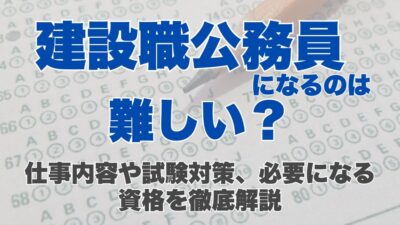
建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士消防設備士コンクリ技術士
建設職公務員になるのは難しい?仕事内容や試験対策、必要になる資格を徹底解説
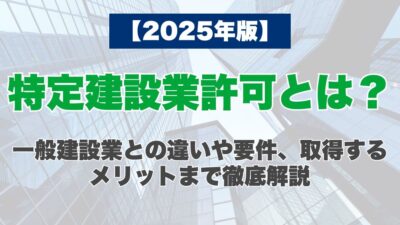
造園施工管理技士建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士
【2025年版】特定建設業許可とは?一般建設業との違いや要件、取得するメリットまで徹底解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介
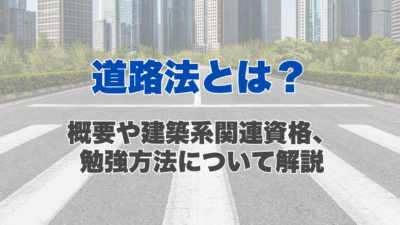
道路法とは?概要と罰則、登場する建築系の資格や勉強方法について解説
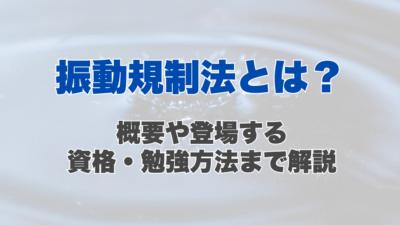
振動規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
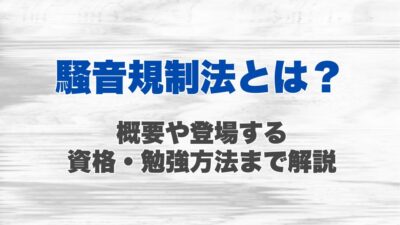
騒音規制法とは?概要や登場する資格、勉強方法まで解説
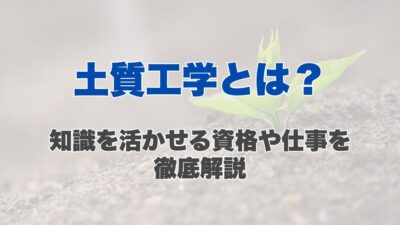
土質工学とは?知識を活かせる資格や仕事を徹底解説
