受変電設備とは、電力会社から送られてくる電気を受電(電気を受け取り)、変電(施設内で使える大きさの電気に変える)ための設備のことです。とはいえ、「受変電設備ってキュービクルのこと?何となくは分かるけど具体的には分からない」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、受変電設備の基本的な役割から種類、構成機器や安全対策まで詳しく解説します。また、受変電設備に関わる仕事で必要となる第一種電気工事士や電験三種などの関連資格も触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2025年9月30日 更新日:2025年9月30日
高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育電気工事施工管理技士電気工事士
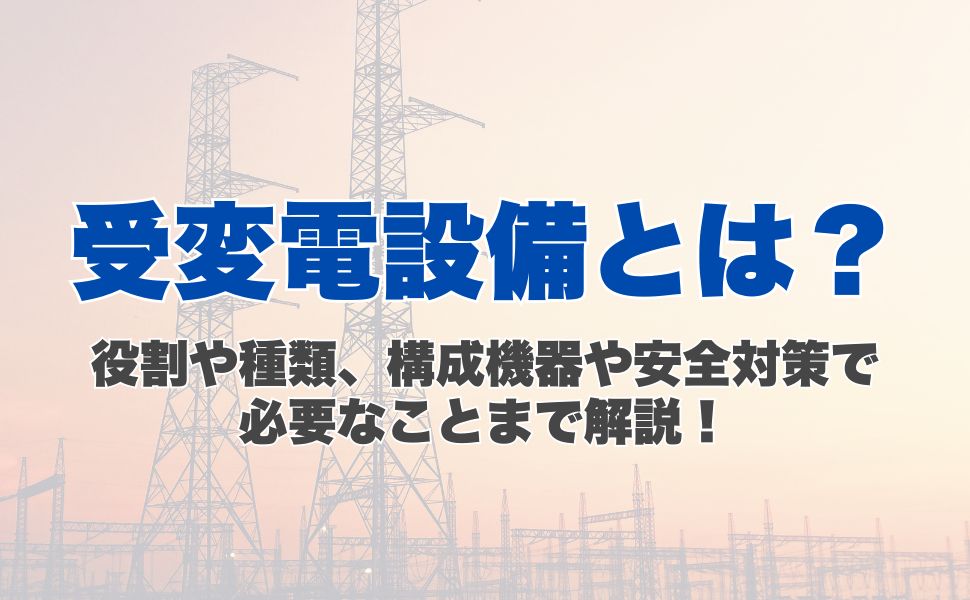
受変電設備とは、電力会社から送られてくる電気を受電(電気を受け取り)、変電(施設内で使える大きさの電気に変える)ための設備のことです。とはいえ、「受変電設備ってキュービクルのこと?何となくは分かるけど具体的には分からない」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、受変電設備の基本的な役割から種類、構成機器や安全対策まで詳しく解説します。また、受変電設備に関わる仕事で必要となる第一種電気工事士や電験三種などの関連資格も触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
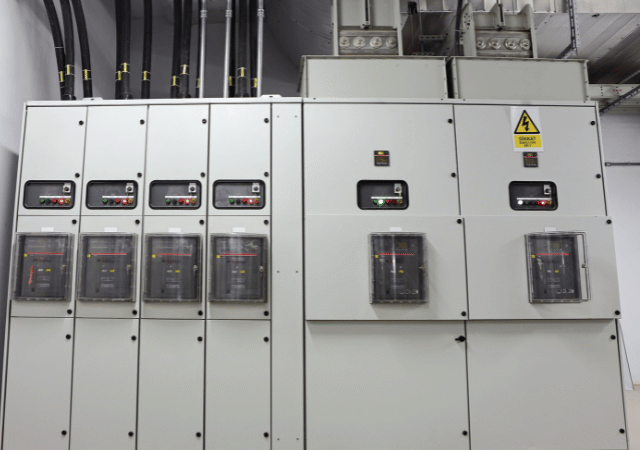
受変電設備とは、電力会社から送られてくる電気を受け取り(受電)、施設内で使える大きさの電気に変える(変電)ための設備のことです。
発電所では電気の無駄を減らすために、20万ボルトや50万ボルトなどの超高圧で送電しています。途中の変電所で22,000ボルトや6,600Vボルトに下がるものの、大きすぎる電圧なので建物内での使用ができません。そこで、受変電設備によって使用できる電圧に変える必要があるわけです。
工場やビル、病院などの大型施設では、この受変電設備が電力供給の重要な役割を担っています。具体的には、電力会社から送られてくる6,600Vや22,000Vといった高圧・超高圧の電気を、100Vや200Vなどの低圧に変換し、施設内の各エリア・設備に安定した電気を供給する役割を担っています。
電圧の大きさは電圧の種類に応じて異なります。主な目安は以下のとおりです。
| 電圧の種類 | 受電電圧 |
|---|---|
| 低圧 | ・直流:750V以下 ・交流:600V以下 |
| 高圧 | ・直流:751~7,000V ・交流:601~7,000V |
| 特別高圧 | ・7,000Vを超える電圧 |
低圧受電は、一般家庭や小規模事業所で使用されます。
高圧受電は中規模以上の工場やビルで採用されており、特別高圧受電は大規模工場や鉄道施設など、より大きな電力を必要とする施設で使用されています。
また、契約電力が50kW以上になると高圧受電が必要となり、2,000kW以上では特別高圧受電を検討することが一般的です。

受変電設備と聞くと、キュービクルのことを想像される方も多いのではないでしょうか。キュービクルの正式名称は「キュービクル式高圧受電設備」なので、受変電設備の1つには含まれますが、「受変電設備=キュービクル」というのは少し違います。
受変電設備の形態をまとめると、大きく以下の2パターンにわかれます。
ここでは、それぞれの種類と特徴について詳しく解説します。
開放型受変電設備は、変圧器や遮断器などの機器を建物内の電気室に個別に設置するタイプです。大規模な工場や大型ビルなど、敷地が広く受電容量が大きな設備に見られます。
開放型は、機器ごとの点検やメンテナンスが簡単である点が特徴です。設置には広いスペースが必要ですが、機器の増設や改修も比較的簡単に行えます。また、故障時には問題のある機器のみを交換できるため、維持管理の柔軟性が高いというのもメリットです。
ただし、充電部が露出しているため、感電などの電気事故を防ぐための厳重な安全対策・管理が必要です。
閉鎖型受変電設備は、言い換えればキュービクル式高圧受変電設備のことです。受変電に必要な機器を金属製の箱に収納しています。コンパクトな設計のため、敷地面積に制限がある中小規模の工場やビル、商業施設などで広く採用されています。
キュービクルの場合、電気室が不要なため建築コストを削減できるのも特徴です。充電部が完全に覆われているため安全性が高く、屋外設置にも適しています。また、建物では契約電力が50kW以上となると電力会社から高圧受電の要請がされますが、受電容量4000kVA(力率0.8とすると契約電力で3200kW)と大幅に上回っており、このことも受変電設備の多くにキュービクル式が採用されている理由ともいえるでしょう。
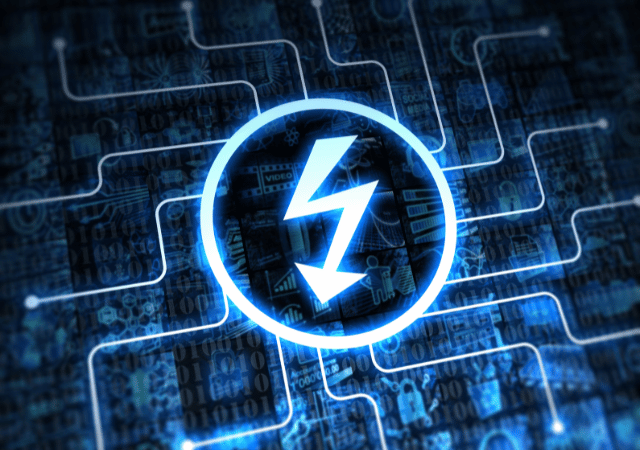
いくつか種類のある受変電設備ですが、構成されている機器には大きな違いはありません。主に以下の機器で構成されています。
ここでは、各構成機器がどういったものかを簡単にご紹介します。
断路器は、電路を無負荷で開閉する装置です。保守点検時に電路を切り離す際に使用され、目視で開閉状態を確認できます。後述する遮断器と異なり、負荷電流や事故電流を遮断する能力はなく、必ず遮断器で電流を切った後に操作が必要です。
遮断器は、通常の負荷電流だけでなく、短絡や地絡などの事故電流も安全に遮断できる装置です。真空遮断器(VCB)やガス遮断器(GCB)などの種類があり、高圧受電設備では真空遮断器が主流となっています。
保護継電器と連動して動作し、異常を検知すると自動的に電路を遮断して設備を保護します。定期的な動作試験や接点の点検が必要で、適切なメンテナンスにより長期間の安定運用が可能です。
変圧器は、電磁誘導の原理を利用して交流電圧を変換する機器です。受変電設備の中でも特に重要な機器で、高圧を低圧に降圧する役割を担っています。油入変圧器とモールド変圧器などいくつか種類があるのも特徴です。
避雷器は、雷サージや開閉サージから電気設備を保護する装置です。通常時は絶縁物として機能し、異常電圧が発生すると瞬時に導通して、サージ電流を大地に放電します。酸化亜鉛形避雷器が主流で、優れた非線形抵抗特性により確実な保護が可能です。
進相コンデンサは力率改善(電圧と電流の位相差をなくして電力利用の効率を高める技術)のために設置し、無効電力を供給して電力損失を低減する機器です。直列リアクトルと組み合わせることで、高調波の流入を抑制する効果もあります。
力率が改善されると、電力会社からの基本料金が割引される制度もあるため、経済的メリットも得られます。具体的には、自動力率調整装置により、負荷変動に応じて最適な力率制御を行うシステムが一般的です。
計器用変流器(CT)と計器用変圧器(VT)は、それぞれ大電流を小電流に、高電圧を低電圧に変換する機器です。これらにより、高電圧・大電流回路の安全な測定・監視が可能になります。
特に、取引用計量には高精度のものが求められ、二次側の開放や短絡は機器破損に繋がるため注意が必要です。
保護継電器は、電気系統の異常を検出して遮断器に動作指令を出す装置です。過電流継電器(OCR)、地絡継電器(DR)、不足電圧継電器(UVR)など、保護対象や検出する異常により様々な種類があります。
現在では、デジタル形継電器も登場しており、複数の保護機能を1台に集約できるようになりました。整定値の設定や動作試験は、継電器の専門知識・試験器を素早く正確に操作する技術が必要で、定期的な点検により信頼性を維持します。
低圧配電設備は、変圧器で降圧された電力を各負荷に配電する設備です。主配電盤・分電盤・動力制御盤などで構成され、ブレーカーや電磁開閉器により回路を保護・制御します。
現代では省エネルギーのため、デマンド監視装置や電力監視用の機器・システムも導入され、安全かつ効率的な電力供給を実現します。

受変電設備に関する作業では、電気的トラブルが常に潜在的なリスクとなります。安全対策を怠ると、設備の故障や停止による経済的な損失だけでなく、人身事故に繋がりかねません。そのため、機器の適切な交換や安全点検の実施が必要不可欠です。
具体的な対策として挙げられるのは、作業前の停電確認と検電、充電部への接近防止柵、保護具の使用などです。点検では、年次点検などで定期的な絶縁抵抗測定・接地抵抗測定、継電器の動作測定などで異常を早期発見します。また、停電中に機器を清掃しながら目視点検をして異常の有無を確認することもあります。
高圧・特別高圧の電気取扱作業者には、労働安全衛生法に基づく特別教育の受講が義務付けられています。CIC日本建設情報センターでは、「高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育」のWeb講座を取り扱っておりますので、受講方法にお悩みの場合は、ぜひ受講をご検討ください。

受変電設備に関連する仕事では専門的な知識と技術力が求められるため、関連資格の取得が大切です。具体的には、以下のような資格があります。
資格を持つことで法的に認められた作業範囲が広がり、キャリアアップにもつながります。それぞれの資格について詳しくみていきましょう。
第一種電気工事士は、最大電力500kW未満の工場やビルなどの電気工事に従事できる国家資格です。受変電設備においては、低圧側の配線工事や高圧受電設備の配線工事など幅広い業務が可能となります。
実務経験がなくても受験可能で、筆記試験と技能試験に合格することで免状を取得できます。ただし、免状交付には3年以上の実務経験が必要です。受変電設備の保守・メンテナンス業務にも欠かせないため、電気工事業界で大きく役立つ資格といえます。
電験三種は、電圧5万ボルト未満の電気工作物の保安監督ができる国家資格です。受変電設備の維持・運用において中心的な役割を担い、電気主任技術者として選任されます。
試験では、理論・電力・機械・法規の4科目に合格する必要がありますが、科目合格制度により3年間以内の全科目合格で試験合格の扱いとなります。工場やビルの専任の電気主任技術者として独立することも可能で、電気系技術者のキャリア設計を考える中で、ぜひとも取得したい資格の1つです。
電気工事施工管理技士は、電気工事の施工計画から安全管理までを行う国家資格です。1級を取得すると、受変電設備の新設・更新工事で専任技術者・監理技術者として活躍できます。
建設業法上の専任技術者になれることから公共工事の入札にも有利で、事業者側にもメリットのある資格です。実務経験が必要ですが、電気工事のスペシャリストとして高く評価されます。

受変電設備は、電力会社から送られる高圧・超高圧の電気を、安全に使用可能な電圧に変換する重要な設備(電気機器の集まり)です。開放型と閉鎖型(キュービクル型受電設備)の2種類があり、施設の規模や用途に応じて選択されます。
変圧器を中心に、遮断器・保護継電器など多くの機器で構成され、それぞれが重要な役割を担っています。安全面では、適切な保護具の使用や定期的な点検、作業者への教育が不可欠です。
CIC日本建設情報センターでは、この記事でご紹介した「第一種電気工事士」や「電気工事施工管理技士」、「高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育」などのWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら、最短距離で資格取得を目指せる内容です。電気業界でこれから働く方、技術者としての付加価値を高めたい方は、ぜひ受講をご検討ください。

送配電設備とは?役割や種類、構成機器や安全対策で必要なことまで解説!
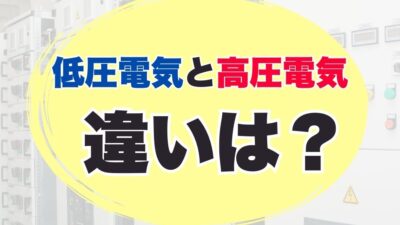
高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育電気工事士低圧電気特別教育
高圧と低圧の違いとは?電圧・料金・設備の違いをわかりやすく解説
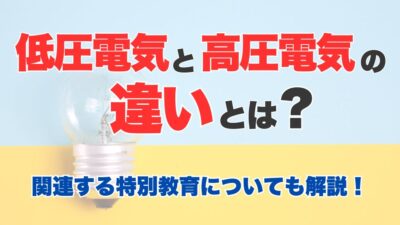
低圧電気と高圧電気の違いとは?関連する低圧電気・高圧電気の特別教育についても解説!

高圧・特別高圧電気取扱者特別教育はWeb(オンライン)受講がおすすめ
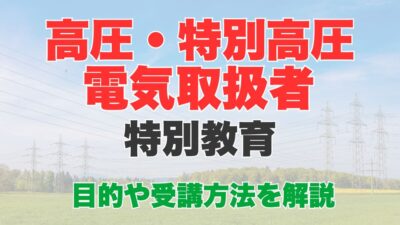
高圧・特別高圧電気取扱者特別教育とは?受講内容や受講方法を解説
