「職場の労働環境を改善したい」「キャリアアップのために資格を取りたい」とお考えの方にとって、衛生管理者は魅力的な資格のひとつではないでしょうか。しかし、「どんな勉強をすればいいの?」「仕事と両立できるかな」といった不安も多いかもしれません。
この記事では、衛生管理者試験の出題範囲や合格に必要な勉強時間の目安、そして一発合格するためのポイントまで詳しく解説します。衛生管理者試験に興味がある方、これから勉強を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
公開日:2025年9月30日 更新日:2025年12月17日
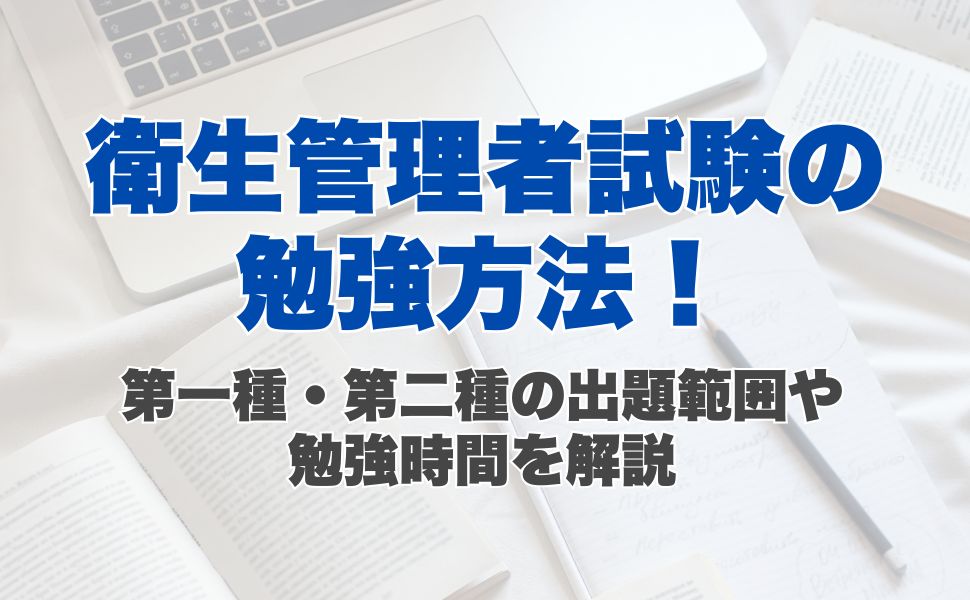
「職場の労働環境を改善したい」「キャリアアップのために資格を取りたい」とお考えの方にとって、衛生管理者は魅力的な資格のひとつではないでしょうか。しかし、「どんな勉強をすればいいの?」「仕事と両立できるかな」といった不安も多いかもしれません。
この記事では、衛生管理者試験の出題範囲や合格に必要な勉強時間の目安、そして一発合格するためのポイントまで詳しく解説します。衛生管理者試験に興味がある方、これから勉強を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
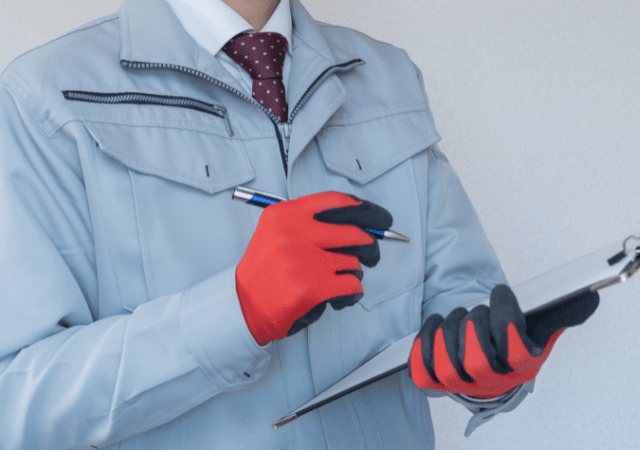
衛生管理者とは、労働者の健康障害を防止し快適な職場環境を確保するため、事業場の衛生全般を管理する国家資格を有する者です。労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者が働く事業場では、業種に応じて「衛生管理者」を必ず選任することが義務付けられています。
主な仕事内容は、事業場の巡視・作業環境の維持管理・作業の管理・健康管理・衛生教育の実施・労働災害の防止など多岐にわたります。
衛生管理者には「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」の2種類があり、それぞれが扱える業種は以下の通りです。
特定の有害業務(ボイラーや放射線を取り扱う作業など)がある事業場では、第一種衛生管理者を選任しなければなりません。自身の働く事業場の業種を確認し、どちらの資格が必要か把握しておきましょう。
衛生管理者の仕事内容については関連記事をご覧ください。
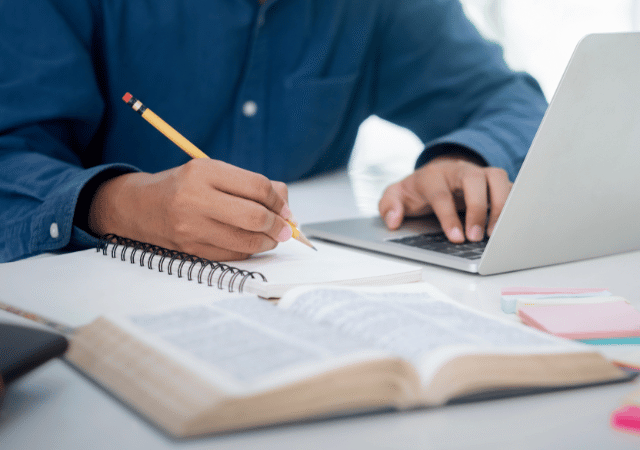
衛生管理者試験は、第一種・第二種で出題範囲が異なります。ここからは、それぞれの出題科目を詳しく見ていきましょう。
第一種衛生管理者試験は、以下の5つの科目から出題されます。
| 科目 | 出題分野 | 出題数(配点) |
|---|---|---|
| 労働生理 | 呼吸器・循環器系、消化器・泌尿器系、感覚器・神経系、内分泌系、血液、代謝、体温調節、疲労、睡眠、健康管理など | 10問(100点) |
| 労働衛生 (有害業務にかかわるもの) |
職業性疾病、有害物の種類と影響、作業環境測定、保護具、騒音、振動など | 10問(80点) |
| 労働衛生 (有害業務にかかわるもの以外のもの) |
労働者の健康障害、作業環境の整備、健康管理、救急処置、VDT作業、産業医、保健師など | 7問(70点) |
| 関係法令 (有害業務にかかわるもの) |
労働安全衛生法、労働基準法、有害業務に関する法令、特定化学物質障害予防規則など | 10問(80点) |
| 関係法令 (有害業務にかかわるもの以外のもの) |
労働安全衛生法、労働基準法、衛生管理体制、健康診断、安全衛生教育など | 7問(70点) |
第一種試験は、有害業務に関する専門的な知識も問われるため、第二種に比べて学習範囲が広くなります。出題形式は、全科目マークシート方式の五肢択一式で合計44問、400点満点です。
第二種衛生管理者試験は、第一種から有害業務に関する分野を除いた以下の3つの科目から出題されます。
| 科目 | 出題分野 | 出題数(配点) |
|---|---|---|
| 労働生理 | 第一種と同様 | 10問(100点) |
| 労働衛生 | 有害業務にかかわるもの以外のもの。健康診断、救急処置、メンタルヘルス対策など | 10問(100点) |
| 関係法令 | 有害業務にかかわるもの以外のもの。衛生管理体制、安全衛生教育、健康管理など | 10問(100点) |
第二種試験は、第一種に比べて出題範囲が狭いため、比較的短期間での合格が可能です。試験は、全科目マークシート方式の五肢択一式で合計30問、300点満点です。
合格基準は、第一種・第二種ともに「各科目の得点が40%以上であり、かつ全科目の合計得点が60%以上」と定められています。
苦手科目があっても得意科目である程度カバーできるものの、特定の科目で極端に低い点数を取ると不合格になる恐れがあります。全科目でまんべんなく得点できるよう、バランス良く学習することが大切です。

衛生管理者試験に合格するために必要な勉強時間は、個人の知識レベルや学習方法によって異なりますが、一般的な目安としては以下の通りです。
第一種は、有害業務に関する専門知識が求められるため、第二種よりも多くの学習時間が必要です。特に、理系分野の知識が少ない方は、労働生理や有害業務に関する部分に時間をかける必要があります。
第二種は、第一種に比べて出題範囲が狭いため、比較的短期間で合格を目指せます。ただし、法律や専門用語を暗記する必要があるため、毎日コツコツと学習時間を確保することが大切です。
ただし、上記の時間はあくまで目安です。効率的に学習を進めるためには、自分に合った勉強計画を立て、実行しましょう。

衛生管理者試験の合格率は、第一種・第二種ともに例年40〜50%程度で推移しています。これは、他の国家資格と比べても比較的高い水準です。
【過去5年間の合格率の推移】
| 年度 | 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
|---|---|---|
| 令和6年 | 46.3% | 49.8% |
| 令和5年 | 46.0% | 49.6% |
| 令和4年 | 45.8% | 51.4% |
| 令和3年 | 42.7% | 49.7% |
| 令和2年 | 43.8% | 52.8% |
| 平均 | 44.9% | 50.7% |
※試験実施機関から公表された全国受験者の平均合格率
上記のデータから分かる通り決して簡単な試験ではありませんが、適切な学習を行えば十分合格を狙える難易度と言えるでしょう。
合格率が高い第二種でも約半数の受験者が不合格になるため、油断は禁物です。計画的に学習を進め、確実に合格を目指しましょう。

衛生管理者試験に一発で合格するためには、ただ闇雲に勉強するのではなく、効率的な学習法を実践することが大切です。ここでは、具体的な3つのポイントをご紹介します。
衛生管理者試験では、過去に出題された問題と似たような問題が繰り返し出題される傾向があります。そのため、過去問を繰り返し解くことが合格への近道です。
最低でも過去5年分の問題を解き、出題傾向や自分の苦手分野を把握しましょう。間違えた問題は、なぜ間違えたのかをしっかり理解することが大切です。解説を読み込み、関連知識をインプットすることで、応用力が身につきます。
一度解いただけでは知識が定着しづらいため、何度も繰り返し解き、問題をスムーズに解けるようになるまで繰り返しましょう。過去問を解くことで、知識のインプットとアウトプットを同時に行えるため、効率的に学習を進められます。
合格基準は「各科目の得点が40%以上」と定められています。得意な科目で高得点を取れても、苦手な科目で40%を下回ってしまうと、不合格になってしまいます。
特に、第一種試験では「労働生理」や「関係法令」が苦手と感じる方が多いようです。苦手科目を克服するため、以下の対策を実践してみてください。
苦手科目を放置せず、克服することで、合格の可能性が大きく高まります。
独学で学習を進めるのが難しいと感じる方は、通信講座や予備校などを活用するのも有効な手段です。
自分に合った学習方法を見つけることで、モチベーションを維持しながら、合格を目指せるでしょう。
効率的に学ぶためには、質の高いプロの講座をお手軽価格で受けられる「CIC日本建設情報センターの対策講座」がおすすめです。「一発合格を目指したい!」という方は、ぜひチェックしてみてください。

この記事では、衛生管理者試験の出題範囲から合格に必要な勉強時間、そして合格率まで詳しく解説しました。
衛生管理者になるためには、国家試験に合格しなければなりません。合格率が比較的高いとはいえ、決して簡単な試験ではないため、事前の準備が合否を分けます。
独学での対策に不安がある場合は、CIC日本建設情報センターの対策講座をご活用ください。
合格点を確実に狙えるように設計された分かりやすい講座で、合格への最短ルートを目指しましょう。
