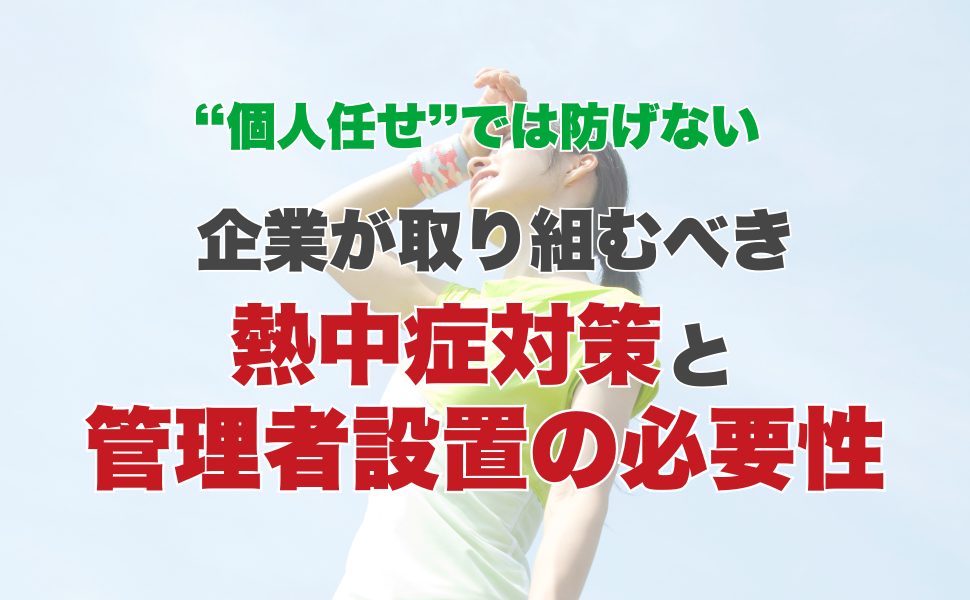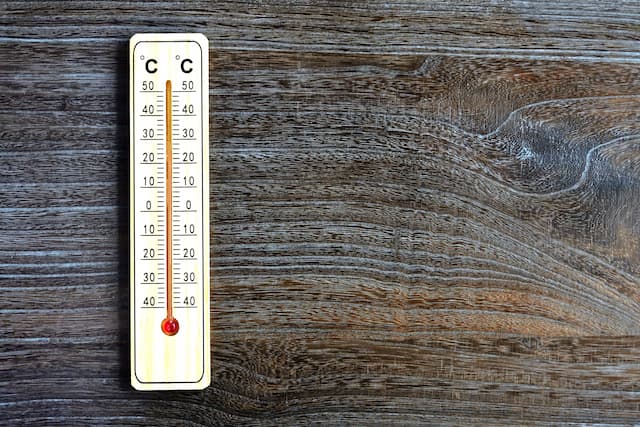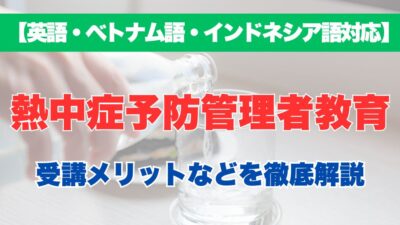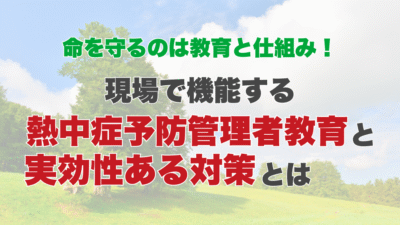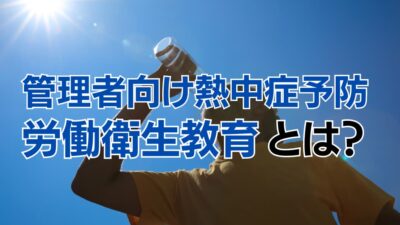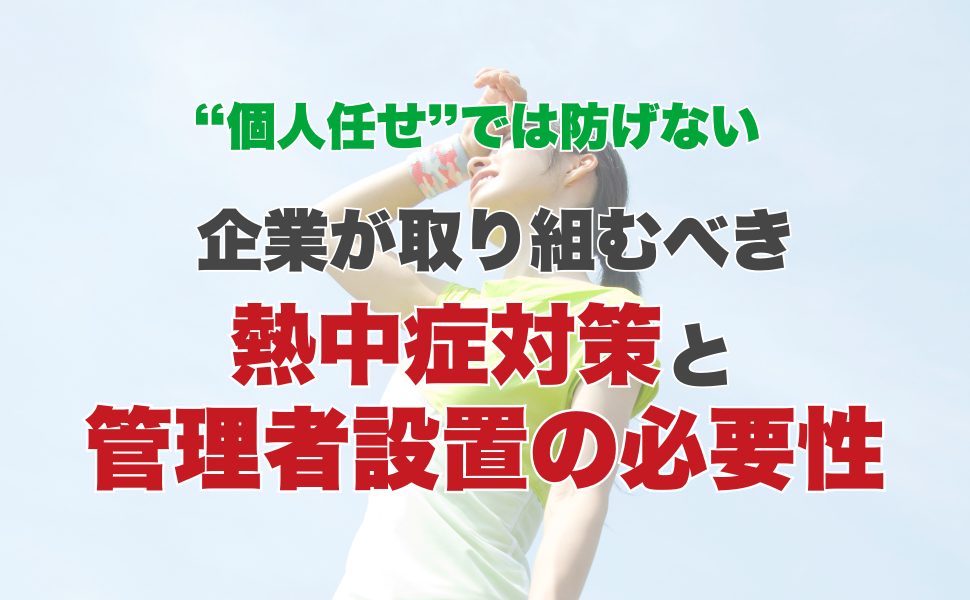
建設業を中心に、熱中症対策は企業全体が取り組むべき課題として注目を集めています。2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人、そのうち31人が亡くなっており、依然として熱中症対策は無視できない問題です。
実際、令和7年(2025年)6月1日から労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策を行うことが事業者に義務づけられました。
この記事では、企業が取り組むべき熱中症対策と管理者設置の必要性について解説します。なぜ必要なのか、管理者はどのような役割を担うのかまでご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

熱中症対策が“個人任せ”では限界を迎えている

まず、熱中症に対していえるのが「個人任せでは限界を迎えている」という点です。厚生労働省の統計によると、2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人、そのうち31人が亡くなっています。中でも建設業が割合として最も多く、次いで製造業や運送業が続きます。
また、注目すべきは、経験豊富な40歳以上の労働者が多くの割合を占めていることです。「慣れているから自分は大丈夫」と過信していると、重大事故につながりかねません。
企業にとって熱中症対策は、労働契約法第5条に定められた安全配慮義務の一環です。年々熱中症による死傷者の人数が増えていることから、「水分をこまめに取りましょう」という掛け声だけでは不十分といえます。組織として、確かな根拠にもとづいた熱中症対策を考えることが大切です。
なぜ「熱中症予防管理者」が必要なのか?
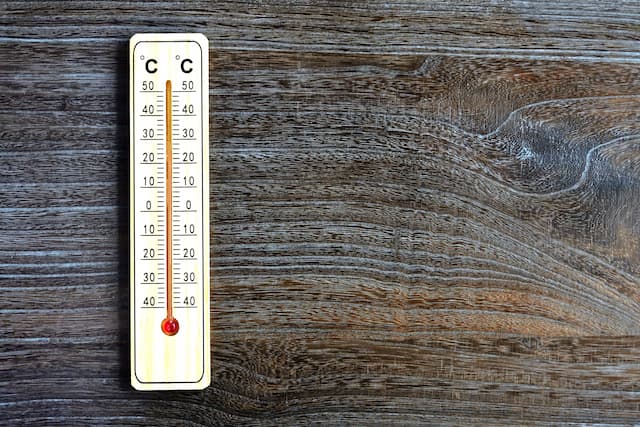
先ほど、熱中症対策が個人だけの対策で限界を迎えている点について解説しました。ここからは、個人での対策が限界を迎えている点を踏まえて、なぜ熱中症予防管理者が必要なのか解説していきます。
- 気候変動によるリスクの増加
- 熱中症による労働災害の深刻化
上記2点を深掘りして解説しますので、ぜひ参考にしてください。
気候変動によるリスクの増加
東京都心の猛暑日(35℃以上)は、2024年には19日を記録、真夏日(30℃以上)は61日を記録しています。熱中症のリスクは例年よりも高まりつつあるというわけです。
特に建設現場では、アスファルトやコンクリートから放射された熱により、気温以上に過酷な環境が考えられます。夏の晴れた日で気温30℃の場合、体感温度上では40℃を超える場合もあります。このことからも、暑い日はただ休憩時間を多くとればいいというわけではないといえるでしょう。
熱中症予防管理者は、WBGT値(暑さ指数)を活用した科学的な判断を行います。例えば、WBGT値が28℃を超えた場合は軽い作業のみを行うなど、明確な基準に基づいた判断が求められます。
熱中症による労働災害の深刻化
熱中症の注意すべき点は、その進行の速さです。人の体は高温に弱く、熱中症が発症してからの対応が遅れると、意識を失ったり後遺症が残ったりする可能性があります。熱中症が発症した当日に亡くなるケースも珍しくありません。
特に以下のケースに該当すると熱中症のリスクが高まります。
- 環境:気温・湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、急に暑くなった、熱波が襲来したなど
- 身体:糖尿病や精神疾患などの持病がある、低栄養状態の方、脱水状態にある、前日のお酒や睡眠不足による体調不良など
- 行動:激しい運動や慣れない動き、長時間の屋外作業、水分補給ができない状況など
熱中症予防管理者は、こうしたリスクを把握し、必要に応じて作業内容を調節するなど、柔軟な対応を行います。特に建設業は屋外作業を取り扱うことが多いため、熱中症リスクに対しての対策が重要です。

義務化の背景と法令

続いて、熱中症対策が事業者に義務化された背景や該当する法令について解説します。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
義務化の対象業種・時期
熱中症に対する措置の中でも、「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係労働者への周知」に関しては、義務化されました。対応を怠った場合、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業者に適応される恐れがあります。
対象となる作業環境は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業」です。また、該当しない作業であっても作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は、熱中症のリスクが高まるとして熱中症対策が推奨されています。
また、同一の作業現場にて、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者(労働者を管理監督する者など)についても、同様です。
該当法令
職場における熱中症対策の強化について、労働安全衛生規則が改正されており、令和7年(2025年)6月1日から施行されています。法令で義務化されるポイントは、以下の2点です。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知すること
- 熱中症が発症する恐れがある作業(※)を行う際は、「作業からの離脱」「身体の冷却」「必要に応じて医療機関の診察・処置を受けてもらう」「事業場にて緊急連絡網を整備する」など、熱中症悪化を防止するために必要な内容・実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知すること
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
熱中症予防管理者の役割とは?

熱中症予防管理者の役割は、主に以下の3つです。
- 現場の管理
- リスク評価
- 対策の計画と実施
それぞれの内容について詳しく解説します。
現場の管理
熱中症予防管理者の役割の1つ目が現場の管理です。現場において、以下のような役割を担います。
- 各作業現場における熱中症リスクの把握と指導体制の整備
- 作業環境(温湿度、換気状況、直射日光の有無など)の定期チェック
- 体調不良者の早期発見と迅速な対応の指揮(初期対応、救急搬送の判断)
- 現場責任者・作業員との情報共有、報告を受ける体制
現場における熱中症リスクの把握から体調不良者の早期発見、情報共有から体制の整備などを整えるのが主な仕事です。
熱中症の症状が現れている労働者を発見した場合、直ちに作業を中断させて涼しい場所で休憩を取らせます。吐き気などがなく、意識がはっきりしてる場合は、スポーツドリンクなどを飲ませ、首筋や脇の下を冷やすなどの処置を担います。
リスク評価
熱中症予防管理者の役割の2つ目がリスク評価です。以下のような役割を担います。
- 気温、湿度、WBGT値などの定期的なモニタリング
- 作業内容や従業員の年齢・健康状態を踏まえた個別リスク評価
- 高リスク時間帯や作業の特定と、その都度の対応(作業中止・休憩の強化など)
- 災害事例(労働災害)や過去の熱中症発症履歴の分析と共有
リスク評価は、データの蓄積を中心に行います。気温や湿度、WBGT値をモニタリングしたり、過去の災害事例や熱中症発症履歴から分析・共有したりします。
また、作業内容や従業員のデータをもとに個別リスク評価するのも特徴です。データに基づき、現場にあった熱中症対策を行います。
対策の計画と実施
熱中症予防管理者の役割の3つ目が対策の計画と実施です。以下のような役割を担います。
- 熱中症対策の年間計画の立案(設備投資など)
- 教育・研修スケジュールの企画と講師の調整
- ポスター、社内報、朝礼での注意喚起体制
- 対策の効果検証とフィードバックによる改善提案
現場での役割や現場環境のリスク評価以外にも、熱中症対策のための計画や教育・研修の企画、注意喚起などを担うのが特徴です。実施した対策にて効果を検証し、より良くしていくための改善も担います。

社内の体制づくり・意識改革

熱中症対策は、社内全体で体制を整え、労働者一人ひとりが意識しなければなりません。そのため、熱中症予防管理者を選任し、管理者を中心に意識改革していくことが大切です。
例えば、体制づくりとしては、熱中症予防管理者の選任以外にも以下の点を意識してみましょう。
- 作業環境の見直しや
- 休憩・水分補給の見直し
- 作業時間の見直し(真昼間はなるべく避ける)
- 日々の健康管理など
熱中症の発症リスクが高まる条件を把握し、予防管理者を中心に体制を見直すことで発症リスクを抑えられます。また、意識改革としては、以下の点に注意してみてください。
- 無理をしない・させない文化
- ポスターや朝礼などで注意喚起
意識改革として、労働者が無理をしない・事業者側が無理をさせないことを徹底しましょう。いざという時でも相談しやすい環境を整え、日頃から朝礼やポスターなどで注意喚起することが大切です。
CIC日本建設情報センターの熱中症予防管理者

CIC日本建設情報センターでは、熱中症予防管理者のWeb(オンライン)講座を開講しています。実際の役割・作業に基づいて、必要なポイントをコンパクトにまとめたテキストと、専門講師によるわかりやすい動画講義から、短期間で効率よく知識や技術を身につけることが可能です。
CIC日本建設情報センターのWeb講座は、以下の手順で受講できます。
- CIC日本建設情報センターのWeb講座に申し込む
- 入金確認後、メールでログイン情報が送付される
- 受講(視聴)が開始する
- 受講完了後、自分が選択した修了証を受け取る
また、「受講者が実際に画面の前で学んでいるのか分からない」とWeb講座の受講に不安を感じる事業者の方もいらっしゃるかもしれません。CICの講座では顔認証システムを採用しており、受講者が画面の前にいない場合は学習が進まない仕組みです。このため、講座を修了した時点で「受講者本人がしっかりと受講を終えた」ことを証明できます。
受講方法でお悩みの場合は、ぜひCIC日本建設情報センターの講座をご検討ください。
まとめ

この記事では、企業が取り組むべき熱中症対策と管理者設置の必要性について解説しました。
熱中症は、建設業だけでなく企業全体として無視できない問題です。2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人、そのうち31人が亡くなっており、中でも建設業は最も多い割合を占めています。
熱中症予防管理者は、現場の管理・リスク評価・対策の結果と実施の3つの役割を担います。熱中症の発症を防ぐだけでなく、もしもの際の適切な対応はもちろん、普段からの予防体制の整備や意識改革にも取り組みます。
CIC日本建設情報センターでは、熱中症予防管理者のWeb講座を用意しております。命にかかわる重要な内容ですので、ぜひ受講をご検討ください。