近年の法改正により、建築物の解体・改修工事ではアスベストの事前調査が原則として全ての工事で義務化され、含有が不明な建材に対する取り扱いの重要性が飛躍的に高まりました。
特に含有の有無を明らかにする「分析」は、健康被害と経営リスクを回避する上で決定的な意味を持ちます。
今回は、アスベスト業務に携わる方々に向けた、分析の実践的ガイドです。法規制の要点から、正確なサンプリング、分析手法の選択、信頼できる業者選びまで、確実な一歩を踏み出すための知識をお伝えします。
公開日:2025年11月20日 更新日:2026年2月22日
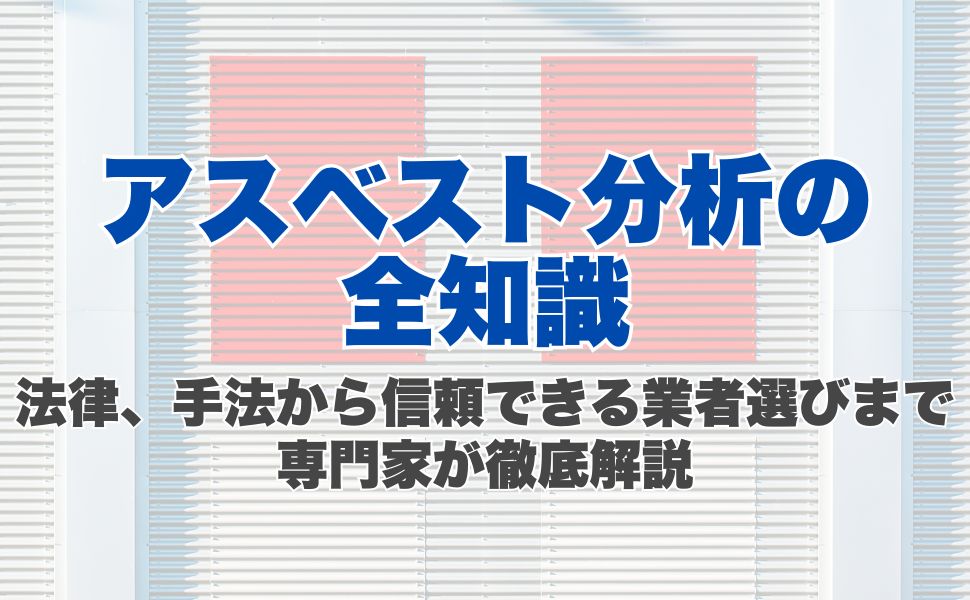
近年の法改正により、建築物の解体・改修工事ではアスベストの事前調査が原則として全ての工事で義務化され、含有が不明な建材に対する取り扱いの重要性が飛躍的に高まりました。
特に含有の有無を明らかにする「分析」は、健康被害と経営リスクを回避する上で決定的な意味を持ちます。
今回は、アスベスト業務に携わる方々に向けた、分析の実践的ガイドです。法規制の要点から、正確なサンプリング、分析手法の選択、信頼できる業者選びまで、確実な一歩を踏み出すための知識をお伝えします。

法改正後の現在、アスベスト分析が持つ意義は、単に含有の有無を明らかにすることに留まりません。それは、健康、経営、環境という3つの側面から、事業者が果たすべき社会的責任の根幹をなすものです。
正確な分析は、数十年後に発症する深刻な健康被害から作業員や公衆を未然に守るための、最も基本的な安全対策です。
不適切な調査や分析は、罰則や事業停止命令に直結します。また、将来健康被害による損害賠償請求に発展する可能性もあります。
分析によって非含有が証明されれば、過剰な対策や高コストな廃棄物としての処理が不要になり、更に不必要な廃棄物を減らすことは、環境負荷を低減します。
分析対象となるアスベスト(石綿)は、法律で定められた6種類が存在し、全てが国際がん研究機関(IARC)によって発がん性が最も高い「グループ1」に分類されています。極めて細かい繊維を吸い込むと、数十年という長い潜伏期間を経て、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こすことが明らかになっており、法律は厳格な管理を求めているのです。
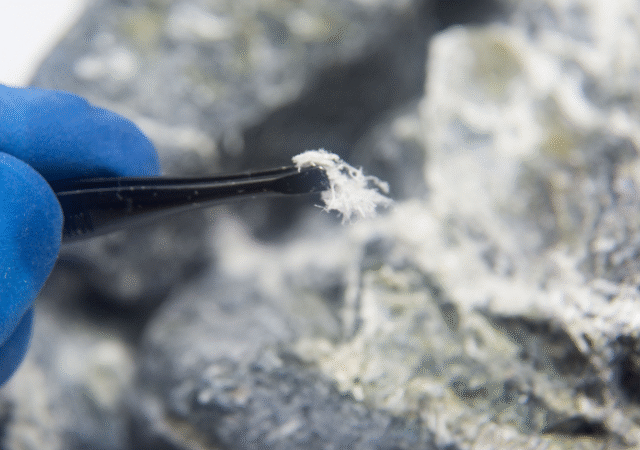
アスベスト分析の精度は、現場での試料採取の質が大きく関わってきます。不適切なサンプリングは、後の全プロセスを台無しにするため、細心の注意が必要です。
採取はアスベストを飛散させる可能性のある行為です。採取箇所の養生、霧吹きなどによる「湿潤化」、国家検定合格の防じんマスクや防護服の着用は必須です。
最も飛散性が高いため、特に慎重な作業が求められます。また、劣化状況や採取場所によっては、採取時に周囲が広範囲にわたって剥がれ落ちる可能性があります。採取場所の選定は慎重に行ってください。採取の際は、表面だけではなく、躯体に届くまで深く採取します。
レベル2建材は、採取時に粉塵状になった試料が非常に飛散しやすいという特徴があります。リネンやライナー等の梱包材を崩す場合は、粉塵が零れ落ちたり舞う可能性を考え、十分養生を行ってください。
カッターナイフ等で試料を切り出します。そのままでは飛散の可能性があまりないレベル3建材ですが、この作業ではかなりの粉塵が発生します。建材の特性に合わせて、飛散防止を徹底してください。
基本的には1箇所から採取を行います。大きさは最小1cm角とされていますが、採取後や輸送中に層構造が崩れ、分析が困難になることがあります。これを防ぐため、採取の大きさを確保する等、層構造を維持する工夫が強く推奨されます。
含有の有無を判断するのは0.1%程度です。これは、繊維が数本混じった程度でも、不含有が含有になってしまう事を示しています。このくらいはいいだろう、という考えは捨て、試料ごとに手袋やカッターの刃を交換(または念入りに清掃)し、採取した試料は個別に二重梱包するなど、汚染防止策を徹底しましょう。
採取した試料には、試料の取り違えが起きないよう、日付、採取地点、試料名等を記入します。
採取地点は石綿が飛散しやすい状況になっているので、飛散防止対策を施した補修を行います。また、周辺には採取時の粉塵等が散っている事が多いため、再発塵に注意しながら清掃を行います。
次に、定性分析と定量分析の違いについて解説します。
「アスベストが含まれているか、いないか」を0.1%を基準に判定します。現在の事前調査で求められるのはこの分析です。
「どのくらいの割合で含まれているか」を明らかにします。かつては含有率の規制基準が5%や1%だった時代に必須でしたが、現在では定性分析で「有り」と判定されれば規制対象となるため、実施されるケースは限定的です。
現在最も主流な方法は、定性分析であるJIS A 1481-1です。その他、JIS A 1481-2~5まで、4種類の規格が存在します。
プロセス:実体顕微鏡と偏光顕微鏡を用いて繊維の形態や光学的特性を観察し、アスベストの種類を特定します。
利点:国際規格(ISO 22262-1)に準拠し、仕上塗材などの層別分析が可能です。
留意点:分析結果が分析者の経験と技量に大きく依存します。
JIS A 1481-2(X線回折・顕微鏡併用法): X線を用いた機器分析が主軸です。試料を粉砕するため層別分析ができません。
JIS A 1481-3, -5(X線回折法による定量分析): X線を用いた機器分析です。客観的な数値データが得られますが、層別分析はできません。
JIS A 1481-4(顕微鏡法による定量分析): 顕微鏡を用いた分析です。手間と時間がかかりますが、天然鉱物中の不純物アスベストも定量可能です。

「石綿障害予防規則」および「大気汚染防止法」に基づき、建築物等の解体・改修工事では、規模の大小を問わず事前調査が義務付けられています。そして、設計図書や目視調査でアスベストの有無が明確にならなかった場合、分析による調査が必須となります。
分析でアスベスト含有が確認された場合、発じん性(飛散のしやすさ)に応じてレベル1〜3に分類し、リスク評価を行います。この評価に基づき、建物の将来計画に沿った対策が決まります。
リスク評価の結果、直ちに飛散する危険性が低いと判断されても、それで終わりではありません。建材の劣化状況を定期的に点検し、損傷や劣化が見られた場合には封じ込めや囲い込みといった対策を講じる必要があります。
レベル1〜3の分類に応じた、法律で定められた厳格な飛散防止措置を講じて除去作業を行わなければなりません。
不適切な調査やリスク評価は、過去に多くの飛散事故や健康被害を引き起こしており、正確な分析に基づく適切なリスク評価が極めて重要です。

分析報告書は、法的な効力を持つ公的文書であり、プロジェクトの安全とコンプライアンスを証明する証拠です。さらに、建物を維持する場合、この報告書は建物の「石綿履歴」として極めて重要な役割を果たします。将来の所有者や工事業者がこの記録を参照することで、無駄な再調査や不適切な工事を防ぎ、長期的な安全管理に繋がります。
記録の保存期間は法律で定められており、「分析結果報告書」を含む「事前調査の結果の記録」は工事終了後3年間の保存が義務付けられています。
報告書では、石綿の有無だけでなく、法に則した有資格者のトレーサビリティがとれているかが非常に重要です。

業者の選定は、プロジェクトの成否、作業員の安全、そして企業の法的責任を左右する、極めて重要なリスクマネジメントの一環です。
厚生労働大臣が定める高い技能を持つ者(例:日本作業環境測定協会のAランク認定技術者など)の在籍数を確認します。
分析者の経験は正確な分析に直結します。分析実績は、経験を裏付けます。
官公庁や大手ゼネコンからの受注実績は、高いコンプライアンスが求められる案件をクリアしてきた信頼の証明です。
人為的ミスを最小限に抑えるため、別の経験豊富な分析者が再確認するプロセスが確立されているかを確認します。
X線回折装置(XRD)を保有し、定量分析にも対応できる業者は、より高い精度を担保できる総合的な技術力があることの指標となり得ます。
試験所の能力に関する国際規格の認定は、非常に高い信頼性の証です。

法規制の強化により、アスベスト分析は建築・解体プロジェクトにおける標準的かつ中心的なプロセスとなりました。法規制の正確な理解、現場での細心の注意を払ったサンプリング、実験室での精密な分析、そして結果の適切な解釈と、どの段階においても高度な専門性が求められます。
確実に実行できる有資格の専門業者を選定することは、プロジェクトの安全、予算、そして法的な正当性を担保する上で非常に重要な要素となるでしょう。
「石綿の窓口」では、一つの試料の分析から大規模な建築物の全体調査の計画まで、あらゆる疑問や課題に対して、信頼性の高いソリューションを提供します。
相談及び見積もりは無料です。まずは知見を得る第一歩として、お気軽にご相談ください。
「石綿の窓口」について詳しくはこちら
お問い合わせ電話:03-5843-7103
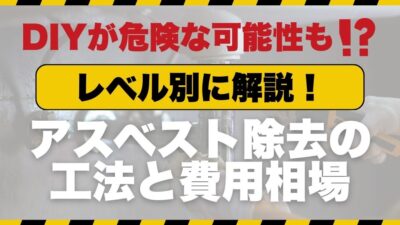
アスベスト除去の工法と費用相場をレベル別に解説!DIYが危険な可能性も!?
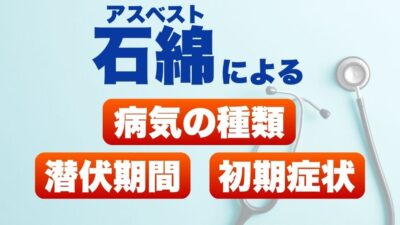
アスベスト(石綿)による主な病気の種類と潜伏期間、初期症状を解説
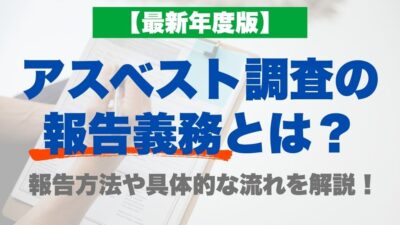
【2026年最新】アスベスト調査の報告義務とは?報告方法や具体的な流れを解説!
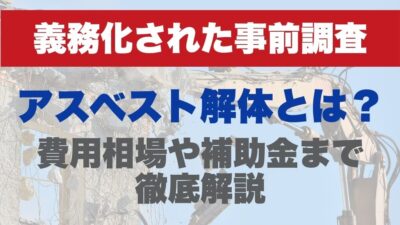
アスベスト解体とは?義務化された事前調査や費用相場、補助金まで徹底解説
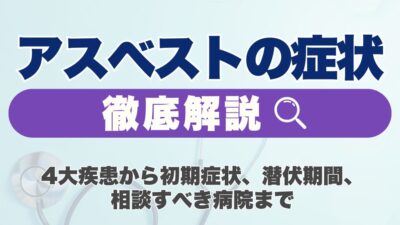
アスベストの症状を徹底解説!4大疾患から初期症状、潜伏期間、相談すべき病院まで
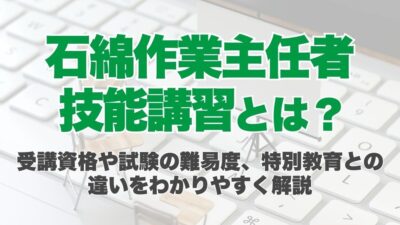
石綿関連石綿特別教育石綿技能講習建築物石綿含有建材調査者講習
石綿作業主任者技能講習とは?受講資格や試験の難易度、特別教育との違いをわかりやすく解説

石綿関連石綿特別教育石綿技能講習建築物石綿含有建材調査者講習
【2026年】アスベスト関連資格一覧!資格取得の難易度や費用を法改正と合わせて解説

【2026年最新】アスベスト事前調査とは?対象となる工事・費用相場・義務化された報告ルールを徹底解説
