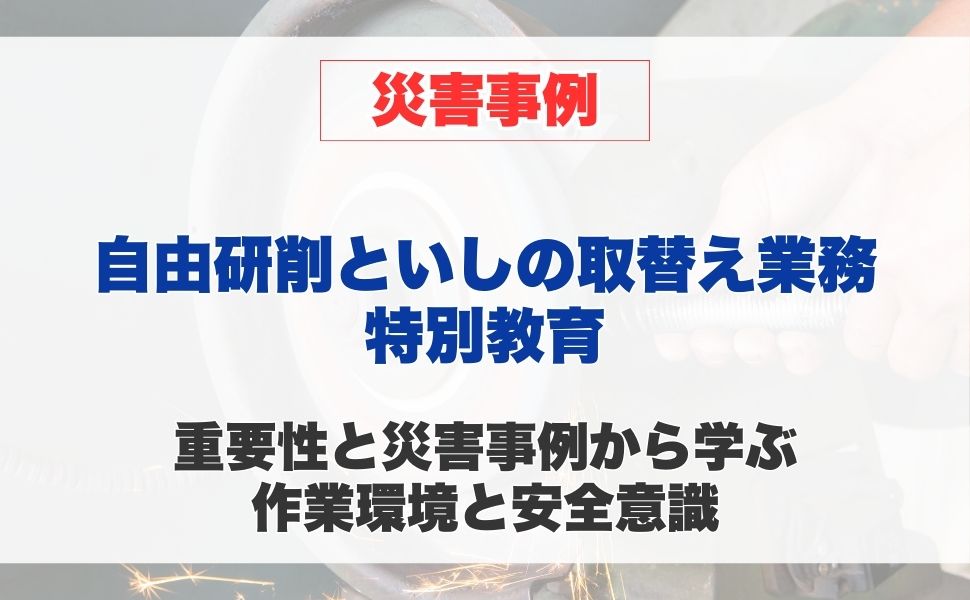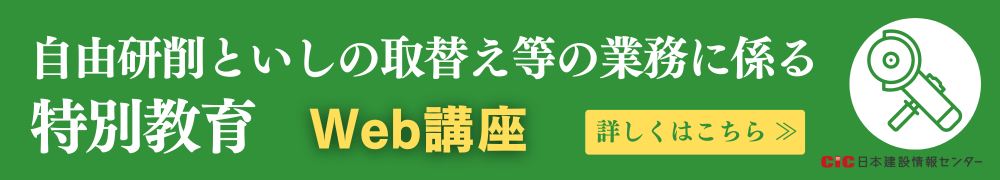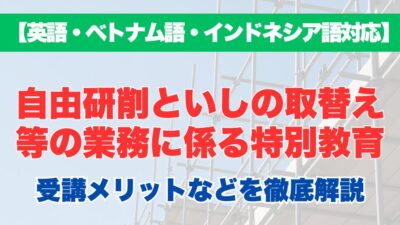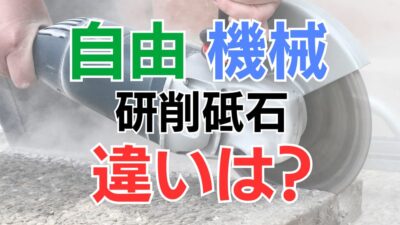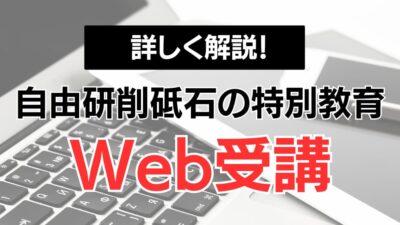自由研削といし(グラインダー砥石)は、金属加工や建設現場で欠かせない工具ですが、高速回転する危険な機械です。砥石の破裂による死亡事故や重傷事故が生じており、労働災害の中でも特に危険を伴う作業のひとつです。
労働安全衛生法では、自由研削といしの取替えや試運転の業務を担う場合、事業者は労働者に対して特別教育を実施することが義務付けられています。ただし、なぜこの特別教育が必要なのか、その重要性を十分に理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育の重要性について詳しく解説します。実際に発生した災害事例から原因を分析し、労働災害を防止するために必要な対策もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。