金属などの材料を高精度に仕上げるための「研削砥石(けんさくといし)」。建設業や金型・工具製造業など、様々な業界で重宝されている工具ですが、具体的にどんな特徴や種類があるのかご存じではない方も多いでしょう。
この記事では、研削砥石とは何か、研削砥石の性能を決める5大要素、研削砥石の種類について詳しく解説します。さらに、自由研削と機械研削の違い、研削砥石の取替え等業務特別教育の内容もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
公開日:2024年6月18日 更新日:2025年10月24日
金属などの材料を高精度に仕上げるための「研削砥石(けんさくといし)」。建設業や金型・工具製造業など、様々な業界で重宝されている工具ですが、具体的にどんな特徴や種類があるのかご存じではない方も多いでしょう。
この記事では、研削砥石とは何か、研削砥石の性能を決める5大要素、研削砥石の種類について詳しく解説します。さらに、自由研削と機械研削の違い、研削砥石の取替え等業務特別教育の内容もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

研削砥石(けんさくといし)とは、金属や石材などの素材を削ったり形を整えたりするための工具で、研削盤やグラインダーに取り付けて使用されます。
砥石は、研磨材(砥粒)や結合材などで作られており、対象物に当てると高速回転することで無数の鋭い粒が表面を研磨し、美しい仕上げと正確な精度の寸法に仕上げることが可能です。切れ刃の役割を持つ砥粒(とりゅう)は、使用するうちに摩耗していきますが、その都度落ちて新しい砥粒を出してくるので、長時間切れ味を維持することができます。これは「自生(発刃)作用」と呼ばれており、研削砥石の特徴の1つといえます。
研削砥石は、用途に応じて形状や粒度が異なり、粗削りから精密加工まで幅広く対応可能です。製造業や建設現場などで広く利用されており、作業効率の向上や精度の高い仕上げに欠かすことができない工具です。

研削砥石の性能は、下記5つの要素によって決められます。
上記5つの要素について見ていきましょう。
砥粒(とりゅう)とは、対象となる工作物を削り磨いていく刃の働きをするものです。
研削・研磨工具に使用される砥粒は、アルミナ系や炭化ケイ素系の「一般砥粒」と、ダイヤモンド系や立方晶窒化ホウ素(CBN)系の「超砥粒」に分類されます。種類に応じて加工対象は異なり、アルミナ系であれば鉄鋼材料、炭化ケイ素系であれば非鉄金属などに使用します。
粒度とは、砥粒のサイズのことです。粒度の数値が大きくなるほど砥粒は小さくなります。
粒度は、研削面の仕上精度に基づいて選定する必要があり、削り量を多くしたいときは粒度の小さいもの、表面を滑らかにしたいときは粒度の大きいものを選びましょう。
結合度とは、結合剤が砥粒を保持している度合いのことであり、「硬度」と呼ばれることもあります。
度合いはアルファベットで表され、Zに向かうほど結合度は高くなります。基本的に、硬い加工物には結合度の低い砥石、柔らかいものには結合度の高い砥石を選択するのが良いでしょう。
組織とは、砥石の容積に対して砥粒が占める割合のことであり、「砥粒率」とも呼ばれています。
砥石に占める砥粒の割合が多いと、組織は高くなり密な構造になります。一般的に、対象物の材質が硬質脆質の場合は組織が密な砥石を使用し、軟質粘質の場合は組織が粗いものを選択してみてください。
結合材とは、砥粒同士を結合・保持するものであり、通常「ボンド」と呼ばれています。
ボンドは、メタル・ビトリファイド・レジンボンド・電着などの種類があり、それぞれ特徴が異なります。「メタルは砥粒の保持力が強く寿命が長い」「ビトリファイドは精密な研削加工に向いている」などのポイントを押さえておくことで、適切な結合剤を選ぶことが可能です。

研削加工に必要な研削砥石には、自由研削砥石と機械研削砥石の2種類にわかれています。それぞれの違いは取り扱う機械の種類です。
自由研削で取り扱う機械と機械研削で取り扱う機械についてそれぞれ挙げてみました。
自由研削砥石は携帯グラインダーや卓上用電気グラインダーなどに取り付けます。溶接で盛り上がった部分を削ったり(ビート取り)、部品の不要な出っ張った部分を削り取ったり(バリ取り)というような作業で使用します。
自由研削はグラインダーや高速カッターなど、手に持って作業するのが主です。
自由研削砥石の取替え等業務で特別教育が必要な主な機械です。
機械研削砥石は、工業機械に取り付けて使用します。自由研削砥石とは違って手に持って作業することが難しい加工物用です。
自由研削砥石の取替え等業務で特別教育が必要な主な機械です。

金属加工で必要な研削砥石は、自由研削砥石と機械研削砥石の2種類があります。自由研削と機械研削の違いは取り扱う機械です。
それぞれ研削砥石の取り扱いを誤ると重大な事故を招く危険性があるため、作業員には高い知識が求められます。
研削砥石の取替え等業務特別教育も自由研削と機械研削にわかれており、それぞれ内容にも違いがあります。
従事する業務内容を確認し、受講する特別教育を選ぶ必要があります。
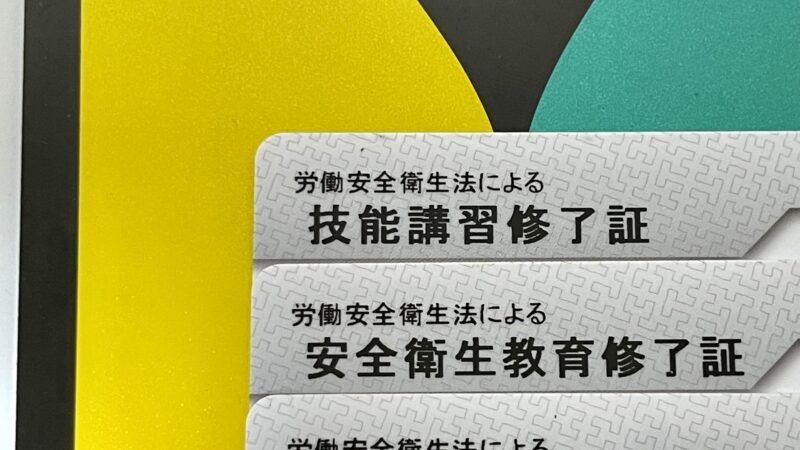
研削作業とは、研削砥石を高速回転させて行います。手に持って作業するグラインダーにしても工業用の研削盤にしても機械の主軸に砥石を取り付け回転させて切断します。
砥石がダイヤモンドホイールのように金属の台にくっついているものとは違って、安全基準が異なります。
研削砥石の取り扱いを誤れば、砥石が破損し重大な事故を招いてしまうこともあります。作業員に高い知識がなければ非常に危険な作業となるのです。
労働安全衛生法(労働安全衛生規則)では、研削砥石取替え業務・試運転業務は危険の伴う業務と定められており、特別教育の受講を義務づけています。
特別教育の受講をさせずに作業員を従事させた場合には、事業者にペナルティが課せられることになっています。

自由研削砥石の取替え等業務特別教育を受講するにあたり、内容の解説をいたします。
自由研削砥石は、グラインダーや電気カッターなどの手で持って作業を行う電動工具が対象となっています。該当する作業員は自由研削砥石の取替え等業務特別教育を受講しなければいけません。
受講は学科・実技を1日にまとめて行うことが多く、併せて6時間以上かかります。長丁場にはなりますが1日で業務に従事できるようになりますので早めに取得することをおすすめします。
自由研削砥石の取替え等業務特別教育の講座は、学科と実技を受講します。
学科は基礎知識と取付け・試運転の方法についての知識と関係法令を身につけるカリキュラムとなっています。
| 教育科目 | 受講内容 | 受講時間 |
|---|---|---|
| 自由研削用研削盤、自由研削砥石、取付具等に関する知識 |
|
2時間 |
| 自由研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識 |
|
1時間 |
| 関係法令 |
|
1時間 |
| 実技教育 |
|
2時間 |
| 合計 | 4時間 |
参照元:e-Gov
自由研削用砥石の取替え等業務特別教育は、全国の講習機関で開催されています。どこで受講しても構いません。
費用としては約1万円〜1万4,000円程度が相場のようです。
学科のテキストは受講料に含まれていることが多く、主催団体によっては会員と非会員で受講料が違う場合があります。
CIC日本建設情報センターは、自由研削砥石の取替え等業務特別教育のWeb講座を実施しています。
顔認証システムを搭載したWeb講座で、いつでもどこでも受講することができます。またWeb講座に起こりやすいミスや不具合などの対応もされており安心です。
| 内容 | 受講時間 |
|---|---|
| 自由研削用研削盤、自由研削用砥石、取付け具等に関する知識 | 2時間4分 |
| 自由研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 1時間5分 |
| 関係法令 | 1時間8分 |
| 合計 | 1時間17分 |
実技については、各事業者で2時間以上実施することが必要です。
CIC日本建設情報センターでは実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画+PDF資料」を送付しています。また学科カリキュラムのみeラーニングにて受講することも可能です。益々手軽に受講できるのが嬉しい点です。
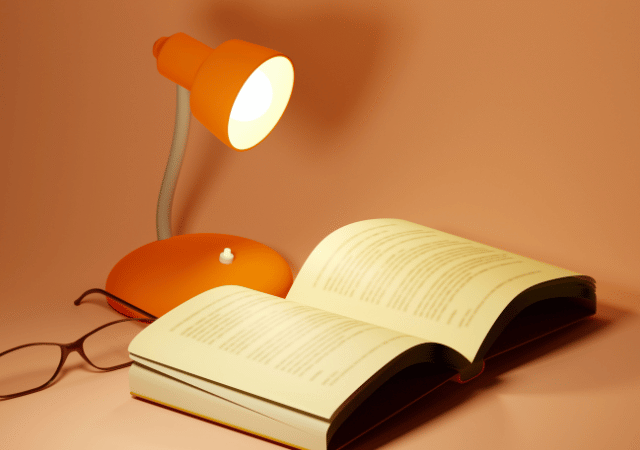
機械研削砥石の取替え等業務特別教育を受講するにあたり、内容の解説をいたします。
機械研削砥石は、平面研削盤や円筒研削盤など工作機械が対象となっています。特別教育の対象者については自由研削砥石の取替え等業務特別教育と大きな違いはありません。
ただ取り扱う機械によって内容に違いがあり、受講時間も違うため注意が必要です。
機械研削砥石の取替え等業務特別教育の学科と実技の講座のカリキュラムは以下の通りです。
機械研削砥石の特別教育講座は、機械研削用の砥石盤や砥石、取付け具などを中心に学びます。
| 教育科目 | 受講内容 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 機械研削用研削盤、機械研削用砥石、取付け具などに関する知識 |
|
4時間 |
| 機械研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識 |
|
2時間 |
| 関係法令 |
|
1時間 |
| 実技教育 |
|
3時間 |
| 合計 | 10時間 |
参照元:e-Gov
機械研削砥石の取替え等業務特別教育の受講は4つの方法があります。
機械研削砥石の取替え等業務特別教育は、全国の講習機関で開催されています。どこで受講しても構いません。
受講料
約1万円〜2万円程度
学科のテキストは受講料に含まれていることが多いです。
学科のみの講習を行っている講習機関で受講する場合は、各事業所において選任した講師と共に、実際の器具を用いて2時間以上の実技を行いましょう。

研削砥石には自由研削砥石と機械研削砥石があり、それぞれ取扱う機械によって異なる特徴があります。その違いに伴って受講しなければいけない特別教育にも違いがあります。
どの業務に従事するかによって学ぶ内容に違いがありますので、しっかりと確認をした上で受講するようにしましょう。
研削砥石に関する業務は危険を伴うため必ず特別教育を受講する必要があり、もし怠った場合には事業者にペナルティが与えられます。
従業員の安全確保のために、また自分の身を最低限守るために必ず研削砥石の取替え等業務特別教育を受講し、知識を取得しておくことが大切です。
