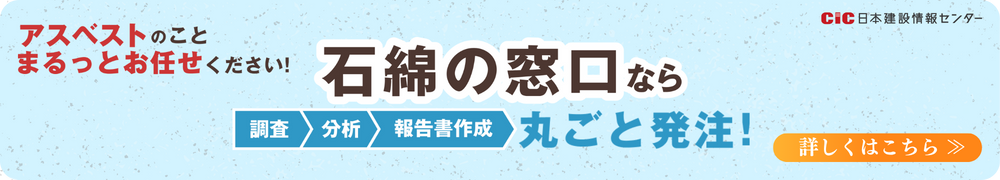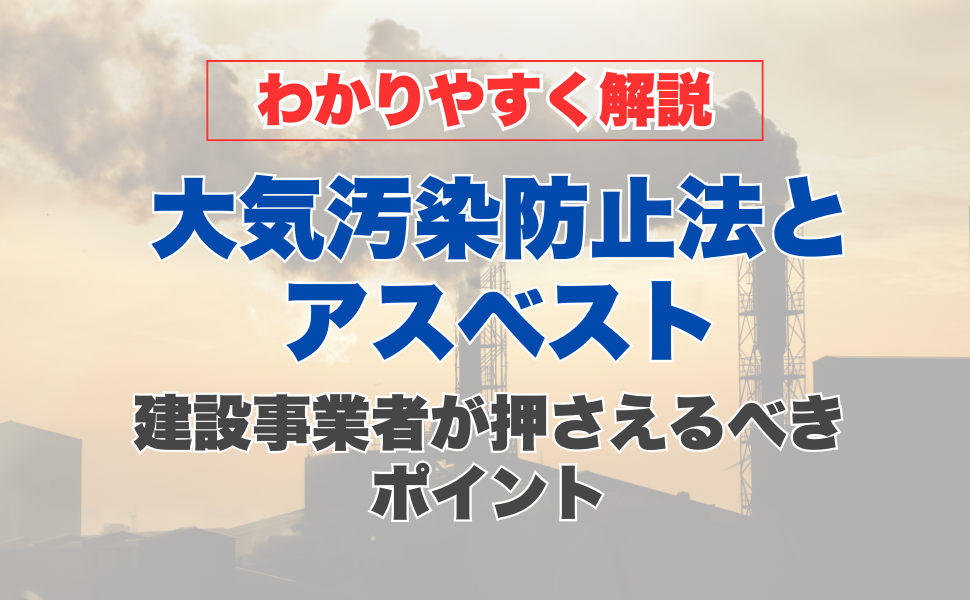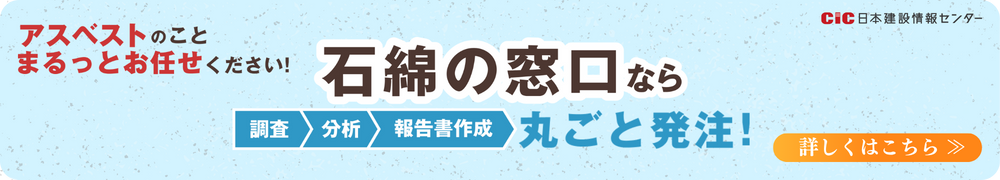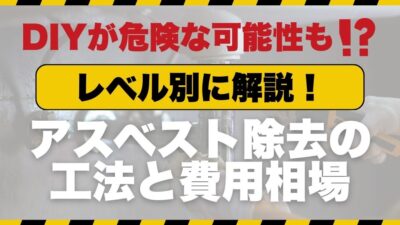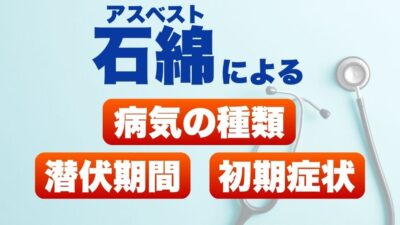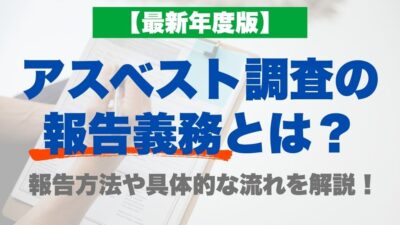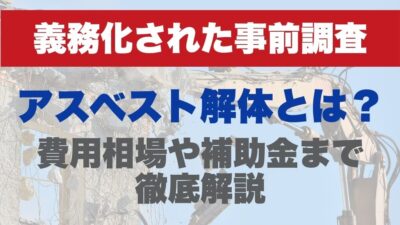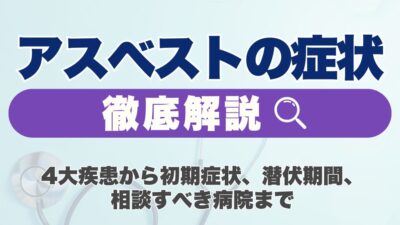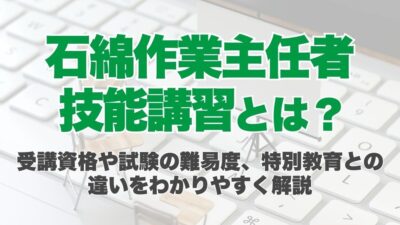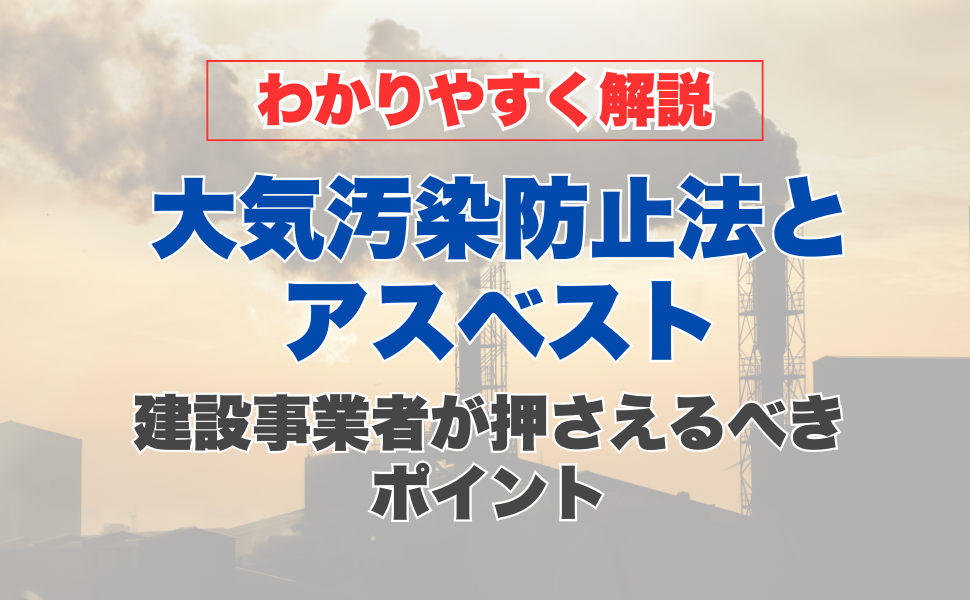
「うちの工事、アスベスト調査って必要なの?」「大気汚染防止法って聞いたことはあるけど、実際何をすればいいの?」
建設・解体工事を手がける事業者の多くが、こんな疑問をお持ちではないでしょうか。
実際、アスベスト規制は年々厳しくなっており、知らないうちに法令違反をしてしまうリスクも高まっています。
行政のホームページを見ても専門用語ばかりで分かりにくく、「結局、自分の工事は対象なの?」「具体的にどんな手続きが必要なの?」といった実務的な疑問になかなか答えが見つからないのが現実です。
この記事では、そんな建設事業者の皆さんに向けて、大気汚染防止法とアスベスト規制について、現場で本当に役立つ情報を分かりやすくお伝えします。
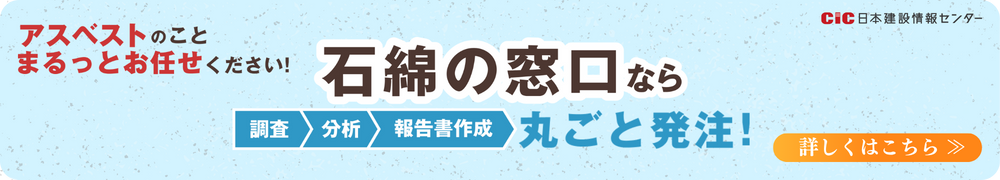
大気汚染防止法って何?アスベストとの関係性も解説

大気汚染防止法は、工場や建設工事から出る有害物質による大気汚染を防ぐための大切な法律です。アスベストについても、その飛散による健康被害を防ぐため、建設工事で厳しい規制が設けられています。
大気汚染防止法とは?基本的な仕組み
大気汚染防止法は、有害物質が大気に排出されることを規制し、国民の健康と生活環境を守ることを目的とした法律です。
1968年、高度経済成長期の深刻な大気汚染問題を背景に制定されました。この法律では以下のような内容を総合的に規制しています。
- 工場からのばい煙規制
- 自動車排出ガス規制
- 建設工事から発生する粉じん規制
建設業界では特に、解体・改修工事における石綿含有建材の適切な処理が義務付けられています。
この法律により、建設事業者はアスベストの飛散防止に関する具体的な義務を負うことになり、適切な対応が法的に求められています。
アスベスト規制が厳しくなった理由
アスベスト規制の強化は、深刻な健康被害の実態と、今後大量に発生する解体工事への対応が背景にあります。
アスベストによる中皮腫や肺がんなどの健康被害が社会問題化し、建設労働者や周辺住民への影響が深刻化したことは記憶に新しいです。同時に、高度経済成長期に建設された建物の解体ラッシュも今後本格化していきます。
近年の主な法改正は以下の通りです。
- 2022年4月改正:一定規模以上の工事で調査結果の報告を義務化
- 2023年10月改正:事前調査の有資格者による実施を義務化
これらの規制強化により、建設事業者には従来以上に厳しいアスベスト対策が求められており、専門的な知識と適切な手続きが欠かせなくなっています。
大気汚染防止法の規制対象かどうかの判断方法

自分が手がける工事が大気汚染防止法の規制対象となるかどうかの判断は、事業者にとって最も大切なポイントです。対象工事の見極めを間違えると、重大な法令違反につながる可能性があります。
対象となる建築物と工事の判断基準
大気汚染防止法の規制対象となるのは、石綿含有建材が使用された建築物の解体・改修工事です。
アスベストの飛散リスクが高い作業を特定し、確実な飛散防止対策を行う必要があります。法律では、建築物の用途や規模に関わらず、石綿含有建材を扱う全ての工事が対象です。
対象となる建築物
対象となる工事
- 解体工事
- 改修工事
- 修繕工事(小規模な部分改修も含む)
レベル1・2の石綿含有建材が使用されていた場合は都道府県への作業内容の届出も必要になります。
建物の種類や工事規模に関わらず、石綿含有建材の有無が規制対象の判断基準となるため、事前調査による確認が欠かせません。
築年数によるアスベスト含有可能性
建築年代により石綿含有建材の使用可能性を判断でき、特に1975年以前の建物は高い確率で含有している可能性があります。
日本では段階的にアスベストの使用が規制され、最終的に2006年に原則禁止となりました。そのため、建築年代によって含有の可能性をある程度推定できます。
年代別の含有可能性
- 1975年以前:吹付けアスベストの使用可能性が高い
- 1980年代まで:石綿含有成形板を多用
- 1990年代:石綿含有スレートボードなどを使用
- 2006年以降:建材の在庫処分により一部で使用の可能性
築年数は大切な判断材料ですが、確実な判定には専門的な事前調査が欠かせません。推測だけで判断するのは危険です。
実際に何をすればいい?必要な手続き

大気汚染防止法に基づくアスベスト対策では、事前調査から作業完了まで複数の段階的な手続きが必要です。各段階での適切な対応により、法令遵守と安全な工事を実現できます。
事前調査から届出まで
石綿含有建材の事前調査と、必要に応じた都道府県への届出が法定義務となっています。
工事前に石綿含有の有無をしっかり把握し、適切な飛散防止対策を計画することが大切です。一定規模以上の工事では行政による監視・指導を可能にするため、事前調査結果の報告も義務付けられています。
事前調査の流れ
- 図面調査:建築図面や過去の改修履歴を確認
- 現地調査:有資格者による現場での目視確認
- 分析調査:必要に応じてサンプル採取・分析
事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による実施が必要です。
届出が必要なケース
レベル1・2の石綿含有建材が確認された場合、工事開始14日前までに都道府県等への届出が必要になります。また、一定規模以上の解体・改修工事では調査結果の報告も義務付けられており、調査結果は工事現場での掲示も必要です。
専門的な事前調査と適切な届出手続きにより、法令遵守の基盤をしっかり整えることができます。
参考:環境省
適切な作業実施のポイント
石綿含有建材の除去作業では、飛散防止対策の徹底と作業基準の遵守が最も大切です。
不適切な作業により石綿が飛散すると、作業者や周辺住民の健康被害につながります。そうなれば企業は深刻な法的責任を負うことになるでしょう。
必須の飛散防止対策
- 作業場所の隔離
- 負圧設備の設置
- 作業者の防護服着用
- 湿潤化による飛散防止
- 廃棄物の適切な梱包・処理
監視・確認作業
- 大気濃度測定による飛散状況の監視
- 作業完了後の清掃確認
これらの作業基準をしっかり実施することで、安全な石綿除去作業と法令遵守を両立できます。
違反のリスクと専門調査の重要性

大気汚染防止法違反は、事業継続に深刻な影響を与える重大なリスクです。一方で、専門的な調査と適切な対応により、これらのリスクをしっかり回避することができます。
違反時の処分・影響
大気汚染防止法違反は、行政処分、刑事罰、経済的損失、社会的信用失墜など、事業に致命的な影響をもたらします。
アスベスト飛散は人命に関わる重大な環境問題です。そのため、違反に対しては厳しい処分が科されるよう法整備が進んでいます。
行政処分・刑事処分
- 改善命令・作業停止命令
- 除去作業基準違反:3か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 作業基準適合命令違反:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
経済的影響
- 工事停止による工期延長
- 追加対策費用の発生
- 損害賠償責任
長期的な事業影響
- 建設業許可への影響
- 取引先からの信頼失墜
- 長期的な事業継続への支障
これらの深刻なリスクを考えると、事前の適切な対策投資は欠かせない経営判断といえます。
安心確実な調査業者の選び方
信頼できる石綿調査業者の選択が、法令遵守と事業リスク回避の決定的な要因となります。
石綿調査は高度な専門知識と経験が必要な業務です。調査の質が後の全ての工程に影響し、不適切な調査は重大な見落としや誤判定につながります。これでは深刻な法令違反リスクを生み出してしまうでしょう。
適切な調査業者の選定基準
- 建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が在籍
- 十分な調査実績と専門設備を保有
- 調査から分析まで一貫したサービス体制
- 迅速かつ正確な報告書作成能力
- 工事業者との利害関係がない独立した立場
工事業者と利害関係のない独立した立場で、客観的な調査を実施できることも信頼性の大切な要素となります。
専門性の高い調査業者との連携により、確実な法令遵守と安全な工事実施を実現できます。
まとめ

大気汚染防止法に基づくアスベスト規制は、建設事業者にとって避けて通れない大切な法的義務です。規制の内容は複雑ですが、適切な事前調査と専門業者との連携により、確実な法令遵守と安全な工事を実現できます。
特に大切なポイント
- 築年数に関わらず全ての建築物で事前調査を実施する
- 有資格者による専門的な調査を依頼する
- 調査結果に基づいた適切な届出と作業実施を行う
違反時のリスクは事業継続に関わる深刻なものですが、これらの対策をしっかり実施することで回避できます。
CICでは、アスベスト調査から分析まで一貫してサポートする「石綿の窓口」を提供しています。有資格者による確実な事前調査により、お客様の法令遵守と安全な工事をお手伝いいたします。アスベスト対策でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。