玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け作業に携わる労働者を対象に受講が義務づけられている安全衛生教育です。日本人・外国人労働者に関係なく受講が義務づけられており、学科講習のみの内容で構成されています。
この記事では、玉掛け業務従事者安全衛生教育の概要や外国人労働者に受講してもらう方法について解説します。注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
公開日:2025年5月13日 更新日:2025年5月14日
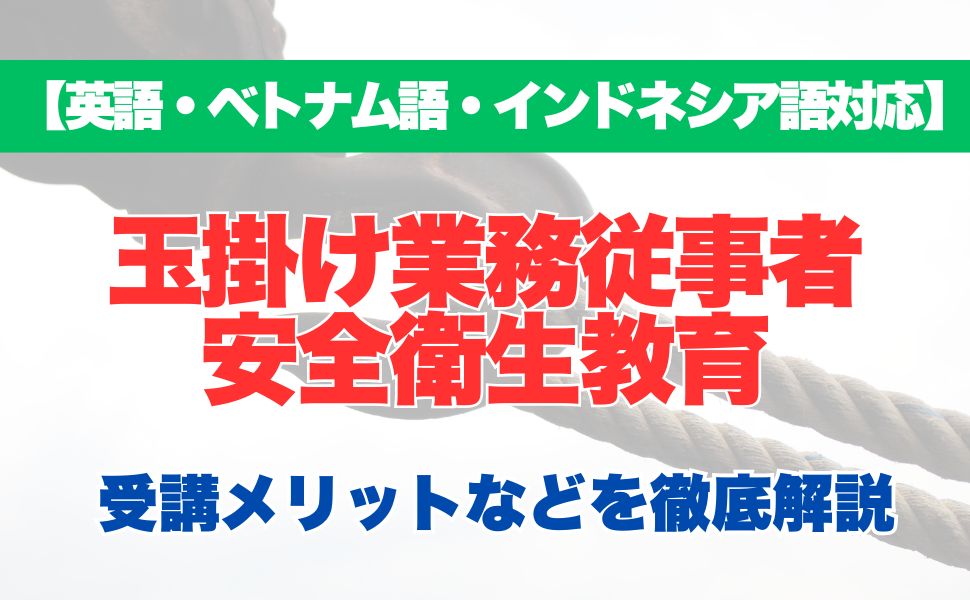
玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け作業に携わる労働者を対象に受講が義務づけられている安全衛生教育です。日本人・外国人労働者に関係なく受講が義務づけられており、学科講習のみの内容で構成されています。
この記事では、玉掛け業務従事者安全衛生教育の概要や外国人労働者に受講してもらう方法について解説します。注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け作業に携わる労働者を対象とした安全衛生教育です。労働災害を防いで安全な作業環境を維持するために、一定の期間ごとに実施することが法令で義務づけられています。
安全衛生教育の対象となる主な作業は、以下のとおりです。
これらの作業に従事する労働者は、高所作業や重量物の取り扱いといった危険を伴う環境に身を置くことになります。
作業の危険性や安全を守るために知識を正しく理解し、労働災害を防ぐ観点から見ても、玉掛け業務従事者安全衛生教育の受講は必要不可欠です。
玉掛け業務従事者安全衛生教育の受講対象者は、「玉掛け作業に従事する人」です。厚生労働省が公表する内容によると、以下の内容とのことです。
出典:厚生労働省 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針、15 玉掛け業務
日本人・外国人労働者に関係なく上記に該当する方は安全衛生教育の受講対象となります。事業者は忘れずに安全衛生教育を受講してもらいましょう。受講方法に関しては後述します。
以下の表は、玉掛け業務従事者安全衛生教育の受講内容をまとめたものです。
| 受講科目 | 受講時間 |
|---|---|
| 最近の玉掛け用具の特徴 | 1時間 |
| 玉掛け用具等の取り扱いと保守管理 | 2.5時間 |
| 災害事例及び関係法令 | 1.5時間 |
| 合計 | 5時間 |
玉掛け業務従事者安全衛生教育は、学科講習のみの実施です。
実技講習は行われないため、5時間の講習の中で必要な知識を学習する必要があります。また、上記の受講時間は最低受講時間なので、実際の受講時間は受講する機関によって異なります。
講習機関の公式サイトからカリキュラム・講習時間はチェックできるため、事前に情報を把握しておくとよいでしょう。
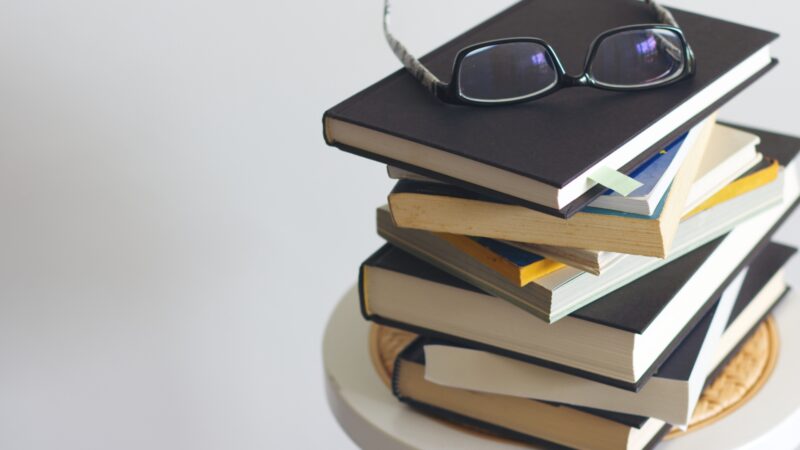
玉掛け業務従事者安全衛生教育には、主に以下3つの受講方法があります。
一般的なのは、各講習機関で実施される講習の受講です。講師の手配が不要でスムーズに受講できる一方で、現地まで足を運ぶ必要があります。特に外国人労働者の場合、交通機関の利用に慣れていないと迷ってしまう可能性があります。また、運転免許を持たない場合、企業側で送迎を手配しなければならない可能性がある点もデメリットです。
次点で挙げられる出張講習は、講師を事業所へ招いて受講する方法です。移動の負担がなく、受講者にとっては安心して参加できる点がメリットです。ただし、講師の交通費や宿泊費などが発生する場合、高いコストがかかります。また、受講人数が少ないと依頼を受けてもらえないことがある点もデメリットです。
受講者・事業者両方の視点から受講しやすい方法は、Web(オンライン)講座です。オンライン形式で学べるため、受講者は自分のペースで学習できます。また、移動の負担もなく送迎の必要や出張費用の支払いなどもありません。
さらに、英語を含めた複数の言語に対応した講座であれば、外国人労働者でも安心して受講できる環境が整います。CIC日本建設情報センターでは、英語・ベトナム語・インドネシア語に対応したWeb講座もご用意していますので、ぜひご検討ください。
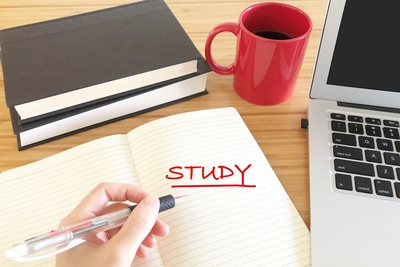
外国人労働者が玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する際、受講できるかどうかは、主に以下2つの基準に基づいて判断されます。
| 1. 日常生活に必要な日本語の理解力がある | ・講習に関する読み書きや会話において、日本人労働者と同程度の日本語力があること |
|---|---|
| 2. 専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分ある | ・講師の説明のうち、専門用語以外の内容を概ね理解できること ・ひらがなやカタカナを読むことができる程度の日本語力があること |
これらの基準を満たしていないと判断された場合には、たとえ受講途中であっても退席を求められたり、修了証が発行されないといったケースも想定されます。
そのため、日本語力に不安がある場合は、Web(オンライン)講座の受講を検討するのも有効な選択肢です。Web講座であれば、事業者の管理下で受講・修了することで、修了証の取得が可能です。事前に外国人労働者の日本語理解度を確認したうえで、最適な受講方法を選びましょう。
なお、多言語対応のWeb講座は、あくまで一定の日本語能力を有する受講者(上記表①に該当)を対象とした補助的なツールです。そのため、翻訳の正確性を保証するものではありません。
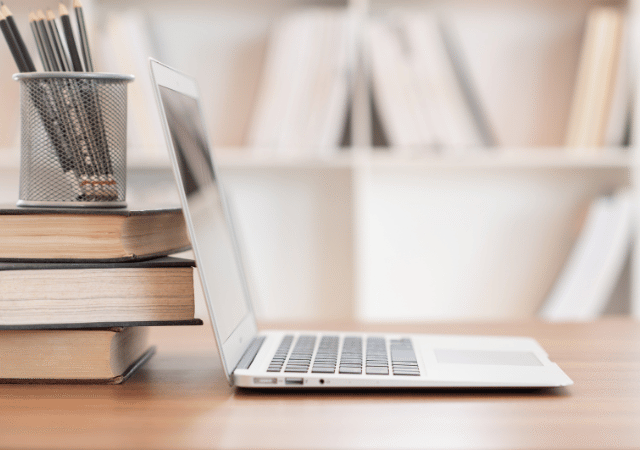
日本語を理解できる外国人労働者が玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する場合、Web(オンライン)講座の利用がおすすめです。Web講座には以下のようなメリットがあります。
たとえば、日本語をある程度理解できるとしても、講義では話のスピードが速いことから内容を理解するのに時間がかかる可能性があります。聞き逃した箇所が生じることも考えられるでしょう。
一方でWeb講座であれば、再生を一時停止したり繰り返し視聴したりなど受講者のペースで進められます。必要な知識をじっくりと理解を深めることが可能です。
また、Web講座は、通勤中や休憩時間などの空き時間を有効的に活用して学習できます。ただし、事業者側が労働時間外での受講を強制することは認められていません。受講を時間外に行う場合は、時間外手当を支給するなどの柔軟な対応が必要です。

玉掛け業務従事者安全衛生教育を外国人労働者が受講する際、注意点は以下のとおりです。
それぞれの内容について詳しく解説します。
日本語で実施される玉掛け業務従事者安全衛生教育を外国人労働者が受けるには、ある程度の日本語の読み書きが必要です。
たとえば、「特定技能」の在留資格を持っている外国人の方は、日本語能力試験(JLPT)N4合格が条件となっており、基本的な日本語力があると認められています。そのため、N4を持っていれば特別教育の受講もスムーズに進めやすくなります。
ただし、受講者の日本語理解が不十分と判断された場合、受講できないこともあるため、ご注意ください。また、日本語力が不十分なまま修了とすると、事業者側の責任が問われる可能性があります。
講習機関によっては、受講前に日本語力をチェックするところもありますので、事前に確認しておくと安心です。
日本語で実施される安全衛生教育では、条件付きで通訳の同席が認められる場合があります。ただし、通訳が可能なのは基本的に専門用語に限られており、一般的な説明や補足などの内容は基本的に通訳できません。
また、通訳が同席していても必ずしも受講が許可されるとは限らず、講習内容の理解が困難だと判断された場合は、別の受講方法を検討する必要があります。
外国人労働者向けの講習を行っている教育機関はありますが、すべての言語に対応しているわけではありません。
たとえば、英語対応の講習は比較的多いですが、フランス語やイタリア語、中国語の方言(北京語・上海語など)までカバーしているところは限られています。
そのため、受講者の得意とする言語で受講できるかどうかは申し込み前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

CIC日本建設情報センターでは、外国人労働者の方でも受講できる玉掛け業務従事者安全衛生教育のWeb講座を提供しております。ここからは、CIC日本建設情報センターのWeb講座の特徴を詳しく解説します。
日本で働く外国人労働者の中には、ベトナムやインドネシア出身の方が多数います。CIC日本建設情報センターのWeb講座は、外国人労働者の母国語に寄り添ってベトナム語とインドネシア語に対応しています。
さらに、「英語の方がわかりやすい」というご要望にも応え、英語字幕にも対応しているのが特徴です。外国人の方でも安心して学べる環境を整えており、玉掛け業務従事者安全衛生教育もスムーズに受講できます。
CIC日本建設情報センターのWeb講座では、受講者ごとに専用アカウントが発行されます。進捗や履歴は管理画面からいつでも確認できるため、自分のペースで効率よく学習を進めることが可能です。計画的に学びたい方にもぴったりの仕組みといえるでしょう。
CIC日本建設情報センターのWeb講座は、顔認証システムを導入しています。受講中に席を外すと学習が進まない仕組みのため、修了時には本人がきちんと受講していたことの証明が可能です。受講の信頼性を重視する事業者の方にも安心です。
玉掛け業務従事者安全衛生教育の修了後、受講者には修了証が発行されます。CIC日本建設情報センターのWeb講座では、修了証を「PDF版」と「カード版」から選べるのが特徴です。
PDF版は、修了直後にダウンロードが可能で、すぐに証明書を用意したい方向けです。一方のカード版は、持ち運びに便利で、現場などで提示を求められる場面でもスムーズに対応でき、おすすめです。
講座のお申し込み時にどちらかを選択できるため、用途に合った形式をお選びください。

この記事では、外国人労働者が玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する方法について解説しました。
安全衛生教育の受講方法には、講習会への参加や出張講習の依頼などがあります。しかし、日本語の理解度が足りないと受講できない場合があります。また、交通機関で迷ったり送迎の必要性が出てきたりするリスクや講師の出張費や宿泊費の負担による費用面での問題など、メリット以外で生じるデメリットも踏まえた上で選ばなければなりません。
これらの問題をクリアできる受講方法として、Web講座があります。Web講座であれば、日本語が聞き取れなかった箇所や分からない部分を巻き戻しや一時停止するなど、自由な視聴が可能です。多言語に対応した講座であれば、より受講者に合わせてじっくりと理解を深められます。
CIC日本建設情報センターでは、英語・ベトナム語・インドネシア語字幕に対応した玉掛け業務従事者安全衛生教育のWeb講座を用意しております。外国人労働者の方でもモチベーションを維持しながら計画的に学習を進められる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育クレーン安全教育ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育ゴンドラ取扱い業務特別教育巻上げ機の運転の業務に係る特別教育移動式クレーンの運転特別教育移動式クレーン運転士安全衛生教育フォークリフト玉掛け特別教育玉掛け安全教育高所作業車クレーンローラー特別教育小型車両特別教育
重機・建設機械の免許を徹底解説!種類や取得費用・期間をご紹介!

玉掛け業務従事者安全衛生教育の目的と受講内容をわかりやすく解説

玉掛け業務従事者安全衛生教育はWeb講座で!Web講座のメリットと注意点を解説
