施工管理技士合格をアシスト 建設業特化の受験対策
- 【独学合格を目指す方はこちら】
- 企業研修・社員研修
- CIC出版の書籍
- 石綿の窓口
- 建設キャリア転職
公開日:2024年7月1日 更新日:2025年9月12日
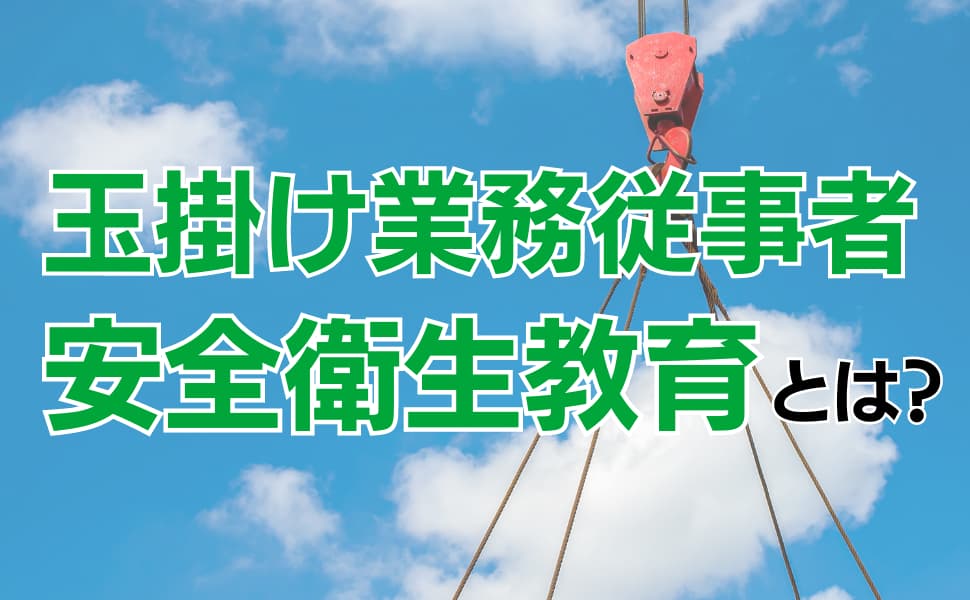
過去に玉掛けの資格や教育を受けた人で、現在も玉掛け作業を行っている人は、法律で定められた玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する義務があります。
この記事では、玉掛け業務従事者安全衛生教育の目的や関連する法律、受講内容など詳しく解説します。

玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け資格を取得した人や安全教育を終了した経験者を対象に行います。目的は、作業の危険性や器具の正しい取り扱い方などを再度勉強して労働災害をなくすことです。
簡単に言えば、玉掛け作業の「再教育」です。そのため、現在でも玉掛け作業に従事している人が対象です。
玉掛け作業とは、クレーンなどで荷物を吊り上げるときに、ワイヤーやスリング、フックなどの道具を使って、安全に吊り上げられるように荷物を固定する作業です。
安全に吊り上げるには、荷物の重心を正確に計算し、適切な道具を使って正しい位置や方法で固定する必要があります。しかし、適当な計算や正しく固定されていなければ、ワイヤーなどの固定具が外れ、落下した際に荷物に挟まれる危険や建造物などにも甚大な被害が及ぶ可能性があります。
玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け作業に従事している人を対象に行う教育です。危険な作業環境で働く労働者の安全確保と事故を未然に防ぐため、教育を一定期間ごとに実施することが法律で義務付けられています。
主には以下の業務に関する吊り上げ作業が該当します。
これらの玉掛け作業に関わっている労働者は、危険リスクを理解した上で安全に作業することが求められるので、玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する必要があります。
また、玉掛け業務従事者安全衛生教育は、労働安全衛生法の規定に沿って実施しており、次のように法律で定められています。
簡単に言えば「厚生労働大臣が公表した内容に基づいて、危険な作業を行っている人に対して、安全と衛生について教育をしなさい」という内容です。
厚生労働大臣が公表している「必要な指針」は厚生労働省 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針で確認できます。
また、上記の基になっているものが、以下の安全衛生法第61条、安全衛生法施行令第20条です。
また、労働安全衛生法の第61条にある「その他の業務で、政令で定めるもの」について、労働安全衛生法施行令では次のように定めています。
以上の法律を簡単にまとめると、「1トン以上の玉掛け作業をする人は、定期的に玉掛け業務従事者安全衛生教育を受けないと作業をしてはいけません」という内容です。
玉掛け作業を行っている人は常に危険と隣り合わせです。そのため、玉掛け業務従事者安全衛生教育を受けて、危険性や安全確認などを再認識が必要です。
例えば、玉掛けが正しく行われていなければ、次のような事故を引き起こしたり、巻き込まれたりする可能性があります。
過去に資格取得や教育を受けていても自己過信や怠慢、日常的な慣れなどにより、いつ事故に巻き込まれるかわかりません。
また、労働災害が発生すると、命の危険や五体満足に生活できなくなる可能性があります。さらには工事の一時中断や継続中止など、会社や地域社会にも不利益が生じます。
いつもと変わらぬ楽しい日常を送るためには、最悪の事態を回避することが重要です。その方法の一つとして、安全に関する再教育を行うことが効果的だと位置づけられています。
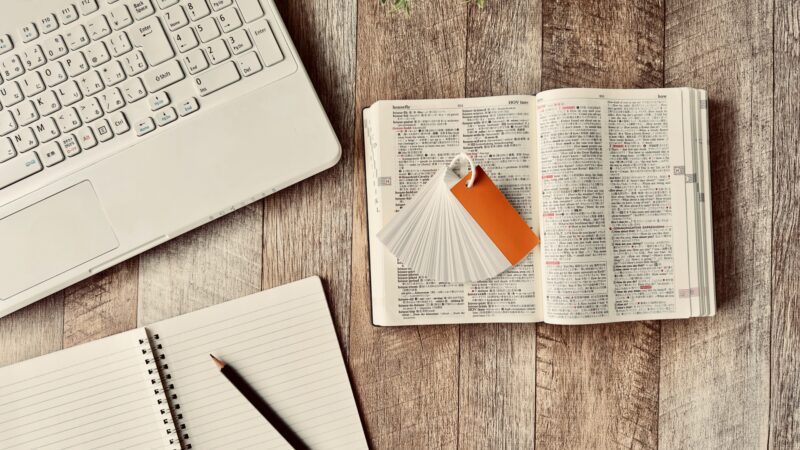
受講資格と受講概要は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項に基づき、厚生労働省が公表しているので詳しく解説します。
受講資格は「玉掛け作業を行っている人」が対象です。厚生労働省が公表した内容には以下のように記載されています。
出典:厚生労働省 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針、15 玉掛け業務)
公表されている指針では、年齢や玉掛けの経験年数に関する記載はありません。そのため、玉掛け作業を行っている労働者であれば誰でも受講できます。
日本建設情報センターの受講料は、以下の価格です。
| 受講料:11,000円(税込) | |
| 注意事項 |
|
また、厚生労働省から公表された指針では以下のように細かく定められています。
上記内容に基づいて、日本建設情報センターでは以下のカリキュラムで行っています。
| 科目 | 範囲 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 最近の玉掛け用具の特徴 | 1時間2分 | |
| (1)玉掛用具等の構造上の特徴
(2)クレーン等の安全装置等の特徴 |
||
| 玉掛け用具等の取り扱いと保守管理 | 2時間35分 | |
| (1)玉掛作業の安全
(2)玉掛用具等の点検・整備 |
||
| 災害事例及び関係法令 | 1時間34分 | |
| (1)災害事例とその防止対策
(2)労働安全衛生法令のうち玉掛けに関する条例 |
||
| 合計学習時間:5時間11分 | ||
厚生労働省が公表している指針にもありますが、事業主は、実施した教育の記録は個人別に保存しなければなりません。
そのため、日本建設情報センターを受講すれば、事業主の代わりに修了証を発行します。
修了証には以下の2タイプがあり、お申込み時にどちらか選択可能です。
| 修了証タイプ | 内容 |
|---|---|
| 修了証PDF
(カード型修了証なし) |
|
| 修了証PDF + カード型修了証 |
|
注意点として、お申し込み後にカード型修了証の追加発行の申し出があっても、原則対応していないので十分ご留意ください。

玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する主なメリットは次の3つです。
玉掛けに関する最新の知識や情報が得られれば、自分だけでなく作業場で一緒に働く仲間の危険リスクの回避にも役立ちます。そして、危機管理が作業場や職場の全体に浸透すれば、職場の雰囲気が変わるので労働災害の撲滅にも貢献できます。

玉掛け業務従事者安全衛生教育の受講方法は、講習会への参加や社内で実施する方法と、Web講座を利用する方法の2パターンあるのでそれぞれ解説します。
社内で実施する場合は、厚生労働省が公表している指針に基づき、講師を選任する必要があります。
講師を務める人は、玉掛けの経験者であれば誰でも良いわけではありません。指針によれば「玉掛けの最新の知識と教育技法についての知識及び経験」がなければ講師はできないので十分注意してください。
社内で実施する場合には次の方法があります。
どちらも難しいようであれば、外部企業や安全衛生団体などが開催している講習会に参加する方法もあります。
費用や日程、会場などは各企業や団体によって異なりますので、事前に応募先に確認してください。
令和3年1月25日に厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表されたことで、eラーニング等により安全衛生教育を実施することが可能になりました。
そのため、日本建設情報センターでもWeb講座「玉掛け業務従事者安全衛生教育」を開始しています。Web講座は24時間受講可能となっており、場所や時間に捉われず、自分の好きなタイミングで受講できるメリットがあります。
また、本講座では、AI顔認証システムを導入しており、「受講者様本人が、規定時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定できます。このシステムにより、受講者様が確実に安全衛生教育を受講していることを保証しています。

玉掛け業務従事者安全衛生教育は、労働安全衛生法で定められており、玉掛け業務に従事している労働者の安全と労働災害を撲滅するために行われる教育です。改めて教育を受けることで、最新の危険リスクや危機管理の知識・情報などを得られるメリットがあります。
また、厚生労働省からもオンラインでの受講が許可されており、気軽に受けられる環境を整えているので積極的に受講して労働災害の防止にお役立てください。

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育クレーン安全教育ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育ゴンドラ取扱い業務特別教育巻上げ機の運転の業務に係る特別教育移動式クレーンの運転特別教育移動式クレーン運転士安全衛生教育フォークリフト玉掛け特別教育玉掛け安全教育高所作業車クレーンローラー特別教育小型車両特別教育
重機・建設機械の免許を徹底解説!種類や取得費用・期間をご紹介!
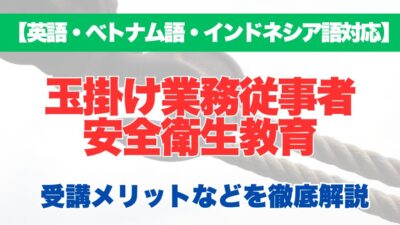
【外国語対応】玉掛け業務従事者安全衛生教育の受講するメリットなどを徹底解説!

玉掛け業務従事者安全衛生教育はWeb講座で!Web講座のメリットと注意点を解説
