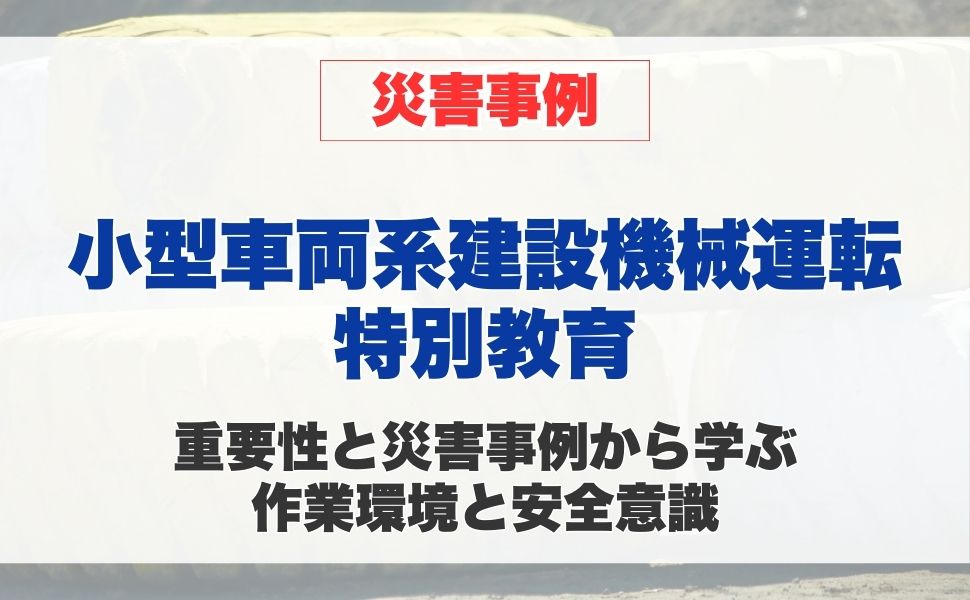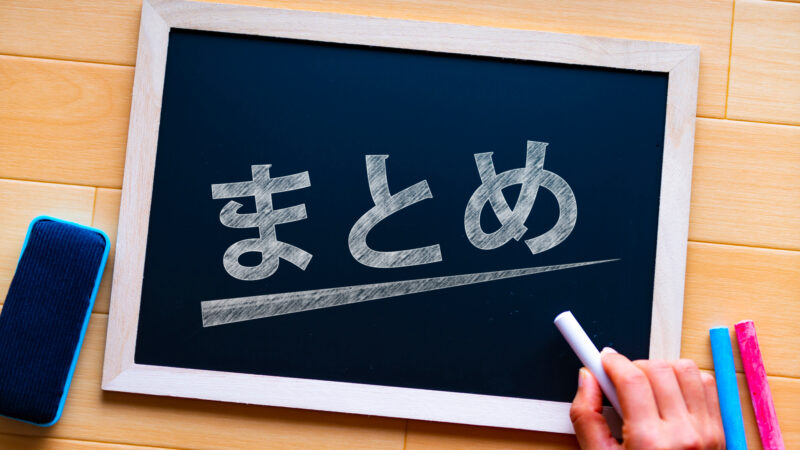自動車を運転するときに「運転免許証」が必要であるように、小型車両系建設機械を運転するためには、「特別教育」を受講し、修了証を取得する必要があります。
作業者が特別教育を受講しないまま運転作業を行う、または、管理者が作業者に受講させないまま運転作業をさせると、事業者には罰則が科される可能性があります。また、死亡事故を含む労働災害のリスクも高まります。
今回は小型車両系建設機械に関わる3つの災害事例を安全意識の観点からご紹介します。特に受講を考えている作業者の方、受講させなくてはならない管理者の方は必見です。