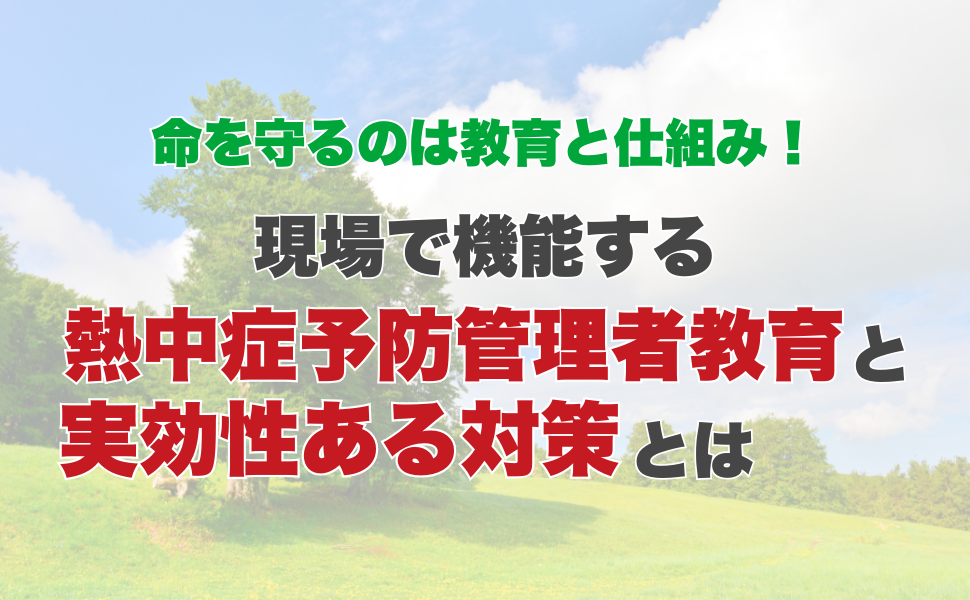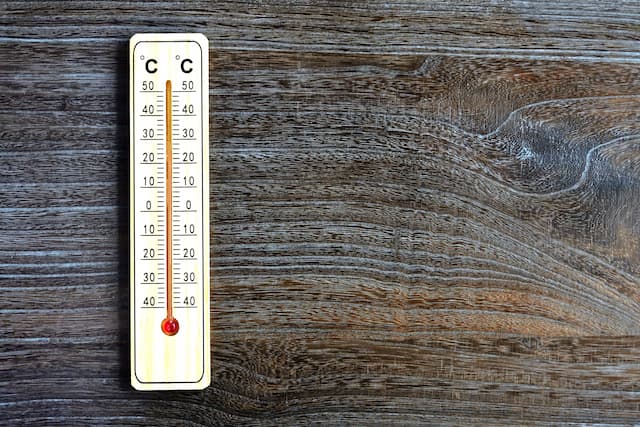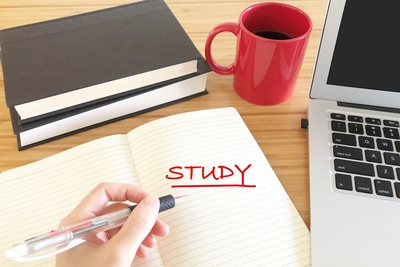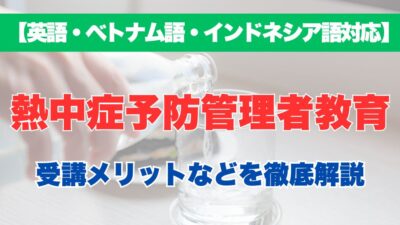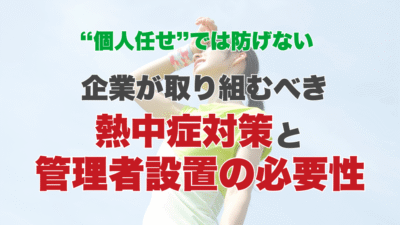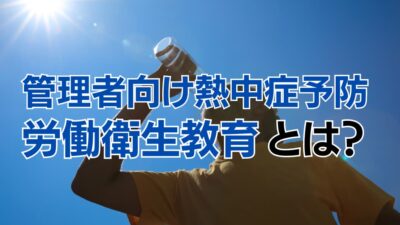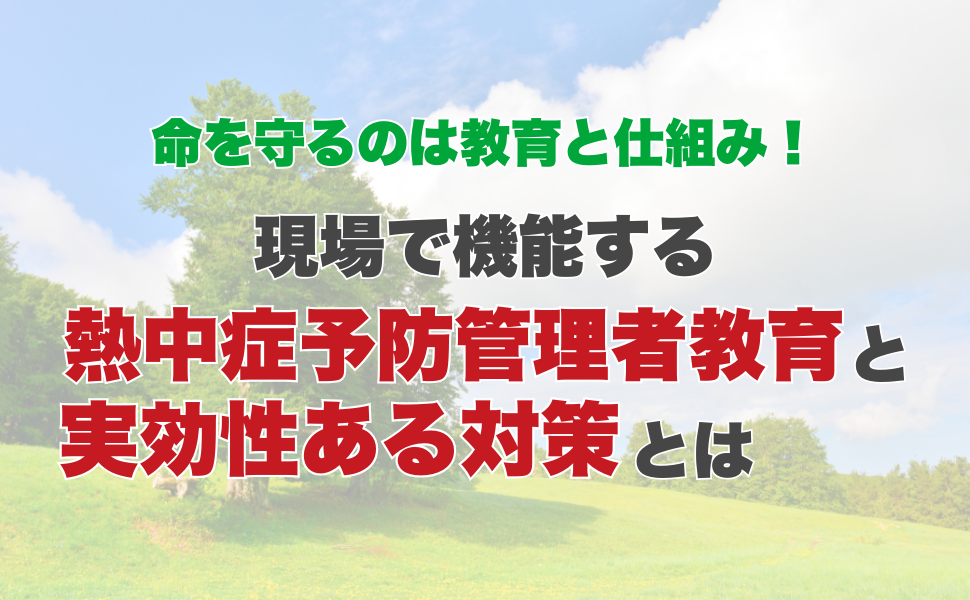
暑い時期になってくると、現場仕事で切り離せない問題が熱中症です。厚生労働省のデータによると、2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人、そのうち31人が亡くなっており、熱中症対策をとっていても内容が不十分であれば命を守ることはできません。
そのため、現場で熱中症対策が失敗する理由などを把握し、熱中症予防管理者を中心に対策をとったり意識づけを徹底したりすることが大切です。
この記事では、現場で機能する熱中症予防管理者教育と実効性ある対策について解説します。実際の事例を交えながら詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

水分補給だけでは防げない熱中症

建設現場や製造業の現場で「こまめに水分を取りましょう」という声かけを耳にすることはあるかもしれません。ただし、実際には水分補給や声かけだけでは熱中症を防ぎきれないのが現実です。
厚生労働省のデータによると、2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人、そのうち31人が亡くなっています。特に建設業が最も多い割合を占めており、次いで製造業や運送業の割合が多い傾向です。
また、現場での経験が豊富である40歳以上の労働者が多くの割合を占めています。そのため、「自分は現場に慣れているから大丈夫」と過信していると、大きな事故につながりかねません。
熱中症の発症には、環境要因(気温・湿度など)、身体要因(体調・持病の有無など)、行動要因(作業時間・休憩頻度など)の要素が影響します。たとえば、アスファルトやコンクリートから放射された熱により、気温30℃でも体感温度は40℃を超える場合があります。
これらが影響を及ぼし、令和7年(2025年)6月1日から労働安全衛生規則が改正されて、熱中症対策を行うことが事業者に義務づけられました。企業にとって熱中症対策は、労働契約法第5条に定められた安全配慮義務の一環であり、組織として熱中症対策を講じることが求められています。
現場で熱中症対策が失敗する理由
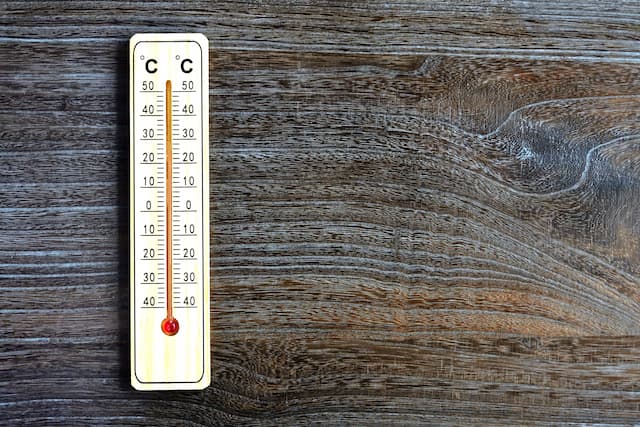
多くの現場である程度の熱中症対策が実施されているにも関わらず、対策が失敗してしまうのはどうしてでしょうか。その理由は、主に以下の3つです。
- 対策ルールがあいまい
- 判断が個人任せ
- 緊急時の行動が属人化
失敗の理由・原因を把握することで、より効果的な対策をとりやすくなります。ここでは、それぞれの内容についてみていきましょう。
対策ルールがあいまい
対策が失敗する要因の1つ目が「対策ルールがあいまい」という点です。「暑い日は休憩を多めに」「体調が悪くなったら申し出る」などのあいまいな指示では、現場での判断がしづらくなるでしょう。
また、WBGT値(暑さ指数)による作業制限の基準が設けられていても、実際の測定や記録が徹底されていなければ十分な熱中症対策とはいえません。たとえば、「WBGT値が28℃を超えた場合はどうするか?」などの具体的な明確なルールがなければ、現場の管理者・監督者も判断に迷いやすくなります。
「まだ大丈夫。もう少し時間が経ったら水分補給しよう」というような楽観的な判断が生じないよう、リスクを把握して必要な対策をとることが大切です。
判断が個人任せ
対策が失敗する要因の1つ目が「判断が個人任せ」という点です。熱中症の初期症状は、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、大量の発汗などが挙げられますが、作業者自身が「疲れているだけ」と判断してしまうケースが考えられます。
特に建設現場では、工期のプレッシャーや周囲への遠慮から、体調不良があっても個人の判断で申告しない選択をとるかもしれません。現場経験のあるベテランな方であっても「自分は大丈夫」と過信せず、初期症状が見られたらすぐに対処することが大切です。
個人の判断に委ねることがないようにしましょう。
緊急時の行動が属人化
対策が失敗する要因の1つ目が「緊急時の行動が属人化している」という点です。熱中症が発生した際の対応が、偶然その場にいる経験者の判断に委ねられている場合、救急車を呼ぶタイミングや応急処置の方法、搬送先の選定などの判断が明確にされていません。
現場責任者が不在の時間帯や新人が多い現場では、対応が遅れてしまう可能性もあります。熱中症は、発症当日に亡くなるケースもあるため、誰もが迅速かつ的確に行動できる体制づくりが必要です。

「熱中症予防管理者」が行う課題解決

ここまで、熱中症による労働災害の現状や対策が失敗する理由・原因を解説しました。このことからも、熱中症予防管理者を中心に対策に取り組むことが大切といえるでしょう。
ここからは、熱中症予防管理者が行う課題解決について解説します。具体的な課題解決のポイントは、以下の3つです。
- 暑熱順化
- ルールの整備と意識づけ
- 緊急時マニュアルと訓練の整備
それぞれの内容についてみていきましょう。
暑熱順化
暑熱順化とは、体が暑さに慣れることで熱中症にかかりにくくなる生理的な適応現象のことです。熱中症予防管理者は、作業者の暑熱順化状態を把握した上で、段階的な作業計画を考えます。
暑熱順化を促進する具体的な方法として、作業開始前の2週間程度から計画的に暑熱環境での活動を増やしていきます。初日は軽作業を1時間程度から始め、徐々に作業強度と時間を増やしていく方法が効果的です。また、新規入場者や長期休暇明けの作業者には、特に注意を払う必要があります。
ルールの整備と意識づけ
熱中症予防管理者は、ルールの整備と意識づけにも取り組みます。厚生労働省の公表によると、WBGT値(暑さ指数)が31度以上の場合は原則として作業中止、28度以上31度未満は「厳重警戒(激しい運動は中止)」、25度以上28度未満は「警戒(積極的に休息)」 という基準が示されています。予防管理者は、WBGT値を上手く活用しながら、熱中症対策に講じていきます。
具体的な対策としては、以下のとおりです。
作業開始前に労働者の健康状態を確認し、作業中は巡視を頻繁に行って労働者に声をかけるなどして体調の管理を徹底します。ほかにも、適度な休憩時間を確保するのも整備づけるルールの1つです。
水分・塩分の摂取については、少なくとも、0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム40~80㎎/100㎖のスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度は摂取することが望ましいとされています。熱中症予防管理者は、作業者の水分摂取状況を確認するためのチェック表を作成し、定期的な摂取を確実に実施させます。
緊急時マニュアルと訓練の整備
熱中症予防管理者は、緊急時の対応を誰もが実行できるよう、具体的なマニュアルを作成したり訓練の整備をしたりします。体調不良者を発見した際の報告ルート、応急処置の正しい手順、救急要請の判断基準などを明確にし、現場の目立つ場所に掲示します。
応急処置の基本手順は、「涼しい場所への移動」「衣服を緩める」「体を冷やす(首、脇の下、足の付け根)」「水分補給(意識がはっきりしている場合)」の4ステップです。意識がもうろうとしている、自力で水分が取れない、吐き気や身体のだるさなど、症状が改善しないといった場合は、直ちに救急車を呼びます。救急搬送
また、定期的な訓練も欠かせません。熱中症発生を想定したシミュレーション訓練を実施し、全作業者が緊急時の役割を理解して迅速に行動できるよう取り組みます。組織単位での体制づくりや意識づけを行うのも熱中症予防管理者の大きな役割です。
事例紹介|管理体制の見直しで変わった現場の声

ここからは、実際に熱中症対策として管理体制を見直した現場をご紹介します。
- 熱中症予防のためのクールハウスの設置
- 熱中症対策ハウスの設置
- 作業指示・安全指示書及び現地KY記録表の導入
自分たちで熱中症対策を行う場合の参考にしてみてください。
事例1. 熱中症予防のためのクールハウスの設置(竹中工務店)
1つ目の事例が「熱中症予防のためのクールハウスの設置」です。いつでも気軽に使えるクールハウスを設置することで熱中症対策を図った事例になります。
事例の特徴は、以下のとおりです。
- 熱中症緊急対処手順を見える化
- メットシャワーを設置
- ウォシュレットトイレを配置
- ハウス内部には熱中招待作品を用意
- 労働者の熱中症ゼロ宣言を掲示
参考:熱中症予防クールハウスの設置
事例2. 熱中症対策ハウスの設置(五洋建設)
2つ目の事例が「熱中症対策ハウスの設置」です。壁・天井に水を流し、デザインや設備によって感覚的・視覚的・聴覚的に涼しさを与えて熱中症を起こさないようなハウスを設置した事例になります。
ハウスの特徴は、以下のとおりです。
- 屋根も熱くなるので水を流す
- 流した水は散水として再利用する
- 製氷機・冷水器・アイスクリームなどを用意して熱中症を予防する
- 横断幕を掲げて見える化を図る
- パネルに海や水中のシールを貼って視覚的に涼しくする
- 風鈴や水の流れる音で聴覚的にも涼しくする
- ミストシャワー・打ち水・声かけ運動によって第三者にも涼しさを感じてもらう
参考:防げ熱中症 感じろ!! 涼 風 流 – あんぜんプロジェクト
事例3. 作業指示・安全指示書及び現地KY記録表の導入(鹿島建設)
3つ目の事例が「1時間ごとに1回の休憩を記録できるKW用紙」の導入です。作業の実施内容や安全衛生の指示事項、現地での危険予知などを記録できる用紙となっており、こまめに記載することで必要な対策をとっていくものとなります。
用紙の特徴は、以下のとおりです。
- 作業箇所ごとに作業内容を記録できるようになっている
- どんな危険が潜んでいるかまで記載することで現地での危険予知の精度を高められる
- 本日の休憩時間を記録することで熱中症対策に必要な行動をしっかり確保できる
参考:夏季限定で1時間ごとに1回の休憩を記録できるKY用紙 – あんぜんプロジェクト

CIC日本建設情報センターの熱中症予防管理者教育
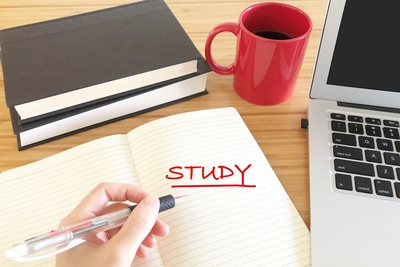
CIC日本建設情報センターでは、熱中症予防管理者教育のWeb(オンライン)講座を開講しています。豊富な実績に基づくノウハウや現場での役割・作業に基づいて、必要なポイントをコンパクトにまとめたテキストと、専門講師によるわかりやすい動画講義から、短期間で効率よく知識や技術を身につけることが可能です。
CIC日本建設情報センターのWeb講座は、以下の手順で受講できます。
- CIC日本建設情報センターのWeb講座に申し込む
- 入金確認後、メールでログイン情報が送付される
- 受講(視聴)が開始する
- 受講完了後、自分が選択した修了証を受け取る
また、CICの講座では顔認証システムを採用しています。顔認証システムによって、受講者が画面の前にいない場合は学習が進まないのが特徴です。そのため、「受講者が実際に画面の前で学んでいるのか分からない」と不安に感じる事業者の方にも安心といえるでしょう。
受講方法でお悩みの場合は、ぜひCIC日本建設情報センターの講座をご検討ください。
まとめ

この記事では、現場で機能する熱中症予防管理者教育と実効性ある対策について解説しました。
熱中症対策は、依然として企業の大きな課題といえます。厚生労働省のデータによると、2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人、そのうち31人が亡くなっており、熱中症対策をとっても内容が不十分なことから失敗するケースも珍しくありません。
熱中症対策は、熱中症予防管理者を中心に、暑熱順化・ルールの整備と意識づけ・緊急時マニュアルと訓練の整備を図ることが大切です。予防管理者は、熱中症の発症を防ぐだけでなく、もしもの際の適切な対応はもちろん、普段からの予防体制の整備や意識改革にも取り組みます。
CIC日本建設情報センターでは、熱中症予防管理者教育のWeb講座を用意しております。命にかかわる重要な内容ですので、ぜひ受講をご検討ください。