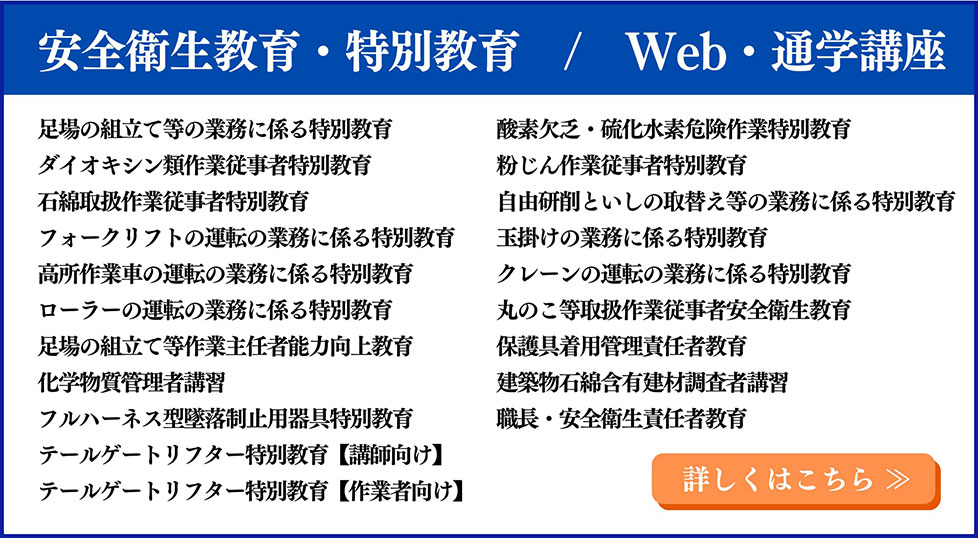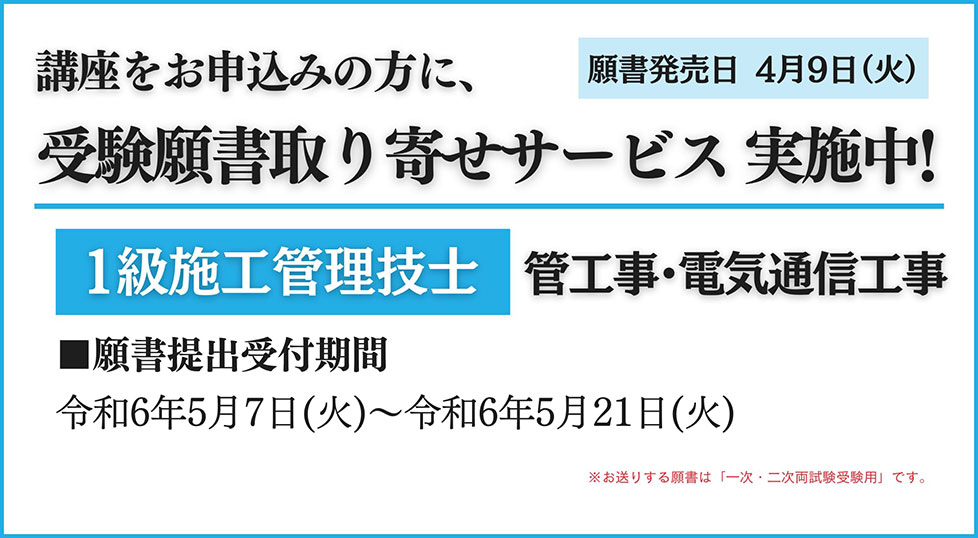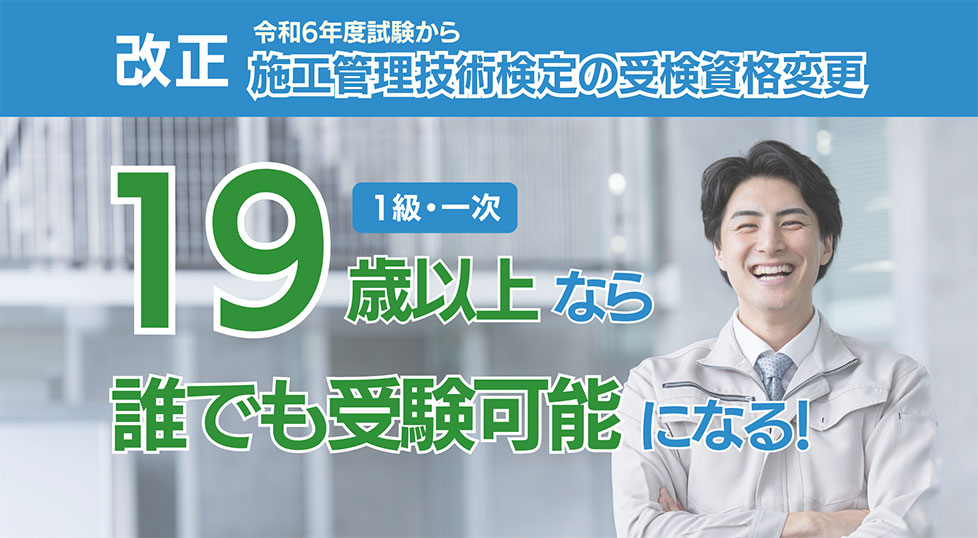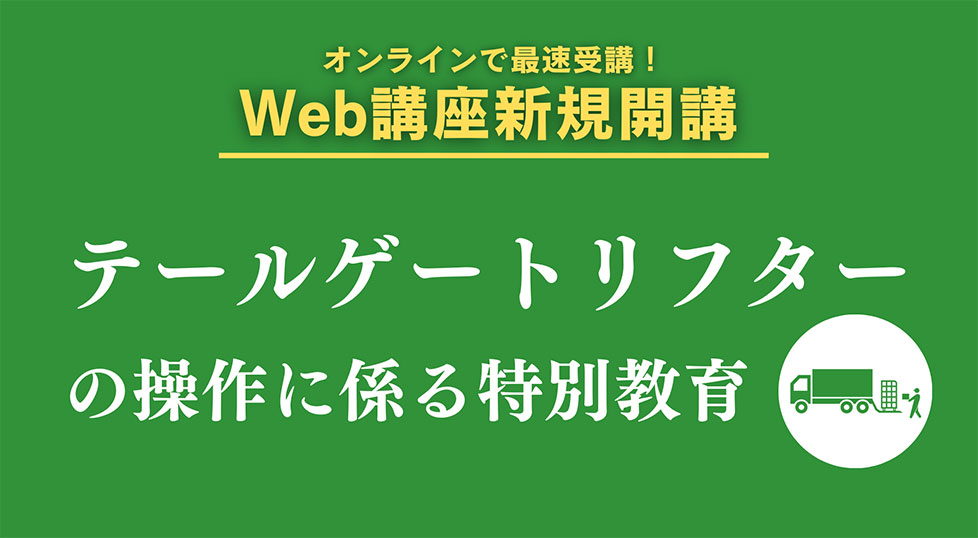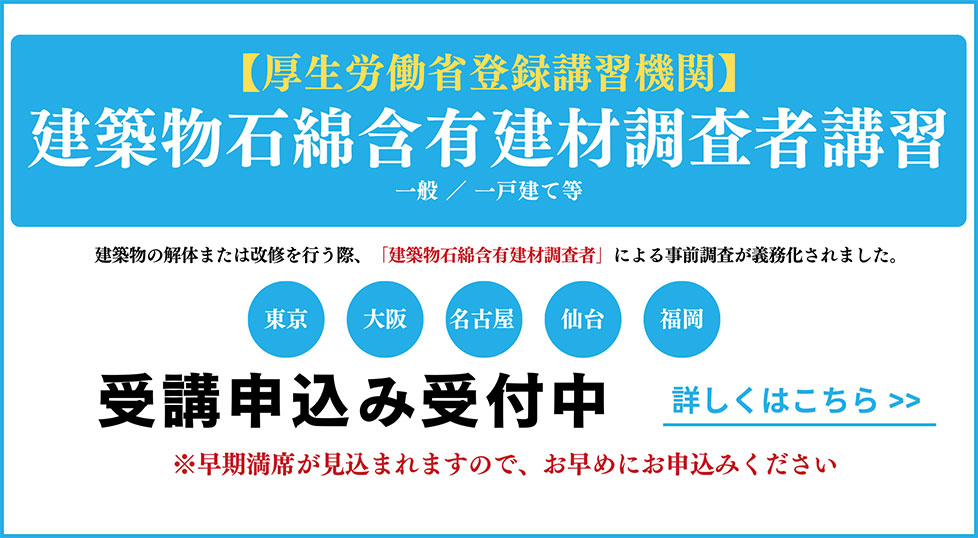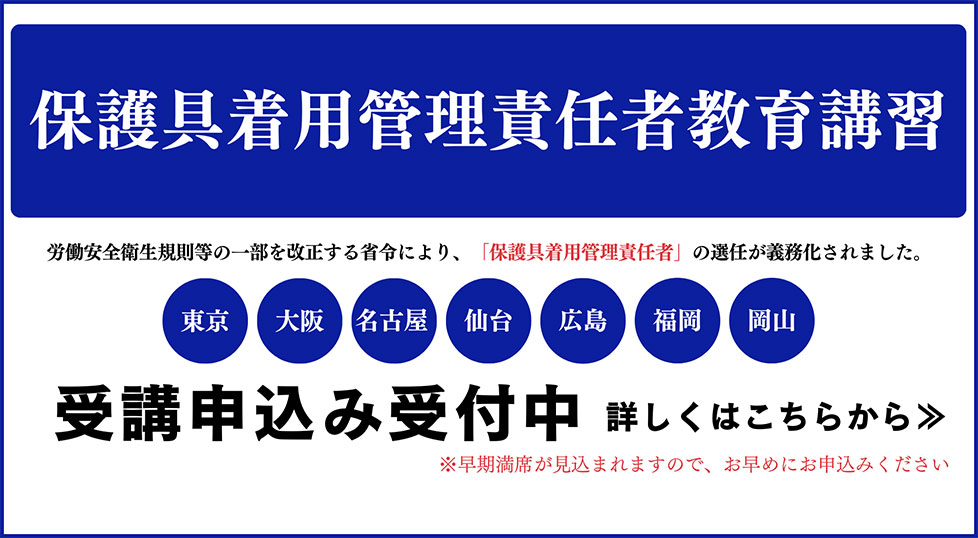施工管理技士合格をアシスト
建設業特化の受験対策
施工管理技士
安全衛生教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育
- フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 保護具着用管理責任者教育
- 化学物質管理者講習
- 建築物石綿含有建材調査者講習
- テールゲートリフター特別教育【講師向け】
- テールゲートリフター特別教育【作業者向け】
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- 職長・安全衛生責任者教育
『工作物石綿事前調査者講習』近日開講予定! 資料請求・優先受付開始!
設備関連資格
建設・職場衛生関連資格
お知らせ・講座情報
1分でわかるCIC資格講座の特徴
CIC開設25年。個人のかたはもちろん、業界リーディングカンパニーをはじめ
企業からの一括受講も多数。信頼の実績。

短期集中型の講習会だから
仕事に支障をきたさず
参加できた

自分の都合に合わせた
映像講義で
無理なく学習

本番でも施工経験記述に
不安を感じることなく
挑めた
ABOUT CIC
厳選講師陣とスタッフの組織力で
みなさまの受講を徹底サポート